| トピックス |
|---|
「スイス=ブラジル1924――ブレーズ・サンドラール、詩と友情」
管 啓次郎+工藤 晋
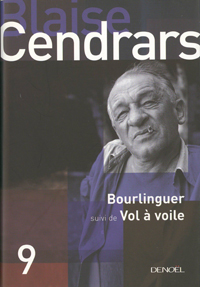
管:ブレーズ・サンドラール、スイス生まれの世界旅行者、冒険家、片腕の詩人、嘘つき、小説家、多くのアーティストたちの友人。2007年は彼が生まれて120年にあたる記念すべき年だった。別にこの「記念」に年は関係ないのだが、それはそもそも便宜的なこと。生誕97年だろうが114年だろうが123年だろうが、われわれは詩人のことでも画家のことでも何にもしなかった人のことでも、いつ思い出したってかまわない。それでもブレーズには自分を「ブレーズのともだち」と考えたがる人が世界中にけっこういて、昨年は世界の各地でこうしてブレーズをめぐる活性化された思い出の総量が、相当なレベルに達したものと思われる。
ひとつには、どうやら、スイス政府自体が文化的なプロモーションに力を入れているせいでもあるようだ。サンドラールの誕生日(9月1日)ごろにスイス大使館主催で何かイベントをやらないかと、春先に声をかけてくれたのはスイス・ロマンド(フランス語圏)文学の第一線の研究者である正田靖子さん。ぼくの最初の本『コロンブスの犬』(1989年)の大きな部分はブラジル滞在記で、その中にサンドラールの詩の引用がいくつもあることを思い出してくださったみたいだ。相談するうちに、サンドラールの生涯の中でもブラジルとの関係に焦点を当てれば、おもしろいまとまりのある流れができるだろうということになった。最初はボサノヴァでも流しながらぼくがしんみり話をする、という程度の案だったのだが、それではちょっとさびしすぎる。ぼく自身、1985年以来ブラジルを訪れていないので、あの強烈な国がまるで幻の国みたいに思えている(ジル・ラプージュの不朽のブラジル旅行記『赤道地帯』の身振りを結局なぞっているにちがいない)。イメージがぼんやりしている。さて、どうしようか。
今福龍太さんに相談することにした。かつて一緒に作った『ブラジル宣言』(1988年)という本は、今福、ぼく、港千尋、旦敬介の全員にとって、「ブラジル」という無根拠な出発点を刻むものだった。今福さんはこの数年もブラジルに何度も行って、レヴィ=ストロースの足跡を追う自分のプロジェクトも精力的に進めている。会って相談するうちに、話はどんどん大きくなった。山口昌男先生にも登場してもらおう。アフリカニストとしての山口先生は、サンドラールのアフリカ関係の著作に早くから敏感に反応してきた人だ。高橋悠治さんもお呼びしよう。現代日本が誇る戦う音楽家である高橋さんに、ブラジルの代表的作曲家ヴィラ=ロボスや、ポール・クローデルの秘書としてブラジルに滞在したダリウス・ミヨーの曲を生で演奏していただくとは、想像しただけでほとんど気が遠くなるくらい。そして今福さんは、いつもながらの冴えた感覚で数々の図版を準備し、そのプレゼンテーションに重ねて、ぼくが新たに訳したサンドラールのブラジル詩編のいくつかを朗読してゆくことにした。これでもうプランはできあがったも同然。あとは即興で。だいじょうぶ、だいじょうぶ。
みんなの都合を探るうちにブレーズの誕生日である9月1日(1887年にブレーズが生まれたこの日、ぼくが大好きなブラジルの画家でブレーズにとっても魂の姉のような存在だったタルシーラ・ド・アマラルが1886年に生まれている)ではなくやや遅れた10月27日開催となった。そして遅れたことはむしろ僥倖だった! 当日は季節外れの台風。朝からどんどん風雨が強さを増し、恵比寿の道路が川みたいになる。これじゃお客は来ないね、といいながら、ぼくらはそれをブレーズ台風と呼び、準備を進めた。ところが思いがけないことに、開始時刻まぎわになると、人がどんどんやってくるのだ。ついさっきまで誰もいなかったホールが、またたくまに半ば濡れねずみの人たちでいっぱいに。なんという不思議な盛り上がり。それから後、終了までのことは、ぼくは進行にかかりきりであまり覚えていない。そこで以下に、当日の報告を、友人の工藤晋(フランス語圏カリブ海文学)に書いてもらった。これで様子はわかると思う。交替します。
工藤:東京日仏会館で、スイス出身のフランス語詩人・作家ブレーズ・サンドラール生誕120周年記念シンポジウム(スイス大使館主催)が開催された。フランスとの国境に近いジュラ山脈の町、ヌーシャテル州ラ・ショー=ド=フォン生まれ。生田耕作訳による『黄金』『世界の果てまで連れてって』などの小説や、いくつかの詩の翻訳によって日本に知られる作家ではあるが、みずからの世界放浪人生を映し出した破格で壮大なスケールの創作活動の全貌は、いまだ十分に紹介されているとはいえないだろう。
今回のシンポジウムでは、サンドラールの旅=人生の中で大きな事件であった、1924年のブラジル旅行に焦点があてられた。第1次世界大戦で右手を失ったあとの心身の退廃を乗り越え、シュルレアリストたちとの確執や映画への接近を経て新しい文体を模索していたサンドラールは、奇しくもブルトンの『シュルレアリスム宣言』が出版された年にブラジルに渡り、画家のタルシーラ・ド・アマラルや詩人オズヴァルド・ジ・アンドラージといったブラジル・モデルニズモの芸術家たちと交友する。そのブラジル体験は作家に決定的なインスピレーションを与えた。
シンポジウムは2部構成だった。前半はスイス大使館のピーター・ネルソンさんと管啓次郎さんによるTu es plus belle que le ciel et la mer(君は空と海よりも美しい)のバイリンガル朗読に続き、ロベール・ドアノーが撮影したサンドラールのすばらしい肖像写真のスライド・ショーで幕開け。まず最初に、在日スイス大使フィヴァ氏が挨拶した。自身、サンドラールの熱心な読者であると語り、サンドラールと同年におなじラ・ショー=ド=フォンで生まれた建築家ル・コルビュジエほかの人々にも言及して、スイス文化芸術の国際性を強調された。通りいっぺんの外交的挨拶ではなく、非常に熱のこもった、内容のあるスピーチで、聴衆も強くひきつけられた。
ついで清岡智比古さんによるレクチャー「サンドラールの生涯」では詩人の生涯が要領よく解説された。中でも1924年に発表された代表的詩集のひとつ『コダック』が、じつは作家が敬愛するギュスターヴ・ルルージュ(ヴェルレーヌの親友)が書いたとある冒険小説の文を使ったコラージュ作品であるという、驚くべき事実が印象的だった。そして山口昌男さんが今福龍太さんを聞き手として「世界の創造者サンドラール」を語る。単なる「モダニスト」といったレッテルでは片付けようもない巨大な詩人の想像力を、時代の新しい知のかたちの探器(センサー)であるとする76歳の山口先生のとつとつと進むディスクールは、空間の猟捕者サンドラールの旅に重ねた、ご自分のアフリカ=ブラジル=スイスを結ぶ旅の軌跡そのものだった。
シンポジウム後半は、言葉と映像と音楽の即興的なセッションとして進行する。今福さんによる洗練された映像構成「1920年代ブラジルへの想像の旅」によってサンパウロの都市風景など当時のブラジルやサンドラール周辺についての貴重な資料が紹介されたが、その発表を縫って、管啓次郎さんによるサンドラールのブラジルに関する詩作品の翻訳朗読が挿入される。旅の高揚感をわしづかみにするような野太いポエジー。もうひとつの呼び物は、高橋悠治さんによるピアノ・ソロ。サンドラールがそのバレエ組曲『世界の創造』の脚本を書いたダリウス・ミヨー、ブラジルを代表するヴィラ=ロボスによって作曲された珠玉の小品たちに加えて、何と高橋さん編曲によるアントニオ・カルロス・ジョビン作品が2曲、宝石のようにセッションのなかに散りばめられた。これがいかに異例な事件であるかは、高橋さんのファンにはよくわかることであろう。至福のセッションを終えてロビーに出ると、大使館提供のスイス・ワインとスイス・チーズが聴衆全員に振舞われた。驚くべきホスピタリティ。
ジャンルや空間を縦横無尽に踏破する旅人サンドラールの想像力にふさわしいこの夕べを語るのに忘れてはならないもうひとつの出来事は、ロビーで販売された手作り本制作集団BEKAによる120部限定の小冊子である。これには感動した。手書きとタイプ打ちによって、本シンポジウムでその一部が発表されたサンドラールの伝記的情報やエッセー、訳詩と原文テクストが収められたその「書物」は、シンメトリーも天地もない紙片が凧糸で縛られた異様な装丁で人を驚かせた。それもまた、いくつもの場所を渡り、常識的秩序をやすやすと乗り越えてゆくサンドラール的「世界」への共振の試みであるように思われた。こうして秋の嵐の荒れた一日が、そこに集った互いに見知らぬ人々にとって、忘れがたい一日となった。
管:ふたたび交替します。最後に、ぼくがサンドラールを好きなわけを、3つばかり紹介します。
(1)どこかで彼は書いていた、「サティはトナカイの肉が好きだった」と。人が人を語るにはいろんなやり方があるけれど、ひとことで人(他人)を表すとき、その人(自分)のまぎれもない傾向が現れる。ぼくにとっては、このひとことでサティが身近になった。それはブレーズの磁力のせいだといっていいだろう。
(2)サンドラールが自分の犬(ハウンド+スパニエル系の雑種?)を残された左手で撫でている写真が、何枚かある。あのいかつい老人には、あまり似合わない可憐な犬。でも彼はその犬に「ヴァゴン=リ」という名前をつけていた。意味は「寝台車」。彼以外、どこのだれがそんな名前を犬につけるだろう!
おいで、寝台車。おすわり、寝台車。いい子だね、寝台車。おあがり、寝台車。しあわせな犬だったにちがいない。
(3)サンドラールはいつも左手で手紙を書き、最後にこう書き添えた。De ma main amie(私の、友情の手による)。小説はたぶんレミントンのタイプライターで打ち出した。それから仕事を終えると、手紙やはがきを手で書いた。このことはヘンリー・ミラーが書き残している。ヘンリーはブレーズを心から尊敬していて、彼が長いパリ生活ではじめて会ったフランスの作家がサンドラール、最後に(パリを離れる日に)偶然会ったのも彼だった、という。この効果は、上記の(1)のせい。
これでおしまいです。(管啓次郎+工藤晋)