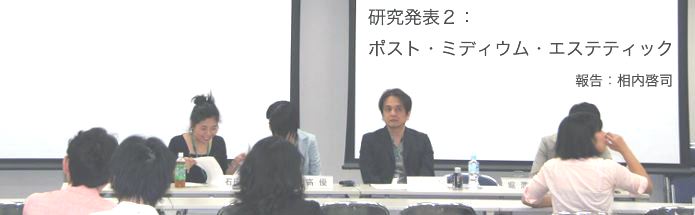| 第4回大会報告 | 研究発表パネル |
|---|
7月5日(日)京都造形芸術大学 瓜生山キャンパス 人間館4階NA403教室
研究発表2:ポスト・ミディウム・エステティック
実写・アニメーション・身体——モーション・キャプチャーを中心に
石田美紀(新潟大学)
拡張する写真——ネイサン・ライアンズの「残像」展(1967)を手掛かりに
日高優(群馬県立女子大学)
「間メディウム性」の系譜学
堀潤之(関西大学)
【コメンテイター】北野圭介(立命館大学)
【司会】堀潤之
1990年代以降急速に発展を遂げてきたデジタル機器やインターネットという新たなミディア、とりわけ情報ミディアの活用がこれまで意識化されていた諸文化、諸地域における固有の歴史的な世界像とはことなる新たな情報化された世界像というイマジネーションを出現させている。本パネルは、そうした情報関連ミディアがもたらす現象としてのドラスティックな世界像の変貌が、「現代美術」のあり方にも影響を及ぼしている点に着目し、近年とくにその関わりを深めている映像、写真、身体論、画面論などを対象とする学問的研究についての再考をうながすものといえる。
ここでは、パネル構成を担当した北野圭介・堀潤之の両氏によって、各ミディウムの個別研究の深化に加え、その定義そのものが前提として詳細に検討されることはなかったが、「ポスト・メディウム」の地平を見据えた新たな理論構築が必要ではないかと提案されている。
石田美紀さんの『アニメーション・身体——モーション・キャプチャーを中心に』では映像とCGがもたらす関係についての考察が2つのトピックとして取り上げられた。[1・CGによって新たに問い直される映画のステータス]、[2・操作される身体と「中の人」になること]である。前者では実写を非CGとし、CGを主体にとらえる。そして今日的な映画の一つの特徴をCGと非CGがどこまでも混淆している=CGによる写真映像的なリアリズムの体現とする。また、写真映像を、C・S・パースの記号概念を援用して、「類似記号」ではなく「指標記号」とすることによって解釈の可能性が広がるとする。CGと身体性との関係において、CGは実写やモーションキャプチヤーにおける身体を覆いつくし、その身体性は指標記号の指し示すものに変わる。後者において映画的鑑賞の経験と3Dアクションゲームの操作性という経験の差異に注目し、ゲームのプレイヤーは鑑賞者であるとどうじに、そのスターの「中の人」になるという主客未分化な状態になるとして、そこに他者との自己同一化の欲望が投影されながら、自己の痕跡と他者との類似性が重なり合う「もどき」の経験を構成するとしている。
日高優さんの発表では『拡張する写真——ネイサン・ライアンズの「残像」展(1967)を手掛かりに』ではタイトルどおり、その展覧会の内容の紹介が中心におかれた。そこでのライアンズの問題意識が写真と被写体との固定的、不変とされる対応関係、いいかえれば写真と対象との関係を類似性や、指標記号としての機能に固定化し、知覚と意識の関係をパターン化し非人間化することに対する批判である。どうじに、そのような関係から視点をずらし、写真家自身に感覚受容体としての身体性を回復させることであったとする。それは写真家の開かれた感覚に対して、世界の様相が拡張された生の経験として現前することを意味する。そこでは木製パズル写真、彫刻化する写真、版画化する写真、ペイントされる写真、マルチ写真などさまざまな試みがあったことが紹介された。そしてこのような事例が、「ポスト・ミディア」に通底する先駆的な試みとしてすでに60年代にあったと指摘する。
堀潤之さんの『「間メディウム性」の系譜学』では[1・映画からポストシネマへ]、[2・マノヴィッチ「ポストメディア」論]、[3・「間メディウム性」の系譜]について発表された。1では1990年代以降の映像を巡る多様な変化について語られ、現代美術との横断的な表現の増加、DVDなどのメディアによる受容面の多様化、映像制作におけるデジタル化をとり上げた。そこではとくにマノヴィッチの言説、デジタルミディアによる映像制作は「最終的にはアニメーションのある特殊ケースになった」を引用している。2ではマノヴィッチの[ポスト・メディア]論を紹介する。その内容は以下の引用に集約される「ポスト・メディアの美学が必要とするのは、ある文化的オブジェクトがどのようにデータを組織化し、どのようにユーザーによるそのデータ体験を構造化するのかを描写できるような諸々のカテゴリーである」(下線は原文のまま。ただし、配布資料に記載の引用文では傍点のところ、web上の表示の都合により下線に変更)。3は[クラウスの「ポスト・ミディウム」の状況とヴィデオの出現]と[レイモン・ベールによる「諸イメージの間」Entre-imagesとフィリップ・デュボアによる「イメージの異種交配」métissage des images]に触れる。クラウスの引用を要約すれば、「モダニズムの論理がテレビのもつ異種混淆性によって打破された。ヴィデオ装置が伴うのは言説上の混沌、諸々の活動が首尾一貫性をもたず理論化できず、それらを統合する核をもっているとは考えられないような状態である。いいかえれば、われわれはポスト・ミディウムの時代を生きているのだ」と。そしてフィリップ・デュボアは「今日、私たちはもはや、ある芸術やあるミディウムを、別の芸術やミディウムを介してしか語ることはできない」「一種の理論的な不純性においてしか、様々な交叉が組織され、複数のエクリテュールの効果が相互浸透する空間としてしか、思考することはできない」と指摘する。
コメンテーターの北野圭介さんはこれらの発表を受けて、ポストミディウムエステティックという問いについて、1970年代のクラウスらによるグリーンバーグ批判にまでさかのぼって解説し、同じことのくり返しではないかという疑問を投げかける。個々の発表についてそれぞれ簡単に触れたが、とくにマノヴィッチの — デジタル技術にすべての情報が一元化される — とするポスト・ミディア論について批判し、メディウムの衝突という可能性についてのポスト・ミディア論の必要性を指摘した。またレイモン・ベールについて、その理論の分かりやすさと、ポストモダン論でもなく、ニューメディア論でもないメディア論の可能性を探るものであると評価した。 間ミディウム性という観点から、映像をこれまでとはちがうものとして探っていく見たてに可能性があるのではないかと締めくくった。
最後に質疑応答の短い時間がもたれたが、質問者からこれまでの議論はハイブリッドメディア論や、間メディア性についての議論ではないか。マノヴィッチに見られるようなミディウムの歴史性、固有性を抹消させるポスト・ミディア論という概念があまり有効性をもつようには思えないが、それを超える理論的な水準はあるのか、という質問がなされた。また、ベールの中にも70年代的発想が残っている点の指摘なども含め、このパネルはそれらを整理し、乗り越えるための美学的な論理を模索しようとする方向性をもつものではなかったのかという疑問が発せられた。結果的に、発表者がただ発表して終わるわけにはいかないという緊張感の高まりとともに、このパネル全体のテーマに対する発表者、コメンテイターの意識のちがいがうきぼりになったカタチでのタイムアップとなった。
個人的な印象評にすぎないが、個々の発表においても、その内容が多岐にわたるように全体の印象としてはかなり研究途中段階の要素が多く、論点についても未整理感を免れないようにも思えた。「 」付きの「ポスト・ミディア」論としても、歴史的状況や今日の状況を、また他者の理論をトレースする以上の何かが求められていることが、あらためて浮き彫りになるパネルだったように思う。

石田 美紀

日高 優

堀 潤之

北野 圭介
相内啓司(京都精華大学)
発表概要
実写・アニメーション・身体——モーション・キャプチャーを中心に
石田美紀
1990年代以降、映像と身体が取り結ぶ関係はあらたな局面を迎えている。当然のことながらその要因として、デジタル技術の発展と、それを使いこなす表現技法の変化があげられる。
本発表では旧くて新しい技術であるモーション・キャプチャーに注目し、身体表象との関係について次の二点を中心に考察する。
〈実写〉映画における身体表現とスター(『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ、『ポーラー・エクスプレス』、『ベオウルフ―呪われし勇者』)
〈アニメーション〉映画における身体表現の変容(アニメ版『ロード・オブ・ザ・リング』、『魔法にかけられて』、『エクス・マキナ』)
以上の論点が選ばれるのは、デジタル技術によって変容を被ったのが〈実写〉における身体表象だけではないからであるが、それを踏まえて〈実写〉と〈アニメーション〉の相似と相違をも視野に入れて議論を進める。
拡張する写真——ネイサン・ライアンズの「残像」展(1967)を手掛かりに
日高優
1960年代から70年代にかけて、視覚の冒険とも呼ぶべき新しい潮流が写真において現れる。この時期、多くの写真家が写真の可能性を拡張すべく多様な実験をおこない、ジャンル横断的な作品づくりへと向かったのである。モダニズムの思潮下で「ストレート」の美学が長らく支配的であったアメリカにおいて、この潮流は最も鮮明に確認される。だが、写真研究がこの潮流をこれまで本格的に論じることもないまま、こんにちに至った。
こうした状況をふまえて、本発表では上述の潮流を分析し、そこに孕まれていた「ポスト・ミディウム」の地平に向かう写真の可能性を考察する。具体的には、ネイサン・ライアンズが企画した写真展「残像」(1967)を特に身体という問題系に焦点を当てて分析する。まず、この潮流の背景をライアンズの思考から探った上で、さまざまな身体の次元(写真家や観者の感覚受容体や運動体としての身体、身体を巡る視覚的経験など)を織り込むことによって写真表面を重層化する手法が当該作品において実験されていることを明らかにする。そして、身体を系とした写真表面の重層化の手法が写真の加工や操作を画面に導きいれる導線となったこと、さらには他のメディアを呼び込む潜在的な場として写真が拡張されて機能した可能性を考察する。なお、「残像」展は同じくライアンズによる前年の写真展「社会的風景に向かって」が高く評価される裏で殆ど等閑視されてきたが、本発表で「ポスト・ミディウム」の視角から光を当てることによって、写真研究におけるその意義も確認することができよう。
「間メディウム性」の系譜学
堀潤之
映画/写真/美術といった既存の枠組みに容易に収まらない映像作品は、いまや、もはや珍しいものではない。資本と労働の集約が必須であるため、比較的その外延が堅固に定まっている映画というミディウムにおいてさえ、他のメディアとの相互浸透の動きが生まれつつあるのではないか。ところで、そのようなミディウム横断的な指向性には、歴史的な先例が数多く存在する。フランスの映画作家・映像作家に限れば、1970年代以降ヴィデオをいち早く取り入れたジャン=リュック・ゴダールと、書物、写真、コンピュータなど多くのメディアを自在に往還するクリス・マルケルがとりわけ刺激的な作品を生み出してきた。
本発表では、映画・映像をめぐるフランスの理論的言説のうち、映画という一つのメディウムの枠内にとどまって、映画固有の理論を打ち立てるやり方とは逆に、映画、写真、ヴィデオなど複数のメディウム間の交渉を重視する言説に注目する。具体的には、レイモン・ベルールの提唱する「諸映像の間」(entre-images)や、フィリップ・デュボワの「諸映像の交雑」(métissage des images)といった1980年代に展開された概念を整理した上で、それらの諸概念が今日の映像を取り巻く状況に対してなお有効であるのかどうかを検討する。