| 座談会 | ページ2 |
|---|
学会誌『表象』刊行記念座談会
「新しいアソシエーションの形をもとめて」
| 桑野 隆(早稲田大学) | 中島隆博(東京大学) |
| 門林岳史(日本学術振興会特別研究員) | 宮崎裕助(日本学術振興会特別研究員) |
| 佐藤良明(広報委員会=司会) | |
佐藤 それともう一点、前半部分の特集は今おっしゃった通りでしょうが、後半部分は、カッシリと若手の論文発表の場になっている。既成の学会にはなかなか面倒を見てもらえない内容でも、こちらに投稿してくれればオーケーですよというメッセージも、同時に発しているわけですね。片方で、今をときめく人たちの発言を載せておいて、そういう場に、まだほとんどキャリアのない研究者への登竜門としてスペースを用意してあるというのは、若い人たちへのお膳立てとして、すごいサービスだなあと思います。既成の学会からはみ出たことをやっていて、にもかかわらずというか、いや「だからこそ」でしょう、これからの時代を担うべき人たちへ結集を呼びかけるという作りになっているわけですが、その後半の「純学会誌」的な部分に関して、活性化の見通しみたいなものをお持ちなら、うかかがわせてください。
門林 次号以降あたらしい書き手にどのように寄稿してもらうかということですが、今回のこの特集は、有名性に頼りすぎているという点が明白にあると思うんですね。「この学会はこれだけの人たちが集まってくるところなんだ」ということを示す意義はあると思っていますが、このまま、有名な人たちが代わる代わる出てくるというやり方はもたないということも認識しています。今回は前半に有名な人、後半にはこれから活躍するかもしれない若手というふうに割れてしまったんですが、今後は特集の方に、若い仲間を増やしていきたいですし、同時にエスタブリッシュした人たちの論文投稿というかたちでのお力添えも期待したいと思っています。
宮崎 実は、有名性に頼らないかたちで、本誌を機能させていくということを最初から考えていました。今回の特集は、たまたま活字化するにふさわしいシンポジウムが行われたあとだったので、それを特集にもってきたわけですが、毎年、大会のシンポジウムのテーマが特集になると決まっているわけではありません。臨機応変に特集を新しく組んで、新しい書き手を発掘するというやり方も、今後必要になってくるでしょう。他方で、学会誌のいいところは、公募制の原則が貫かれるところです。商業的な批評誌だと、どうしても、売れ筋の執筆陣に固定されたり内輪の人間関係に左右されたりといった傾向が出てきますよね。そういう偏りは、公募制をとる以上、取り払われます。会員ならいかなる人も公平に審査をうけて論文掲載の権利を有する、という原則は言うまでもないことですが、それが明確になっているということは、やはり利点として強調しておきたい。もちろん過度の平等主義や手続き主義は、逆効果にもなりえますが、この原則があってこそ、実際に内容重視でいけるわけだし、まったく新しい書き手が生まれる可能性も開かれるわけですから。
佐藤 これだけ間口を広げて、新しい人たちを歓迎しながら、各号新しい特集を組んでいくというのは、むずかしいだろうなあと思いますが、ご自身、たくさんの間口をもってらっしゃる中島さん、いかがでしょうか?
中島 実際の編集を担当したのが、桑野先生やわたくしではなく、今日ここには来てらっしゃらない方を含めて、若い編集委員の方々だった──ということが重要だと思うんですね。この雑誌が従来の学会誌と根本的に違うところは、学会のお偉いさんが方向性を決めて、それにただ若い人が労力を提供するというのではなく、そもそもこれを作るときに若い人がアイディアを出して自分たちで設定とデザインをしていったことだと思います。前半のシンポジウムや対談などにしても、企画段階から若い研究者のアイディアがかなり入っています。まあ最初だから、有名な方に来ていただくということを一応はやりました。しかし、わたくしが見ている限りでも、若い研究者の方に、アイディアは溢れんばかりにあります。それをうまくつかんで増幅するようなかたちに、この媒体をもっていけたらと思っています。
従来の学会誌のあり方というのは、publish or perish と言われるように、とにかく何か論文を出さなきゃいけない、そのための単なる排泄の場所だったともいえます。そうじゃなくて、学会=association の本来の精神、みんなとつながっていく、そしてここから一緒に波をおこしていく、associate or perish ですね、そういった場所として、この雑誌は出発したのだと思います。一見すると、総花的に何でもありに見えるかもしれませんし、従来のカテゴリーからすると、こんなにいろいろあってどうするんだろうという恐れをもつ読者もいるかもしれない。しかし人文学のいちばんの快楽がここには詰まっているんだと考えるべきではないでしょうか。自由に問いを立てて、それを他の人と共有して考えていく、そういった人文学の基本がまだ可能な場所があるということが、ここに示されている。そこから、今まで遠慮していた人たちが、じゃぁちょっと関わって書いてみるかという「小さな勇気」を得られるかもしれない。こういう自由なassociationが広がっていかないだろうかと夢見るのです。
雑誌の編集に戻ると、何も最初にプログラムがあって始まったわけではなく、議論しながら、あっちいったりこっちいったり、すったもんだしながら編集作業は進んでいきました。わたしは、そのプロセス自体に今の人文学の、いちばんの突端が現れていたと思っています。ですので、この雑誌がみなさんからいい評価を受けたとすれば、その思いと起こした波が読者に伝わったからでしょうし、今後もその波を起こし続けることをやりたいですね。
桑野 表象文化論学会自体ほかの学会と比べると相当若い人が中心になっているように思われますが、『表象』を実質的に作りあげてきた編集委員にしてもとても若い。これは珍しいことでしょう。そして、門林君と宮崎君がみずから翻訳した「人文学の未来」や、それから「人文知の未来」というテーマで寄稿をお願いした方々の選択の仕方にしても、これからの『表象』はこうありたいというメッセージが明確に出ています「共同討議」がどちらかというと<表象>の過去を振り返っているのに対して、この「人文知」の現在から未来にかけての部分は、とりわけ若い読者に訴えかけている部分ともいえます。これがきっかけとなって刺激的な論文がどんどん寄せられることを楽しみにしています。ちなみに、今回掲載できたのは、ジャンルからすると思想と美術、それに映画ということでしたが、文学・演劇・音楽などに関する論文も次回以降登場してほしいですね。
中島 雑誌の作り方自体が、表象文化論的というんでしょうか、一体どんな人たちが編集しているんだろうと思わせる雰囲気がありますよね。雑誌のディテールが十分楽しめるものになっています。ですので、望むらくは、多くの若い研究者に編集に参加してもらいたいですね。論文を書く方というかたちではなくても、手伝いたいとか、雑誌作りに自分のアイディアをぶつけたいという思いを持った人に、飛び込んでもらいたいと思います。

宮崎 裕助

中島 隆博
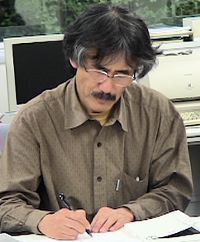
佐藤 良明