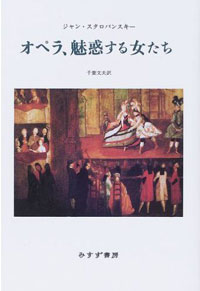| 新刊紹介 |
|---|
ジャン・スタロバンスキー
『オペラ、魅惑する女たち』
千葉文夫 (訳)、みすず書房、2006年10月
歴史というものが、出来事連鎖の安定した記述などではなく、現在を生きる者たちによる再創造だと実感させる例としてオペラほどに格好なものはない。この場合に動力となるのは、純然たる文献学的手続きというよりも、実際の上演の動向であり、その内実をなす流行と趣味の変遷であるといえよう。 1930年代半ばにグラインドボーン歌劇場がフリッツ・ブッシュを音楽監督に迎えて実現したモーツァルト=ダ・ポンテ三部作の上演以前の同作品の扱いがどのようなものであったのか想像するのは困難である。忘却の歴史は再発見の歴史でもあり、アビ・ヴァールブルクの表現を借りるならば、そもそもオペラとは、すぐれて「古代の残存」というべき世界なのだ。
ジャン・スタロバンスキーのオペラ論は魅惑もしくは魔術を意味するenchantementなる語の含蓄をときほぐす試みである。ここには世界の脱魔術化のプロセスに対抗し、カルメンの名の語源に潜む「魔力」こそがオペラの本体であると見据える視線が存在している。バランスよくオペラ劇場の上演レパートリーを眺めわたそうとする配慮は認められない。それどころかヴェルディもプッチーニもほとんど扱われず、ヴァーグナーへの言及はあっても、指輪四部作に触れずに終わるのがこのオペラ論なのだ。ジュネーヴ大歌劇場の公演プログラム用の文章がもとになっているという事情を考慮に入れても、著者の選択の独自性は際立つ。ひとことで言えば、スタロバンスキーの関心が向かうのは、国民国家形成に結びついた19世紀オペラの世界ではなく、ギリシア神話あるはホメロスからアリオスト、タッソへいたる汎ヨーロッパ的な伝統に結びついた世界なのである。その中心、いやむしろ黄昏に位置するというべきモーツァルト=ダ・ポンテは、作曲家と台本作者の共同作業の幸福な例をなしている。 (千葉文夫)