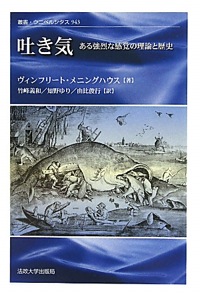| 新刊紹介 | 編著、翻訳など | 『吐き気――ある強烈な感覚の理論と歴史』 |
|---|
竹峰義和ほか(訳)
ヴィンフリート・メニングハウス(著)『吐き気――ある強烈な感覚の理論と歴史』
法政大学出版局、2010年8月
ひとは、何に対して吐き気を催し、いかにこの吐き気(むかつき)を表現するのか──「吐き気」をめぐる感性への問いは、摂食行動における拒絶反応のような、たんなる生理学的な問いの対象であるにはとどまらない。この問いは、たとえば食や芸術の美的趣味、犯罪や不正義に対する道徳感覚、あるいはサルトルの『嘔吐』(原題 La Nausée は「吐き気」の意)が描き出した実存感情のように、すぐれて文化・社会・言語的に規定された次元において課されているのである。
本書は、この「吐き気」の感覚が、18世紀から現代に至るまで、西洋近代における文学・思想・芸術等のさまざまな事象に通底する根本的な経験だということを包括的に描き出した画期的な大著である。その企ては、メンデルスゾーン、ヴィンケルマン、レッシングといった古典主義の文学・思想から、カントを経て、ニーチェ、フロイト、そしてカフカ、バタイユ、サルトル、クリステヴァといった20世紀の作家・理論家の著作までを広く検討の対象とし、「過去二百五十年の標準的な見解のなかで、吐き気がどのように理論化されてきたのか」(序章)を明確にたどり直している。
本書の「吐き気」への着眼は、しかし、けっして「醜いもの」や「おぞましいもの」の表象をめぐる百科事典的なパノラマに終わってはいない。その歴史的「かつ」理論的な要諦は、「吐き気」が人間感性にとって本質的な危機──カール・シュミットなら「例外状態」と呼んだような──を指し示すことにより、美学=感性論(エステティクス)そのものの可能性の条件とそのリミットを明るみに出すという点にこそある。本書は、著者の膨大な人文学的博識と文献学的営為が一貫した理論的視座のもとで結実した、比類なき「反エステティクス」の系譜学なのである。(宮﨑裕助)