ベルリオーズ ドラマと音楽:リスト・ワーグナーとの交流と共に
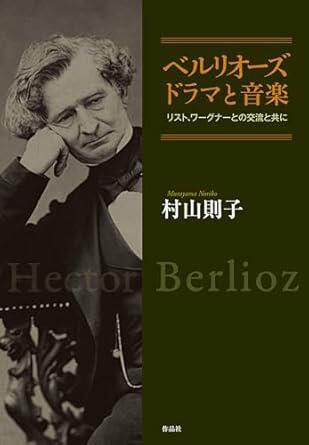
19世紀のフランスを中心に活動したベルリオーズ(1803~69)は、現在も演奏会レパートリーに定着している《幻想交響曲》や、リヒャルト・シュトラウスが評価し後世に大きな影響を与えた管弦楽法の著作などが良く知られている。しかし、オペラ《ベンヴェヌート・チェッリーニ》や《トロイアの人々》から《レクイエム》《ファウストの劫罰》にいたる大規模な声楽とオーケストラによる作品は、近年は上演数が増加したとはいえ、いまだ実演に触れる機会は少ない。本書は、いわゆる「オペラ」や「交響曲」といったジャンルを逸脱するベルリオーズのこれらの作品群を、「ドラマと音楽」という観点から一貫して捉え直すことを試みた。
本書は3部構成である。ベルリオーズ自身による『回想録』や書簡を中心に、その生涯を通時的に概観する第1部につづいて、第2部では具体的な作品論が展開される。《幻想交響曲》と《レリオあるいは生への回帰》、ワーグナーが賞賛した《ロメオとジュリエット》、作曲家の生前は全曲上演が叶わなかったオペラ《トロイアの人々》らが分析の対象となる。とりわけ、「目に見えないオーケストラ、合唱、独唱付き叙情的なモノドラマ」という特殊な編成の《レリオあるいは生への回帰》を取り上げる第1章第6節は、《幻想交響曲》との2部構成での演奏を構想した過程やシェイクスピアへのオマージュを詳細に分析し、本作がベルリオーズの作品における声、ドラマおよび音楽の関係が変遷する重要な契機となったことを示している。第3部は、フランツ・リスト(1811~86)、リヒャルト・ワーグナー(1813~83)という同時代の二人の音楽家との交流を、書簡を中心に丹念に追っていく。ベルリオーズとリストは1830年12月に行われた《幻想交響曲》初演の前夜に出会い、リストがベルリオーズ作品の編曲や演奏を積極的に行うなど、30年以上にわたって交友が続いた。ワーグナーは《ロメオとジュリエット》の初演に立ち会い、「自身の音楽的、詩的な感覚の概念を暴力的なまでに存在の根本に押し戻すほどの印象」(本書、199頁)を受けたと述べる。しかし、その後の互いの交友や芸術家としての評価は距離や葛藤を感じさせるもので、両者と交流が深かったリストとの付き合いにも影を落とすことになる。三つ巴のやり取りの背景には、パリ、ロンドン、ワイマールなどの音楽界の状況も浮かび上がり、同時代の文化制度のなかでみずからの創作を実現しようとした音楽家たちの三者三様の生きざまが滲みでている。
ウェルギリウス、シェイクスピア、ゲーテなどの文学からベートーヴェンらのドイツ語圏の音楽家との影響関係まで広く視野に収めた本書の成果は、フランス音楽に関する著者の継続的な研究のなかで、ラモーやリュリを扱ったバロック期に関する研究と(『ペローとラシーヌの「アルセスト論争」』)、20世紀初頭のドビュッシーに関する研究(『メーテルランクとドビュッシー』)をつなぐものと位置づけられる。本書が示す通り、ベルリオーズの異彩を放つ作品群は、リスト、ワーグナーのみならず、メンデルスゾーン、シューマン、ハンスリックらドイツ語圏の作曲家・音楽評論家や、フランス音楽学の大家フェティスらとの交友や緊張関係が育んだ。演劇と音楽の、あるいは啓蒙主義・古典主義とロマン主義の結節点としてのベルリオーズの創作は、19世紀半ばの入り組んだ独仏関係に新たな光を当てる鍵となりうることも本書は示唆していよう。
(白井史人)