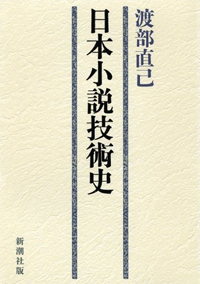| 新刊紹介 | 単著 | 『日本小説技術史』 |
|---|
渡部直己
『日本小説技術史』
新潮社、2012年9月
本書が目指すのは、「序文」にあるとおり、「技術」という視点から日本近代文学史を「転倒」させることである。著者によれば、「従来の『日本近代文学史』」は、この問題について「何ひとつまともには語ってこなかった」。この大いなる不在の起源を、著者は坪内逍遥『小説神髄』の有名な一文「小説の主脳は人情なり、世態風俗これに次ぐ」に見出す。小説とは人情すなわち内面を表現し、同時代の状況を反映するものだという通念が、「筆を執ってたんに書いていた」作家の姿を忘れさせていたのだというのである。
第一章では、日本近代文学史を転倒させようとする筆者の目論見が明確な成果を挙げている。『小説神髄』と逍遥の実作を読みながら、事実(fact)の探求と虚構(fiction)の必要性との確執、著者特有の言い回しによれば「理論書ばかりか、実作の随所にも(とうぜんより顕著に)露頭するその紛糾にまつわる様態」がつぶさに検討される。さらには逍遥の小説作中人物が「偸聞(たちぎき)」をする場面が繰り返し描かれ、物語を左右するのに注目し、この創作上の工夫が(『小説神髄』で逍遥が批判した)曲亭馬琴のフィクション論「稗史七則」に登場するのみならず、馬琴の代表作『里見八犬伝』の前半部にも頻出することをあばきだす。著者による馬琴作品の分析は、もはや逍遥を論じるための迂回の範囲を超えて独立した評論となっているが、この部分を含め江戸時代のフィクションに関する論述は実に興味深い。
他方で、馬琴から逍遥へと図らずも受け継がれてしまったフィクションの技術と一線を画すような、小説独自の技術が近代日本でいかに発展したかを跡づける作業には、さらなる整理が必要であるかに思える。たとえば著者は「三人称多元」描写が漱石の『道草』や『明暗』でいかに「器械的」に、ぎこちなく用いられているかを示すが、漱石の苦労のうちには、全知の語り手をいかに導入するかという、日本に限らず近代小説全般に関わる困難が問われていたように思える。別の章で著者が詳解する岩野泡鳴の「一元描写」も、方向性こそ異なるが、同様の困難を克服するための技術であったようだ。こうした論点は本書の随所に顔を出しているものの、ついにひとつの歴史として収斂するに至らない。その代わり、とりわけ最後の二つの章において、本書は近代小説史と小説技術との対応を検証するよりも、作家の生の歴史と小説の書かれ方との不思議な符合にドラマを見る方向へと脱線している。それが妙に面白いから困るのだが、しかし技術の歴史を書くという所期の目標を達成するには、あえて言葉と人生、作品と作家には関係がないという唯物論的・言語論的な立場を貫くべきだったかもしれない。
もっとも、これは本書にとってそれほど大きな問題ではない。「技術史」という切り口を見出した上で、これだけの大著を書き上げ、独力で小説史の新しい見方を確立した功績は明らかである。しかし同時に、本書は完結した歴史書ではなく、応答を求める挑発の書として読まれるべきだろう。評者自身の応答は別の機会に記すことにしたいが、日本文学だけでなく、近代小説という古くて厄介な問題に関わっているすべての人にとって、本書を読み通すことは必須であるとのみ、いまは断言しておきたい。(武田将明)