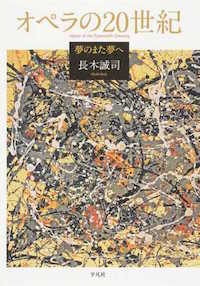| 新刊紹介 | 単著 | 『オペラの20世紀 夢のまた夢へ』 |
|---|
長木誠司(著)
『オペラの20世紀 夢のまた夢へ』
平凡社、2015年10月
「そもそも、ひとは何故にオペラを喜んで観るのか」(513頁、以下本書より)という根本的な問いを常に読者に意識させながら、イタリア、フランス、ドイツ、イギリス、東欧、ロシア、アメリカなど、様々な地域で20世紀に書かれたオペラを渉猟した大著である。19世紀ヨーロッパの芸術・社会制度の産物とされてきたオペラというジャンルが、20世紀においていかに「しぶとく生き続けている」(16頁)のか、その変容のあり方を作品論の積み重ねによって描き出していく。「スタイルの逆流と反撥が絶えず直線的な前衛モダニズムに対抗し続けること、歴史への安直な視線を混乱させるようなスタイルの衝突が絶えず生じること」(10~11頁)と著者が述べるように、地域ごと・時代ごとの論述を通じてその差異や変遷を際立たせる章もあれば、時に地域や時代を超えた大胆な系譜も示唆される。
幾つか例を拾っておこう。第2部では1920年代のヨーロッパにおけるアメリカニズムと並行して、アメリカにおけるヨーロッパ文化としてのオペラの普及を合わせ鏡のように論じる一方で、第3部では「暴力」の表出の変容を主題としてシェーンベルク/ノーノ/ラッヘンマンへ、セクシュアリティを主題としてベルク/シマノフスキ/ブリテン/ヘンツェへと、両大戦間から1970年代以降へと縦断する複数の系譜が描き出される。
また第5部では、オペラ的な「歌」も、筋も崩壊し、歌劇場という枠からも逸脱していくシュトックハウゼン、カーゲル、ベリオ、ケージらの戦後の様々な「オペラ」が扱われる。日本でこうした作品の実演に触れる機会は少ないが、本書の記述を通読した読者にとっては、それぞれの作品が提起する問題の核を掴むのは容易だろう。イタリアにおける「レパートリー・オペラ」と出版との関係を論じた第1章から、「レパートリーと演出の時代(第18章)」を経てケージの《ユーロペラ》──歌手が「レパートリー」とするアリアをチャンス・オペレーションで切り貼りする──が論じられる第24章へとつながる論述により、《ユーロペラ》が持つ批判性が歴史的文脈のなかに位置付けられることで、普段はヴェリズモを好む読者も、ケージを聴く「現代音楽」ファンも、現代演出を楽しむ観客も、それぞれがオペラの20世紀に通低する問題へと必然的に導かれていくことになる。
さらに、本書は20世紀の「オペラ」論であると同時に、極めて19世紀的な(と考えられている)オペラというジャンルからみた「20世紀」論である。映画・ラジオなどの新興メディア、文学・音楽・演劇のモダニズム、ファシズムやユダヤの問題と個々の事例が切り結ぶ関係は、オペラ論にとどまらない多くの問題を提起する。「現代オペラ」という時代区分すら曖昧な呼称のイメージを一新し、オペラの「21世紀」のあり方への問いかけに満ちた必読書である。(白井史人)