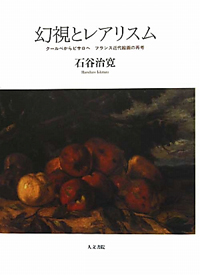| 新刊紹介 | 単著 | 『幻視とレアリスム:クールベからピサロへ フランス近代絵画の再考』 |
|---|
石谷治寛
『幻視とレアリスム:クールベからピサロへ フランス近代絵画の再考』
人文書院、2011年7月
本書で採用されているのは、芸術作品の中に「知覚のモード」の反映を読み込む手法である。
冒頭章では、クールベの自画像に、「自己の身体感覚の確認」という契機が読み取られる。そこに表象されているのは、自らの身体の「不確かさ」であり、それは同一性を欠落させたもので、様々な幻視(幻覚や錯覚、夢という19世紀に注目を集めた現象)を生む。このようなあやうさを信じることが、クールベにとっての「リアリスム」であった、というのが著者の主張である。続いて、画家自身が遺したテクストに内在する言語的メタファーの分析を通じて、同時代の政治・社会状況の経験が絵画作品にいかに反映されたかが明らかにされる。夢の心理学と裸婦表現のエロティシズムが、政情不安とりんごの身体性とが結合する。
続く各章では、労働の場面を描いたピサロらの作品に、「疲労」をめぐる言説をはじめ、当時の労働に関する科学や生理学が反映されていることが説かれる。それはかつての「メランコリー」とは断絶した、新時代の身体観が生み出す概念である。都市における疲労や倦怠という問題は、「リズム」という概念によって装飾や工芸とも接続される。
第6章で展開されるのは、自然美の観照という(芸術においては古典的な)テーマと、当時の科学的知見の結合である。著者は「環境」という言葉の登場をミシュレらの言説から見出し、それがクールベの絵画に直接影響していることを説く。また、印象主義者たちが好んで採用した「連作」形式は、プルードンの労働にまつわるテクストと呼応するものであり、彼ら特有の描画モティーフや筆触とともに、自然が工業の経済的単位へと移行するプロセスを反映しているのだと主張する。
本書の最終章では、19世紀末に現出した都市の祝祭空間(謝肉祭、ドレフュス事件、パリ万博)と、都市景観を描いた絵画に捕捉された群集の姿について、当時の反ユダヤ主義の言説も紐解きつつ、都市に対してメディア論的な分析が施されている。絵画(古典的な芸術の一分野)、映像メディア(当時新進の技術であった映画)、そして様々なテクストを丹念に精査しつつ、著者は19世紀末の都市空間におけるスペクタクルが、人々を巨大な群集へと溶解させつつ、かつまた集団毎の区分や対立を明確化するという、二律背反的な役割を担っていたことを明らかにしてみせる。
この著作の大きな特徴のひとつは、絵画表現における「身振り」への注視、また同時代の美術批評やカリカチュア(いわば通俗的なジャーナリズム)への目配りにある。また、例えば芸術写真と科学写真とが並列的に扱われている点からも分かるように、著者は(永らく美術史学を支配してきた)審美的な価値判断から逃れて、縦横に同時代の資料を渉猟しつつ分析を進めてゆく。しかし本書の最大の特性は、芸術作品の中に同時代の知覚のモードの体現を見出し、知覚にまつわる生理学の文献にその論拠を求めるという分析手法にあるだろう。ここには、著者も邦訳に携わったジョナサン・クレーリーの影響が伺われるが、本書はさらに進んで、個々の作家や作品に肉薄した分析を展開している。この手法により本書は、前時代とはまったく異なる、19世紀特有の知覚のモードを切り取ることに成功しているであろう。(小澤京子)