アリサ・ベルゲルの作品上映とトーク──民族/移動/戦争から考えるアート
■開催まで
2024年7月21日(日)、同志社大学今出川キャンパスで、来日中のアーティスト、アリサ・ベルゲル(Alisa Berger)さんを招いて、最新作《RAPTURE I-VISIT》の上映と、トークを行った(以下、敬称略)。
 アリサ・ベルゲル作品上映@同志社大学、2024年7月21日
アリサ・ベルゲル作品上映@同志社大学、2024年7月21日
アリサ・ベルゲルは、1987年にロシア連邦ダゲスタン共和国のマハチカラで生まれ、ウクライナのリヴィウに一家で移住。ドイツで教育を受けた。その後、ケルンのメディア・アート・アカデミー (KHM) とコロンビア国立大学ボゴタ校で映画と美術を学び、現在はフランスのル・フレノワ国立現代芸術スタジオに所属。母は高麗系、父はユダヤ系の家系を持つアーティストである。
 Alisa Berger, portrait ©Ravi Sejk
Alisa Berger, portrait ©Ravi Sejk
私がアリサ・ベルゲルの作品を初めて見たのは、イベントのわずか3週間前、東京都美術館で開催していた「ずれはからずもぶれ」展でのことだった。《RAPTURE I-VISIT》の映像に映るのはウクライナ出身の友人のマルコである。ウクライナのドンバス地方でのロシアとの戦争から避難するため国を出たマルコは、母の死にも立ち会えず実家を受け継ぐこともできない。その現実へのアクションとして、マルコをVR技術を使って仮想的に彼の家に帰すプロジェクトの《RAPTURE I-VISIT》には、現代アートの課題と可能性が詰まっていると感じた。テクニカルな興味に引きずられて使用されることの多いVRは、本作品においては、戦時下に置かれた人々の過酷な現状を、遠く離れた観客にも追体験させる優れたメディアとして機能していた。
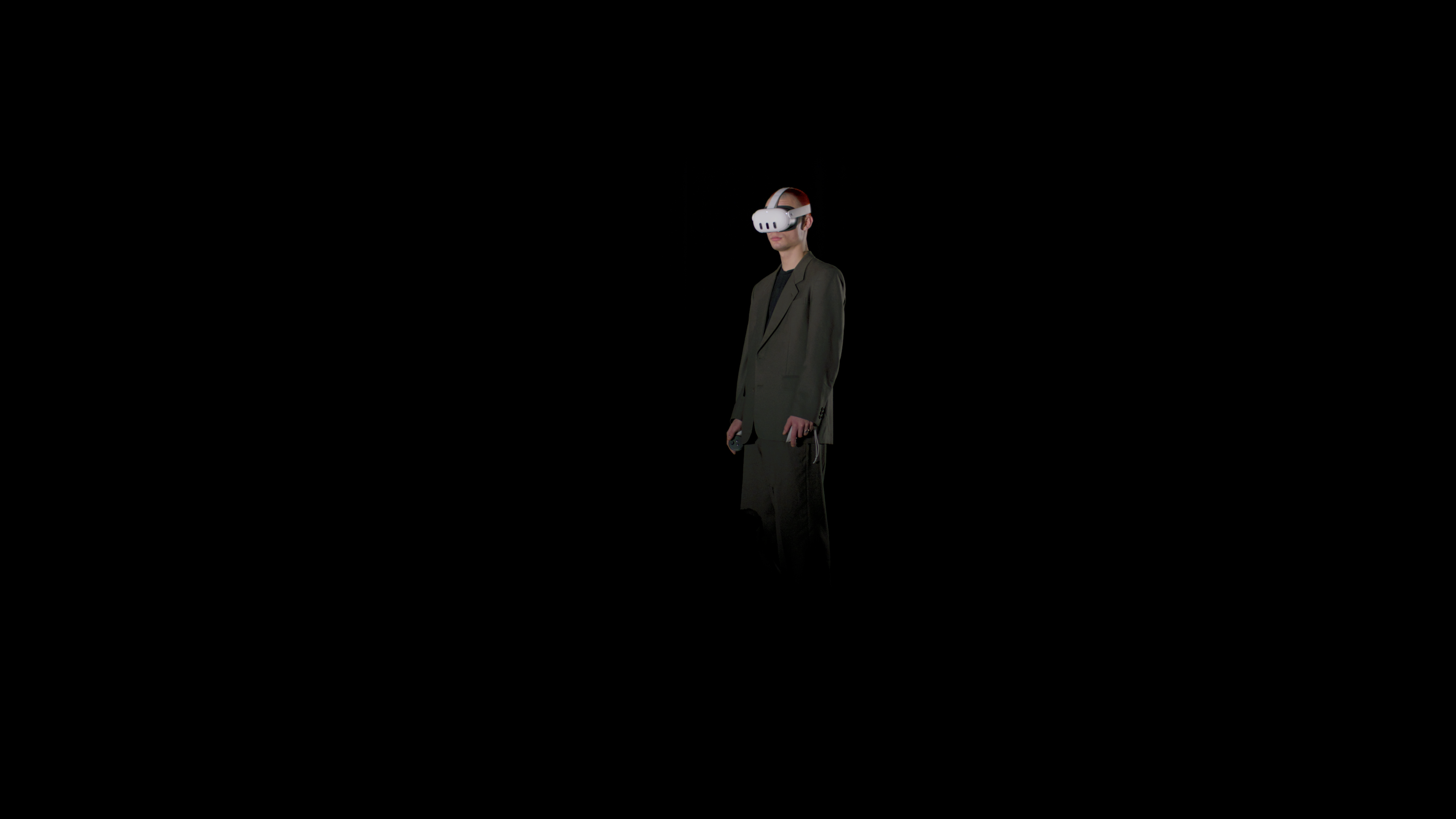 RAPTURE I – VISIT, 2024 ©Alisa Berger
RAPTURE I – VISIT, 2024 ©Alisa Berger
ところが、「ずれはからずもぶれ」展をキュレーションしたユミソンによれば、「可哀そうなマルコをお家に返してあげる話」くらいにしか、多くの人には受けとめられていないという。展覧会場で作家本人と立ち話をした私は、ベルゲルの作品をもっと深く知りたくなり、京都でシンポジウムを開くことにした。
7月21日は、宣伝が行き渡っていなかったにも関わらず、東京からの参加者もあり、予想を超えた大勢の方たちが同志社大学の教室に来て下さった。ディアスポラの文化に関心を持つ方から、朝鮮史、映画史、ロシア文化など、多岐にわたる研究者や市民たちが集まった。ベルゲルの複雑な内容のトークと議論の通訳は、金美穂(国際連帯/正義オーガナイザー、同志社大学博士後期課程)にお願いした。
■企画説明と「移民」表象への疑問
当日は、午後3時にまず北原の趣旨説明と、ユミソンによる「ずれはからずもぶれ」展の概要紹介から始まった。その後、《RAPTURE I-VISIT》(約20分)の上映、アリサ・ベルゲルのトークと質疑応答を行って、研究会は6時前に終了した。
人文科学や社会科学の重要な課題である人の移動について扱う美術作品は、国際展では数多く見られる一方、日本国内ではいまだに主要な潮流とはなっていない。「定住」を正常な状態とみなし、「移動」を管理の対象として扱うことは、伊豫谷登士翁によって鋭く批判されてから久しいが、日本の美術の学術分野における「移動」の視点からの研究は、カルチュラル・スタディーズやポストコロニアル理論の影響を大きく受けた他の視覚表象分析(映画や大衆文化研究)や文学研究に比べて、著しく遅れていると言える。そのような状況においてアリサ・ベルゲルの映像作品は、「移動/移民」を相変わらず他人事とみなし従来の単純な二元法に還元することを拒む、示唆に富むものだった。
趣旨説明で北原は、アリサ・ベルゲルの作品と背景を理解する一助として、母方のルーツである「高麗人(コリョサラム)」の歴史的な大きな移動についても、地図を用いて説明した。1937年7月、日中戦争勃発直後、スターリン体制下のソ連政府は、極東ロシアで暮らしていた朝鮮人たち約17万人を、カザフスタンやウズベキスタンなどの中央アジアに強制移住させた。日ソ関係が緊張するなかで、極東ロシアに多くの朝鮮人が住んでいることが、日本の侵略の口実になることを恐れたからである。実際、教員だったベルゲルの曽祖父は、カザフスタンに追放されたのちスパイの疑いで射殺されたという。
その後、一家が移住したダゲスタン共和国の首都、マハチカラで、アリサの母はユダヤ系の父と出会い、アリサが生まれた。さらに生後1歳でのウクライナのリヴィウへの引っ越し。母方の祖先たちのこの大きな移動の背景に日本の植民地支配の歴史があったことは事実である。彼女は、父方の祖先も含めて両親のルーツをたどる旅を重ね、いくつもの映像作品にした。
■「ずれはからずもぶれ」展
続いてシンポジウムでは、ユミソンによる「ずれはからずもぶれ」展の紹介があった。2024年6月10日から30日まで、都美セレクショングループ展2024のひとつとして開催された同展には、アリサ・ベルゲルら7名が参加した。
「第二次世界大戦中に米国の日系人収容所に収容されていた曽祖父と自分を重ねる近藤愛助、ナチスドイツに連行されドイツ各地の収容所を巡ったユダヤ人の母の足跡を辿るイシャイ・ガルバッシュ、日帝時代に朝鮮を逃れた母とユダヤ系の父のファミリーツリーを追うアリサ・ベルゲル、ユミソンの父は北と南で揺れ動く韓国のアイデンティティの確立の中で大虐殺の現場に遭遇し、ハ・ジョンナムは嫁入りとして日本から韓国へと渡った。イレン・トクは知識の集積である本の中を物理的に旅をする人々を描く。吉川浩満は膨大な書物の中の知識を横断しながら言葉をつむぐ。」(同展HP)
キュレーターでありアーティストでもあるユミソンが出品した作品のひとつである《ホームレスの振る舞いは「移民」のそれ(美術手帖『「移民」の美術』より》は、メジャーな美術雑誌に潜む、「移民と難民と肉体労働者と不法滞在者をごっちゃに」した「移民」への眼差しに対する異議申し立てである。ユミソンは、それらの問題含みの言葉を工業用ミシンを使って刺繍し、ブックカバーに仕立てた。
イベントではここまでがイントロダクションで、いよいよ作品上映とトークに入った。
■作品上映《RAPTURE I-VISIT》とトーク
《RAPTURE I-VISIT》(2024、4Kステレオサウンドカラー、19’22”)は、日本では東京都美術館での初公開に続き、同志社大学で2回目の上映となった。
映像に登場するのは、ヴォーグダンサーのマルコである。14才のとき、ウクライナとロシアの国境のドンバスで戦争が始まり、18才で徴兵を逃れるため、国を出た。それ以来、帰っていない。
「マルコが実家を相続するためには、ロシアに入国する必要があるが、それは直ちに徴兵され、故郷であるウクライナを敵にして戦わされることになる。もし、ドンバスに戻らず、実家を相続しなければ、家は政府に奪われることになる。それは、ロシアによって占領され破壊された、ウクライナの全ての領土に起きていることでもある。」(作品解説)
マルコがドンバスに帰れないもうひとつの理由に、性的マイノリティであることが挙げられる。ホモフォビアの強いドンバスと、ロシアでの同性愛宣伝禁止法の制定やLGBT活動の違法化が追い打ちをかける。そして、マルコは今は24才。2018年以来、初めて家をVRで訪れることになる。
作品のタイトル「RAPTURE」は、神学の「ラプチャー(携挙)」の概念を拡張し、場所の変化を表すという。「比喩的には、それは酩酊、夢、瞑想、または恍惚状態に見られる「精神的距離」を表す」(作品解説)。実家の様子を立体的に再現するために、ベルゲルは、業者に依頼して、住む人のいないドンバスの実家の内部を何百枚もの写真にした。それらの写真は3Dスキャンによって再現され、マルコと観客はドンバスの実家のアパートを間近に見るのである。(当日参加したロシア文化研究者によれば、実家のアパートは、フルシチョフカというソ連政府が推奨して建てた安価な集合住宅であり、行ったことがなくても間取りも手に取るようにわかるそうだ。)
「Unforeseen Deviations(予期しない逸脱)」と題したトークで、アリサ・ベルゲルは、《RAPTURE I-VISIT》の説明だけでなく、これまでの作品についても映像を見せながら解説してくれた。
例えば、代表作のひとつ《Three Borders》(2017、55min)は、ユダヤ系の父親と、日本の植民地下で朝鮮から逃れた先祖をもつ高麗系の母親双方の三世代にわたる家族の歴史をたどった映像作品である。ゲーテ・インスティトゥート・モスクワが「国境」を主題として委託したインスタレーションの一部として制作された。視覚イメージの大半は自分の家族のオリジナルの写真を用い、ベルゲルの母の描いた水彩画も加えた。だが、≪THREE BORDERS≫は、いわゆるドキュメンタリーではない。一人称語りが混在し、ボイスオーバーやマジカルリアリズムのテクニックを用いた、極めて詩的な実験映像である。その特徴は高麗人の歴史や現在の姿を映したベルゲルの《K-SARAM: TALE OF THE PIG HEAD》(2021)にも共通する。
さて、トークのなかで浮かび上がったのは、「民族/移動/戦争」に加えて、「身体」というキーワードだった。アリサ・ベルゲルは「からだは、自然と直結する証」であり、「テクノロジーに支配されたからだは弱い」と言う。最近は日本の舞踏に関心を持ち、日本に滞在して《INVISIBLE PEOPLE》(2023)を制作している。
最後に、ベルゲルは公開前の次作品《RAPTURE II- PORTAL》も少し見せてくれた。画面に映るのは、ウクライナの破壊された街。その廃墟をダンスの力で再生させるかのように踊るマルコのクィアなシーンが鮮烈だった。「からだ」にどんな希望を見ることができるのだろうか。
 RAPTURE II – Portal, 2024 ©Alisa Berger
RAPTURE II – Portal, 2024 ©Alisa Berger
質疑応答は映像満載のトークが長引いたため、時間がなくなってしまった。翌日から済州島にシオモニ[夫の母]の墓を探しに旅立つという日本人の参加者が、《Three Borders》で映し出されたロシアで暮らす朝鮮人たちのチェサや墓参りのシーンに触れて感想を述べ、日本との身近な接点に全体テーマを一気に引き戻す締めくくりとなった。
[追記] 本稿を書く上でアリサに連絡を取ったところ、ベルリン国際映画祭2025のフォーラム・エクスパンデッド部門で、《RAPTURE》の上映が決まったと聞いた。
------
アリサ・ベルゲルの作品上映とトークイベントを開催するにあたって、同志社大学の菅野優香先生、秋林こずえ先生、佐藤守弘先生ら多くの友人たちに助けられました。あらためてお礼申し上げます。助成を受けた科研費:「美術における「移動」の表現と思想」(科研・基盤c 代表:北原恵)