研究発表2
日時:2024年11月23日(土・祝)13:00-15:00
- マイケル・フリードの芸術理論における恐怖と演劇性/茶圓彩(京都大学)
- クレメント・グリーンバーグ「アヴァンギャルドとキッチュ」再考──ヴァルター・ベンヤミンの政治の美学化の観点を軸に/大澤慶久(東京藝術大学)
- フィクション鑑賞における共感とは何か──ナナイの代理経験理論の検討/岡田進之介(東京大学)
【司会】加治屋健司(東京大学)
本研究発表では、アメリカの美術批評家に関する発表が2つ、分析美学に関する発表が1つ行われた。各研究発表と質疑応答の概要を報告する。
最初の発表者の茶圓彩氏が考察の対象としたのは、アメリカの美術批評家、美術史家であるマイケル・フリードである。フリードは、1967年に発表した論考「芸術と客体性」でミニマル・アート批判を行い、その際、ミニマル・アートの特徴のひとつに「演劇性」を挙げた。フリードの演劇性については、ロバート・スミッソン、パメラ・M・リー、クリスタ・ノエル・ロビンスによる考察・研究がある。それらはいずれも、ミニマル・アートのもつ終わりのなさに対するフリードの恐怖や不安を指摘しているが、フリードと交流があり影響を与えた哲学者のスタンリー・カヴェルの議論との関係が十分考察されてこなかった。茶圓氏の発表は、演劇性に関する議論を含むカヴェルの「愛の回避:『リア王』を読む」を参照しつつ、フリードの演劇性の議論における恐怖の源泉を考察したものである。カヴェルによれば、舞台に生まれるのは虚構世界である以上、演劇の観客による世界認識には終わりがない。カヴェルはその世界を承認することで終わりのなさを克服しようとするが、フリードはその終わりのなさを承認せずに、それに対して恥や無力さを感じるために、恐怖や不安を感じたのだと茶圓氏は論じた。

大澤慶久氏の発表は、アメリカの美術批評家クレメント・グリーンバーグの「アヴァンギャルドとキッチュ」を再読するものである。大澤氏は、この論考は全体主義に対する批判の中で生まれたものであり、ナチス批判の文献の翻訳活動や、発表媒体である『パーティザン・レヴュー』の方針と密接に関係していたと指摘する。グリーンバーグはこの論考でアヴァンギャルドの芸術は「反省」を促すのに対して、キッチュは即時的に享受されると述べ、後者がファシズムのプロパガンダの有効な手段とみなした点に大澤氏は注目する。他方、ヴァルター・ベンヤミンは、「複製技術時代の芸術作品」において、複製技術の発達によってアウラが消滅すると述べ、それまでの芸術が精神の集中と沈潜を求めたのに対して、映画などの複製技術による芸術は散漫な大衆に気散じの態度を生み出すと論じた。大澤氏は、気散じは新しい可能性をもつ一方で、政治による美学化の手段として、全体主義体制による大衆動員にも繋がりうる点で、グリーンバーグのキッチュと共通があると指摘した。最後に、キッチュや気散じ的な知覚様式の問題は、現代のソーシャル・メディアにおける即時的な反応を考察するうえで重要な視座を提供していると述べて発表を終えた。

岡田進之介氏の発表は、分析美学の観点から、小説や映画演劇などのフィクション作品の鑑賞における作中の登場人物(キャラクター)に対する共感(キャラクター参与)を考察したものである。岡田氏によれば、先行研究はキャラクター参与を鑑賞者と登場人物の同一化と説明してきた。それに対して、登場人物へのシンパシーや状況への同化とする解釈が提案されたが、岡田氏は、それらの解釈でも説明できない事例があり、説明が不十分であると指摘する。そこで、岡田氏は分析美学者のベンス・ナナイの「代理経験」という理論がキャラクター参与を適切に説明できると述べる。代理経験とは「他者本位的な実践的利害が私たちの経験を彩る経験」であり、この観点から見れば、シンパシーのないキャラクター参与も説明できるし、同化に対する曖昧な記述も克服できるとする。だが、岡田氏は、ナナイの議論には参与の対象や参与における情動経験といった問題が残されているとする。そこで岡田氏は、参与の対象とは、作品がその実践的利害の情報を相対的に最も開示しているキャラクターであり、私たちは、作中の対象や出来事の価値的性質に注意を向けることで、それを表象する情動が喚起されると論じた。岡田氏は、キャラクター参与とは異なる感情的な参与に物語参与があるとして、フィクションに対する2つの感情的参与があると指摘して発表を終えた。
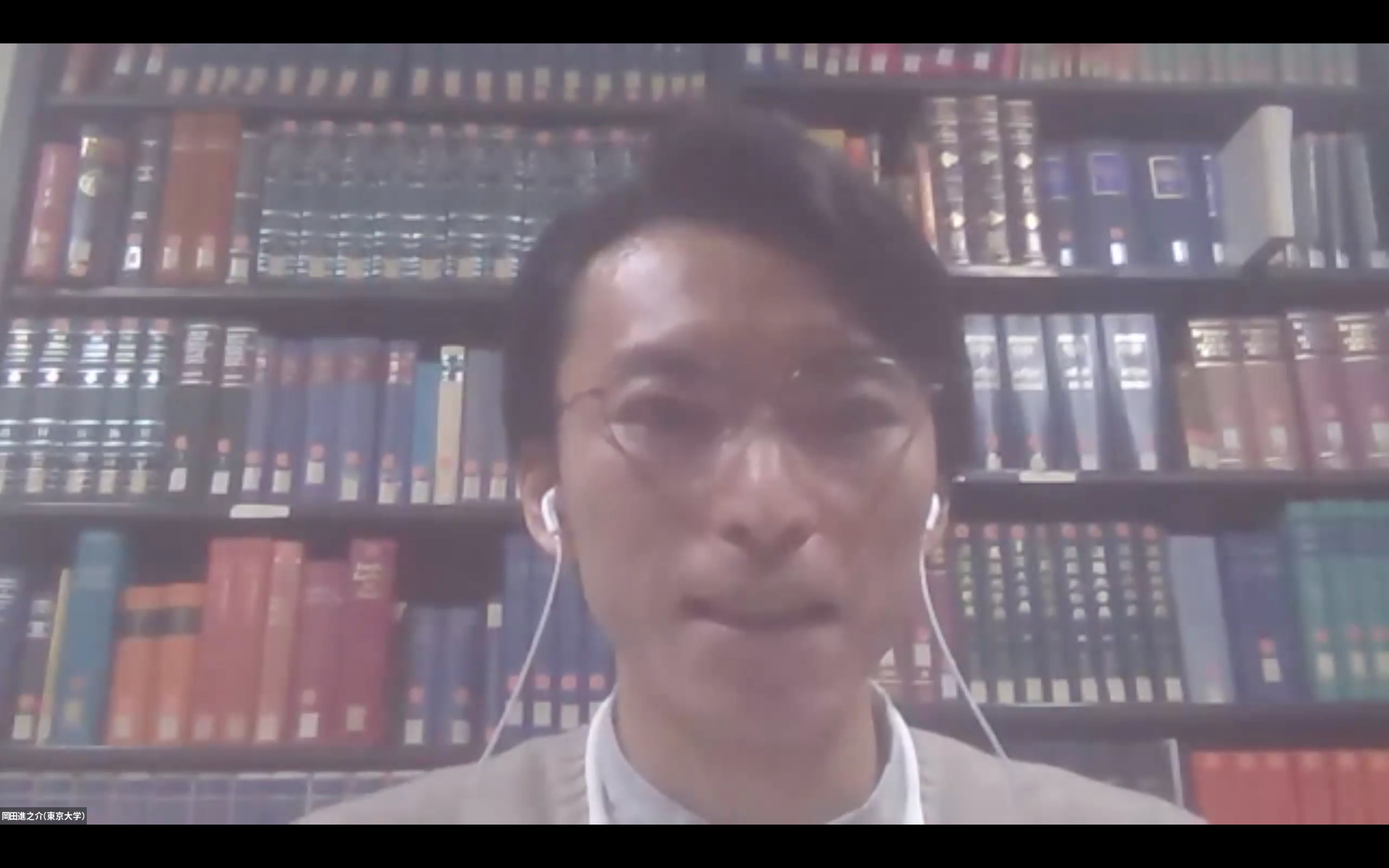
質疑応答では、茶圓氏に対して、フリードの恐怖や不安は個人の実存の問題なのか、それともマッカーシズムや、スーザン・ソンタグが論じたような同時代の大衆文化との関わりで生じた歴史的なものなのかという質問があった。茶圓氏は、フリードの恐怖や不安の源泉を考察することが本発表の目的であり、これから検討していきたいと述べた。大澤氏には、グリーンバーグとベンヤミンの関係に関する先行研究はあるのか、グリーンバーグとアドルノの関係はどうだったのかという質問があった。大澤氏はこれから先行研究を参照したいと述べる一方、今回は同時代の議論を考察の対象としたのでアドルノは考察から除外したと述べた。従来肯定的に論じられてきたベンヤミンの「気散じ」概念をキッチュと結び付けることに対する指摘もあった。岡田氏に対しては、物語参与がキャラクター参与の前提となっているのではないかとする指摘があったが、両者は情動の対象が異なるので概念的に区別されると応じた。

3つの発表のうち、2つはアメリカの美術評論家を論じたもので、もう一つは分析美学の発表だったが、いずれの発表も作品の鑑賞経験に関するもので、共通する問題関心があった。研究発表の後に20分ほどの懇談時間が設けられた。そこではグリーンバーグやフリードの時間性の概念や、グリーンバーグの反省の概念についても意見が交わされ、今後の研究の発展を大いに感じさせる議論が行われた。
マイケル・フリードの芸術理論における恐怖と演劇性/茶圓彩(京都大学)
本発表では、アメリカの美術批評家、美術史家並びに詩人であるマイケル・フリード(Michael Fried: 1939-)の論考「芸術と客体性」(1967)で提示された概念である「演劇性」の内実を明らかにするものである。
「芸術と客体性」は、フリードが1960年代から1970年代にかけてモダニズム美術批評家として活躍した時期に執筆され、今日ではフリードの代名詞となる記念碑的論考である。また、「演劇性」とは、ミニマル・アート(フリードの言葉に言い換えればリテラリズム)に対して人を媒介にして作品が成り立つという独自の意味づけを施した術語である。
ただ、この論考の発表後、ロバート・スミッソン(1967, 1968)や、パメラ・M・リー(2006)、クリスタ・ノエル・ロビンス(2018)を通じて、フリードの「演劇性」と名のつく状況や作品への態度はその作品がもたらす絶え間なく拡張されていく空間・時間・意味に対するフリードの恐怖の現れであると言及されてきた。しかしながら、これらの先行研究では、フリードがこの概念と関連づけるカヴェルの著作物との検討があまり精緻にはなされておらず、この概念がどのような思想のもとで形成されたのかが曖昧なままになっている。
そこで、本発表では上記の先行研究を基軸とし、この恐怖が先行研究において問題となった背景を詳らかにすると同時に、カヴェルの著作物の分析を踏まえてこの恐怖の源泉は、作品を通じて経験される鑑賞者の孤独にあることを結論づける。
クレメント・グリーンバーグ「アヴァンギャルドとキッチュ」再考──ヴァルター・ベンヤミンの政治の美学化の観点を軸に/大澤慶久(東京藝術大学)
本発表では、アメリカの美術批評家クレメント・グリーンバーグの1939年の高名な評論「アヴァンギャルドとキッチュ」に従来の解釈とは異なる視点から光を当て、それが20世紀中頃の「政治の美学化」と、グリーンバーグ自身の美学的基盤に基づく独自の論理として展開されたものであることを明らかにする。
これまでの解釈では、この評論はアヴァンギャルドを高級文化、大衆文化を低級文化とする対立軸において、グリーンバーグがアヴァンギャルドの自律性を擁護しエリート主義的姿勢にあるという見方が主流であった。しかしこの評論はファシズムの台頭期にアヴァンギャルド芸術の危機的状況下で書かれたものであるという点は見過ごされがちである。それゆえ『パーティザン・レヴュー』の当時の誌面の方向性や、ヴァルター・ベンヤミンが1936年に発表した「複製技術時代の芸術作品」における「政治の美学化」の文脈の中でこの評論を再考する必要がある。そこで本発表ではグリーンバーグが同評論で提示している「反省」という美学的概念に着目し、ベンヤミンの「政治の美学化」の論理を見据えつつ、アヴァンギャルドが促す「反省」の機能と、「反省」を要さない即時的な快の享受を可能にするキッチュの性質を検証する。以上の考察を通じて本発表は、この評論を政治的・美学的文脈で捉え直し、さらには現代におけるソーシャルメディアとポピュリズムの観点からその現代的意義についても考察を加えたい。
フィクション鑑賞における共感とは何か──ナナイの代理経験理論の検討/岡田進之介(東京大学)
小説や映画、演劇などのフィクション作品の鑑賞において私たちは登場人物に「共感」するとされ、またそれがフィクション鑑賞の重要な要素とされることもある。本発表は現代の美学的研究を参照し、そのような共感の本性について検討する。
英米圏の現代美学でフィクション鑑賞における共感は、登場人物と鑑賞者が情動を共有する「同一化」として定式化されてきた。しかしノエル・キャロルなどは、登場人物が作中の対象を情動の対象とするのに対し、鑑賞者は人物を含めた状況全体を対象とするため、同一化は成立し得ないと主張する。近年では同一化を一種の想像的活動とすることでそれを擁護する論者もいるが、そこでの想像概念は問題含みである。
本発表では同一化とは異なる仕方で共感を分析したベンス・ナナイの代理経験理論を、具体例に即して検討する。ナナイはAesthetics as Philosophy of Perception(2018)の中で、共感として名指される現象は、鑑賞者が主人公の利害に基づき特定の作品内容に注意を集中させることだとする。この理論は想像概念に頼らずに共感を説明できる点で優れる一方、①どの登場人物が共感の対象になるのか②注意の集中と情動の関係はどのようなものか、などの点で説明が不十分である。本発表はこの二つの点を明確にすることで共感の本性を明らかにし、作品批評のための新たな理論構築に貢献することを目指す。