Post-choreography Jérôme Bel’s Choreography and Movement in Malfunction
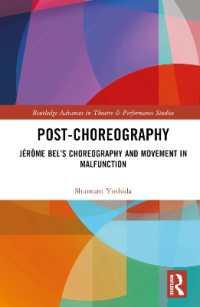
本書は、現代のコンテンポラリーダンスにおける最重要の作家の1人である振付家ジェローム・ベルの創作および上演における、ダンサーの身体から「誤動」が引き出される「振付」に着目し、それを「ポスト・コレオグラフィ」として位置付けるものである。
誕生以来、現代に至るまでのおよそ3世紀が経過している「コレオグラフィ=振付」という概念は、絶えず変容し続けていると言われる。そのような「コレオグラフィ」の歴史的系譜に関する研究領域において、本書はこの概念の最新状況を示して得ているという点に大きな意義がある。そして、本書ではダンスとコレオグラフィの歴史において、とりわけ20世紀の実践者たちが直面した問題に対する一つの解法も示されている。それは、振付家という作家の権威性とそれに対するダンサーの従属性である。
本書の意義をより明確に示すために、「コレオグラフィ」という概念について補足的に触れておきたい。この概念はルイ14世治世下の1700年に誕生し、当時においてすでに、宮廷人と兵士の身体の動きを細かく制御する政治的技術という性質を持っていた。振付とは他者の身体に対してきわめて権力的な行為であり、ミシェル・フーコーに倣うならば従順な身体を作り上げる「ミクロ・ポリティクス」の一環を成す近代的な技術である。つまりコレオグラフィが対象とするダンサーの身体は常に既に何らかの権力に貫かれているが、本書は、「ポスト・コレオグラフィ」という概念を提案することで、踊る身体を権力から解放するというダンスのアポリアに対してラディカルに挑戦する。
本書の構成は以下のとおりである。第1章では、ポスト・コレオグラフィの前提を明らかにするための予備的な議論が展開される。まず、欧米のダンスの展開を踏まえ、身体を記号化する振付の歴史的系譜がたどられ、次に、振付の方法論からの逸脱として身体のノイズを発生させる歴史的なアプローチが確認される。興味深いのは、西洋の振付の歴史からの解放に見えたカニンガムの偶然性による振付もまた最終的には振付家の独裁へと収斂していったという指摘である。これは振付家の権限から逸脱する身体を評価しようとする著者が「ポスト・コレオグラフィ」という概念を別に立てなくてはならかった理由でもある。
第2章では、パリ近郊の住民を対象に実施されたベルのワークショップ『Atelier Danse et Voix』(2014年)を皮切りに、ブリュッセル、ヴェネツィア、ミュンヘンで実施されたアマチュアとプロフェッショナルのダンサーを対象としたワークショップについての事例研究が示される。ベルの創作において重要な身体とは、ダンスの高度な技術を身につけたプロフェッショナルのそれではなく、アマチュアの身体であることが確認される。
第3章では、『Atelier Danse et Voix』の延長上で創作・発表された『Gala』(2015年)のパリ、日本、タイでの公演の比較研究が行われる。この作品では「振付」は振付家のベルではなく大半はダンスのアマチュアである各々の参加者に委任される。『Gala』のパリ公演は、長期のワークショップを共に過ごす中で、参加者たちがイニシアティブをもって「ポスト・コレオグラフィ」を協働的に実現し得た稀な例として位置付けられるが、本書における重要な指摘は、この作品がその後、一種のパッケージ化を経た日本やタイでの公演では、肯定されるべき参加者の誤動や集合的知識の形成など、この作品を支えていた重要な要素が失われていったということである。振付家が不在であった日本、タイ公演において逆説的に振付家の権威が作動してしまったという興味深い観察結果が報告される。
第4章では、参加者のパフォーマンスにおける機能不全の動きが再検討される。ベルとあわせて従来のコンテンポラリーダンスのコレオグラフィのシステムを破壊した事例として、トラジャル・ハレルとマイケル・クリエンの作品が例に挙げられ、参加者の身体が「振付」という管理から逃れ、身体のノイズを発生させる様態について述べられている。
本書の優れた点は、著者本人がリサーチ・アシスタントとしてまた出演者としておよそ2年間ジェローム・ベルの創作現場に関わり、その参与観察の経験が研究に十分に活かされていることである。振付家ベルとダンサーとの関係性に対するつぶさな観察は、振付家の権限を減少させ、出演者に主体性や権限を付与する「ポスト・コレオグラフィ」という新たなモデルを説得力あるものにしている。また『Gala』の事例研究において述べられたように、同一の作品でも「ポスト・コレオグラフィ」がうまく機能する場合としない場合があることを発見したことは大きな成果だと思われる。このような上演の性質の差異への着眼は、著者が継続的に現場に関わっていたから可能になったことであろう。
「ポスト・コレオグラフィ」から現れるある種の理想のダンスは、創作の環境や条件の些細な変化で一瞬で消えてしまうエフェメラルな生成物なのかもしれない。それは、芸術のマーケットとも結びついて機能する「作家」や「作品」というパラダイムに引き寄せられた瞬間に消え去ってしまう。逆説的であるが、芸術という制度の中で、私たちは芸術的探究の最上の到達点を常に見られるわけではない。しかし、本書は、ダンス史の中で導出された一つの理想的な身体/ダンスの生成と消失の現場を捉え、学術的な知の形としてその痕跡を残し得た稀有な研究成果である。ダンスおよびパフォーマンス研究に従事する者にとって大きな気づきを与えてくれる書と言えるだろう。
(越智雄磨)