第二次世界大戦期イギリスのラジオと二つの戦争文化:BBC、プロパガンダ、モダニズム(慶應義塾大学法学研究会叢書 別冊20)
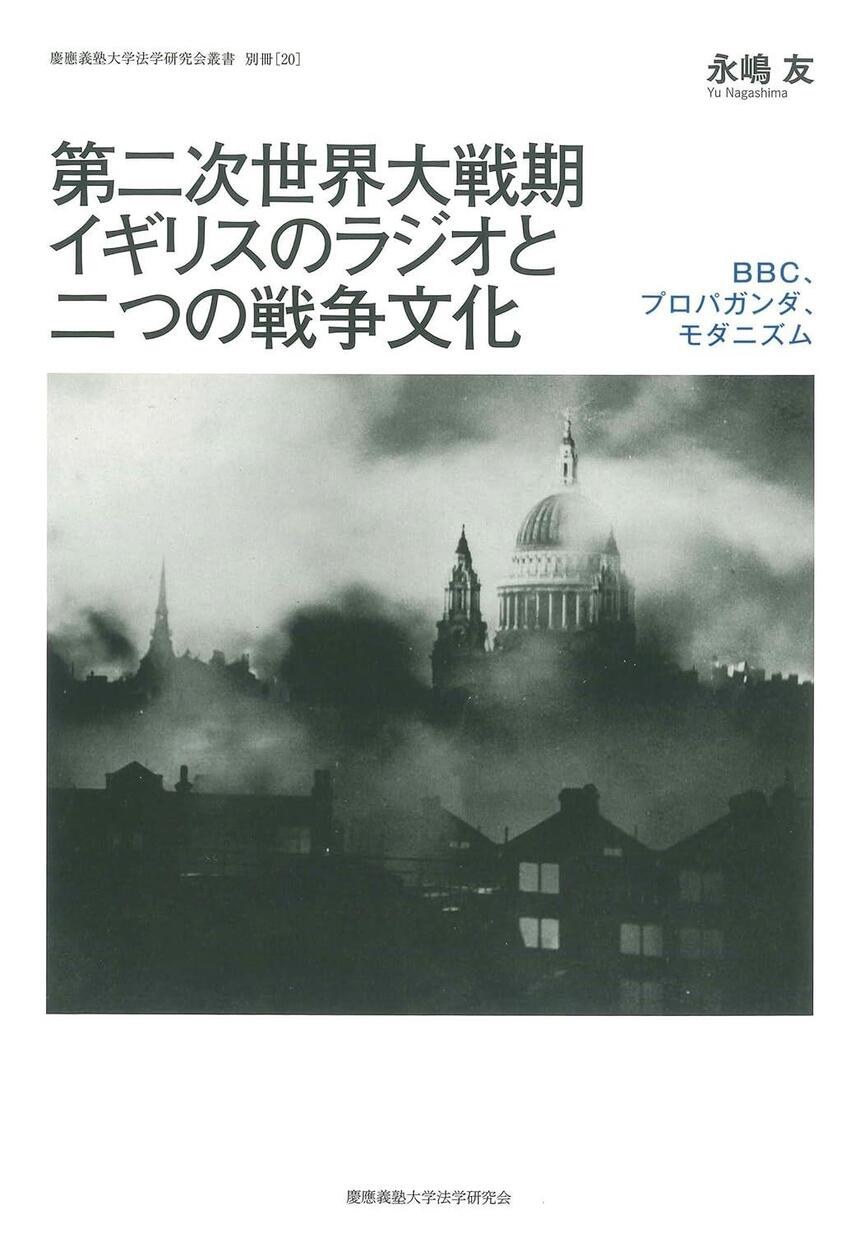
本書は第二次世界大戦期のBBCラジオ作品を詳細に分析し、プロパガンダとモダニズムの混交という特異な形式を描き出すものである。この試みはBBC文書保管センターの膨大な資料調査に裏打ちされており、ラジオ制作関係者の試行錯誤や聴衆の声を丹念に拾い上げている。そこから、戦時下のラジオ放送による共同体感覚の醸成と、それに対する人々の多様な反応が、具体性かつ説得力をもって提示される。著者は考察において、〈公式戦争文化〉と〈非公式戦争文化〉という二つの枠組みを掲げている。ラジオ放送は、〈公式文化〉として政府の意向を反映しつつ、そこから取りこぼされる兵士や市民の不安・苦痛の声を〈非公式文化〉として、聴取者の共感を模索した。この両文化の接近やせめぎ合いに関して本書が加えている考察は、第二次世界大戦期イギリスの歴史研究で軽視されてきた、ラジオ作品のプロパガンダ的側面を浮かび上がらせる。ラジオは広く公共に向けた放送でありながら、個人への語りかけとしても受け取られうるメディアである。大戦後、こうしたパブリック/プライベートに跨る特徴を踏まえ、サミュエル・ベケットやディラン・トマスによる番組をはじめ、モダニズムの潮流にあるラジオ作品が盛んに創作されることになる。この先取りともいえる表現―内的な声、幽霊の声、超自然的な声―を戦時中のラジオ放送に見出したことが、本書の特筆すべき点だろう。
本書は第一章から第四章を通し、それぞれ国内戦線、海事、敵国、国際関係といった主題ごとに、ラジオ放送の中でもとりわけラジオドラマとラジオフィーチャー(ノンフィクション形式のラジオ番組)を論じている。著者がしばしば言及する「ラジオ向き(レイディオジェニック)」という語は、ラジオならではの特質を生かすことで「音声や放送の原点」(p.34)を表象しうる特徴を指す。各章では繰り返し、戦争による犠牲者を死者や幽霊の声として登場させるラジオ作品が取り上げられ、ラジオの特質にふさわしい音声とモダニズム的手法を通じて描写される「人びとの意識、夢、記憶、内なる声」(p. 265)といった主題の重なりに光が当てられる。とりわけ第二章は海事の主題をめぐり、音声の特殊効果やエコーを用いつつ、船乗りと霊的なものの遭遇を描く小説とその翻案ラジオドラマを分析する。著者は、暗闇と静けさが支配する海上の船がレイディオジェニックであり、「そのような環境で船乗りはラジオ聴取者のようになる」(p.98)ことを指摘する。こうした海とラジオの親和性からは、初期の無線技術が船同士の連絡手段として発達し、どこかわからない場所にいる姿の見えない者との交流が、数々の海上の幽霊譚を生み出したことを筆者は想起させられた。当時の心霊主義とメディア・テクノロジーの交錯の歴史を映し出すという点で、本章は非常に興味深かった。
BBCは世界でも先駆けてラジオ放送を開始した局の一つであり、初期からの最新技術や実験的放送の積極的な模索はラジオ研究において主要な考察対象である。しかしながら、イギリスの放送文化、とりわけラジオドラマやフィーチャーに焦点を当てる研究や翻訳書は本邦においてほとんど紹介されていない。本書は国内でのイギリス放送文化研究の端緒を開くと同時に、アーカイヴ調査の活用やラジオにおける政治的手段と芸術の混交を描き出したという点において、ラジオ研究のさらなる広がりをみせるものであろう。
(朴夏辰)