問いが世界をつくりだす:メルロ゠ポンティ 曖昧な世界の存在論
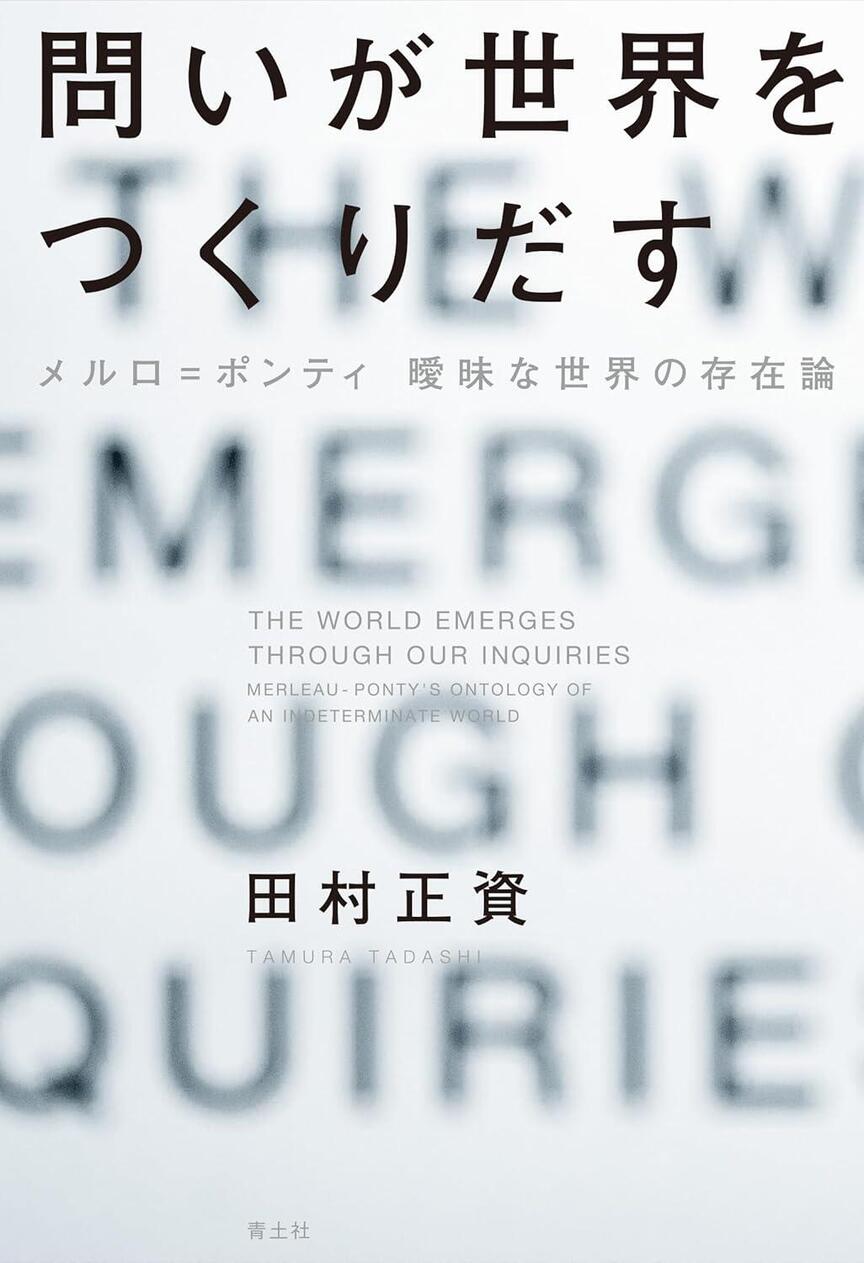
本書の主たる目的は、フランスの現象学者モーリス・メルロ゠ポンティが晩年に掲げたあるテーゼの解明である。彼の未完の遺著『見えるものと見えないもの』(1964)にあるそのテーゼはこう表現されている──「実在する世界は試問的な様態で存在する」(本書16頁より再引用)。ここから私たちが何を得られるかを明らかにするという目標に向けて、本書は、メルロ゠ポンティの前期の著書をも視野に収めながら議論を着実に進めてゆく。
本書の序論に先立つ「はじめに」は、哲学に慣れ親しんでいない読者にも本書の問題意識を伝えることを期したものであり、これ自体がひとつの名文である。以下のリンク先で公開されているので、関心のある方には一読をお勧めする。https://note.com/t_interrogatif/n/ncd4a6f3d6185
他方で「はじめに」に続く本書の本体は、学術的であるばかりでなく、ほぼ一貫してストイックである。私にとっては本体の硬派な行論こそ本書の美点なのだが、もしかすると、「はじめに」に誘惑された読者は本体の内容の難しさに面食らってしまうかもしれない。私としてはここで、本書をなるべくわかりやすく要約するために、本書では取り上げられていない映画『ロッキー』(1976)の一場面を引きあいに出そうと思う。
『ロッキー』に関してもっとも有名なのは、「ロッキーのテーマ」が劇伴として流れるトレーニング・シークェンスである。そのなかの一場面において、主人公ロッキー・バルボアがフィラデルフィアの南9番通りをランニングしていると、道端の男性からいきなり、差し入れとしてオレンジを投げ渡される。これは制作陣が予期していなかった出来事らしい。
ロッキーに扮するシルヴェスター・スタローンが、オレンジを投げられた瞬間にそれをオレンジとして認識できていたかどうかはわからない。いずれにせよ、その瞬間のスタローンの視界においては、橙色の円形が接近していたはずである。唐突な出来事だったにもかかわらず、オレンジを投げられた直後のスタローンは、オレンジを受けとるのに適した態勢へ身体をスムーズに移行させている。
オレンジを投げられた直後の一瞬を取り出してみよう。そのときスタローンに見えているのは、あくまでもオレンジの(スタローンにとっての)表面であり、オレンジの背面がどうなっているかは彼にはわからない。このわからなさを表すための概念である「未規定性」(indéterminé)に、本書第1部(第1–3章)の焦点が据えられている。
投げられた直後のオレンジはスタローンにとって、わからない部分を持つものであり、かかる意味において曖昧である。にもかかわらず彼はその瞬間に、手をちょうど良い形(球体を受けとめられる形)にしてちょうど良い位置(オレンジが来るであろう位置)へ運ぶよう促されている。本書の言葉遣いでもって言い換えれば、オレンジという対象についての経験がスタローンの身体を動機付けている。まさしく「動機付け」が、本書第2部(第4–7章)のタイトルである。
本書が引く一節(237頁)のなかでメルロ゠ポンティは、知覚とは「問いかけの思考」として理解されるべきものだと述べている。オレンジを投げられたスタローンの、指を少し丸めた手は、眼前の曖昧な世界に対して「あなたにはこの手がちょうどフィットするのでは?」と問いかけている──そう言えるかもしれない。それが適切な問いかけであったがゆえに、スタローンはオレンジをキャッチできた。同じ状況でオレンジをキャッチできない者もいるだろう。しかしいずれにせよ、(適切なものもそうでないものも含む)さまざまな問いかけを受けとめられるような仕方で世界は存在している。本書第3部(第8–11章)でいよいよ解明されるテーゼ「実在する世界は試問的な様態で存在する」を、私はこのように理解した。
『ロッキー』を引きあいに出した以上の要約は、わかりやすさを期した私なりの工夫であるとはいえ、本書のストイックさに似つかわしくないほど軽薄かつおおざっぱである。本書はあくまでも専門的な哲学書であり、メルロ゠ポンティの著作以外にも英語圏の現象学研究やウィトゲンシュタインの哲学などが俎上に載せられるが、個々のトピックは丁寧に扱われている。本書の第2部と第3部のあいだにある、経験の外へ踏み出す大きな一歩(知覚論から存在論へという一歩)に関しても、それがメルロ゠ポンティにとっては不合理な飛躍ではなかったことの論証に本書は最大限の努力を傾けている。
本書による論証の哲学的評価は、現象学の専門家ではない私の手に余る。かわりにここで強調しておきたいのは、本書の行論に対して私が感動を覚えたということである。すなわち、メルロ゠ポンティ哲学の奥義を目指して、前期の著書の読解という起点から議論をこつこつ積み重ねてゆくという本書のスタイルに対してである。かかる誠実さにより喚起される感動が、本稿──このいささか軽薄な紹介文──をきっかけにより広く共有されることを私は願っている。
(入江哲朗)