相互扶助論 : 進化の一要因
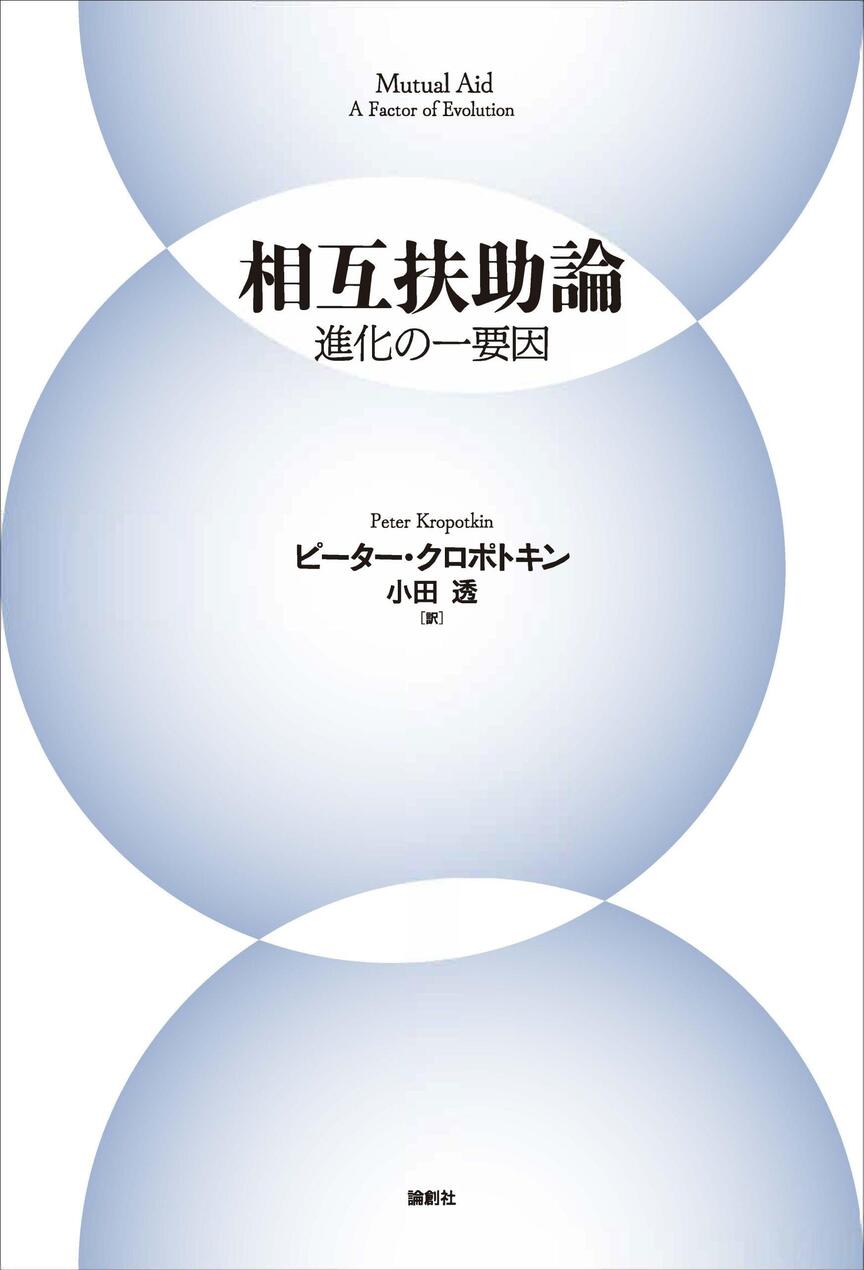
ロシアの地理学者にしてアナキストであるP・クロポトキン(1842‐1921)の『相互扶助論——進化の一要因』(1902)は、この惑星の生命史に遍在する相互扶助の感性と実践の物語である。
チャールズ・ダーウィンの進化論が『相互扶助論』の理論的枠組みをなす。もともとは、血で血を争う仮借なき生存闘争をこそ進化の要因と捉える社会ダーウィニズムの代表格的な論者であったトマス・ハクスリーにたいする反論として執筆されたものだが、英国の総合雑誌『19世紀』で1890年代に断続的に連載されるなかで、クロポトキンの構想はダーウィンの解釈をめぐる問題をはるかに超越し、遠大なものとなっていった。
1902年に単行本としてまとめられた本書は、動物のあいだの相互扶助(一、二章)に始まり、先史時代や古代や未開社会における相互扶助(三、四章)、中世における相互扶助(五、六章)、そして、同時代における相互扶助(七、八章)というかたちで、動物と人間の両方を、過去と現在の両方を、それぞれの連続性を前景化するかたちで焦点化しており、その意味では、ダーウィンの『人間の由来』(1871)につらなるテクストである。ダーウィンが、豊富なデータや文献のみならず、「ビーグル号」での世界周航の体験をも引き合いに出しながら、解剖学的、生理学的な水準だけではなく、感情や知性や道徳といった水準においても、動物と人間のあいだに確かな連続性を見出したように、クロポトキンもまた、若かりし頃シベリアと満州で目の当たりにした自然を思い返しながら、膨大な数にのぼる同時代の文献を参照しつつ、相互扶助が動物にも人間にもひとしく備わっている社会的本能であり、人類はどこにいても、いつの時代でも、相互扶助をたえず実践してきたと力説したのだった。
『相互扶助論』のなかでは、さまざまな言語的文脈、文化圏、学術領域が絡み合っていく。19世紀に姿を現しつつあった新しい知のパラダイム——遺伝学、人類学、考古学、社会学——が同居している。参照される文献は英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、イタリア語など多岐にわたる。取り上げられる事例はヨーロッパやロシアにとどまらず、北アフリカからカフカースから中央アジアまで、南米から北米からアジアまで幅広い。
当時利用できた科学的証拠によって「自然状態」を検証することが『相互扶助論』の狙いのひとつであった。ホッブズ的な万人の万人による闘争と、ルソー的な汚れなき楽園の両方を反証すること。人間の本性を単純な性善説や性悪説で捉えるのではなく、さまざまな感性や衝動のせめぎ合いと捉えること。個人があって集団があるのではなく、集団が先にあったという発想の転換を導入すること。クロポトキンは自然や人間を理想化しているという批判がしばしばなされてきたし、たしかにそのような一面があることは否定できないかもしれない。しかし、クロポトキンは、観察者の社会的偏見が自然の観察に反映されてしまう危険性や、歴史的記録に内在する構造的な歪みについて明確な批判意識を持っていたことは、強調しておかなければならない。
アナキズム界隈でこそ古典としての地位を保ってきたものの、19世紀的な実証主義を奉じる革命家によって、科学的な知のパラダイムがますます専門化していった20世紀初頭に出版されたがゆえに、総合的な書である『相互扶助』は誤読や誤解にさらされてきたところがある。本訳書に収録されているデヴィッド・グレーバーとアンドレ・グルバチッチによる「序」が触れているように、社会生物学と進化心理学は、「相互扶助」ではなく、「利己的な遺伝子」(ドーキンス)という観点から、動物の協力行動を解明しようとしてきた。クロポトキンが参照した人類学は、進化論的な文明段階論に立脚するものであり、本書で繰り返し使われる「野蛮人」「未開人」という用語は、いまや、古色蒼然と見えるどころか、人種差別的に響くだろう。共同体や名もなき人々を主人公とした日常生活体験の歴史を物語るという試みは、国民国家の歴史とは相容れないものでもある。
しかし、現在、状況は変わりつつあるようだ。クロポトキンと『相互扶助論』は、さまざまなところで、はるかに好意的なかたちで言及されるようになってきている。とりわけ、COVID-19の世界的流行を経て、わたしたちの生がどれほど相互に依存しているかがこれ以上ないかたちで明らかになったいま、相互扶助的な感性や実践は、わたしたちの日常生活のなかで、クロポトキンが本書で描き出したような姿を取り戻しつつある。みずからの命を賭けた自己犠牲のような英雄的行為としてだけではなく、日常にあふれているちょっとしたケアの実践として。
とはいえ、本書には、21世紀を生きるわたしたちが直面している問題をたちどころに解決してくれるような処方箋は記されていない。それに、相互扶助は両義的なものである。相互扶助は競争や無関心、個人主義や国家によって抑圧されうる一方で、相互扶助それ自体が共同体の成員にたいして抑圧的にはたらくこともありうる。しかしながら、相互扶助とは、進化の所産として、動物たちにもわたしたちにも生来的に備わっているものであること、人類は、さまざまな困難に見舞われるたびに——敵対的な自然環境、大規模な移住による人間集団の混淆、国家による中央集権化——、共感や連帯の範囲を外へ外へと拡大させ、より包摂的な相互扶助の形態を創出し、その倫理をより平等で公正なものへと進化させてきたことを教えられるとき、わたしたちは、国民国家体制やグローバル資本主義経済にたいするオルタナティヴな倫理的基盤を自分たちがすでに持ち合わせていることに、あらためて気がつくことになる。『相互扶助論』はいまこそ再読されるべき、いまこそあらためて読まれるべき古典である。
(小田透)