ゾンビの美学 植民地主義・ジェンダー・ポストヒューマン
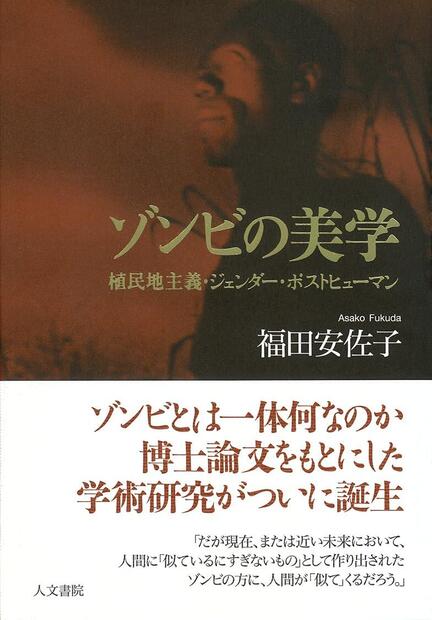
本書は自身の博士論文を元にした著者初の単著で、全5章に序章と終章が付された構成となっている。それぞれの章では「ゾンビ」という名で語られてきたものの定義、その変遷について具体的な作品を用いた分析がなされている。
序章において、先行研究で語られてきた時代の変化に伴う3つの区分「クラシック・ゾンビ(ヴードゥー・ゾンビ)」、「モダン・ゾンビ(ロメロ・ゾンビ)」、「走るゾンビ(ダッシュ・ゾンビ、ミレニアム・ゾンビ)」を概観し、続くそれぞれの章で時代区分に沿った作品を具体的に紹介していく本書は、2つの大きな問いを軸としている。
まずそもそもゾンビは、「人に似ている」ものであるが、「似ている」という表現により「同じものではない」ことが強調されている存在でもある(15-17頁)。どこまでも似ているがしかし確実に人間とは異なる存在としてのゾンビは、いかなる点によって「似ているに過ぎない」と判断され得るのだろうか。本書はそのような判断基準がどの時代にどの場所でどのように定められているのかと問い分析していくことにより、あるゾンビが描かれた時代や社会状況に肉薄することを試みている。
同時に、このようなゾンビと人間とを区別するものを検証していくにあたり著者が重要視しているのが、各時代において異質な作品や異例の要素という「例外」の部分に注目していくという姿勢である。時には、ゾンビと人間の区別として頻繁に用いられる匿名性がゾンビに固有名詞を与えることで失われたり、人間と同様のジェンダーやセクシュアリティの在り方が存在しないはずのゾンビの表象に「女性性」が付与されたりすることがある。それらの「例外」は主流となっているゾンビのイメージを揺るがしかねない重要な表象であるはずだが、先行研究では単に例外として注視されることなく看過されてきた(16-17頁)。しかし著者によればこのような「例外」こそ、各時代の変化、新しい表現の可能性を感じ取ることができる次世代への萌芽であり、注目すべきものである(247頁)。各時代におけるゾンビの「例外」をどのように捉えて分析し、位置づけることが可能であるのか。これが、本書における2つ目の大きな軸となる問いである。
第一章、第二章は「クラシック・ゾンビ(ブードゥー・ゾンビ)」と呼ばれる、主にハイチにおける伝承や欧米諸国によってそれらを元にしつつも歪められてしまった解釈を元に描写されるゾンビを扱った作品について分析されている。第一章ではハルペリン・プロダクション制作の『恐怖城(ホワイト・ゾンビ)』(1932年)を取り上げ、当時の白人社会が求めていた「反乱をおこさない黒人奴隷」のイメージとゾンビとの結びつきについて紹介しながら、そのような状況における「例外」である白人女性のゾンビや、新しい人種階級であったムラートの登場人物を含む複雑な人種階級制度について議論がなされている。
『私はゾンビと歩いた!』(1943年)を分析する第二章では、西洋社会によって作られた「ヴードゥ教と人形」、そしてそれらとゾンビとのつながり、という誤った認識が形作られた経緯に触れながら、西洋/非西洋という二項対立を見せながらも最終的にすべてを曖昧にしていくという本作の「例外」的なプロットについて言及されている。本作においてわかりやすいモンスターとしてのゾンビが登場しないこともまた、ゾンビというものの定義を曖昧にさせ、さらには誤ったステレオタイプを強化するかのように思われつつも最終的には完全な対立関係をなくしてしまうという本作の特徴と呼応していると著者は主張している。
第三章ではジョージ・A・ロメロの「デッドシリーズ」を中心に「モダン・ゾンビ(ロメロ・ゾンビ)」と呼ばれる近代のゾンビについて分析がなされている。主にハイチを舞台に描かれたクラシック・ゾンビとは異なり、西洋社会における「隣人」がゾンビとなること、そしてスラッシャー表現の登場など、ロメロ作品は現代に続くゾンビイメージに大きく貢献している。しかし同時に、ロメロ自身が当初作り出した「ゾンビ」とは異なる「例外」的なモンスター像を続く作品で次々と登場させ、さらには他の作り手たちの「例外」的なゾンビ像に寛容であったことによって、その後のゾンビが描かれるフィクション空間が豊かになったと著者は指摘する。
第四章では再びロメロ作品、そして『28日後…』(2002年)『28週後…』(2007年)を中心に「モダン・ゾンビ」と「走るゾンビ(ダッシュ・ゾンビ、ミレニアム・ゾンビ)」の過渡期を取り上げ、ゾンビ映画における女性の表象と「女性性を付与されたゾンビ」に注目して分析がなされている。ゾンビ映画における主な女性キャラクターがいかに表象されるかだけでなく、人間が持つ生殖機能、性別、セクシュアリティが存在しないはずのゾンビに付与され描かれる「女性性」について問う本章は、ゾンビと人間との区別について考える際、さらにはゾンビにそのような性質を付与する作り手の人間について考える際にも重要な問いを提示しているといえるだろう。
『ワールド・ウォーZ』(2013年)を分析する第五章では、既存の人間や生に関する考え方が変化していく中でポストヒューマニズムの問題と共鳴するゾンビ作品のありかたについて議論されている。現代におけるゾンビは新自由主義の時代に使い捨てにされる労働者の姿とも重なり、人間とゾンビが区別されるのではなく、むしろ接近していく状況が示唆される。さらにはマキシム・クロンブが指摘したホモ・サケルの形象とゾンビとの近しさについても言及がなされ、身体的には生きているけれども共同体の政治的な生からは排除され、存在しつづけるしかない人間というホモ・サケルの概念がいかに現代の状況と繋がっているかが分析されている。
全体を通して本書は、人間に「似ているに過ぎない」ゾンビが人間といかに区別されるのか、という条件を「例外」となる部分を丁寧にすくい上げながら分析していくことで、先行研究が見過ごしてきた、しかし重要である表象を提示する。ある時代の「例外」が次の時代の萌芽となるという著者の主張は、次々と「例外」を生み出し、自身以外の作り手による「例外」にも寛容であったゾンビ映画の巨匠ロメロの姿勢とも通じるものであろう。そして新しいものを常に生み出し、時代によって変化していくゾンビだからこそ、そこにある「似ていないもの」の表象に注目することが大きな意味を持つ。ハイチを舞台に始まった「クラシック・ゾンビ」から、現代社会における労働者の在り方とも重なる「ミレニアム・ゾンビ」まで、「人間に似ている」つまり「確実に人間とは異なるもの」であるゾンビを分析し、その変遷と、さらには変わらずあり続けるゾンビの性質の「核」もしくはその本質について丁寧に分析している本書は、人間とゾンビを、ゾンビが描かれる時代の状況も含めて見つめ捉えることのできる充実した一冊となっている。
(藤原萌)