シェイクスピアと日本語 言葉の交通
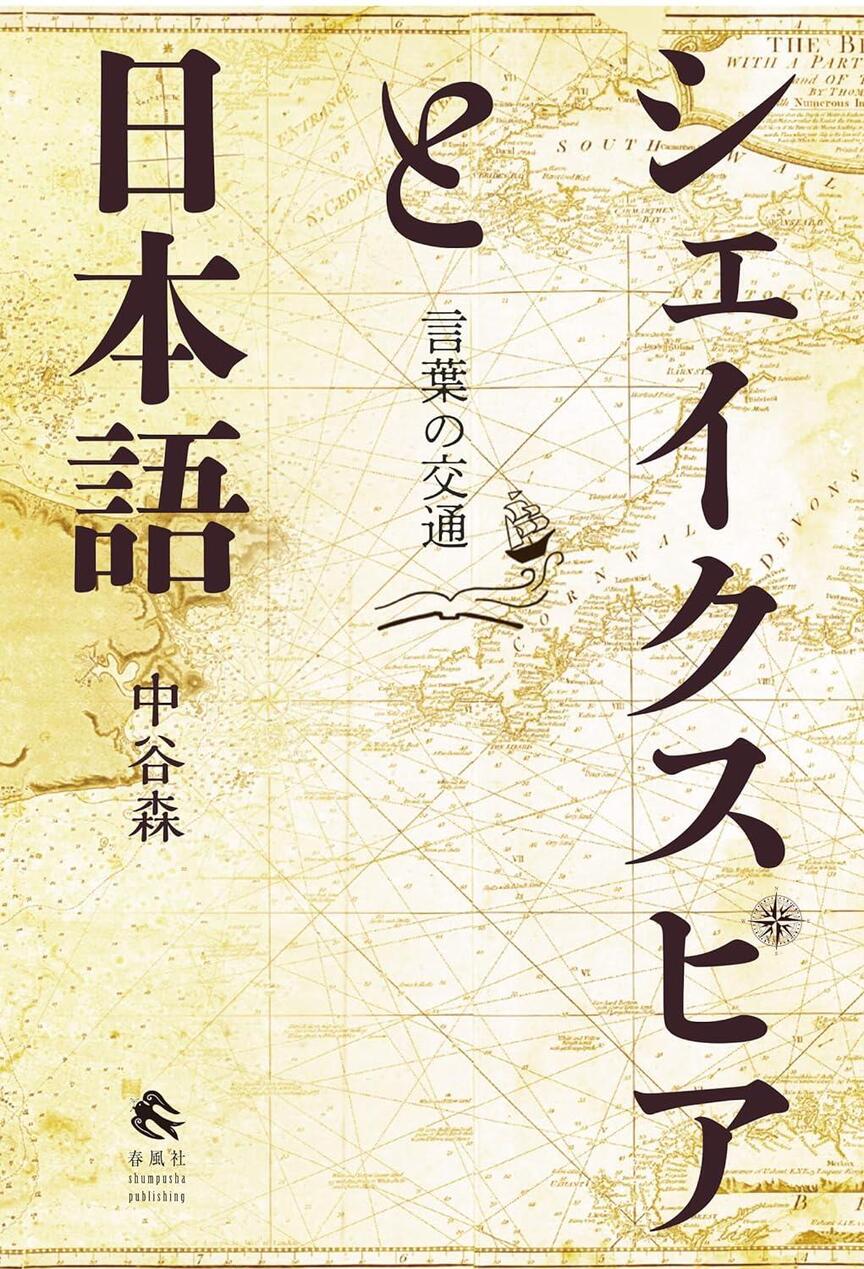
「白菊にしばしためらふ鋏かな」––夏目漱石は、シェイクスピアの戯曲『オセロー』の主人公オセローが、妻デズデモーナを殺害する際の情景をこのように詠んだ。本書の中で著者の中谷森が言及しているこの句には、シェイクスピアの英語による言語芸術を、いかに日本語という全く異なる言葉へと翻訳するのかという困難な挑戦への一つの解答がある。漱石の句は、オセローとデズデモーナを鋏と白菊に例え、かつオセロー自身の感情とも詠み手のそれともとれる曖昧な視点から、愛する妻を手にかけようとしてオセローが逡巡する情景をわずか17文字の俳句の中に巧みに描き出している。すなわち、本書によればそれは「シェイクスピアの言葉と日本語における言語芸術との複雑な交渉」であり、この句を引用した平川祐弘の『夢幻能オセロ』は、「新しい言語表現の模索と創造」(p. 240)への取り組みである。
明治以降、シェイクスピアの戯曲は坪内逍遥をはじめ数多くの手によって翻訳・翻案されてきた。その中で本書が取り上げるのは、「口語」やリアリズムへと結びつく日本近代演劇の方向性ではなく、「芸術としての日本語がもつべき形」を模索した作品である。小林秀雄の翻案小説『おふえりや遺文』(1931)、福田恒存翻訳の『ハムレット』(1955)、木下順二翻訳の『マクベス』およびその改訳(1970、88)、そして平川祐弘作・宮城聰演出の『オセロー』(2005)という性質の異なる四つの事例を取り上げ、英語を日本語という全く別の言語へと翻訳することの困難と、独自の言語表現が生み出されていくプロセスに迫り、その「必然的に実験的かつ創造的」で「複雑かつ独自の過程を、緊張感のある交渉の営み」(p. 39)として解き明かしていく。
「口語」ではない劇言語は、当然ながら「口語」ではない発話を求める。本書が取り上げる翻訳にある種の硬さや読みづらさを感じるとしたら、それは私たちがまだその発話の仕方を知らないからかもしれない。彼らが新しい言語表現によって翻訳の言葉を「書いた」のだとしたら、シェイクスピア作品が劇である以上、それを「発話する」方法を探求することもまた、シェイクスピアの日本語のもう一つの可能性なのではないだろうか。「発話」を含む上演の問題は、本書の範囲を外れる(宮城聰演出『オセロー』に言及するのみである)が、ぜひ今後の展開を期待したい。
(宮川麻理子)