ベートーヴェンと大衆文化 受容のプリズム
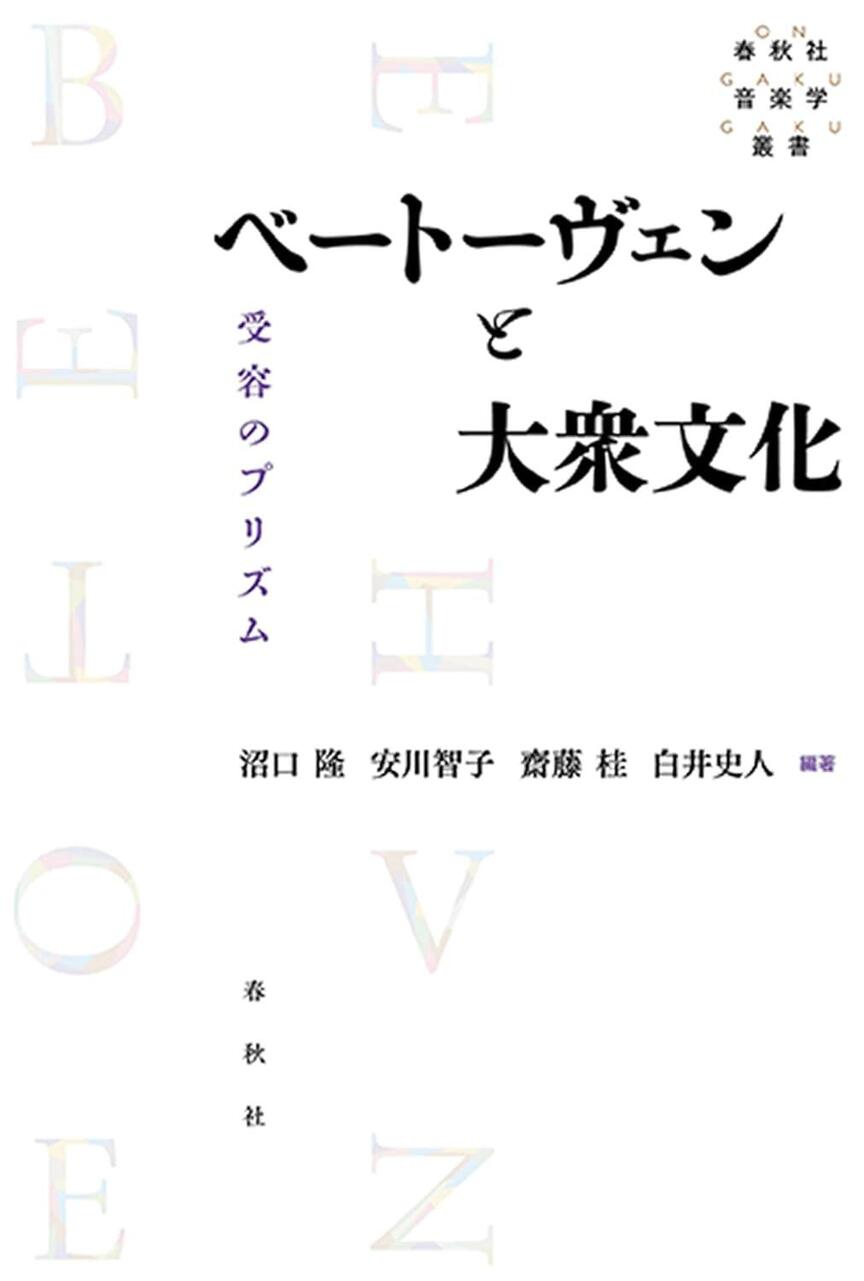
2020年は、ベートーヴェンの生誕250周年にあたる。その節目を記念し、ドイツやオーストリアのみならず、ヨーロッパ各地で演奏会やイヴェントが企画されていた。年が明けて、この音楽家が没した3月26日が近づいてくると、各地の祝祭的な雰囲気はますます本格化した。生地ボンではベートーヴェン・ハウスを中心に大規模な展示と交響曲の演奏会シリーズが準備され、多くの自筆譜を所蔵するベルリン州立図書館での回顧展には、ヨーロッパや世界各地の愛好家や専門家が集う──と、誰もが信じることができたのは、2月下旬から3月にかけて新型コロナウイルスがヨーロッパで猛威を振るい始めるまでであった。3月上旬にドイツでもロックダウンが始まり、多くの展示や演奏会は開催されず、ベルリンの展示も開幕してから一週間も経たぬうちに閉鎖を余儀なくされた。
本書のきっかけとなったのは、その後に続くコロナ禍の2020年11月に、オンラインで開催されたシンポジウムである。その経緯の詳細は、編者であるベートーヴェン研究者・沼口隆による「はじめに」に譲るが、生誕250年を記念した企画であるにもかかわらず、ベートーヴェンをいわゆる「専門」の研究対象としている訳ではない研究者を広く集めた構成が異色であった。フランス(安川智子、第3章)、日本(齋藤桂、第5章)、ドイツ(白井史人、第2章)の近現代の音楽を研究する立場から、およそ100年前の1920年代に焦点をあてて、ベートーヴェンをめぐる世界各地のさまざまな動きをどのように捉えるか、それぞれの立場から見える景色を重ね合わせることで本書が立ち上がった。さらに企画が膨らむ過程で、日本における児童教育(山本耕平、第4章)や、小沢昭一と浪花節(鈴木聖子、第6章)、さらに宮澤賢治による受容とその作品のアニメーション化など(土田英三郎、第7章)、さまざまな立場からのベートーヴェン論が一冊の書物に同居することとなった。『ロマン・ロラン全集』の編集に携わるジル・サン=タロマンのエッセイや、木村直弘による宮沢賢治のベートーヴェン百年祭に関する論考、「題名のない音楽祭」のプロデューサーの大石泰による回想などを収めたコラムも、こうした議論にさらなる多角的な視点を与えている。
ベートーヴェン研究の「外部」にいると自認しながら、編者の一人に名を連ねることになった立場であらためて本書に目を通すと、われわれが語っているのは、はたして「ベートーヴェン」という一人の音楽家であったのか、という素朴な問いが浮かぶ。それぞれの執筆者はもちろん「ベートーヴェン」について語っているものの、われわれが共有していたのは、ひとつの固有名を通して明るみにでてくる近現代の音楽や社会をめぐるシステムそのものの方だったのではないだろうか、と。芸術と学問、「ハイ・アート」と「大衆文化」、国民意識、メディア、近代化と教育・・・こうした問題の細部にことごとく顔をだす「ベートーヴェン」の音楽が湛える魅力としぶとさのメカニズムを、本書は明らかにしているはずだ。
(白井史人)