戦後フランスの前衛たち 言葉とイメージの実験史
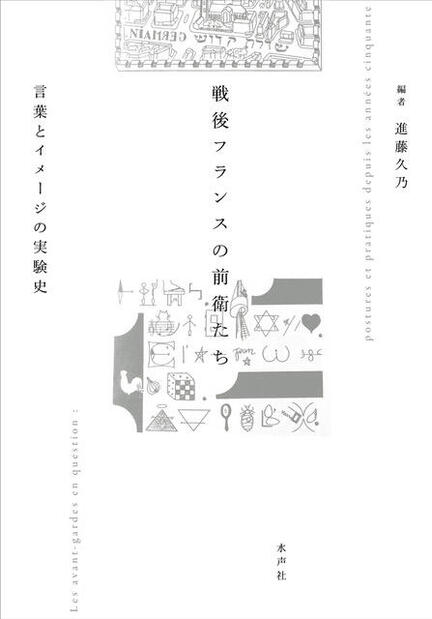
未来派からダダイスムを経てシュルレアリスムに至る流れについてはこれまで比較的よく論じられてきた。しかし一般的にシュルレアリスムが衰退したと言われる1940年代半ば以降の前衛についてはほとんど論じられてこなかった。近年の研究では、「前衛」──とりわけ新しさを追求し過去との断絶を強調するという意味における前衛──という概念自体が批判的に論じられるようになり、それぞれの芸術運動がいかに前衛ではないかという点に焦点が当てられているようにみえる。その結果、個々の運動体や詩人・芸術家が過去の伝統や同時代と結んだ複雑な関係が浮き彫りになった。
そのような中、「前衛」という概念自体も、新しさの追求に還元されるものではなく、詩的言語の探究、文学・芸術と社会との関わりの模索といった多様な側面を持つものとして再考すべきであろう。そもそも前衛について語られる際、第二次世界大戦以降に前衛を名乗ったグループや詩人・芸術家は含まれていないようにみえる。本書は、戦後フランスで前衛として活動を行なったグループ──コブラ、レトリスム、アンテルナシオナル・シチュアシオニスト──や視覚詩・音声詩の詩人たちに焦点を当て、前衛の問題点がいかに発展したのかを探ろうとしたものである。
ベルナール・ハイツィックやジャン=ジャック・ルベル、ジュリアン・ブレーヌなど、グループを結成せずに活動した詩人の多い音声詩の領域については、ガエル・テヴァルが雑誌やフェスティヴァルというまとまりを通した概要を描いてみせ、ジャン=ピエール・ボビヨは理論的な通史を示してくれた。また、前衛の概念に対峙したコレージュ・ド・パタフィジックやジャン・ポーラン、近接した問題意識を持ちつつ周辺に留まったフランシス・ポンジュ、サミュエル・ベケットについての論考を加えることで前衛の相対化を試みた。
今後は、本論集の多くの論考で前景化された詩的言語の実験的側面の多様な形について、美術や音楽とのジャンルの越境の問題と共に考察することが課題のひとつとなってこよう。北脇昇論やピエール&イルゼ・ガルニエ論で浮き彫りとなった前衛の国際性の問題も重要な論点となることだろう。今回扱うことのできなかったテル・ケルや『TXT』、ベルギーシュルレアリスムの関わりなどを含め、現代に至るより詳しい見取り図を描きつつ、前衛の複雑さと可能性を明らかにしていくことを目指したい。
(進藤久乃)