文学的絶対 ドイツ・ロマン主義の文学理論 (叢書・ウニベルシタス)
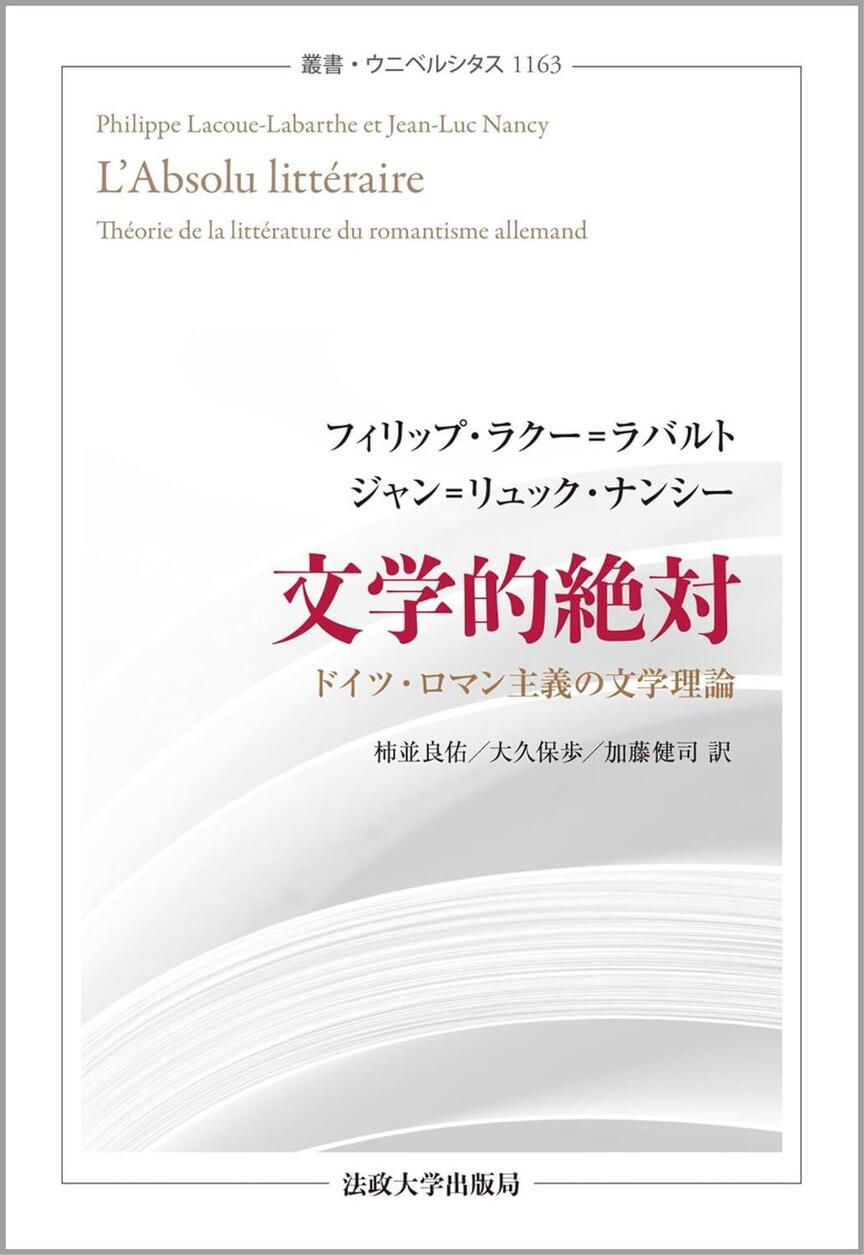
本書は、フランスの哲学者・思想家ジャン=リュック・ナンシーとフィリップ・ラクー=ラバルトによって1978年に著された、初期ドイツ・ロマン派の研究書である。18世紀末の世紀転換期にドイツの一地方で繰り広げられた、若者たちによる文学運動、のちに「ロマン主義者」と称されることになる彼らがごく短い時期に著し残したテクスト群が、本書の対象である。そうしたテクストのアンソロジーと著者たちの注釈から本書は構成される。
フランス現代思想の一翼を担った著者たちは、なぜそんな古臭い文学理論に取り組んだのだろうか。それは、今から2世紀以上も前にドイツのイェーナで切り開かれた地平のなかに著者たちが、そしておそらくわれわれも、まだいるからである。それは「文学」という地平である。著者たちは、今では自明に見える「文学」という営みを、その揺籃期に遡って探究する。この意味で本書は、一種の系譜学的研究であると言えるだろう。
フランス革命とカントの批判哲学の衝撃のもとで、雑誌『アテネーウム』に集ったシュレーゲル兄弟やシェリングたちは、ドイツ観念論の傍らで、「文学(ポエジー)」とは何かと問い、さらにはこれをみずから生み出そうと試みた。本書の分析は非常に多層的であり、ここでその概略を示すことさえ困難である。だがあえて乱暴に要約すれば、次のようになるだろう。ロマン主義とは、カントの批判哲学によって超越的審級が失墜したのちに、カント的主体(もはや内実のない「空虚な形式」)を通して、理念という無限を美的に、つまりは芸術作品として、文学として呈示する(darstellen)試みだ、と。有限な作品によって無限を呈示しようというこのプロジェクトは、最初から失敗することを運命づけられている。ここからさまざまな帰結が生じる。フリードリヒ・シュレーゲルは、断章や会話といった形式を採用することで、雑多なテクストの外に無限の存在をネガティヴなかたちで示唆するだけだ。また、あらゆるジャンルを含みうるジャンル、みずからについての理論すら含みうるジャンルである「小説(ロマーン)」が重要視される。結局のところ、ロマン主義者にとって文学は、「それは何か?」と絶えず問われる存在であるほかなく、理念という無限へと漸進的に近づくプロジェクトであるほかない。まさにこの運動こそが作品であり、主体ですらあるのだ。
では、なぜ今、『文学的絶対』なのか? 21世紀も四半世紀を過ぎようとしているときに、もはや「歴史」になりつつあるフランス現代思想の本を、今さら読む価値などあるのだろうか。答えは先ほどと同じことになるだろう。われわれが「文学」の地平のなかにまだ、おそらく、いるからだ。俳句でも詩でもなく小説こそが「文学」だとみなされていることがその証左のひとつであるだろう。日本において本書と対応する仕事として、柄谷行人の『日本近代文学の起源』(初版1980年)を挙げることができる。柄谷は、日本の近代において、ドイツと同様ごく短期間に、「文学」の装置が作り出されるさまを描いたのだった。柄谷自身は後年、近代文学の終焉を告げ、議論を巻き起こした。たしかに今や国民的作家と呼ばれる存在は消え、「文学」の社会的地位は下落したように見える。われわれはついに「文学」の地平から抜け出したのだろうか? このことを問い直すためにも、本書を手に取らなければならない。
(大久保歩)