増補改訂 境界の美術史 「美術」形成史ノート
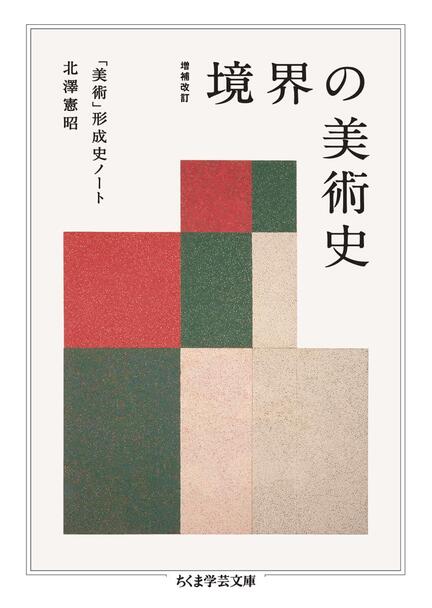
本書は、日本における「制度史・制度論」の先駆的論者である、北澤憲昭の、2000年に刊行された論集の、増補改訂された文庫版である。同じく「ちくま学芸文庫」において、本書と対をなす『眼の神殿』(初版:1989年、文庫版:2020年)と一緒に、文庫版という手に取りやすいかたちで出揃ったことは、必読書籍の整備という点で、喜ぶべきことである。
ただ、本書の刊行の意味は、必ずしも「新しい古典」の文庫入りを示すだけではない。日本での美術史における「制度論」は、時代的にも、欧米の「ニュー・アート・ヒストリー」とほぼ同じ流れにある(例えば、本文庫版「解説」において、中嶋泉が、T. J. クラークと、クラークに対するグリゼルダ・ポロックの批判を取り上げているように)と言っていいが、「美術」概念が形成される、近代以降の日本が主題化される点において、ネーション・ステートをめぐる批判的検討に成り得ているゆえに、21世紀も四半世紀過ぎつつある今日においてもなお、亡霊のように残存しているネーション・ステートを深く再考することにおける意義を示すとともに、「タコツボ」的に「日本」にとどまるのではなく、むしろそのボーダー(境界)を逆照射する潜在能力を、いまだ発揮している。近年の美術史研究において主流であるとも言っていい「トランスナショナル」なアプローチにおいて、かえって扱いづらくなってしまう、「ナショナルなもの」の再考は、いまだなお検討の余地を残しているということがわかるのだ。それゆえに本書は、新たな問いかけをなすものとして、その効力を失っていない。
近年の北澤の仕事においては、しばしばニクラス・ルーマンの社会システム理論が援用されるが、本書を注意深く読んでいると、美術についての論述にあたって、ルーマンの理論が接続可能であることが、すでに予期されていることにも驚く。グローバルな「コンテンポラリー・アート」の社会的・経済的伸張に伴い、「美術」の内実が「なんでもあり」の空洞化に、良くも悪くも帰結してしまっている今日において、まだ絵画・彫刻といった西洋美術の移入についての歴史的議論が有用なのかと、疑う向きもあるかもしれない。しかし、むしろ、「近代日本美術」の形成の経緯をたどることにおいてすら、今日の美術の実践および美術史研究、さらには文化の政治学の現状に至る論理的帰結として、北澤が縷々論じているところの、紆余曲折を経て編成された日本の「美術」の形成過程において、既にビルトインされていることにこそ、読者は思いを馳せるべきであろう。
(土屋誠一)