洲浜論
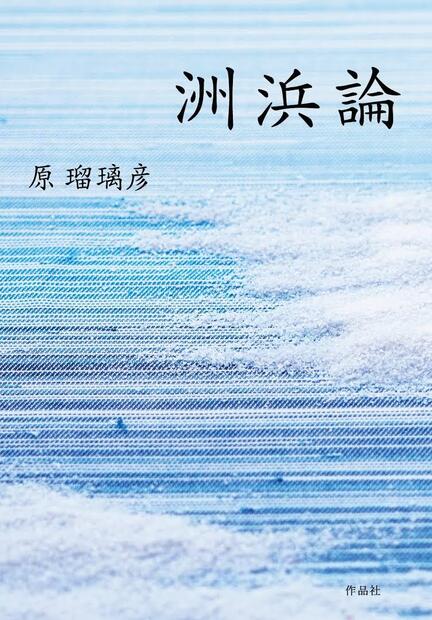
洲浜とは砂浜が曲線を描く海辺のことだが、本書はこうした海辺の表象が日本文化のなかで果たした機能を解明しようとする。原瑠璃彦氏の博士論文「洲浜の表象文化史」を大幅に改稿して成った、画期的日本文化論である。
急な脱線で恐縮だが、ポストモダンの批判的転回を経たあとで、「日本文化論」はストレートに受け取るのが難しい言葉だ。少なくとも私には、「世界的に珍しい日本的なもの」という結果から原因となる諸事象が構成されているのではないか、ナショナル・アイデンティティへの欲望に突き動かされているのではないかという批判意識がつきまとう。しかし本書はそうした批判をくぐり抜けたうえでなお、堂々と新たな日本文化論と呼ぶにふさわしい仕事である。
中心的な分析対象となる平安時代宮廷の歌合で用いられた洲浜台(洲浜を模したミニチュア)については、参照可能な全ての一次資料と膨大な先行研究を網羅したうえで議論が展開されている。個別の事例に今後異論が出ることはあっても、本書の主張の根幹を導く手続きにおいて恣意的な資料選択がなされていないことは明確である。そして、これは洲浜のミニチュアという一文化事象の研究なのではない。そのイメージがそれ以前から、またそれ以後に日本文化のなかでどのように機能したのかを考えるべく、和歌史、庭園史、美術史、芸能史等を横断した探求がなされており、まさに日本文化論と呼ぶにふさわしい拡がりと深さをもった研究である。
さて、洲浜の表象の機能とは何か。日本の文化史の風景が描かれた巨大な絵巻物かタペストリーを想像してほしい。従来の日本文化論が、いわばそこに描かれた「図」を見ようとしてきたとするなら、それらの図が浮かび上がるための「地」として機能したのが洲浜の表象である。これが本書の主張だ。洲浜は、平安後期から院政期までの200年の間に州浜台として形象化された以降は、表舞台から引っ込む。その当時でさえ、歌合というイベントの背景としてあっただけで、それ自体は歌題として言及されない。しかし、能をはじめ様々な文芸が描く場面だとか結婚式のような儀礼だとかの背景に、洲浜の風景は存在し続ける。洲浜は原氏が本書のなかで述べるように、日本文化の「図」となる諸表象が立ち上がるための触媒であり、あるいはそれらが生成する場として機能する「日本文化の無意識」なのである。
ほかにも「水平的な超越性」「自然の観念的見立て」「聖地と生殖」といった興味深い論点がある。詳しくは本書を読まれたい。書物としての価値にも言及しておく。凡例表記、章扉、段組の変更など、奇を衒うわけではないがおしゃれなデザインであり、図版も豊富で、大部の本なのに非常に読みやすい。添付されたカラー刷りの洲浜関連年表と、洲浜を模したテキスタイルの写真を表紙としたこの本自体が、洲浜表象の新たな表現物と言ってよいくらいだ。3600円は破格ではないか。
最後に、本書「補論2」の初出時に評者が書いた紹介文を引用紹介することをお許しいただきたい。本書各章の水準を推し量る参考となると思う。
「研究展望」(『能楽研究』47号、2023年3月)より
「洲浜」とは、洲が曲線を描きながら出入りする浜辺のこと。それを模した飾り物「州浜台」が作られたり、絵画、庭園などでしばしば描かれたりして、祝賀的な意味をもった。そこには多くの場合松の木が組み合わされ、いわゆる「白砂青松」の理想的な海辺の表象が形成された。原瑠璃彦「海辺の松風と波音 : 州浜の音をめぐって」(『青山総合文化政策学』10号)は、日本文化においてこうした州浜が表象されるときに、人々はそこでどのような音を想像的に経験したのか、というユニークな問いを探求する。
結論から言えばそれは松風の音である。その具体相として、和歌の諸例と『源氏物語』と並んで、能『高砂』『箱崎』などが分析される。これらの分析の出発点は植木朝子の論考で、植木は自然音である松風を琴のような楽器音にたとえて認識することを「聞きなし」と名付け、これが和歌よりも今様・平曲・謡曲といった芸能の場に現れやすいと指摘した。著者はこの観点から世阿弥の脇能における海辺の音風景に注目する。すると『高砂』は、海辺に音楽ないし歌として聞きなされた松風が吹き、そこが聖地と化すことを軸としたドラマとして解釈でき、州浜の表象の系譜に加えられるべき作品に見えてくる。そのことはその後の『高砂』受容からも言える。近世の婚礼の場では『高砂』の祝言謡が謡われ、そこには島台(州浜台の末裔)が出され、しかも島台のモチーフに『高砂』が用いられたという。著者によるこのあたりの仮説提示と例証は実に面白い。
最後の『箱崎』その他の脇能の分析では、それらも海辺で松風の音(と波音)が鳴り響くのを観客が想像的に聞くような作品であることに改めて気づかせ、さらにそこに見られる「自然音がそれ自体仏の法の声である」という本覚思想の表現が、中世に浄土世界の表象として州浜の図像が用いられるようになったことと関連していると示唆する。このように、本稿は能楽研究の側だけから見ても、世阿弥の脇能の作品世界における自然音がどのような意味作用を伴って想像されるのかを文化史的文脈から論じるという、極めて斬新なアプローチによる研究として高く評価できる。
(横山太郎)