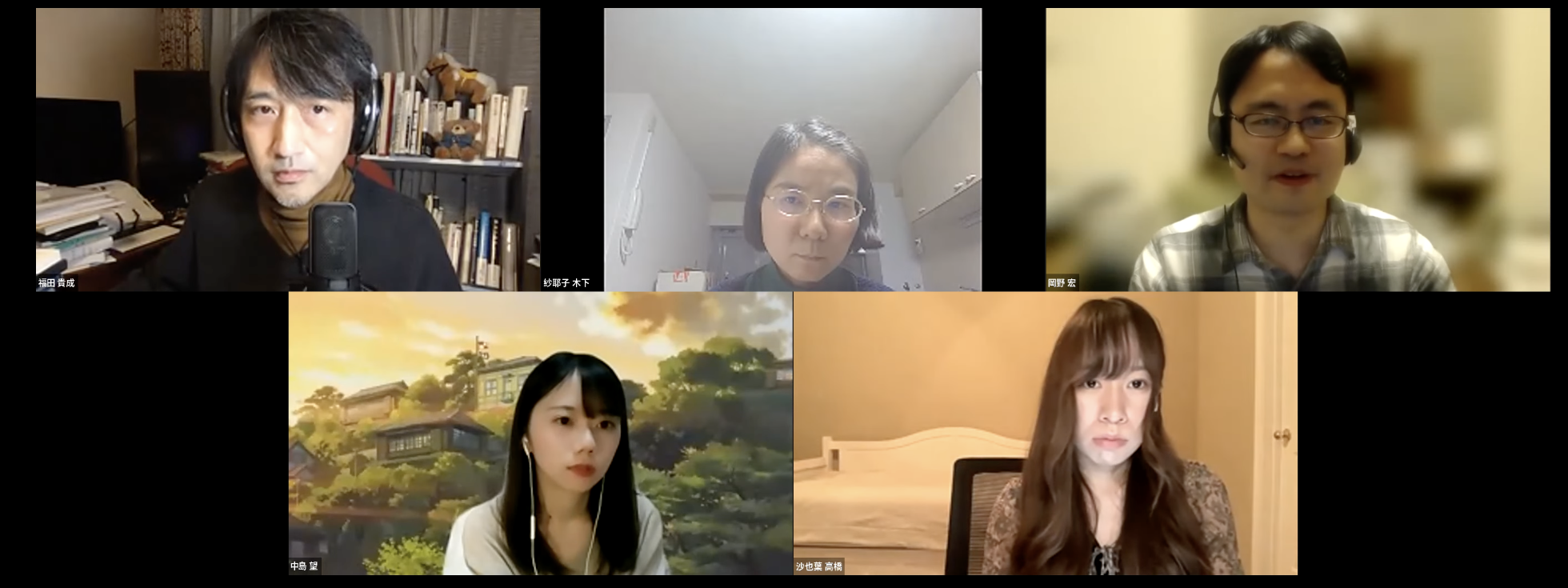日程: 2022年11月13日(日)16:00〜18:30
場所:オンライン
- 「聞こえない音の言説空間」の変容──「超音波」「低周波音」「体感音響」を事例に/岡野宏(電気通信大学)
- 聴覚で捉える新海誠作品──モノローグ・シーンに注目して/中島望(学習院大学)
- 彫刻と「場」、あるいは「場」の彫刻──日本におけるポストミニマリズム受容と「人間と物質」展に着目して/高橋沙也葉(京都大学)
- 岡本太郎作品における現代性と呪術──《明日の神話》のイメージ分析を中心に/木下紗耶子(東京大学)
司会:福田貴成(東京都立大学)
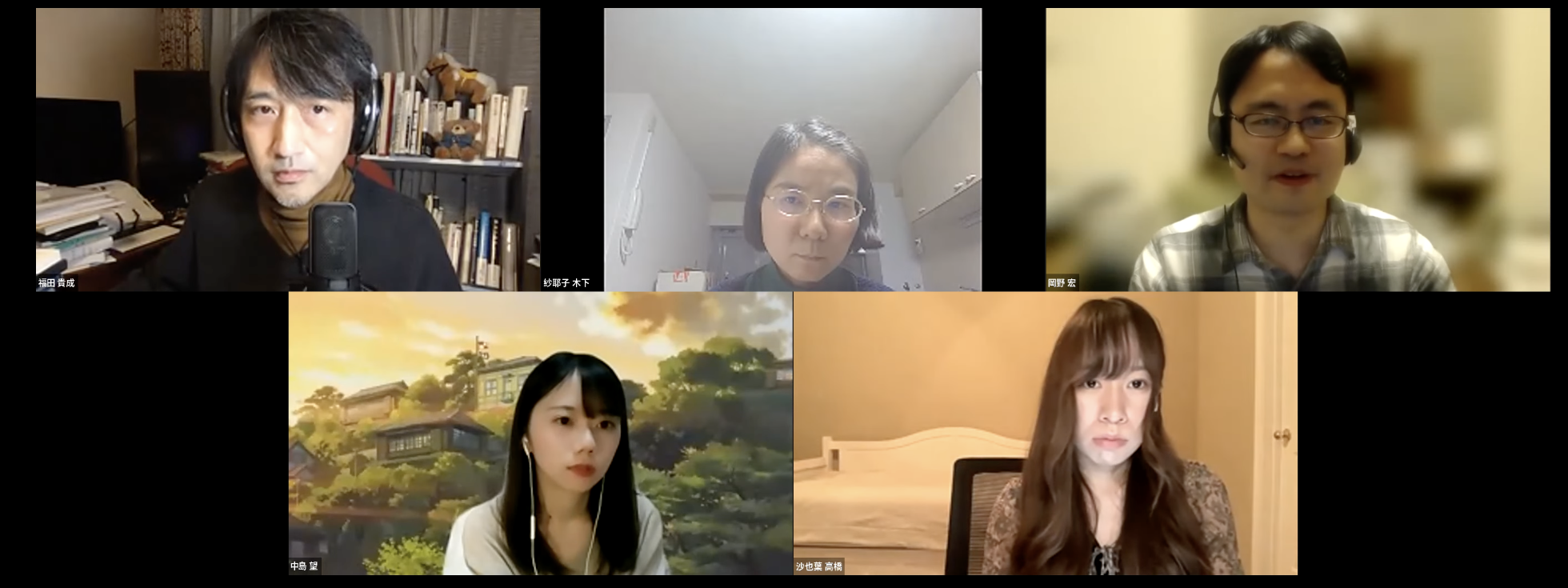
研究発表7ではそれぞれ「聞こえない音」「新海誠と聴覚」「ポストミニマリズム」「岡本太郎《明日の神話》」を主題とした4本の発表が行われた。テーマは異なるが随所に共通点も見られ、発表同士が緩やかに連関するように感じられた。
岡野宏氏による「「聞こえない音の言説空間」の変容──「超音波」「低周波音」「体感音響」を事例に」では、人間の可聴域外にある音=「聞こえない音」をめぐる言説がいかに変化したか、50年代以降の新聞や専門誌・雑誌を中心とする一次資料に基づいて示された。
たとえば戦前から戦後にかけて「聞こえない音」の代表格であった超音波は、進歩史観的な意識が共有された時代背景も手伝って、技術開発を目的とした「科学技術」という専門的な領域で理解されていた。しかし岡野氏によれば70年代頃を境に決定的な変化が見られるという。ここで注目すべき事例として、「低周波音」と「体感音響(=振動)」の2点が提示される。
工場や発電機による家屋の揺れといった「低周波音」が引き起こす問題は、60年代の騒音公害とは異なる新たな公害として社会問題となった。低周波音に関する理解は一般に普及するようになったが、症状の個人差が大きいなどそこには心的な要素(主観性)が入り込み、学術的な理解との乖離も見られたという。一方「体感音響」の言説は、工学者の糸川英夫による1972年の講演がその理論的支柱となっている。特筆すべきは、この講演が、音楽を純粋な聴取の対象として捉える当時の「ハイファイ信仰」が取りこぼした「音楽の重要な本質の何か」、つまり近代的な音楽観に対する批判を含んでいた点である。「体感音響」の言説は音楽を伴う形で日常に浸透するようになり、たとえば低音を振動に変換し、音楽を聴くことを目的とした「ボディソニック」の製品化や音楽療法、さらに近年のハイレゾ音源ブームへと拡張してきたと岡野氏は指摘する。
非日常から日常へ、身体的作用から心的へ、「聴取」の周辺へという変化は高度経済成長期から安定成長期への移行を反映している。そこでは「聞こえない音」に対する期待と不安が表裏一体となり、広い意味では近代的な「主体=主観性」(クレーリー、スターン)への懐疑や恐れを見出すことができるとして発表が締め括られた。
質疑では、「聞こえない音」に「科学的」な理路を求める考え方に、80年代当時のニューエイジ思想やニューサイエンス的なものの受容との関連が見られるかという質問があがった。岡野氏は、明らかな関係性は見られないが、「聞こえない音」の言説が一種のオルタナティブな見方の中で重要視されていたと説明した。
続いて中島望氏が「聴覚情報で捉える新海誠作品──モノローグ・シーンの「音」に注目して」と題した発表を行った。これまで新海作品をめぐる議論の中では、さざ波や雨といった風景描写やアニメーションにおいて周縁的な背景描写(二次的運動性)が、ときにキャラクターの身体などの主要な動き(一次的運動性)よりも優勢となるという特徴がしばしば言及されてきた。しかし新海作品の「音」に注目してみると、映像と同じく自然音や生活音といった「背景音」が前景化し、「一次的運動性へと移動する」傾向がみられるにもかかわらず、音響的な側面についてはほとんど議論されてこなかった。中島氏の発表の目的は、こうした問題提起に基づき、新海作品における「音」と映像の関係性を考察することにある。ここでは、聴覚的かつ新海作品の特徴であるモノローグ・シーンに着目し、背景音と映像の同期関係について分析がなされた。
具体的には2007年の『秒速5センチメートル』のモノローグ・シーンを例に、「A:映像において一次的運動性が優位であるシーン」(=キャラクターなどの主要な動き)と「B:映像において二次的運動性が優位であるシーン」(=風景描写あるいは物語とは直接関係のない動き)が比較された。その結果、Aでは「一次的運動性へと移行した」映像と音同士が「ぶつかる」のに対し、Bでは背景音は背景描写たる映像の動きと同期し、音全体の環境の中に二次的運動性である雨の映像が「なじむ」。それゆえ、バラバラであるはずのモノローグと風景(背景)描写は、映像と同期した背景音を通して繋がっていると中島氏は指摘する。
マリー・シェーファーの「サウンドスケープ」の理論を援用すると、この現象は新海作品における「映像のサウンドスケープ化」と位置付けられるという。ここでいうサウンドスケープ(音の風景)は個々の音が組み合わされた音環境全体を指し、それゆえ「普遍性」が生じるとされる。ここから、『秒速5センチメートル』のモノローグ・シーンを見る者が各々の「心象風景」として受容することの可能性が示された。
質疑では、モノローグの「声」が一次的運動性として提示されているが、声のテクスチュアやそのフェティッシュな特質を考慮した場合、二次的運動性としても捉えることが可能かとの質問がなされた。これに対し中島氏は、今回の発表では物語の構成を考える上で、環境的に鳴り響く音と映像の関係性という、これまで等閑視されてきた問題にまず注視した旨を確認した。また聴覚文化を専門とする司会の福田貴成氏から、「サウンドスケープ」の概念に関して、シェーファー以降「一般性」の解釈をめぐって展開された議論は、発表の最後に示された「誰のものでもないが、だからこそ誰のものでもある」という一般性と個別性の問題に通ずるのではとの見方が示された。
高橋沙也葉氏による「彫刻と「場」、あるいは「場」の彫刻──日本におけるポストミニマリズム受容と「人間と物質」展に着目して」では、1970年の東京ビエンナーレ「人間と物質」展の前後における国内外の美術動向に関する当時の言説について、「ポストミニマリズム」の受容の様相、具体的には美術評論家の藤枝晃雄と中原祐介による批評に光を当てることで再検証が試みられた。先行研究では「概念芸術」ないし「観念芸術」と物質への志向という二項対立的な言説が展開されたことが指摘されたが、高橋氏は、ミニマリズム(ミニマル・アート)以後の様々な動きが、新たな「観念」と「物質」の可能性を開くものとして紹介され、評価されていたことに着目する。
たとえば藤枝は「グループ位」やクレス・オルデンバーグによる「土を掘ってそれを元どおりに埋める」作品に、他のアースワークやアンチフォームの「精神的なロマンティシズム」とは異なる「作品を消し去ろうとする価値の否定」を見出していた。中原祐介もカール・アンドレの作品を「環境を芸術化するためではなく、逆に環境と融合することによって、芸術の無化を目指している」として評価した。高橋氏は、新たな評価基準の理論的背景の一つに、1969年に邦訳されたアラン・ジュフロワの論考「芸術の廃棄」を挙げる。「芸術の廃棄」では、「審美性の排除」を試みる作品の内部で「積極的なストライキ」が生じる可能性があるとされた。こうした議論の展開を経て、中原は、作品と具体的な「場」の不可分な結びつき、および「場」を具現化した作品が優れた批評性を持ち、さらに「会場否定」になりうるという「臨場主義」を主張するようになる。藤枝も作品とその成り立ちが特定の場所や空間と結びつく作品を評価し、「物質」をむしろ観念的な作品に対する「ある種のカウンター」とみなした。
ただし、彼らのいう「場」とはある特定の「位置」や「地点」という意味に近く、美術館の相対化にとどまっており、美術制度や政治に批判的な作品は評価の対象に含めなかった点を高橋氏は最後に指摘した。
質疑では、①一般的に「ポストミニマリズム」という用語の定義は人によって異なり、明確ではないこと②ジュフロワの「芸術の廃棄」について、中原は対談の中であくまで「表現の廃棄」だと述べており必ずしもジュフロワの議論に共感・賛成したわけではなかったのではないか③「アンチフォーム」をミニマリズムに含むかという問題についてはどう捉えるか、との質問が投げかけられた。それに対し、①③今回は「ミニマリズム以後の彫刻」という意味で用いたが、今後はモリスやアースワークについての日本での議論を細分化して考察したい②ジェフロワに対する藤枝と中原の差異にも注目したいとの回答がなされた。
続く発表は、木下紗耶子氏による「岡本太郎の作品における現代性と呪術──《明日の神話》のイメージ分析を中心に」である。ここでは、1968年開催のメキシコ・シティ・オリンピックに合わせて制作され、現在は渋谷駅構内に設置されている壁画《明日の神話》のモチーフについて、同時期の岡本の著作やドローイングに基づくイメージ分析がなされた。
まず核の表象についてであるが、岡本太郎は1954年の《燃える人》ですでに原爆の主題を扱っており、《明日の神話》のモチーフの源泉が見られる。1952年の論考「縄文土器論」で岡本は、現代的悲劇の象徴である原爆の災厄と核技術は「宛も彼ら〔原始人〕が超自然の世界と交渉したように同じく不可視ではありながら極めて現実的に迫ってくる切実な問題」と述べ、現代の芸術を規定しうるほどのものだと捉えていたことが分かる。
一方《明日の神話》のドローイングからは、《燃える人》の身体や閃光、うねうねとしたモチーフと構図が踏襲されつつ、新たなモチーフとして、メキシコにおける太陽信仰の人身供儀を連想させる骸骨や太陽、燃えさかる炎、人間の集合体が加えられた様子が見て取れる。これらのモチーフは、1970年に岡本自身によって、世界のあらゆる呪術的なイメージに関する連載「わが世界美術史」(『芸術新潮』)の中で論じられている。たとえば炎については、絵巻物の造形表現における呪術性や、炎が祭りにおいて共同体の中核となると同時に「個人の精神」として社会に対する抵抗を示すものであると説明された。ただし《明日の神話》の群像表現については「集合的な無数の死者」(黒い人間)と「個々人の人間の生」(白い人間)の表象として、岡本が独自に取り入れたものだと考えられるという。この点で、《明日の神話》は複数の視点によって神話的な世界観を描き出そうとした試みであると木下氏は指摘する。また「わが世界美術史」で論じられる沖縄の大御嶽の「空(くう)」の思想に基づけば、岡本はこの「空」を起点に、見えない・触れられない超越的な世界を現代社会に対する呪術として提示した。この「空」から形や色が引き出されるという状態に、ある種の緊張関係と「イメージの反転運動」が見られるのではないかとして結論が結ばれた。
質疑では、1954年の新聞紙上の岡本の文章は原子力の平和利用を肯定的に捉えるようにも読めるが、同時代の美術界のなかでは特異な例だったのではないか、また第五福竜丸事件を契機に岡本の姿勢に変化が生じたと考えられるかという質問がなされた。木下氏からは、確かに岡本の核に対するアンビバレンスな態度は見逃せないとの言及があった。(報告者が該当記事を再度読んだところ、「平和利用」への風刺だと解釈できた。)核のモチーフを起点として、太陽の塔を含む岡本作品と戦後社会との関わりについては今後さらに検証がなされるのではないかと感じられた。
司会の福田貴成氏が指摘したように、発表同士の繋がりが見られ、たとえば60年代、70年前後という時代性や、「不可視性」の問題と「聞こえない音」が根底で繋がっているという感覚は、領域を超えた俯瞰的な視野の豊かさを示唆しているようであった。
「聞こえない音の言説空間」の変容──「超音波」「低周波音」「体感音響」を事例に/岡野宏(電気通信大学)
本発表は、1970年代の日本で、発表者が「聞こえない音の言説空間」と呼ぶものの変容が起こったのではないかという仮説を「超音波」「低周波音」「体感音響」という3つの事例をもとに検証する。現段階では、発表者は「聞こえない音の言説」を「聞こえない音、すなわち何らかの理由によって可聴的ではない音ないし振動が、何らかの心身への働きを持つ」とする言説として定義している。その意味での最も人口に膾炙した「聞こえない音」は「超音波」であろう(なお、ここではそうした「働き」が事実として存在するかは棚上げにする)。
その上で、本発表では1970年代にこの言説空間の様態が変容したとの仮説を立て、その検証方法として、1950~60年代における「超音波」を巡る言説と、1970年代以降の「低周波音」および「体感音響」を巡る言説を、同時代の新聞・雑誌などの活字媒体を主たる検討資料とし、比較考察する。なお、各言説が表現される媒体の種類にはばらつきが存在するが、このこと自体もそれらの言説の特性を示している。
具体的な論点は、「聞こえない音」の働きが①非日常から日常の空間に移行し、②身体的な働きからより心的なそれへと強調点が移行し、とりわけ③「聴取」の周辺で形成されるようになる、というものである。ごく駆け足にだが、こうした傾向が「サブリミナル音源」などの1980年代以降の事象にも見られることが確認される。こうした変容が一定の広がりを獲得した背景には「安定成長」経済への移行という社会状況が存在すると考えられるが、その上で、発表者はこの変容を近代的な「主体性=主観性」(クレーリー)に対する懐疑ないし不安を示すものと理解している。
聴覚で捉える新海誠作品──モノローグ・シーンに注目して/中島望(学習院大学)
本研究では、聴覚的な側面から新海作品を捉え直す。従来の研究では、デジタル時代の恩恵を受けた緻密な風景描写(視覚情報)が新海作品の主な特徴として活発に議論されてきた。一方で、新海作品で頻繁に盛り込まれている自然音、生活音(効果音)や「モノローグ」(声)などの映像と共に鳴り響く「音」は、映像や観客に少なからず影響を与える重要な要素であることは間違いないが、先行研究では聴覚情報についてはあまり議論されていない。
本論では、映像作品研究において重視されつつある「音」の存在を、「効果音」「声」「音楽」という、アニメーションや映像作品全般の音の分類に則って抽出し、それら3つの音が同時に鳴り響くモノローグ・シーンに注目する。ここでは「効果音=自然音や生活音」「声=モノローグ、朗読」「音楽=BGM」とし、それぞれがミシェル・シオンのいう「画面内の音」「画面外の音」「非物語世界の音」に対応するかどうかを確認する。しかし本論では、この3つの音を個別に拾って分析するのではなく、同時に鳴り響く複数の音が一つのスクリーンに映し出される環境全体の中でどのように融合し、映像との関係性の中で機能しているのか、マリー・シェーファーのサウンドスケープ(=音の風景)の議論を援用しながら検討する。
彫刻と「場」、あるいは「場」の彫刻──日本におけるポストミニマリズム受容と「人間と物質」展に着目して/高橋沙也葉(京都大学)
1970年5月、第10回日本国際美術展(東京ビエンナーレ)「人間と物質」展は、「アンチフォーム」「アースワーク」「アルテ・ポヴェラ」といったミニマリズム以後の彫刻の転換を牽引した国外の作家らを国内の動向とともに紹介した。60年代末の日本では、包括的なカテゴリーとしての「概念芸術」、および「観念」と「物質」の二項を軸として新たな芸術の傾向が論じられていたが、本展のコミッショナーを務めた中原佑介は、人間と物質の関わり合いが起きる現場となった展示空間・展示場所もまた作品の重要な要素として前景化していることを指摘し、さらに「臨場主義」なる概念を提出した。この時期に中原に続く形で「人間と物質」展をめぐって彫刻と場の関係性を問う批評が複数発表されていることは注目に値する。
鈴木勝雄(2016)は「概念芸術」をめぐる議論を追った研究の中で、60年代末のアメリカを中心とするポストミニマリズムの実践もまた、60年代半ばより展開した「環境芸術」に対抗するものとして捉えられる「概念芸術」の批評と結びつきながら、藤枝晃雄らによって日本に紹介されてきたことを指摘している。本発表はこの時期の日本におけるポストミニマリズムの彫刻の受容に焦点を当て、その新たな動向がたしかに「概念芸術」と密接に関わり合いながらも、野外彫刻が探求した作品と空間や場との関わりという課題を引き継ぎ、「概念芸術」とは異なる「観念」と「物質」の関係性の可能性を開くものとしても論じられていたことを明らかにする。具体的には、議論の中心となった中原佑介、藤枝晃雄、峯村敏明らが野外彫刻展およびポストミニマリズムの動向について発表した批評を手がかりに、70年の「臨場主義」をめぐる議論を捉え直し、当概念、ひいては「人間と物質」展を60年代より続く美術市場・制度批判と体制批判の文脈の中で再考することを試みたい。
岡本太郎作品における現代性と呪術──《明日の神話》のイメージ分析を中心に/木下紗耶子(東京大学)
芸術家・岡本太郎(1911-1996)は30年代のパリで思想形成したのち戦後の日本で前衛芸術運動を展開した。岡本は50~60年代、縄文や東北、沖縄文化に関心を向けながら従来の美学を覆す「日本」の姿を思索したが、60年代後半頃より、大阪万博テーマプロデューサーとして世界各地の民族資料に接し、「日本」を超える、芸術の呪術性の探究を著述および制作の主軸に据えていった。
現在、渋谷駅にある壁画《明日の神話》(67-69)は、「日本」を巡る思索および、制作地・設置場所であるメキシコの文化にもとづくモチーフを複数取り込んだものである。すなわち、50年代より継続する原爆やメキシコ古代文明における供儀のイメージであり、岡本はここで、現代性を象徴する特権的な条件としての「核」の問題と古代の死生観の共存を神話として描きだそうとする。沖縄の御嶽で「空」の神秘性に接することで思考的展開を迎えた岡本にとって、この身振りは、「空」が喚起する死者や悲劇の記憶、およびそのイメージに人々を対面させ、世界に呪術的に働きかけることを試みるものである。
本発表では《明日の神話》の最初期のスケッチと下絵からそのイメージの生成に迫る。また、その同時期に、民族学・民俗学に接しながら探求された岡本の芸術思想について、雑誌連載「わが世界美術史」(1970)を中心に言説研究を行うことにより、《明日の神話》の多面的な解釈を試みる。