【選考委員】
- 阿部賢一
- 佐藤元状
- 平倉 圭
- 山口裕之
選考委員会 2022年5月15日(日) オンラインミーティング
選考過程 2021年12月に、表象文化論学会ホームページおよび会員メーリングリストをつうじて会員から候補作の推薦を募り、以下の著作が推薦された(著者名50音順)。
【学会賞候補作】
- 甲斐義明『ありのままのイメージ スナップ美学と日本写真史』東京大学出版会
- 河野真理江『日本の〈メロドラマ〉映画 撮影所時代のジャンルと作品』森話社
- 古川真宏『芸術家と医師たちの世紀末ウィーン 美術と精神医学の交差』みすず書房
- 貞包英之『サブカルチャーを消費する 20世紀日本における漫画・アニメの歴史社会学』玉川大学出版部
- 渡名喜庸哲『レヴィナスの企て 『全体性と無限』と「人間」の多層性』勁草書房
- 中村大介『数理と哲学 カヴァイエスとエピステモロジーの系譜』青土社
【奨励賞候補作】
- 宇佐美達朗『シモンドン哲学研究 関係の実在論の射程』法政大学出版局
- 髙山花子『モーリス・ブランショ レシの思想』水声社
- 松木裕美『イサム・ノグチの空間芸術 危機の時代のデザイン』淡交社
- 山本祐輝『ロバート・アルトマンを聴く 映画音響の物語学』せりか書房
【特別賞候補作】
推薦なし
選考作業は、各選考委員が候補作それぞれについて意見を述べ、全員の討議によって各賞を決定してゆくという手順で進行した。慎重かつ厳正な審議の末、学会賞に甲斐義明氏と渡名喜庸哲氏の著作を、奨励賞に河野真理江氏の著作をそれぞれ選出することに決定された。
応募の際には「学会賞」「奨励賞」それぞれのカテゴリーでのエントリーが行われたが、実際の選考の際には、「表象文化論学会賞規定」でそれぞれの賞の資格の範囲に当てはまるものはその対象に含めるというかたちで検討を行った。
なお河野真理江さんは、昨年惜しくも逝去された。ただ、当該作の内容が今後の表象文化論の進展に大きく貢献することはたしかであり、河野さんに続く若手研究者の研究奨励にもつながると考えられるため、このたび、奨励賞として選出する運びとなった。
受賞者挨拶(2022年7月2日)
【学会賞】甲斐義明『ありのままのイメージ スナップ美学と日本写真史』東京大学出版会
このたびは拙著を表象文化論学会賞に選んでいただき、ありがとうございます。選考委員の先生方、学会の運営業務を担当されている先生方、そして、私の著書を推薦してくださった方に、心より御礼を申し上げたいと思います。
『ありのままのイメージ:スナップ美学と日本写真史』は私の初めての単著で、2012年にニューヨーク市立大学の美術史学プログラムに提出した博士論文が元になっています。出版に至るまでは様々な方々のお世話になりました。とりわけ東京大学出版会の木村素明さんは10年以上前にお会いして以来、ずっと私の仕事を気にかけてくださり、今回の本は、企画立案から完成まで、木村さんとともに作業を進めていきました。なお、木村さんが編集を担当された本が、表象文化論学会賞を受賞するのは、今回が3度目だそうです。
気づかれた方もいるかもしれませんが、木村さんが担当された本の多くで「イメージ」という単語がタイトルに使われていて、この本に「イメージ」が入っているのも木村さんの提案によるものです。「ありのままのイメージ」という、学術書らしくないタイトルの由来については、東京大学出版会のウェブサイトに寄稿したブックガイド(https://note.com/utpress/n/n53d5f00aad16)に書きましたので、そちらを読んでいただけますと幸いです。
本書は日本の写真界で「スナップ」と呼ばれる撮影技法およびジャンルの、1920年代から現代に至るまでの歴史を振り返ったもので、一方で、スナップをめぐる写真界の言説や、著名な写真家のスナップ作品を分析することで、その「制度」としての側面を明らかにすることを目指し、他方で、そうしたスナップ撮影行為の背後には、写真という媒体を用いて「世界のありのままの姿に触れようとする願望」があるのではないか、ということを論じました。
今申し上げたとおり、本書は、元々は英語で書かれた博士論文で、全文がProQuestというオンライン・データベースで公開されていますので、それを読んで連絡をくれる海外の研究者も時折いるのですが、書籍として出版する際は、英語ではなく、まずは日本語からという気持ちが強くありました。そもそもどうして博論で日本のスナップをテーマにしたのか、ということについては、本の「あとがき」に詳しく書きましたが、ここで簡単に述べますと、第一に、日本の写真史について英語で書かれた研究に対する需要があったということ、第二に、私自身が写真撮影を趣味としていて、スナップになじみがあったことがその理由です。
では、なぜ書籍化を日本語で、ということですが、日本の写真についての論文を英語で発表したことに対する、ある種の後ろめたさがあったからです。やはり日本の写真史について書くのであれば、日本の読者にその中身を判断してもらわなければならない、そうしないのはズルいのではないか、という気持ちを持っていましたので、その意味では、どのような文脈であれ(現時点で私はまだどのような理由で学会賞に選んでいただいたのか知らないのですが)、日本語版を評価してもらえるということは、自分にとって大きな意味があることです。
この本の題材は日本の写真史ですし、私自身も、私を知る方には写真の研究者、「写真の人」と見られていると思います。例えば、原稿執筆の依頼があるとすれば、その9割9分が、写真という特定の媒体に関するものです。これは客観的には「当然だ」と思うと同時に、主観的には不思議に感じることもあります。というのも、「写真のことだけ考えていても、写真はわからない」と最近、特に感じているからです。本音を言えば、「写真の専門家」という肩書きほど胡散臭いものはないのではないかとさえ、思っています。
実際、優れた作品を作っている写真家が、写真だけに関心を持っている、ということは稀です。むしろ彼ら彼女らは、何か表現したいことや、探求したい対象が別にあって、そのための「手段」として写真という媒体を活用している、という印象を受けます。もちろん絵画も映画も文学も、さらには哲学さえも、最終的には何か別のことを感じたり、考えたりするための手段であるべきなのでしょうが、写真の場合、おそらくその媒体特有の性質ゆえに、「手段性」のようなものを、より強く帯びているような気がします。
それに対して、アカデミックな場で写真を扱うと、どうしても写真は「手段」ではなく、探求の「対象」そのものとなってしまいがちです。本書で「ありのままのイメージ」というキーワード、より正確に言えば、その不可能性というテーマを掲げたのは、写真を手がかりとして、写真以外のこと、具体的には、マイケル・フリードの言う「反演劇性の伝統」や、「もの派」の彫刻や、赤瀬川原平の「トマソン」にも共通するような、「作り込まれていないもの」や「わざとらしくないもの」を尊重する美学について、考えるためでもありました。ただし、それについては本書で十分考察し尽したという感じは持っておりませんので、今後も引き続き考えていきたいと思っています。
本日はこのような機会を与えていただき、どうもありがとうございました。
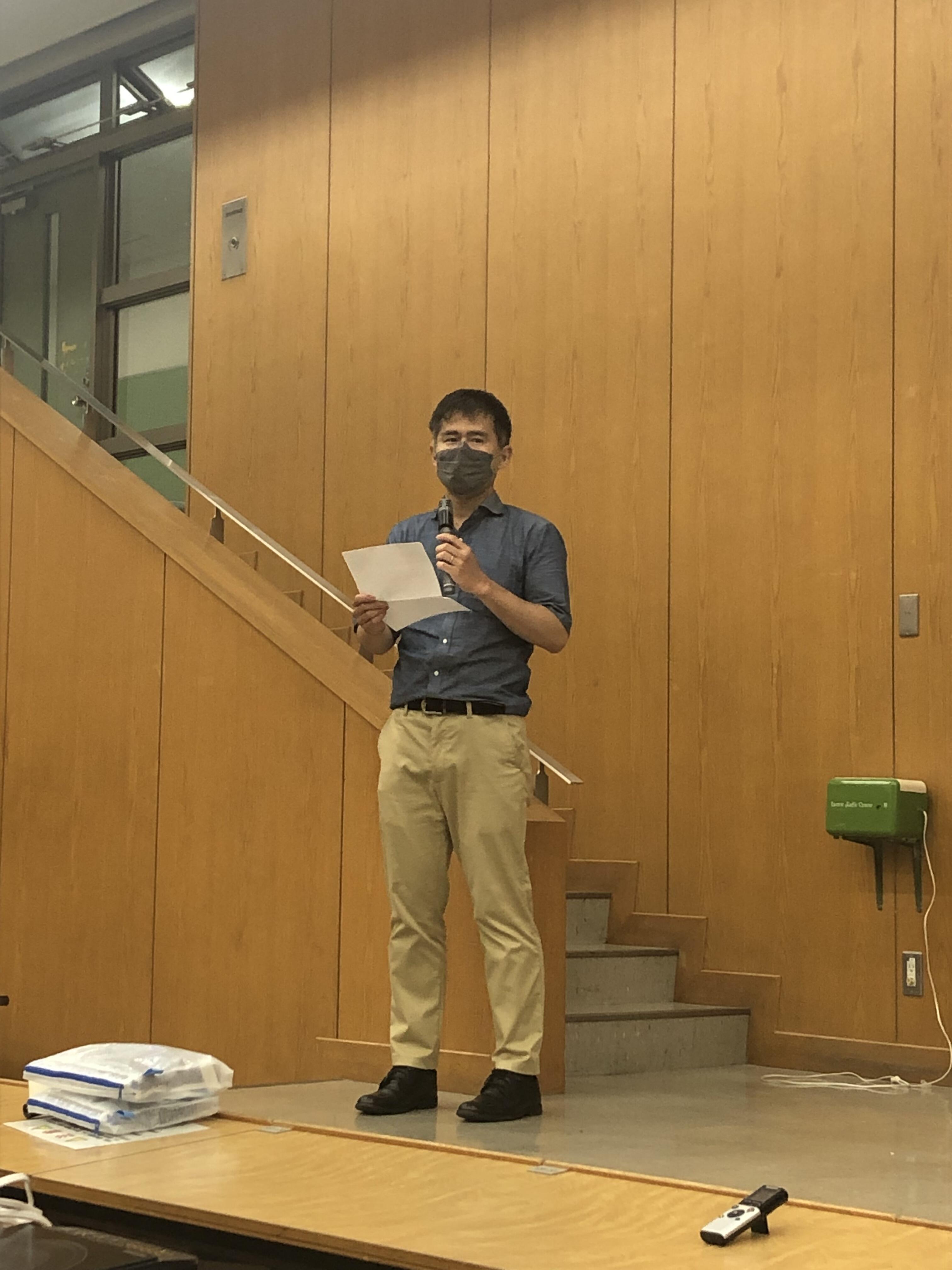
【学会賞】渡名喜庸哲『レヴィナスの企て 『全体性と無限』と「人間」の多層性』勁草書房
この度はこのような名誉ある賞をいただきまして、まことにありがたく、たいへん光栄に思っております。拙い本ではありますが、推薦してくださった方、またお忙しいなかにお時間を割いてお読みくださった審査員の方々にまずは厚く御礼申し上げます。
本日の大会で先ほど行われた料理のパフォーマンス・対談もそうでしたが、つねに日本における表象文化研究・現代思想研究の最先端を走ってきた表象文化論学会の賞を頂戴するというのは、率直に言って、考えてもみなかったことでした。というのも、目下むしろポスト・ヒューマンとか、トランス・ヒューマンとか、「人間」を超脱するような方向性でさまざまな刺激的な議論が深められていると思われるなか、拙著は、あえて「人間」ということを副題に掲げてきわめて地味な議論を展開しているものだからです。また、拙著の帯には「『全体性と無限』で描かれているのは「他者の倫理」ではない」という文句が掲げられておりますが、レヴィナスといえば「他者の倫理」という代名詞があるのに対して、いわば「逆張り」のような主張を提示するかたちにもなっています。
ただし、私としては、通説に異議を唱えて、奇をてらった新説を出すことをそもそも試みようとしていたわけではありません。学会誌の最新号には合田正人先生に書評をいただきましたが、そこで、本書には私自身の動機のようなものが読み取れないと鋭く指摘くださいましたが、それもそのはずで、実は私自身、たとえば10年前には本書のようなものを書くことはまったく想定すらしておりませんでした。むしろ、本書を書かせたのは、私の動機というよりは、まさしく他者たちでした。
後書きにも書かせていただきましたが、博士論文を終えた後、幸い大学にて授業を担当する機会に恵まれ、学生にレヴィナスについて話す機会を得ました。学生の方々にレヴィナスについて説明するわけですが、もちろんなかなか通じない。もちろんレヴィナスの書いていることが難しいということはありますが、とりわけ「他者の倫理」を主軸にするとどうにも辻褄のあわないことがある。自分の論じたいことを書く場合、そういう辻褄の合わない部分は極論すれば触れないままにしておけばよいこともありますが、人に説明するときにはそうはいかない。そういう意味で、授業のコメントで鋭い質問をしてくれた学生はもちろん、ここがわからないということを指摘してくれた学生、あるいは授業中にそこならわかると頷いてくれた学生、いやまったくわからないということを机に突っ伏すなどの態度で示してくれた学生など、それぞれの応答が、「私のレヴィナス」というものを崩してくれました。もちろん、このことは、並行して進めていたレヴィナスの草稿群の翻訳を通じてさらに補強されていきました。翻訳作業もまた、自分の理解の範疇に収まっていなかったものを素通りすることが許されず、理解不能だった他者との対話を余儀なくされるからです。
いずれにしても、拙著はそうした試みを経てようやくまとめることができたものです。拙著が、このような学会で、必ずしもフランス現代哲学を専門となさっている方々ばかりでない審査員の方々に評価いただいたのは、その意味でもたいへん嬉しいことと思っています。逆張りのレヴィナス、というよりは「他者の倫理」には行きつくのではなさまざまなレヴィナスの相貌、その読み方を示すのに、拙著がなんらかの機会になれば望外のことと思っております。
改めまして、この度はまことにありがとうござました。

【選考委員コメント】
- 阿部賢一
まずは選考にあたって設定した個人的な基準について述べたい。本会のHPにおいて、「表象」という概念は「文化的事象を孤立した静的対象として扱うのではなく、それが生産され流通し消費される関係性の空間」と説明がなされている。「関係性の空間」を敷衍すると、学際的、分野横断的な視点を有するものと言えるだろう。次いで、表象文化論学会賞については、同規定第一条に「本賞は表象文化論の分野における独創的で優れた研究および作品等に贈呈される」とある。「独創的」については字句通りだが、「優れた研究」については様々な解釈が成り立つだろう。ここでは、「独創的」を補足する意味合いから「実証的な叙述がなされている研究」として理解した。よって、学際性、独創性、実証的な叙述という三点を重視して選考を進めたことを断っておく。
学会賞として推薦したのは、渡名喜庸哲氏による『レヴィナスの企て──『全体性と無限』と「人間」の多様性』(勁草書房)である。同書は、フッサール、ハイデガーらの系譜も明らかにする広い射程を有しており、レヴィナスに関しては1930年代の論稿から『全体性と無限』に至る一貫した問題意識も見事に示されている。未完小説の分析を含む、広範な議論は、緻密なテクスト読解に裏付けられたものとなっている。また創造の「絶対的な過去」との関係としての「トラウマや教え」という指摘、顔における「見えないものを聞く」という聴覚的次元といった議論は、レヴィナスの思想研究に限定されるものではなく、表象文化論の多くの研究者に示唆を与えるものとなっている。
次いで、私がもう一つの候補として推薦したのが、甲斐義明氏による『ありのままのイメージ スナップ美学と日本写真史』(東京大学出版会)である。木村伊兵衛、土門拳らの写真の美学の本質に迫りながら、日本写真史における「スナップ」の変遷を見事に描き出している。閉じられた過去として写真史を論じているのではなく、今日のデジタル写真の問題にも目配りをした開かれた論考となっている。
二冊ともに学会賞の名前に相応しい奥行きを有する書物であり、今後広く参照されるテクストとなるだろう。
奨励賞を受賞したのは、河野真理恵氏の『日本の〈メロドラマ〉映画──撮影所時代のジャンルと作品』(森話社)である。映画研究で理解される「メロドラマ」という概念とは異なった形で流通する、ローカル・ジャンルとしての日本の「メロドラマ」について、その意味変容を明らかにした論考となっている。何よりも、日本映画の初期のメロドラマ言説では「女性向けの物語」が主であることを明らかにし、作品批評の可能性を見事に提示している。例えば、『新道』(1936)に見られる「去勢化された男性」は、女性観客に対して「自分ならどうする?」という問いかけを投げかけるものであると指摘し、当時の性規範を撹乱する同作の新たな読解の可能性を示している。また井上靖などの事例をあげて文芸との関わりを論じたり、二つの『君の名は?』を踏まえて問題系の広がりを示すことにも成功している。
なお、河野氏は惜しくも受賞前に他界されているが、同氏の著書は同世代、次世代の研究者に多大な刺激を与えるものであり、今後、同氏の意思を引き継ぐ形で研究がなされることを期待すると同時に同氏の功績を心から称えたい。
奨励賞の他の候補作として推薦したのは、山本佑輝氏による『ロバート・アルトマンを聴く──映画音響の物語学』(せりか書房)である。物語学の視点から映画音響を論じる視点は極めて斬新なものであった。文学理論の焦点化を映像にも適用した点は高く評価したい。
今回、候補となったのは十点である。先に述べたように「学際性」「視点の新規性」「実証的な叙述」という三点を基準にした際、今回の受賞作が他の候補作よりも傑出しており、その点は他の選考委員が一致を見たところでもある。いずれにしても、候補作を執筆した十名の著者に対して、知的な興奮をもたらしてくれたことに謝辞を述べたい。
- 佐藤元状
表象文化論学会は、人文学的知の総合格闘技場のようなものだと、私はいつも考えている。映画、写真、絵画、建築、哲学、思想、文学、音楽、なんでもござれだ。そして、その学会賞は、毎年、あらゆる分野の著作の候補作の中から選び出される。もちろん学会員の著作という限定はあるものの、それにしても見事なラインアップだ。今年は学会賞、奨励賞合わせて、10作の候補作を読むことになった。とにかく勉強になる。さまざまなキャリアの段階にいる研究者たちのモノグラフを読むという経験は、かけがいのないものだ。ただ、選考委員であるからには序列をつけなくてはいけない。そこが苦しいところだ。どの作品も素晴らしいが、という前置きは許されない。だから、思い切って、私は自分が一番表象文化論の学会賞並びに奨励賞として相応しいと思い、推薦した3つの候補作についてのみ、選評に記すことにする。なんとこの3つの著作が、選考委員会の総意で、すべて受賞作となったのだから、これらの三作は特別に光り輝いていたのだろう。
今年度の学会賞は、甲斐義明氏の『ありのままのイメージ──スナップ美学と日本写真史』(東京大学出版会)と渡名喜庸哲氏の『レヴィナスの企て ──『全体性と無限』と「人間」の多様性』(勁草書房)に与えられたが、この二作に共通していたのは、「熟成」のプロセスであった。甲斐氏の著作も、渡名喜氏の著作も、それぞれの博士論文をベースにしているが、その完成からおよそ数年が経過して、まとめ上げられたものだ。何事にもタイミングがあり、出版のタイミングを逃したために、出版されずに終わる博士論文も数多い。だが、この二人は、見事なほどに時間を味方につけている。間違いなく、博士論文自体も素晴らしかったのだと思う。ただ、この出版された本には、「追熟」の効果がよく表れている。よく熟成されたボルドーやブルゴーニュのような心地よさと上品さとキレがある。そしてボルドーとブルゴーニュの比較が意味を成さないように、どちらとも同じくらい素晴らしい。私がこの二作を学会賞として推薦した主な理由はそこにある。
私がアマチュアの写真家であるという理由も大きいのだが、『ありのままのイメージ──スナップ美学と日本写真史』は、本当に優れた著作だと思う。スナップの美学の観点から日本写真史を読み直すというその視点だけでも十分に魅力的なのだが、その記述の「スタイル」に、つまりその構成力と文体に私はすっかり魅了された。短い「序論」の後に、第1章から第10章まで、分量に多少の違いはあるものの、同じくらいの長さの章が、家族写真のアルバムのように淡々と続いていく。序論に対応する終章のようなものがつけられているわけでもない。にもかかわらず、全体を読み終えたときに、大きな満足感がある。日本写真史を理解したような錯覚さえ覚える。それはひとえに書き手の構成力に由来しているのだろう。一つの章のなかにどれくらいヴィジュアル資料を入れればよいか、またそれらをどれくらい精緻に分析すればよいか、そのレイアウトはどうすればよいか──そういったことが、すべて計算し尽くされているように思われるのだ。そしてスナップの美学を文体の上で模倣するかのような、クリーンなシンプルな文章。(おそらく博士論文の残滓なのだろうが)まるで論理的な英語の文章をそのまま自己翻訳したかのような、気取らない日本語の文章が、その対象に見事にマッチしているのだ。
『ありのままのイメージ──スナップ美学と日本写真史』が繊細なブルゴーニュだとすると、『レヴィナスの企て──『全体性と無限』と「人間」の多様性』は力強いボルドーである。選評でどこまでワインのメタファーが許されるのか心配だが、私の直感では、サン・テステフのシャトー・モンローズのような味わいだ。何かが立ち上がってくるような立体感があって、かつどこまでも濃厚なのだ。私が感じた立体感は、この著作の堅固な構造に由来すると考えられる。実際、『レヴィナスの企て』は、レヴィナスの思想形成のプロセスを時系列順に追いかけながら、『全体性と無限』を<他者の倫理>とは別の観点──つまり、「人間」の多様性の観点──から読み返す、という明快な目的で書かれているが、本書の構造は、その目的に合致するようなクラシックな構成となっている。「はじめに」から「終章」に向けて、第1部、第2部、第3部、第4部と、レヴィナスの多面的な思想が段階的に明らかにされていくが、その構造のなんと堅固なことか。第3部までの周到な準備を経て、第4部で『全体性と無限』を正面から論じるという、その構成のあざといまでのシンプルさ。そして、この著作の濃厚さは、渡名喜氏の語りのモードに由来しているのだろう。渡名喜氏は、哲学研究者というよりも、むしろ広場の哲学者のように、一人の対話者として、読者に語りかける。あらかじめ哲学的な言説に慣れていない読者でも、セミナーに初めて参加した学生のように、安心して、その濃密な議論に身を任せることができる。そこがこの著作の限りない魅力であり、美質なのだ。
最後に、奨励賞に選ばれた河野真理恵氏の『日本の〈メロドラマ〉映画 ──撮影所時代のジャンルと作品』(森話社)について。すでに知っている人も多いと思うが、彼女はこの本を残して私たちの世界を旅立ってしまった。だから本書は河野氏の最初にして最後の著作となる。本来であれば、著作についてのみ語るのが筋であるのは重々承知しているが、こうした事情に鑑みて、ここでは特別に迂回路をとらせてほしい。
私は彼女に二度会ったことがある。最初は酒席で、最後は学会で、あくまで映画研究者の知り合いのような関係だ。酒の席の彼女は、快活でびっくりするほど話がうまかった。初対面であるにもかかわらず、あまりにいろいろなことを話してくれるので、会の終わりには、何年も前から彼女を知っているような不思議な錯覚を覚えたほどだ。そのときの会合で一番印象に残っているのは、「私は映画のセンスが良い」という台詞だ。もしかしたら、少し異なった言い回しだったかもしれないが、いずれにしても、その意図は明確である。「なんという自信だろう! 若さとはかくなるものか!」と羨ましく思いながら、帰途についたのだが、それから数年後に、成瀬巳喜男シンポジウムで彼女の研究発表を聞いたとき、なるほど、と膝を打った。たしかに彼女は「映画のセンスが良い」と。私には、河野氏が成瀬の映画を直感的に理解していることが、すぐにわかった。懇親会でそのことを話したかったのだが、それは叶わずに終わった。
著作にもどろう。『日本の〈メロドラマ〉映画──撮影所時代のジャンルと作品』の美質は、その圧倒的なセンスの良さにある。河野氏は本書で、ローカル・ジャンルとしての<メロドラマ>という観点から、戦前から戦後にかけての日本の<メロドラマ>の歴史的・文化的特殊性を浮き彫りにしていくが、そこでもっとも光り輝いているのは、具体的な映画作品を論じる際の彼女の批評的センスである。この研究書の偶数章のタイトルを見てみよう。第2章は「『新道』 転覆的な女性映画」、第4章は「映画『君の名は』三部作(一九五三―一九五四) 欲望と道徳のマゾヒスティック・メロドラマ」、第6章は「『猟銃』(一九六一) 権力と背信の洗練されたファミリー・メロドラマ」、第8章は「『続・愛染かつら』(一九六二) 自己言及的でグロテスクなバックステージ・メロドラマ」となっている。本論の8つの章のうちその半分のメイン・タイトルが、あたかも計算されたかのように、映画の作品名となっているのはなぜだろうか。それは端的に<メロドラマ>のジャンルの変遷を主題とするこの映画研究書にとって、個別の<メロドラマ>作品を分析する映画批評が決定的に重要な意味を帯びていることを意味している。つまり、本書は、<メロドラマ>研究書であると同時に、<メロドラマ>映画批評ともなっていて、これらの映画批評には、彼女の類まれな批評的センスが脈打っているのだ。「私は映画のセンスが良い」──それはどこまでも正しかったのだ。
- 平倉 圭
極めて水準の高い著作が集中した年であり、ここから数点を選ぶことは困難であった。審査では、著作としての一貫性・統合性、問いと論じ方を発明していく創造性、非専門家にも開かれた視野の広さと面白さを基準として判断した。
以下、受賞作についてコメントしたい。
甲斐義明『ありのままのイメージ──スナップ美学と日本写真史』(東京大学出版会、2021年)は、その圧倒的な面白さと分析の深度で私を驚愕させた。ニューヨーク市立大学に提出された博士論文を元にした本書は、著名な写真家たちを辿るのではなく、日本において執拗に問題であり続けた「スナップ」という技法/ジャンルを通して、日本写真史の姿を鮮やかに描き直す。大著だが文体はキビキビして読みやすく、制度/イデオロギーとしての「スナップ」の歴史的展開をめぐる重厚かつ緻密なリサーチを個々の写真記述と組み合わせ、読者の写真理解を深部から更新する。
私にとって最大の驚きは著者の写真記述であった。日本近代のプロ/アマチュア写真家たちがスナップという実践を通して何を思考してきたのかが、言説のみならず、写真自体から解明されるのだ。例えば木村伊兵衛《ブロマイド屋》の幾何学的形態と、女性の「無意識」に見える指先の身振りの分析──そこから無意識的偶然と意識的構築の境界性の表現が、あくまで構造的に、明晰に言語化されて分析される。
本書を読むことは、写真を見るための新たな眼が作られていく経験である。「スナップ」という特定の主題を越えて、日本語で書かれた写真論の水準を一挙に引き上げる著作であり、学会賞にふさわしい。
渡名喜庸哲『レヴィナスの企て──『全体性と無限』と「人間」の多層性』(勁草書房、2021年)は、エマニュエル・レヴィナスの主著『全体性と無限』がどのような問題意識から生成してきたのかについて、多数の資料を博捜しつつ、従来の「顔の倫理」を中心化するのではない仕方で解き明かす。そこに現れるのは、この物質的な身体に「釘付け」され「繫縛」されている「私」が、糧を「享受」することにおいて、呼びかけに「応答」することにおいて、また「女性的なもの」を「愛撫」することにおいて、自身の外へと超越しつつ他のものとして統合される複数の回路である。この超越の複数の回路への注目によって、『全体性と無限』のレヴィナスが構想した人間の姿が立体的に浮かび上がる。著者の長年の研究成果をまとめたものであり、その論述の統合性と読解の徹底性から学会賞にふさわしいと判断した。
「女性的なもの」や「家族」や「繁殖性」をめぐる明らかにジェンダー化されたレヴィナスの異様な語彙群が、現代においてどう扱われ、またどう変形されうるのか。『全体性と無限』以降のレヴィナスの変化に関する研究と合わせて、著者のさらなる仕事の展開に期待したい。
河野真理江『日本の〈メロドラマ〉映画──撮影所時代のジャンルと作品』(森話社、2021年)は、フィルム・スタディーズにおける「メロドラマ」概念が成立する以前から日本に存在し、語られ、創造されてきた〈メロドラマ〉の姿を明らかにするものだ。著者が注目するのは、映画研究において標準化された「メロドラマ」と、日本のローカル・ジャンルとしての〈メロドラマ〉の特徴を併せ持つ、著者が「範例的作品」と呼ぶ映画たちである。それらの分析を通して、超越性を劇的に噴出する一種の普遍的メロドラマの地層が、歴史的特殊性を超えて垣間見られる。
読者としての私をとりわけ捉えたのは、著者の身体描写である。例えば『君の名は』三部作のヒロイン真知子(岸恵子)の卒倒を「自らの無力さに対するひけらかしの態度」に見せる、「甲高く粘り気のある声や……泣いているときですらなぜか笑うようにつり上がった口角」への注目がそうだ(129頁)。著者の文を通して、読む者は〈メロドラマ〉の劇的身体の内側へと巻き込まれる。複数の章の最後で示されるメロドラマ映画のリストもたいへんな労作だ。この著者のパッションは、本書に触れる者たちに確実に引き継がれるだろう。その功績を称えて、奨励賞を与えることがふさわしいと判断した。
- 山口裕之
表象文化論学会賞での選考は今年で2年目となるが、やはり強く感じるのは、「表象文化論」という領域のはば広さと、そのなかで「学会賞」を選ぶことの難しさだ。候補作を読み、それらの選考を行うという作業にかかわるとき、「表象文化論」とは何かという出発点の問いに何度もたちかえることになった。
審査にあたって、個人的には次の二つの指針を意識していた。
(1)「表象文化論」の仕事であると見なされるものであること。つまり、一般的に表象文化論に包摂されると理解されている既存のディシプリンの研究であっても、むしろその(軸足となる)ディシプリン固有の研究であると考えられるものは該当しないだろう。
(2) 現代の文化・社会の中に関係づけられるアクチュアリティをもつかどうか。対象の圏内のみに視野が限定されるのではなく、その研究が現代のコンテクストのうちに位置づけられているかどうか。
今回、「学会賞」を受賞した
・甲斐義明『ありのままのイメージ スナップ美学と日本写真史』東京大学出版会
・渡名喜庸哲『レヴィナスの企て 『全体性と無限』と「人間」の多層性』勁草書房
および「奨励賞」を受賞した
・河野真理江『日本の〈メロドラマ〉映画 撮影所時代のジャンルと作品』森話社
の3つの作品については、4人の選考委員の全員が受賞にふさわしい作品として推薦し、問題なく全員の意見がまとまったということは、強調してよいことではないかと思う。
・甲斐義明『ありのままのイメージ スナップ美学と日本写真史』東京大学出版会
「スナップ美学」を日本の独自な「美意識」としてとらえ、その歴史的変遷をたどりながら10章で描き出す、スナップ美学を軸とした「写真史」の試みとなっている。オーソドックスで誠実な手つきにより、きわめて多くの具体的資料・写真に基づいた「写真史」となっており、日本の写真史の文献として最も重要なものの一つになるだろうと感じた。
構成的・論理的志向が前面に出るのではなく、具体性・事実性によって成立した仕事である。そのことは本書の強みであると同時に、一つの大きな「写真史」を描くという意図が、具体的・事実的なものにどうしても集中してゆく各論では後退する印象があったが、それを補って余りある面白さと情報量をもつ著作であった。
・渡名喜庸哲『レヴィナスの企て──『全体性と無限』と「人間」の多様性』勁草書房
エマニュエル・レヴィナスの最初期から『全体性と無限』に至る思想に一貫した「企て」を読み取ることによって(その際、従来の「他者の倫理」という読解の軸をあえて取り去る)、レヴィナスの思想を新たに構成し、それを通じて『全体性と無限』の再読を行うというのが本書の軸である。そのために、第Ⅰ部から第Ⅲ部にかけて時系列的に思考の展開を追いつつ、第Ⅳ部で『全体性と無限』の再読・再構成を行うという流れをとる。分量的には第Ⅲ部までで半分、残りの半分が第Ⅳ部となる。第Ⅳ部のために第Ⅲ部までの叙述が用意されたのかもしれない。
非常にオーソドックスで誠実な思想の読解の作業である。テクストの内在的読解と再構築をたどってゆくことになる。この著作は外に向かって開かれていない印象を与える。しかし、整合性を持って読み解くことに困難がある『全体性と無限』のテクストの内的論理を明確に解き明かしていくという強い意識は明確に示されており、そこにこの著作の意義を強く感じた。
・河野真理恵『日本の〈メロドラマ〉映画──撮影所時代のジャンルと作品』森話社
日本映画史における「メロドラマ」が、映画史全般の中での概念としての「メロドラマ」とは異なる、独特な位置づけをもつものであることを丹念に検証してゆく著作であり、映画理論史と映画そのものに関しての安定した知識、過去の日本メロドラマ映画の資料的調査、そしてまた信頼感・安心感を与える映画に対する感覚といった点でも、日本映画研究にとって非常に重要な文献となるであろうと感じた。各章での個々の特定の作品に焦点を当てた論述の仕方に、いささか表層的な事実的事項の記述とその整理に終始するところも感じさせないではなかったが、ともかく読者を惹きつける筆の運びと安心できる情報提供、全体としての構成のうまさなど、推薦できる本である。
これだけの魅力的な本を出した河野真理恵さんが、この受賞の時点ですでに亡くなっておられるということはあまりにも惜しまれる。ご冥福を心からお祈りしたい。
以下、受賞を逃した候補作についても言及したい。
・中村大介『数理と哲学:カヴァイエスとエピステモロジーの系譜』青土社
ジャン・カヴァイエスの数理哲学を中心に据えながら、「フランス・エピステモロジー」の系譜を描き出すことで「エピステモロジーの思想史」を構成。科学と技術の「重ね合わせ」を意図していることについては、とくに今日的な意義が大きいだろう。
総論での全体の逞しい設計の意図の提示はとても好ましい印象。そこでは濃密なエネルギー感を持つ。著者自身「論文集」という表現をしているが、比較的短い論文が積み重ねられていく印象が強い。各論文とも、明晰な言葉で突き進む。きわめて明快な語り口をもち、そのことはこの著作の長所であるとともに、そこまで単純な整理の仕方だけでよいのだろうかという疑問を誘発せずにはおかないところもある。
単に思想の内在的分析に終始するのではなく、そこには科学・技術と哲学の「重ね合わせ」としての「フランス・エピステモロジー」を捉えるという明徹な意図が終始貫かれている。しかし、全体としての「結論」でもう一度各論文が束ねられることなく、「補論」で終わっているところがなんとなく力を削がれてしまう印象ではあった。
・古川真宏『芸術家と医師たちの世紀末ウィーン──美術と精神医学の交差』みすず書房
「芸術と精神医学のあいだの錯綜した関係を浮かび上がらせることを目的としている」とあるものの、実際には、精神分析・医学的な視点を含めつつ複数の芸術家とその作品についての叙述を行ってゆくことに終始するという印象が否めない。「錯綜した関係」そのものを浮かび上がらせてゆく理論的な軸が示されることによって独自の面白さが生まれたのではないか。美術史に関わる事実的なことがらの叙述が中心を占め、いくつかの思想家の言説に関する言及も比較的表面的なものにとどまる。また、世紀転換期ウィーンのさまざまな事象についての詳細な記述は素材的にそれ自体として興味深いものであるが、それらはほぼ既存の研究(二次文献)に由来するものであるように思われる。
・松木裕美『イサム・ノグチの空間芸術 危機の時代のデザイン』淡交社
個人的にはとても好感をもった著作だった。もともとフランス語で執筆した博士論文を、日本語で「一般向け」に書き直したものとのこと。おそらくフランス語の博士論文は、かなりのレベルのものではないかと感じさせる。
4つの章をどのような意図によって組み立てて論じようとしているかという設計が、「はじめに」できわめて明確に説明されており、この設計にとても共感を覚えるとともに納得できる構成意図となっている。全体に非常に分かりやすく明快・簡潔に「イサム・ノグチの空間芸術」の特質を示す著作となっているが、既存の理解をまとめた単なる概説書なのではなく、そのような視点そのものが著者の研究の成果を示すものとなっており、その意味で理想的なかたちのアカデミックな本と言えるのではないか。
・貞包英之『サブカルチャーを消費する:20世紀日本における漫画・アニメの社会学』玉川大学出版部
「作品は…自明」であるのに対して、「社会は…自明ではない」、それゆえ社会から作品を説明するのではなく、作品から社会を説明するのだ、という前提。しかし、「作品は…自明」という前提を、文学・芸術に関わるものは口にできないのではないだろうか…
ともあれ、まさにそのような立場から、「作品」が分析のための手段としてとりあげられる。「サブカルチャー」は「社会」を語るための単なる素材・証拠品となり、そこにはサブカルチャーのテクストのうちに入り込もうとする表象分析の視点は存在しないように感じられる。しかし、そのことをおけば、本書はこのテーマに関する非常に興味深い研究であることはまちがいない。
・宇佐美達朗『シモンドン研究 関係の実在論の射程』法政大学出版局
「シモンドン哲学の構造と機能、そして発声に光を当て」「この哲学を一つの体系として提示する」というのがこの著作の目指していることだが、個々のテクスト読解そのものの誠実さと真摯さには何の疑いもないとは言え、そのテクスト読解が何を目指すものであるかという位置づけの意識・眼差しがそこには決定的に欠けているように思われる。
なぜシモンドンなのか、シモンドンの哲学を論じるということはどのような意味をもつのかというコンテクスト化がないまま、シモンドンのテクスト表層の謎を解き明かし、思考を説明しようとする。この位置づけがあれば、この著作のもつ力は大きく変わったのではないだろうか。
・山本佑輝『ロバート・アルトマンを聴く──映画音響の物語学』せりか書房
ハリウッド映画の中でのロバート・アルトマンの異色のポジションを、「音」から捉えるという試みは、そのアプローチ・視点そのものの面白さから、アルトマン研究として意義をもつものであるように思われる。それとともに、「音」と「ナラトロジー」を結びつけるという点でも、重要なフィルム・スタディーズの業績となっている。各章の構成は、一見、個別研究を合体させたもののように見えてしまうのだが、全体としての構成の意図を終始保持していることによって、決して作品論的な叙述で終わることはない。終章での「フィクションの新たな叙述に向けて」までうまく構成されている。そして、個々の具体的分析も説得力をもつものであり、全体としてとても好感がもてる著作であった。
・髙山花子『モーリス・ブランショ』水声社
丹念にテクストと向き合う。ブランショのテクストから思考を読み取ろうとテクストに沈潜し、そこから思想の言葉を紡ぎ出す。そのような読みの行為に対する敬意と共感を抱いた。しかし、他方で、思考が自らの内部のゆったりとした空間の中でひたすら生み出されるものとなっており、それが外の世界に対して働きかける力をもつことになるのだろうかと疑問を感じてしまう。
各章の位置づけは序に示されており、執筆者にとって必然性をもつ構成であるのかもしれない。しかし、読者にはやはりそれが読書を通じて流れ込んでいく書き方になっておらず、各章の意図がそれぞれ独立したものとして個々に置かれているように感じてしまう。(小さな論文を後からくっつけたものではなく、全体が描き下ろしであるにもかかわらず。)批評では、語る言葉が対象の作家の言葉に憑かれてしまう。そのような言葉がここにも現れているのかもしれない。