『わざの人類学』
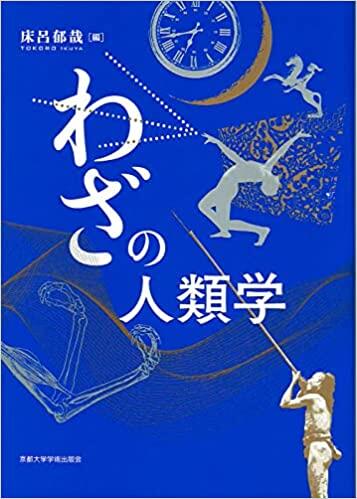
「わざ」とひらがなで表記される実践事象はいたるところに転がっている。身体各部の協調が織りなす身体動作と技法から、芸能や芸術における技芸とその視聴、化粧やコスプレの身体変容アートから、料理法、土木建築、暦、さらには原子力、チンパンジーの生活様式、昆虫の擬態、動物(非人間)の生態関与観察法まで、本書が取り扱うアーツの幅は恐ろしく広い。そして一見したところ、明確な焦点を結ばない。しかし「わざ」なる実践が行儀よく理解の範疇におさまらないことこそ『わざの人類学』が技術論でも身体技法の民族誌でも伝統技芸の記録でもないことの証である。ある論考(西江仁徳論文)が言及しているように、本書自体が「知の技法・わざ」の創造にもなっている。
周知のように、人類学は、存在論的転回以降、動物やモノといった非人間との相互行為の様式を民族誌的に捉えるなかから、複数の存在論の可能性をマジに語り出した。『わざの人類学』はそうした複数の存在論を支えるたくさんの実践たちを「わざ」として括ることで、人と人々とそれらを取り囲むモノや動物たちとの相互作用を可視化しようとしている。学ぶべきは、実践がどのような意味で「わざ」なのか、多様な文脈における多様な「わざ」本性であると思う。それは、編著者の言葉を借りれば、設計/非設計、近代的/伝統的、テクノロジー/テクネー、呪術的/技術的といった理念型の二分法理解の向こう側に迫ることだ。
裏舞台をちょいと告白。本書は東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所(通称、AA研)の数年にわたる共同研究の成果である。編著者の床呂先生に呼ばれて文化人類学の専門家を前に「アフォーダンス」やら「協調」やら「ギブソン」やら「ベルンシュタイン」やらを「わざと学習の本性」なるテーマで話した機縁から私も執筆の機会をいただいた(コロナ禍の前が懐かしい)。ラッキーとばかりに知の交流技法を学習しつつある。さて、この先、何が出てくるかな。
(染谷昌義)