あまりに人間的なウイルス COVID-19の哲学
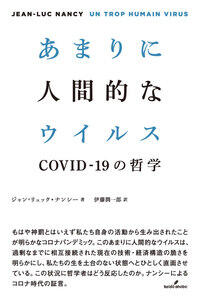
あらゆる思考には日付がある。非常に普遍的にみえる概念を操る哲学であっても、時代のしるしが刻み込まれている、とはよく言われることだが、コロナ論ほどそれを実感させてくれるものはないだろう。そこに刻印されているのは、もはや「時代」という言葉が不適切に感じられるほど短いスパンで移り行く状況である。二〇二〇年の春先から夏にかけてジャン゠リュック・ナンシーが発表したコロナ論を収める本書の端々にも、執筆当時の刻一刻と変化する事態の影を認めることができる。
しかし、哲学者である以上、当然のことながらナンシーは可能なかぎり巨視的な視座を提示しようともする。コロナ禍において問われているのは、手に負えない状況を自分自身の手で作り出し、そこから一向に抜け出せなくなっている「あまりに人間的な」人間のあり方であり、その背後には過剰なまでの「相互接続」が存在しているのだ、と。こう語るナンシーの語調は、一見すると悲観的なものに思えるが、本書のいたるところに現状を突破するための開口部が穿たれていることを見逃してはならない。
そこで鍵となっているのが、「理由がないこと」や「土台のない状態」である。パンデミックはいかなる計算や予測によっても把握できない不確実性の前にひとを立たせるわけだが、それは同時に究極的な保証の不在という人間の生の深部へとまなざしを向けるチャンスでもある。安心を与える保証に飛びつくことなく、不確実性に同意するような生を生きるという結論は、予測された数字を絶対視したり、安手の陰謀論が流行したりする現状からすれば、見かけほど簡単なものではないだろう。しかし他方で、不確実性を織り込んだ生の実践として挙げられている例(芸術、思考、愛、歌など)が、けっして突飛なものではないこともたしかだ。本書は、コロナ禍においていま一度こうした行為に目を向け、不確実性を前にした生がどのようなものであるか再考を迫るとともに、ナンシー自身がいかにしてそのような生を生きたのかを物語る唯一無二の証言となっている。
(伊藤潤一郎)