映画の詩学 触発するシモーヌ・ヴェイユ
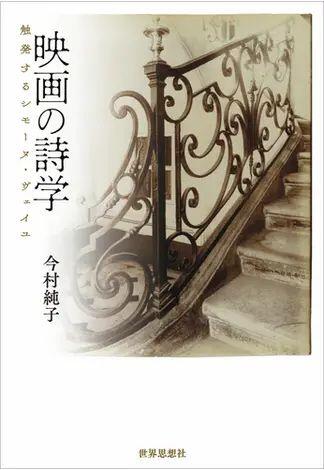
宮崎やメカスやゴダールや小津をはじめとする映画とシモーヌ・ヴェイユの言葉は、本書にあって、例証、あるいは註釈、説明の関係に置かれるのでなく、 それぞれが端的にそのものとして存し、ときに著しい対照を描きながら、またときに完璧に同じことがらを述べ、表すようなものとしてある。たとえば、直截的な並列によっていみじくも「シモーヌ・ヴェイユとマヤ・デレン」と題される終章の末尾近く、ふたりの生と作品は「彼女たちが、確かに「いま、ここ」という 現在の一点にあった」ことを等しく示しているといわれる。あるいは別の章で、 キム・ギドク『春夏秋冬そして春』に登場する老僧が、「放蕩息子の譬えの兄のほう」に触れるヴェイユの言葉とともに、物質にも通じるその特別な受動性において注目される。トルナトーレ『ニュー・シネマ・パラダイス』のうちに探られるのは「イタリアのシモーヌ・ヴェイユ」そのものである。互いに離れるかに見えるものが結ばれるのは、綺想や遊興のゆえではむろんない。もともとそれらは結ばれていたのである。「シモーヌ・ヴェイユからはむしろ離れ、映画という具体的な芸術に沈潜していったときに、ヴェイユの名をいっさい出さず、ヴェイユの思想をいっさい語ることなく、彼女の思想がわたし自身の言葉としてあらわれ出てきたのだ」。巻頭近くのこの言葉は強い確信は湛えるかのようであり、たしかにそうでもあるはずだが、ただそうであるばかりではなく、むしろしごく当然に、「弱い思考」(ヴァッティモ)を丹念にたどること、映し出される無数の身ぶりや表情、風景、流れる音、言葉のひとつひとつへ注意──このヴェイユにおける鍵語のひとつも、いま大きく毀損されようとしている──を向けることへつうじている。副題に含まれた「触発」が深く首肯されるゆえんでもある。
(森元庸介)