宮川淳とともに
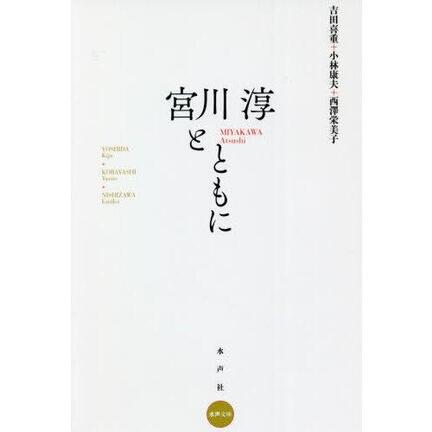
この本のために新たに短いテクストを書き起こしたのだが、その冒頭に「これが最後だ。二度とわが師・宮川淳について書くことはないだろう」と書いた。そうしたら、水声社・社長の鈴木宏から「これはあんまりだから、やめてくれないか」と言われたのだが、わたしは譲らなかった。無謀であることはわかっていたが、その言葉の響き以外に伝えることはないという気持ちだったのだ。
この本は、宮川淳と東大の同級生であった映画監督・吉田喜重氏に、宮川淳の成城大学の学生であった西澤栄美子が2006年に行った長時間のインタビューの記録「宮川淳の思い出」をメインに、わたしが2019年に日仏会館のシンポジウム「イマージュと権力、あるいはメディアの織物」で行った基調講演「エピステーメの衝撃──宮川淳から出発して」などをアレンジして1冊にまとめたものである。44歳で宮川淳が亡くなったのが1977年。それから44年経ち、宮川淳の存在によって知り合い、結び合わされたとも言うべき鈴木宏・西澤栄美子・わたしの三人が、先生の友人であった吉田喜重の思い出の語りを軸として、ささやかな一冊を遠いとおい追悼として捧げるものである。
では、それが表象文化論学会の会員の皆さまにどういう「意味」があるか?と鋭く問う人がいるとしたら、わたしは次のように答えたいかな?──いつか20年後、30年後に、大学の単なる制度としてではない、まさに「知」の一形態としての「表象文化論」の淵源がどこにあったか、というアルケオロジー的問いが発せられることがあるとしたら、そのとき、それは、疑いもなくミシェル・フーコーの思考が怒濤のようになだれこんできた日本の70年代の文化にあるということになるだろう。そして、きわめて激しかったこの「知」の変容にあって、たんなる美術批評などというものを超えて、とりわけモーリス・ブランショあるいはジャック・デリダの思考を背景に「イマージュ」という非人称的にして、なんとも危険な問題系を徹底して追究した宮川淳の仕事は、まちがいなくその原点のひとつであったのだ、と。
(小林康夫)