第12回表象文化論学会賞
【学会賞】宮﨑裕助『ジャック・デリダ 死後の生を与える』(岩波書店)
【奨励賞】入江哲朗『火星の旅人 パーシヴァル・ローエルと世紀転換期アメリカ思想史』(青土社)
馬場靖人『〈色盲〉と近代 十九世紀における色彩秩序の再編成』(青弓社)
【特別賞】該当なし
選考委員
- 沖本幸子
- 郷原佳以
- 平倉 圭
- 山口裕之
選考委員会 2021年5月15日(土) オンラインミーティング
選考過程
2021年1月に、表象文化論学会ホームページおよび会員メーリングリストをつうじて会員から候補作の推薦を募り、以下の著作が推薦された(著者名50音順)。
【学会賞候補作】
- 塚田幸光『クロスメディア・ヘミングウェイ アメリカ文化の政治学』(小鳥遊書房)
- 橋本陽介『中国語における「流水文」の研究 「一つの文」とは何か』(東方書店)
- 宮﨑裕助『ジャック・デリダ 死後の生を与える』(岩波書店)
【奨励賞候補作】
- 井岡詩子『ジョルジュ・バタイユにおける芸術と「幼年期」』(月曜社)
- 入江哲朗『火星の旅人 パーシヴァル・ローエルと世紀転換期アメリカ思想史』(青土社)
- 越智雄磨『コンテンポラリー・ダンスの現在 ノン・ダンス以後の地平』(国書刊行会)
- 橋本陽介『「文」とは何か 愉しい日本語文法のはなし』(光文社)
- 馬場靖人『〈色盲〉と近代 十九世紀における色彩秩序の再編成』(青弓社)
- 宮本裕子『フライシャー兄弟の映像的志向 混淆するアニメーションとその空間』(水声社)
【特別賞候補作】
推薦なし
選考作業は、各選考委員が候補作それぞれについて意見を述べ、全員の討議によって各賞を決定してゆくという手順で進行した。慎重かつ厳正な審議の末、学会賞に宮﨑裕助氏の著作、奨励賞に入江哲朗氏と馬場靖人氏の著作を選出することに決定された。
【受賞者挨拶】(2021年7月3日オンライン)
【学会賞】宮﨑裕助『ジャック・デリダ 死後の生を与える』(岩波書店)
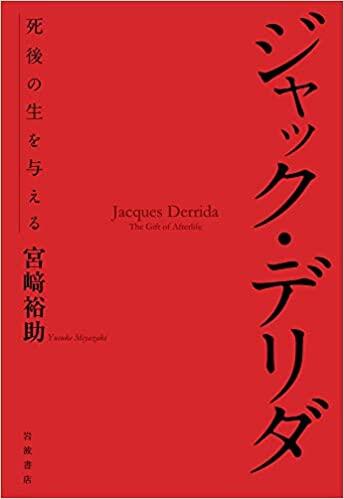
このたびは、表象文化論学会賞を受賞することができ、たいへん名誉に感じております。まずは、査読の労をとってくださった選考委員の先生方、またご推薦いただいた会員の方々、本書を刊行するまでのあいだにお世話になったすべてのみなさまに心からの御礼を申し上げます。
本書は、2004年に亡くなったジャック・デリダの思想を、主に90年代から扱うもので、いわゆる後期デリダ、晩年のデリダを論じたものになります。デリダは哲学者として知られていますが、とくに晩年の主題には、哲学や思想だけでなく、言語、翻訳、文学、宗教といった人文学のテーマから、国家や民主主義、労働、家族、贈与といった社会科学的なテーマ、また、動物、遺伝子、自己免疫といった生命科学のテーマにいたるまで、多岐多様で領域横断的な広がりがあります。このような広がりに答えようとする本書が、いかなる学会で評価されうるのかと言えば、表象文化論学会以外にはありえないのではないかと思っています。
私は表象文化論に、大学院の入学以来、また2006年の学会創設以降は学会の運営や学会誌の編集等で、ほぼ四半世紀にわたって多少なりとも関わってきましたが、いまだによくわからないところがあります。映画、美術、演劇、音楽、建築等の芸術研究、それらと関係する視覚文化論やメディア研究、現代思想といったあたりがおおむね重なる分野かと思いますが、それらに尽きるわけではありません。おそらく長く関わっている人に尋ねても、十人十色の説明があるのではないかと思います。
私自身は、伝統的なディシプリンとしては哲学研究から始めましたが、表象文化論で学ぶようになってからは特定のディシプリンからくる抑圧を一切うけることなく研究できたと感じています。本書には、この学会で発表した原稿が基になっている章もありますし、表象文化論で得られた研究者仲間に多かれ少なかれ負っている問題関心や議論の方向性が数多くあります。振り返ってみると、表象文化論という枠組みがなければ、そしてそこで得られた友人知人たちの存在がなければ、私は本書を書き上げられたかどうかわかりません。
デリダのテクストがときに読解不可能で、いかがわしくすらあるのと同じ意味で、表象文化論が定義不可能で、融通無碍でありながらどこか捉えどころのない怪しい雰囲気を漂わせている、そうしたところを私は気に入っています。表象文化論を設立した中心人物の一人である蓮實重彦先生が「オリンピックなどやりたい奴が勝手にやればよろしい」と喝破したエッセイをつい最近目にしました。途方もない量の著作を積み上げてきたこの権威が、八〇代半ばにしてなお自由闊達な無責任さを炸裂させているの前にして、爆笑と感嘆を禁じえませんでした。
そうした無責任さを引き合いに出すのは、学会といい、学会賞といい、またその受賞スピーチといい、このような儀礼づくめでの場にふさわしくないのかもしれません。しかしだからこそ、さまざまなコンプライアンスや感染病対策の自粛要請でがんじからめになっているいま、無責任さそのものが許されなくなったこの世の中で、表象文化論が担っていたはずの無責任さはどこにあるのかと自問せざるをえませんでした。
今回受賞した私の本がそうした積極的な無責任を体現しえたなどとうぬぼれるつもりはありません。ただ、デリダという書き手の怪物的なテクストに、表象文化論学会賞に見合うかたちで取り組んでいるのだとするならば、本書はそうした無責任さにどこかで触れることができたのではないかと信じています。デリダのテクストは、テクストに対する忠実ゆえの不忠実さを要求するということを本書は強調しています。それと同様に、賞に対する責任ゆえの無責任さ、責任そのものを解きほどく責任をあなたはどのように果たすことができるのか、と、今回のこの受賞が私に問いかけてきている気がしました。そうした無責任な責任をあなたは担う覚悟があるのか、と。
半ば独り言めいた一方的な問いかけによってこのスピーチを締めくくるのはたいへん心苦しいのですが、少しばかりの無責任さの実践として、ここで共有することをご容赦いただければ幸いです。以上をもって、受賞の言葉とさせていただきます。このたびは、まことにありがとうございました。
【奨励賞】入江哲朗『火星の旅人 パーシヴァル・ローエルと世紀転換期アメリカ思想史』(青土社)

このたびは、拙著『火星の旅人── パーシヴァル・ローエルと世紀転換期アメリカ思想史』が表象文化論学会賞奨励賞という栄えある賞を授かり、心より嬉しく思っております。拙著の完成に寄与してくださった方々にいまいちど御礼申し上げます。表象文化論という学問領域に対して私は高校生のころより憧れを抱いておりましたので、「表象文化論」という言葉を冠する賞をいただくことの喜びもひとしおです。
高校生のころからの憧れ、といま申しましたが、具体的には、高校生の私が読んだ表象文化論の本のなかに小林康夫さんの『表象の光学』(2003)と蓮實重彦さんの『表象の奈落』(2006)があり、当時、2冊を見くらべながら「表象文化論とははたして光の学問なのか、それとも闇の学問なのか」と困惑したことをよく憶えております。もちろん実際のところは、表象文化論の研究対象の媒質は決して光に限られず、文字や音や電子を媒質とする対象も表象文化論は盛んに論じており、ゆえに「表象文化論は光の学問か闇の学問か」というのはそもそも問いの立て方が間違っております。ともあれ高校生の私にとっての表象文化論は、光を読解する学問、あるいは光の欠如を読解する学問でした。
そんな個人的記憶を引きあいに出したのは、このたび奨励賞を受賞した拙著『火星の旅人』において論じた19世紀天文学が、まさしく光を読解する学問であるからです。宇宙探査が実現されていない時代において、天体を研究するために天文学者が利用しうる情報は、はるかかなたの天体から地球まで渡ってきたごくわずかな光だけです。拙著で解説したように、19世紀半ばにおけるイノヴェーションののちには、天文学は天体からの光をスペクトル分析できるようになりました。つまり、天体からの光を波長ごとに分解し、わずかな光からとことんまで情報を絞りとることが可能になったわけです。
そんな19世紀の天文学者たちの営みを辿りながら、そして火星からの光を「運河」と誤読したパーシヴァル・ローエルの生涯を研究しながら、私はたびたび、「光の読解者たちについて論じている自分がこうしておこなっていることこそ、高校生のころに憧れていたあの表象文化論ではないか」という考えに囚われました。かかる僭越な妄念は、先述のとおり前提からして誤っておりますが、しかしそれでも、高校生のころからの夢を『火星の旅人』によってある程度実現できたという思いを、このたびの受賞により強めることができました。今後は、表象文化論と天文学史とのインターセクションというテーマもいっそう掘り下げていきたいと思っております。あらためて、このたびはまことにありがとうございました。
【奨励賞】馬場靖人『〈色盲〉と近代 十九世紀における色彩秩序の再編成』(青弓社)
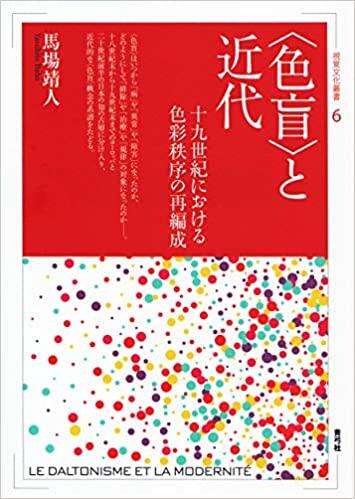
このたびは拙著『〈色盲〉と近代』を奨励賞に選出いただき、誠にありがとうございます。私はこの十年間、一貫して色盲の歴史を研究して参りましたが、まっとうな研究として認めてもらえない期間が長かったので、恩師が口癖のように言っていた「十年同じことをやりつづけていれば誰かが認めてくれる」という言葉だけが希望でした。そして今年はまさしく研究をはじめてからほぼ十年にあたります。そんな年に、今までの人生の半分以上を過ごしてきた母校の早稲田大会でこのような賞を受賞できることを感慨深く思います。
この研究を始めたとき、私は自分の色覚があまり好きではありませんでした。他者との色をめぐるやりとりで不快な思いをすることが何かと多かったからです。ところが、研究をすればするほど、自分の色覚に対する嫌悪感は薄れていったのでした。修士論文を書き上げた頃には、もうすっかりそうした気持ちは消滅し、まるで拙著の中で論じたドルトンのように、自ら進んで自分の色覚をネタにするまでになっていました。こうした意味で、私にとって色盲研究は自らに対する「治療」効果、エンパワメント効果をもっていたと言えるでしょう。
この研究を進めるうちに多くの当事者の仲間も増え、できることの幅も広がりました。それまで自分の主観的な経験にすぎないと思われていたものが、案外どの当事者にも共通するありがちな経験だということに気づくようになったのです。
しかしあるとき、順調に見えたエンパワメントの経過に水を差すような出来事が起きました。色覚検査用に普及している「石原表」の経験の構造について、私自身が病院で精密な色覚検査を受けた際の経験に基づいて論じた論文が、査読で酷評されたうえリジェクトされたのです。
実を言いますと、私はこの論文に自信をもっていました。なぜならそれは、多くの色盲の仲間たちとの「合作」とも言えるようなものだったからです。それは多くの色盲者の協力により、他の当事者にとってもリアリティのある経験であることを確認したうえで書かれたものでした。だからその論文は、最低限の「間主観性=客観性」の要件は満たしていたわけです。
だからこそ、この査読結果を受け取ったとき、私はくやしくて仕方ありませんでした。単にリジェクトされたからくやしかったのではありません。査読者の言葉によって、私自身や他の色盲の仲間たちの色彩経験まで否定されたように感じたからです。他の色盲者たちとのあいだに共有された経験が、「証拠がない」のたった一言でなかったことにされてしまったのです。私はここに多数派の暴力を感じ取らずにはいられませんでした。
たとえば色覚多数派の書き手がある絵についての論文を書くときに、その絵を「青い」と記述するとして、「その絵が青いという証拠を出せ」と言われるでしょうか? そんなことはありえません。なぜなら、それが「青い」ということは、すでに多数派同士で習慣として共有されている確実な事実だからです。それに対して私はもうここでつまずいてしまうのです。それは本当に青いのか? いや、多数派がそう言っているのだから青いのかもしれない。だが私にはそれは青ではなく緑に見える……といった具合に。
「おまえの絵の色は汚い」「おまえの服の色の組み合わせはおかしい、合ってない」「青っていうけど、それ青じゃなくて紫でしょ」――これらはすべて私が子供時代から今にいたるまで多数派から投げかけられてきた言葉です。ここから、「おまえの見ている色は間違っている」「おまえは偽の世界を見ている」というところまではあと一歩です。こうして私たちは、自分の経験を語ろうとするたびにそれを否定され、訂正され、沈黙を強いられてきました。
色覚検査という制度を通して、自分の色覚を「自覚」したり、劣等者としてのアイデンティティを受け入れたりすることを色盲者にばかり押し付けてきたのがこの国の色盲の歴史です。査読の在り方はある意味でこの押し付けを、それこそ「無自覚」に反復してしまっています。
もっとも先ほどの査読の件は、純粋に学問的な理由でリジェクトされたのか、それとも色盲者の自分語りなど主観的で信用ならないという一種の偏見によるものなのか、私自身にも判別がつきません。おそらくその両方なのでしょう。しかしいずれにせよ、断定したり拒絶したりする力をもっているのが色覚多数派であることは、色をめぐる日常会話の場合と何ら変わりはありません。
この国で石原表が誕生してから100年以上の時がたちました。一方で制度的差別は消滅しつつあります。しかし他方で、以上のような数々の「見えにくい差別」がますます見えづらいままはびこり、今もなお多くの色盲者たちが沈黙や諦めを強要されつづけています。査読の名の下に、そういった暴力を再生産したりしないよう、今度はみなさんが「自覚」してくださることが必要不可欠です。しかし、それ以上に肝心なのは、社会全体が色覚問題を自分事として引き受けてくれるようになることです。拙著の受賞が、そのひとつのきっかけとなることを願ってやみません。
第15回大会に際して──表象文化論学会長スピーチ(2021年7月3日オンライン)
田中 純
大会実行委員会をはじめとする皆さんに対し、御礼申し上げます。コロナ禍にもかかわらず、今回の大会がつつがなく開催できたことを心から喜びます。
今日のプログラムであるアニソンに関するシンポジウムやつのごうじさんのインタビューは大変刺激的なものでした。思いがけずも、わたしにとっての「アニソン」の原体験である狼少年ケンの主題歌を聴けました。その「ボバンババンボン ブンボバンバババ」という無意味な音声のリズムは、自分の音楽の原体験でもあったのかもしれません。
学会賞受賞者の皆さん、おめでとうございます。今年度も表象文化論らしい多様な分野の応募作があり、受賞作もその多様性を反映した充実した作品であったことをとても嬉しく思います。
ご存じのように、第1回学会賞特別賞の受賞者かつ「表象文化論」の名づけ親である渡邊守章先生が先日お亡くなりになりました。学会ニューズレターREPRE42号に掲載されている追悼文にも書いたことですが、ちょうど昨年の秋に、東大に表象文化論専攻が出来た頃の雑誌『ルプレザンタシオン』掲載の渡邊先生のテクストを読み、わたしは大変刺激を受けました。渡邊先生が書き残された言葉はいまだに新鮮で、生きています。これはつまり、お亡くなりになっても、いまだ「現役」であるということでしょう。
学会賞受賞作である宮﨑裕助さんの『デリダ論』には次のような一節があります。少し長くなりますが引用します──
「デリダは「すべてを言う権利」としての言語の無条件性のうちに、言語のもつパフォーマティヴな力、すなわち、言及行為によって言及事象を構成しうる発語内的な力、いわば出来事を引き起こすことのできる革命的な力を見いだしている。公言゠職業としてのプロフェッションは、そのような行為遂行的な力を労働から引き出す概念として打ち出されているのである。
そうしたプロフェッションの無条件な働きは、言語のパフォーマティヴな力を介して、いわゆる公共性の思想がしばしば暗に前提としている国家主権の枠組みを越えて、当の公共性の制約や境界を解除し、いっそう越境的で普遍的な場を開いてゆくことを目指している。デリダにとって大学という場、そして人文学という知こそ、歴史的経緯からして、こうしたプロフェッションの無条件性を担保する制度──これを「条件なき大学」とデリダは呼ぶ──として問い直されるべきものなのだ。」
渡邊先生による「表象文化論」という「名」の創造こそは、「出来事を引き起こす革命的な力」の発現だったのではないでしょうか。そして、われわれのこの学会もまた、人文学やアート、芸術創造を「プロフェッション」とする者たちの「条件なき学会」とならねばならないのではないでしょうか。
わたしは昨年秋、東京大学の総長選考問題にいささか関わることになりました。現在では国立大学もまた「経営」のイデオロギーのもとで独裁的な学長権限が拡張されるなど、さまざまなアンチ・プロフェッション的な「条件」を課された場になりつつあります。そうした状況のなか、この学会が、「表象文化論」という名がはじめて口にされた時代の「初発の意志」「起源の意志」を継承し、「条件なき学会」「あえて無責任に語る学会」として、「出来事を引き起こす革命的な力」の場となることを心から願っています。そのためにも、会員の皆さん自身の研究・創造活動あっての学会ですから、引き続きこの学会という場を是非活用していただきたいと思います。
【選考委員コメント】
・沖本幸子
私ごときが「審査」というのは、なんとも居心地が悪かったが、候補作と向き合いながら「表象文化論学会」という場に実にさまざまな研究が集っているというおもしろさと難しさを実感し、改めて「表象文化論」とはなんだろうと考えさせられた2年間だった。
まずは、受賞作品から。
学会賞の宮崎裕助『ジャック・デリダ』。美しい赤の表紙が目を引くが、むしろ丁寧な蓄積を感じさせる本だった。帯には入門書とあり、また、これまで日本であまり論じられてこなかったデリダ晩年の思索に焦点を当てながら、難解な内容をわかりやすく一般に開くように書かれており、デリダとともに自ら考える姿勢を貫いている。氏のジャック・デリダ論の集大成というようなものではないため、学会賞としてふさわしいのかどうか迷いもあった。しかし、本書の背景に、著者の学識の深さ、研究者としてのすぐれた資質を感じられ、こうした開かれた研究姿勢自体も美質と考えた。
奨励賞の馬場靖人『〈色盲〉と近代』。なにより、学問としていまだ成立していないテーマについて、さまざまな学問分野を横断し、多様な方法論を駆使し、試行錯誤しながら、地道に一歩一歩道を切り開いていく姿勢そのものに、エールを送りたいと思った。「表象文化論」には、やはり、既成の学問やジャンルの枠組みを超えうる場であり続けてほしいと思うし、そうした期待に応える研究が今後もさまざまに生まれてくることを願ってやまない。
同じく奨励賞の入江哲朗『火星の旅人』は、日本ではあまり知られていないパーシヴァル・ローエルという日本研究者でもあり天文学者でもあった人物の評伝ながら、膨大な資料を駆使し、優れた文才により、読み物として大変おもしろく仕上がっている。副題にあるアメリカ思想史については後景化している印象だが、マイナーな人物を表舞台に引っ張り出してきて読ませてしまう、その力技を評価したい。ただ一点、今後、この人はどういう方向に研究を進めていくのだろうという疑問もよぎった。研究の芯にあるテーマが見えなかったからだ。器用な人なので、おもしろい素材を発見し続け開花していくのかもしれないが、今後の学問的なテ-マの深まりにも期待したい。
以下、候補作について。
学会賞候補の橋本陽介『中国語における「流水文」の研究』。その着眼点は門外漢にもおもしろく、わかりやすく書かれていて感心したが、本書は、むしろ言語学、中国語学の中で評価されるべきものではないか、と感じた。塚田幸光『クロスメディア・ヘミングウェイ』も、多彩な視点からヘミングウエィの再考を促す身振りに感心したが、考察自体がもう一歩踏み込んだものになってほしかったという気がするし、日本のヘミングウェイ研究という枠組みを超えるものなのかどうかについてもやや疑問を感じた。
奨励賞候補にも橋本陽介『「文」とは何か』があがった。著者の器用さに驚かされつつ、おもしろく読んだが、新書でもあり、学会の賞候補としては小品という印象を免れ得なかった。今後の多彩な活躍に期待したい。井岡詩子『ジョルジュ・バタイユにおける芸術と「幼年期」』、残念ながら、きちんと書かれた博士論文という印象を越えるものではなかった。日本のバタイユ研究に閉じない広がり、深さがほしいと思った。宮本裕子『フライシャー兄弟の映像的志向』。アニメーションと実写とが混淆する作品群への着目、素材のおもしろさが際立っていた。もう一歩踏み込んだ分析になると研究としての奥行きが出てくるのではないか、と感じた。越智雄磨『コンテンポラリー・ダンスの現在』。美学と制度の両面からフランスのノン・ダンスの諸相を考察しており、事例紹介として行き届いたものと感じさせられたが、その目配り故か、逆に本人の問題意識の軸がどこにあるのかわかりにくく、迫力に欠ける印象となってしまったことは惜しいと思った。
・郷原佳以
今年は学会賞・奨励賞合わせて候補作が9作もあったが、誇張ではなく、いずれも力作で、文章も読ませるものが多かった。特に奨励賞は選考会議で絞るのに難航し、一時は4作授賞にしてしまおうかという話にもなった。授賞に至らなかった著作も、けっして学問的な水準を満たしていないということではなく、学際性を重んじる表象文化論に相応しい著作が選ばれたのだと理解していただきたい。以下、各候補作について講評を記す。
学会賞を授賞した宮﨑裕助『ジャック・デリダ』は、デリダのテクストの緻密な読解を示しつつ先行研究からアクチュアリティまであらゆるレベルの目配りをして隙のないところが長所でもあり短所でもあると思う。「死後の生」という全体のテーマに貫かれているとはいえ各章の主題は様々だが、一部の章の完成度は比類がないと思われた。塚田幸光『クロスメディア・ヘミングウェイ』は、ヘミングウェイのメディア横断的な創作背景と時代状況を浮かび上がらせて刺激的なモチーフを鏤めている。ただ、全体にややエッセー的で、またヘミングウェイ研究の常識を前提とした書き方になっており、書籍化する際の工夫が若干不足しているように思われた。『中国語における「流水文」の研究』の著者、橋本陽介はすでに数多くの著作の持ち主で、文学理論と言語学を互いに越境させるその研究は魅力的である。本書の根底にある「文とは何か」という問いも著者の研究に一貫している。ただ、本書は第6章を除けば中国語学の研究書であり、その分野で評価されるのが相応しいと考えた。
奨励賞授賞作は馬場靖人『〈色盲〉と近代』と入江哲朗『火星の旅人』。『〈色盲〉と近代』は、「色盲」概念の歴史的形成過程を明らかにするために複数の分野(生理学、哲学、文学、造形芸術)と言語圏を横断し、自ら研究領野を切り拓いている。色盲をめぐる言説が「生理学的カント主義」に貫かれてきたことを浮かび上がらせる過程はスリリングである。本書は近代が生み出した色覚検査や「補正」の諸問題を具体的に明らかにしながら、色の知覚とは何か、色を言語で表すとはいかなることか、私たちは色と名の関係を自明視してはいないか、等々と読者に問いかけてくる。『火星の旅人』の主人公、パーシヴァル・ローエルを私は知らなかった。日本滞在、天文台、火星運河説、といった面白さといかがわしさを感じさせる要素のみで本論に入ったが、綿密な調査に基づく生き生きとした描写によって彼の生きた時代と場所を辿ることができた。ときおり、何のためにこの人の人生を追っているのだろう、と思うこともあったが、ロマンスと科学をめぐる主題が浮上してくるあたりで面白くなった。副題の「アメリカ思想史」は無理があるように思うが、学際性を体現した著作である。
『〈色盲〉と近代』と共に私が奨励賞に推したのは、宮本裕子『フライシャー兄弟の映像的志向』である。序文から問題意識が明確で、研究の意義がよくわかった。著者は先行研究を精査したうえで、フライシャー・アニメーションにおける実写とアニメーションの混在、動きと動くものの間にある齟齬など、越境的で異質的な性格についての理論的研究に挑み、着実に論じている。取り上げられている映像をYou Tubeで見ながら読むのは至福だった。選考会議では、奨励賞に相応しいという声も多かったが、さらに包括的な研究に期待したいという声や、素材自体が魅力的なのではという声も上がり、今回は見送った。越智雄磨『コンテンポラリー・ダンスの現在』は、丹念な調査と作品分析によって、「ノン・ダンス」と呼ばれる潮流によってフランスのコンテンポラリー・ダンス界に起こった複合的なパラダイム・シフトを制度的かつ美学的に明らかにした労作で、この分野の基本文献となるだろう。橋本陽介『「文」とは何か――愉しい日本語文法のはなし』は、つねに刺激を受けている著者の新刊なので候補作となる前に読んでいたが、予想に違わず面白く、ある種の言語観への異議申し立て、日本語が主観的な言語であることをめぐる議論の冷静な整理など、参考になる点が多かった。ただ、既存の論点をわかりやすく提示することを旨とする新書であり、学会奨励賞の対象にはならないと判断した。井岡詩子『ジョルジュ・バタイユにおける芸術と「幼年期」』は、バタイユの芸術論をめぐる先行研究や動向を踏まえ、「アンフォルム」に代えて「幼年期」を軸に据える提案をしているが、この概念の整理が行われるのは「おわりに」においてであり、本論では焦点がぼやけている印象を受けた。また、主題が限定されすぎており、専門外の読者を惹きつける議論とは思われなかった。
・平倉 圭
いずれの候補作もハイレベルで拮抗し、選考は文字通り難航した。表象文化論ならではの領域横断性と、論じ方そのものを発明していく創造性、非専門家にも開かれた視野の広さとおもしろさをもつ作品を選んだ。
学会賞に選ばれた宮﨑裕助『ジャック・デリダ――死後の生を与える』は、著者が長年デリダを通して多岐にわたる主題について考察してきた論文集である。現世がこのようであること、この現世を成り立たせる巨大な岩盤のようなものをわずかに持ち上げ、その下に「影」を垣間見させる思考の力が全編に満ちる。静かで明晰な著者の文が、デリダとともに、普通は入ることができない岩盤の下の影へと、読者を繰り返し導いていく。圧倒的な力量である。デリダを超えて、SNS上の言語、AIとのコミュニケーションといった今日的主題についての思考が展開されるのも刺激的だ。論文集の性格ゆえに個々の主題についての考察は高度に圧縮されており、それぞれの主題について単著を読みたいという希望も抱いた。
奨励賞の入江哲朗『火星の旅人――パーシヴァル・ローエルと世紀転換期アメリカ思想史』は、すみずみまで完成された、唖然とするような達成である。冒頭から埋め込まれていた謎の記号が最後の最後で意味を明らかにするという展開には、優れたミステリ映画を見るような驚きがあった。徹底した調査に基づく記述には厚みがあり、独特な文体は読者への配慮に満ちて心を捉える。知覚と錯覚のあいだで、存在しない「運河」のパターンを火星に見出し、それによって自身と周囲を触発していくローエルの仕事は、画像分析一般につきまとう狂気を照らしているようだ。しかし著者はその狂気に溺れることなく、旅を最後まで辿りきる。奇矯ではない、複雑だが説得力のある解釈を導くやり方があるということを、私は本書から教えられた。
同じく奨励賞の馬場靖人『〈色盲〉と近代――十九世紀における色彩秩序の再編成』では、カラー図版と本文を行き来することが真にスリリングな思考の経験になるという読書を久しぶりに味わった。思想史、心理学・生理学史、科学技術史、美術史等を横断しながら、色盲という主題をいったいどのように論じればよいのか、その論じ方自体を手探りで発明していく、そのことに大いに惹かれた。「見ること」と「読むこと」のギャップへと読者を巻き込んでいく根本的な仕事である。石原表を草間彌生の絵画に結びつける結論部はやや急ぎすぎと思われ、惜しく感じられたが、著者の手探りの仕事の持続とさらなる展開に期待するという意味で奨励賞にふさわしいと判断した。
その他の候補作も、いずれもきわめて充実した仕事であった。
橋本陽介『中国語における「流水文」の研究――「一つの文」とは何か』は、複数の主語をまたいで連続していく中国語の「文」の構造を、主に1980年以降の中国の小説から豊富な事例を挙げて解明し、そこから従来の言語学における前提を批判するとともに、中国語と他の言語の言語習慣の違いが生む表現を分析する「比較詩学」の可能性を開くという、たいへん大きな仕事である。私のように中国語を理解しない読者にも論点が内側から理解できるよう、事例提示は工夫されている。私は当初、本書を賞に推したが、中国語・中国文学あるいは言語学の専門家集団によって評価されるべき本ではないかという意見があり、同意した。著者の比較詩学がさらに展開していくことを楽しみにしたい。
塚田幸光『クロスメディア・ヘミングウェイ――アメリカ文化の政治学』は、狭義の「文学」のなかにヘミングウェイを閉ざさず、映画や写真、ジャーナル記事、あるいは絵画といった複数のメディア間を横断しながら考察していく野心的な仕事である。文章はきらびやかでスピーディー。異質なものをアナロジカルに結びつける解釈の手付きには、しかし、ときに丁寧さが欠けているように思われた。だがこれは、新たな横断を行うために必要な野蛮さでもあるだろう。
橋本陽介『「文」とは何か――愉しい日本語文法のはなし』は、「文」とは何かという問いから始まって、文と世界とを対応させるというそもそもの発想を疑い、「必要なことを必要なだけ表す」言語という新たな観点へと読者を導いていく。まさに目から鱗であり、著者の理論的仕事のさらなる展開と深化に期待したい。中上健次、太宰治らの文体分析も明晰で驚きがあった。
井岡詩子『ジョルジュ・バタイユにおける芸術と「幼年期」』については、なぜいまバタイユを、なぜ幼年期の観点から論ずるのか、ということが非専門家の私には最初よく分からなかったが、読みすすめるにつれ、実現可能な至高性という問題意識が現れてくる。非従属的な生をどのように生きることができるか、私たちの時代における可能な至高性とは何かというテーマが響いた。
宮本裕子『フライシャー兄弟の映像的志向――混淆するアニメーションとその空間』は、映像内に「異質性と不統一性」をもたらすフライシャー兄弟の志向を、作品の細部と歴史的・技術的文脈から明らかにする。とりわけロトスコープで描かれた混淆的ダンスの分析が私には刺激的だった。冒頭で予告されたフライシャー兄弟の特徴を多様な作品群に繰り返し確認するという構成を取るため、明快さと一貫性の反面、当初の見方が覆されていくというような読書のスリルには欠けるが、まずはフライシャー兄弟の一貫した志向を明確に打ち出すというのが本書の目的であろう。今後の研究の深化が楽しみだ。
越智雄磨『コンテンポラリー・ダンスの現在――ノン・ダンス以後の地平』では、1990年代半ばのフランスに現れた「ノン・ダンス」の前史と生成と展開が、作品の美学的側面のみならず、それを取り巻くきわめて具体的な制度的・政治的文脈――たとえば助成金との距離の取り方――から明快に説得的に描き出される。関係者へのインタビューを含む深い調査に基づく充実した仕事である。ここで論じられた振付家たちの美学的・制度的・政治的な選択は、たとえば現在の日本のダンサー・振付家たちにも多くのインスピレーションを与えうるだろう。
・山口裕之
学会賞に選ばれた宮﨑裕助氏の『ジャック・デリダ 死後の生を与える』は、後期・晩年のデリダの思想に集中した考察であり、その点で従来のデリダ論を越えた特色をもつ。全体として、叙述に密度感があり、思想とテクストに寄り添いながら論を展開しつつ、読者に配慮したわかりやすさがある。それによって、刺激と面白さを読者に持続的に与える力をもつ著作であると感じた。とても充実し安定した書きぶりである。
ただし、全体の構成に向けられた意図という点では、歯がゆさを感じるところがある。「生き延びること」という全体を通底するこの著作のテーマを提示して、「差延としての死後の生」について語る「導入部」をもちながらも、そのあとの三部構成(第I部 政治的なものの亡霊的起源/第II部 人間と動物の生―死/第III部 来たるべき共同体への信)のそれぞれの部分が、全体のテーマのなかでどのように位置づけられ、それぞれどのような主題・課題を担っているのかが(なぜか)序論においてなにも説明されていない。また、それぞれの「部」での前置きとなる文章もまったく置かれていない。そして、各章は(もともと独立した論文として書かれていたという事情をそのまま引き継ぎ)相互にリンクすることはほとんどなく、ほぼ自立した論のように著作の中に置かれている。そして、そのことは最後の「終章」についても変わらない。「終章」は全体をまとめる機能を少なくとも明示的にはもっていない。
各章の内部での論述の基本的な方向性として、デリダのテクストと思想に即して論を展開しながら、単にデリダについて語るだけではなく、宮崎氏があとがきでも述べているように、そのテーマについて宮崎氏が論じるという、ある種のずらしが生じている。このことが、この著作の射程を高めるものとなっているように思われる。そのこともあって、全体としては著作全体のもつ密度の一体感が、一つの著作としての完成度を感じさせるものとなっているように思う。
次に奨励賞受賞の二つの著作について。
入江哲朗氏の『火星の旅人——パーシヴァル・ローエルと世紀転換期アメリカ思想史』は、完成度が高く、うまいと感じさせる著作である。入江氏は、〈ローエルの評伝〉と〈アメリカ思想史〉という二つの軸にそってこの著作を展開させてゆくと序文で述べている。〈ローエルの評伝〉としては、具体的事実・事象を「ローエル一族」の土地との関係に至るまで丹念に緻密にたどるものであり、その意味で力作であり、そして、読者を惹きつける面白さがある。しかし他方で、〈アメリカ思想史〉としては、あまりにも事実的な叙述が前面に出ているために、「思想史」が明確に浮かび上がってこないきらいがある。読者が、テクストのうちに「思想史」を探し出さなければならない。その意味で、全体として「表象文化論」としての特質が弱いのではないかという印象も受けた。
もう一つの奨励賞受賞作、馬場靖人氏の『〈色盲〉と近代——十九世紀における色彩秩序の再編成』は、個人的には、宮崎氏の著作と並んで、今回の候補作のなかでは傑出しているものだと感じた。この著作は、近代の〈知〉の制度・〈視〉の制度に秩序づけられてきた「色盲」のさまざまなコンテクストを、いったんそれらの秩序から開放して「再編成」する。そして、「色盲」という現在の社会的・文化的制度のなかにあたかも自明のものとして組み込まれているものが、どのような社会的・文化的力学のもとに成立してきたかを描き出している。知覚の制度化のプロセスを可視化するとともに、日本によって生み出された色盲識別システム「石原表」(とその後)の政治的バックグラウンドを切り離してゆく叙述のしかたは小気味好い感覚を与える。ジョナサン・クレーリーの影響を強く感じるが、それがきわめてよい方向での成果となって表れているようにも思う。全体として、「表象文化論」が行なってきた営みにきわめてうまく合致する力作であると感じた。
受賞を逃した著作にも表象文化論としてすぐれたものがあり、それらについて言及したい。
塚田幸光氏の『クロスメディア・ヘミングウェイ アメリカ文化の政治学』は、ヘミングウェイ(1899-1961)を映画生成期の作家としてとらえ、1930年代のモダニズム/ファシズム、テクノロジーと戦争の世紀という時代の「コンテクスト」のなかで、「政治と芸術」という補助線を引きつつ、ヘミングウェイの「テクスト」をとらえようとする。まさに「クロスメディア」によって、ヘミングウェイを読むという試みである。しかし、まさにそのために、序章からしてさまざまな事象が混沌と入り乱れて、どのような軸のもとにそれらの事象が語られようとしているのか見えてこない。様々な事象の羅列的提示のようにも見えてしまう。たしかにこのキーワードでくくられた書物となっていて、個々の論考は面白い。そして言葉の推進力もあり、面白く読ませる。だが、各章を通じて何かが展開していって構築されていくという進み方ではない。さまざまな局面やテーマでとりあげられた事象が並列的・パノラマ的に提示されることによって、一つの時代の「コンテクスト」を全体として見せるという意味での魅力はたしかにある。しかし、個々の魅力は大きいとしても、バラバラなものがバラバラなまま提示され続けるという印象が最後まで拭えなかった。
宮本裕子氏の『フライシャー兄弟の映像的志向:混淆するアニメーションとその空間』は、フライシャーのアニメーションにおけるさまざまな「二重性」(実写空間とアニメーション空間、アニメーションの想像的側面と物質的側面、空間の二重性、科学とファンタジー)という特質を「異なる道」と位置づけている。この「二重性」をさらに「映像内の異質性と不統一性」「異質な空間の隣接と、質の異なるものの混在」という言葉に収束させる。そしてそれをフライシャー兄弟の「映像的志向」と呼んで、この特質をフライシャー兄弟のいくつかの代表的作品(「インク壺」、「ベティ」シリーズ、「ポパイ」、「ガリヴァー旅行記」、『バッタ君』)のうちに確認してゆくという構成をとっている。フライシャー兄弟のアニメーションの特質を浮き上がらせるという意味では、この著作はこの領域における重要な研究となるだろう。素材そのものの面白さが著作の強みではあるが、全体を通底するテーゼをいろいろな局面で確認してゆく作業が続くため、最終的な到達点が、同じ「テーゼの確認」の繰り返しになってしまう。そういった印象は、著者が「二重性」と呼んでいる特質とを実際の作品(テクスト)のうちに確認する作業が、表層的なものに終止しているためでもあるだろう。
越智雄磨氏の『コンテンポラリー・ダンスの現在』は、残念ながら受賞しなかったが、個人的にはとてもすぐれた著作だと感じるものだった。この著作は「コンテンポラリー・ダンス」という言葉を標題に掲げているが、実質的には、全体を通じて「ノン・ダンス」の研究をおこなうものである。その成立史、文化政策、ポストモダンダンスとの関係を論じながら、1990年代なかばに生じたフランスの新たな舞踊の傾向、その後のコンテンポラリーダンスにおけるパラダイムシフトを考察している。そこでは、二人の中心人物の作品に焦点が当てられている。テーマ的な一貫性から全体的な統一感が高いと感じる。そして、各章での現場に入りこんだ細部の具体的記述の確かさとその意味での情報価値も高い。この領域での一級の資料となるのではないかと感じた。具体的事象を生み出していった内的力学を描き出すものとなっていたとすれば、さらに刺激的な著作となったのではないかと思われる。