パネル1 リプレイング・エヴァンゲリオン ──身体・演劇・贈与
日時:2021年7月4日(日)10:00-12:00
- アニメーショナル・ボディ──エヴァンゲリオンの中で生産される身体のコラージュ性/難波優輝(セオ商事)
- アニメーションにおける演劇的表現の活用──ATフィールドのない世界/柏木純子(大阪大学)
- 「綾波レイ」と贈与──「仮称」と第3村/新井静(大阪大学)
【コメンテーター】石岡良治(早稲田大学)
【司会】雑賀広海(東京大学)



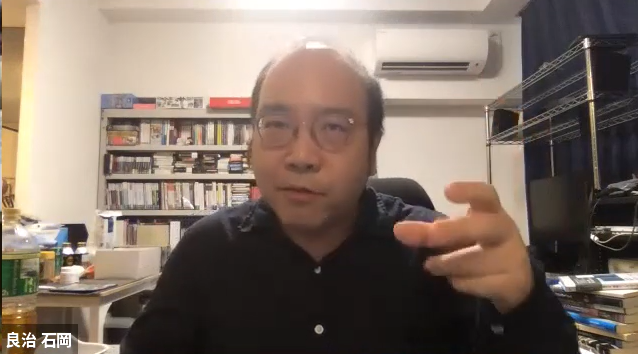

パネル1「リプレイング・エヴァンゲリオン──身体・演劇・贈与」は、1995年から1996年まで放送されたテレビアニメ版、1997年に公開された旧劇場版、2007年から2021年にかけて四部作として公開された新劇場版(それぞれ『序』[2007]、『破』[2009]、『Q』[2012]、『シン・エヴァ』[2021]とする)、そして複数の別バージョンやメディアミックス作品と、何度も再生されて増殖し、巨大なテクスト群となった『新世紀エヴァンゲリオン』(以下、『エヴァ』)をまさに反復・複製・再生の観点から問い直した。発表者はいずれもアニメーションを専門しないのが本パネルの特色であり、メディア論、演劇学、文化人類学と、領域を横断する柔軟な視点から『エヴァ』の新たな解釈が試みられた。
最初の発表者である難波優輝氏の「アニメーショナル・ボディ──エヴァンゲリオンの中で生産される身体のコラージュ性」は、アニメーションで描かれた身体に対する欲望に注目する。アニメーションの身体は、複数のアニメーターが個別に描く無数の身体のコラージュによって形成されている。その表層的で記号的な身体に向ける欲望は、実写映画のスター俳優に向ける欲望とは異なる性質を持つと考えられる。ここで述べられる欲望には、鑑賞者が「ただの絵」に抱く欲望と、作品中のキャラクターが他のキャラクターに向ける欲望が含まれる。難波氏は、これら二つの欲望を連関させることで、何がアニメーションの身体に欲望させるのか、つまり、欲望のまなざしの先にあるものを明らかにしようとする。
まず、難波氏はアニメーションの絵を複数のレベルに分解する。我々がアニメーションを見るとき、もっとも表層にあるのは、絵が映し出されるディスプレイやスクリーン(鑑賞者と絵を仲介するインターフェイス)である。そして、このインターフェイスを通して、内容(描かれた絵)を見る。さらに、内容も二つの層に分離することができる。難波氏によれば、キャラクターの性格や感情を表す記号的表現(例示されるのは、スネ夫のとんがった口や頬を赤らめるアスカの目の下に描かれる赤い線)は、鑑賞者に向けられた表現であり、物語世界内のキャラクターがそれをそのまま見ることはない。いわば、物語世界の内と外ではフィルターがかけられているのである。以上の三つのレベルに加えて、物語における欲望にも目が向けられる。たとえば、碇ゲンドウが綾波レイの身体に亡き妻(碇ユイ)の痕跡を求めるように、アニメーションの身体表象の背後にあるもの、という四つめのレベルが提示される(この四つめのレベルは、「ただの絵」である記号的身体に肉体性を与える支持体のようなものと言えるだろうか)。
難波氏は結論において、アニメーションの身体の向こう側には何もなく空であるとして、支持体の存在を否定する。そのかわりに、アンリアルな記号的身体にリアルな運動をさせ、アンリアルとリアルが衝突することで露呈するギャップに、アニメーション独自の視覚的な誘惑が生まれるとする。本発表で提示される用語のアニメーショナル・ボディとは、リアルとアンリアルという二元論を克服してその狭間に置かれる身体のことであり、その身体性は幽霊的と形容される。モーション・キャプチャで造形されたキャラクターやバーチャルYouTuberの身体が、アニメーショナル・ボディという概念の輪郭をより明確に描き出す。というのも、虚構の身体の背後にいる具体的な人間の存在が強まることによって、リアルとアンリアルのギャップもより鮮明となってくるからだ。このような実体的な人間の身体とそれが拡張された虚構の身体の間のギャップは、パイロットとEVAの関係にも見出すことができるだろう。
二人目の発表者である柏木純子氏の「アニメーションにおける演劇的表現の活用──ATフィールドのない世界」は、『エヴァ』と演劇の関係性に焦点を合わせる。タイトルにあるATフィールドとは『エヴァ』の用語であるが、明示的レベルにおいては使徒とEVAが戦闘中に展開する防御壁のことであり、暗示的レベルにおいては人間が他者との間に築く心の壁を可視化したものである。テレビアニメ版のラストを飾る25話と26話で、主人公碇シンジのATフィールドが取り払われるとき、舞台演劇的な劇空間が現れる。なぜここで演劇的空間が出現するのか、アニメーションに劇空間がもたらす効果とは何か、といった問いを柏木氏は提起する。
『エヴァ』の監督である庵野秀明については、過去の映画、特撮、アニメへの造詣が深いことがよく知られているが、演劇に対しても強い関心を抱いていたという。彼は、アニメーションにはない生のもの(=現実的表現)を演劇に見出していた。そのことだけを見て、テレビアニメ版のラストで出現する劇空間が現実的空間であるとするのは短絡的であると柏木氏は指摘する。なぜなら、前衛的な表現が展開されるラストは、劇空間だけではなく抽象的なアニメーションのイメージも挿入されており、作品全体のテクスト分析から劇空間の機能を明らかにしなければならないからだ。
柏木氏の分析によれば、テレビアニメ版『エヴァ』の劇空間は、現実的空間を表すというよりも、鑑賞者とアニメーションの関係を再配置するために用いられているという。つまり、アニメーションの鑑賞者は、(難波氏の議論にもあったように)表現者(キャラクター)が虚構であることを認めながら現実のものとして受容するのに対し、演劇の鑑賞者は、表現者が現実の存在でありつつ劇空間は虚構であると認識する。こうした二つのメディウムの特性を利用して、庵野はアニメーションと演劇を交錯させ、鑑賞者とキャラクターの関係性を問い直しているのである。この交錯において、『エヴァ』のキャラクターたちは虚構の舞台に立つものとして鑑賞者からは分断され、鑑賞者からは独立した自分自身の場所を獲得する。そのうえで、碇シンジが自分自身の存在を肯定して椅子から立ち上がると、劇空間が崩壊するというクライマックスを迎える。このとき、『エヴァ』はその物語世界を越えて、キャラクターたち自身で物語を再構築する可能性を開いていく。このように、庵野は虚構世界に現実的空間を持ち込むためというよりも、キャラクターが虚構世界を乗り越えて現実的空間に踏み出すための装置として劇空間を利用するのである。
三人目の発表者である新井静氏の「「綾波レイ」と贈与──「仮称」と第3村」は、贈与の概念を応用して、『シン・エヴァ』の前半で描かれる第3村での綾波レイと他者との関係を考察する。第3村のパートは、これまでの『エヴァ』シリーズからすると異様とも言える田舎の風景が描かれる。そのため、先行研究でもすでに第3村の空間は分析の対象となっている。先行研究では、第3村がアポカリプス後の世界において希望や未来を生み出す場であることが指摘され、さらに、久保豊は次世代へと流れる直線的な時間性が支配する異性愛規範の空間であると述べる(「エヴァの呪縛に中指を突き立てる──『シン・エヴァンゲリオン劇場版』にみる成長の主題」、『シン・エヴァンゲリオンを読み解く』河出書房新社、2021年、pp.90-109)。久保によれば、その空間において、時間の流れが宙づりにされた(エヴァの呪縛にとらわれた)パイロットたちは、第3村の社会の中心に参入することはできず、周縁にとどめおかれる。それに対し、新井氏は、贈与を通じた人との関わりから、周縁者としての綾波レイの再考を試みる。
綾波レイは本シリーズでとりわけ特異なキャラクターであり、彼女は唯一の身体を持たず、無数のコピーが存在する人造のクローンである。先天的に与えられた性格は各個体で共有するが、その後上書きされた記憶は共有されず、個体の消滅とともに記憶も消去される。こうして機械のようにプログラムされた彼女の行動は、基本的には入力されたコマンド(命令)を遂行するという形でなされる。しかし、NERV外の空間、とくに第3村の空間では、このような人間と機械のコミュニケーションは成立せず、彼女は人間社会のコミュニケーションの経験や記憶を初期プログラムに上書きしていく。新井氏は、第3村のシーンで描かれる綾波レイと他者との関係性の変化を、彼女が口にする「命令」と「はたらく」という言葉に贈与の概念をあてはめて分析することから紐解く。
新井氏によれば、「命令」は一方的に遂行しなければならないものであることから、マーシャル・サーリンズが述べるところの「否定的互酬」であるのに対し、「はたらく」は「一般的互酬」に相当する。というのも、同じエヴァパイロットの碇シンジや式波・アスカ・ラングレーは労働に従事することなく第3村の社会に居住していることから、働くことは強制されていないことがわかるが、それにもかかわらず、綾波レイは第3村の共同体に暮らす義務として労働に参加しているからである。彼女は機械的にプログラムされているからこそ、NERVでの互酬性の延長線上で第3村の社会システムに臨み、そこで「否定的互酬」から「一般的互酬」に、保守的な人間社会の慣習に馴致されていく。こうして、社会の中に溶け込んでいく綾波レイは、人との関わりを拒絶する碇シンジを第3村の共同体に引き入れようとする。新井氏は、この綾波レイと碇シンジの関係性にも互酬性を見出す。つまり、新劇場版の『序』と『破』で描かれた綾波レイのコピーである『シン・エヴァ』の綾波レイは、碇シンジに対する返礼として、以前の綾波レイのリプレイをおこなっているのである。以上のことから、綾波レイは繰り返しの物語である『エヴァ』を象徴するキャラクターであると言える。
コメンテーターの石岡良治氏からは、それぞれの発表に対して問題の視野を広げるような問いが提出された。難波氏の発表については、鑑賞者に元々内在するフェティシズムによる欲望と、物語を通じて誘導され変形を被る欲望との関係が問われた。柏木氏の発表については、議論の中ではほとんど触れられなかった旧劇場版におけるメタ的描写を取り上げたうえで、演劇学の立場から見た旧劇場版と新劇場版の対比が次の論点として示された。新井氏の発表については、文化人類学の贈与論が孕む問題、すなわち、女性を貨幣のような交換の道具やフェティッシュの対象として扱っているという問題が、第3村での綾波レイの描写にも当てはまるのではないか、という指摘があった。また、参加者からは、難波氏の発表について、キャラクターの背後にいる声優と鑑賞者の関係性を問う質問や、柏木氏の発表について、演者と鑑賞者が同じ空間を共有する従来の演劇だけではなく、コロナ禍以降普及した新たな形式であるオンライン演劇との接続を促す質問が出された。
『シン・エヴァ』の公開からまだ半年も経たないうちに企画されたパネルであるが、鉄は熱いうちに打てと言わんばかりに、直前に刊行されたばかりの書籍での議論も取り入れながら、充実した議論がなされた。複数の研究領野からの議論に耐えられる『エヴァ』のテクストとしての強度をあらためて痛感するとともに、今回提示された様々な論点は、今後、時間をかけて議論されなされなければならない。その足がかりとなるパネルであった。
パネル概要
『シン・エヴァンゲリオン』の上映によって25年にわたるアニメシリーズ「エヴァンゲリオン」に終止符が打たれた。本発表では、繰り返し(リプレイ)を鍵として、エヴァンゲリオンシリーズを身体・演劇・贈与の観点から分析する。
エヴァンゲリオンシリーズは多くの「考察」を生んできた。しかし、本パネル発表では、作品内の意味の整合性の探求の地点に留まらず、なぜエヴァンゲリオンシリーズが繰り返されてきたのかを、贈与・演劇・アニメーションの身体性といったフレームから作品を切り取ることで、新たな解釈を引き出したい。柏木は、TV版エヴァンゲリオンの最終話を演劇的な切り口から取り上げ、Bert Cardullo Stage and Screen (2012)などで論じられてきた演劇と映画のアダプテーション論を現実の身体との関わりから考察する。新井はモースの『贈与論』(1925)を手がかりに、『シン・エヴァンゲリオン』に繰り返し現れる何かを与え、与えられるモチーフを紐解く、そして、難波は複数のアニメーターによって繰り返し描かれるアニメーション固有の身体イメージをトーマス・ラマール『アニメ・マシーン』(2009)における議論と分析美学の描写の哲学と接続させることで分析していく。
最終的に明らかにしたいのは、エヴァンゲリオン作品が繰り返し=リプレイによって他のアニメーションとは異なるどのような鑑賞経験をもたらすのか、そして、アニメーションならではのどのような表現を行っているのかである。
アニメーショナル・ボディ──エヴァンゲリオンの中で生産される身体のコラージュ性/難波優輝(セオ商事)
アニメーションの中でキャラクタの身体はなぜ一貫してそのキャラクタだと分かるのか? アニメーションのキャラクタはつねにコラージュされている。トーマス・ラマール『アニメ・マシーン』(2009)における、シンジの輪郭が変容することで、彼の自我の崩壊を分析する箇所をはじめ、アニメーションキャラクタの身体は、つねに境界のあいまいさを持つ。技術論から言っても、無数のアニメーターたちの手によって一つのキャラクタデザインは無数に描かれ、無数に再演される。わたしたちはアニメーションキャラクタのこうした非一貫性を無意識に見逃しているが、逆にこのようなアニメーションキャラクタの身体のぶれに焦点をあてることで、アニメーションによってしか生まれない奇妙な身体が浮かび上がってくるのではないか。その奇妙な身体──アニメーショナル・ボディにこそわたしたちアニメーション鑑賞者は魅惑されるのではないか。エヴァンゲリオンシリーズはキャラクタの身体を侵食され壊され再生される肉として執拗に描いた作品であり、これらの描写に着目することでアニメーションの身体というメディウム特性を分析していく。
アニメーションにおける演劇的表現の活用──ATフィールドのない世界/柏木純子(大阪大学)
本アニメシリーズでは、他作品のオマージュが多数確認されており、すでに考察・分析が進んでいる。とりわけアニメ、特撮、映画といった映像作品について言及されてきた。そこで本発表では、これまで注目されることのなかった演劇との関連、特に「語り」と「再演」について述べる。演劇と映画のアダプテーションについては、Bert Cardullo Stage and Screen (2012)などで論じられてきたが、現実の身体と描かれた身体をアニメ作品の中でアダプテーションさせることについていかに論じられるだろうか。TV版、劇場版ともに、演劇的表現が顕著に現れているのが「ATフィールド」のない世界である。これは「心の壁」を可視化したもので、登場人物たちはそれぞれ、他人と分かり合える世界を望み、葛藤する。「心の壁」取り払われた時、TV版では高校演劇を連想させる演出が、劇場では全てが芝居だったかのような演出が独白を中心に構成されている。庵野秀明は雑誌記事等で自らの演劇体験について語っており、1996年に完結したTV版の製作時は演劇性について無関心であったものの、後に劇場へ足を運ぶようになり、生きた身体への関心が一層高まったという。劇場版のタイトルに冠する「序破急(Q)」や「終幕」に代わり「終劇」を使用、一度完結したものを再度演出し直す行為なども演劇への関心の現れであると考える。野田秀樹との交流が多く見られることから、演劇文化の中でも80年代の小劇場ブームから現代の演劇文化の変遷をふまえ分析する。
「綾波レイ」と贈与──「仮称」と第3村/新井静(大阪大学)
本発表は『ヱヴァンゲリヲン 新劇場版:Q』及び『シン・エヴァンゲリオン 劇場版』(『シンエヴァ』)に登場する「綾波レイ」(通称「仮称」)と贈与の関係について考察するものである。モースの『贈与論』(Essai sur le don: forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques)(1925)に依れば贈与は「与えること、受け取ること、お返しをすること」の三つの義務を持つ。贈り物をすると返礼があるという互酬性が社会成立の基盤であるという概念付置は、近代の経済観への批判でもあった。一方『シンエヴァ』においては、災害から逃れ生き残った人々が「第3村」という共同体を作っている。お互いに助け合い、分かち合う、互酬性を基盤とした村である。クローン体であり、それまで他の人々と触れ合うことがなかった無垢の「仮称」はここで初めてそういった人々との関係性を築くが、ここで行われた贈与という行為は彼女にとってどのような意味生成をもたらしたのだろうか。あるいは、碇シンジによって名前なき「仮称」が「綾波」という名前を与えられ、再び「綾波」という名前を得たことは彼女にとってどのような意味を持つのか。「仮称」と第3村の関係、あるいは碇シンジとの関係を通して贈与のアポリアが乗り越えられるのかについても考察したい。