思考する芸術 ── 非美学への手引き
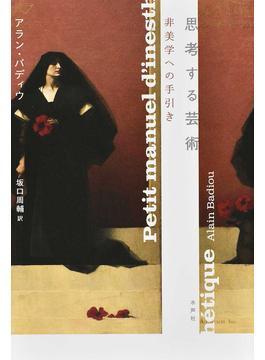
本書は、1998年にフランスで出版されたアラン・バディウの著書Petit manuel d’inesthétique の全訳である。とは言うものの、2021年の現在に20世紀末の著作を日本語にして世に問うことの意味をやはり考える必要はあるかもしれない。ここでは二点挙げよう。
一点目。訳者あとがきにも記したことだが、このバディウの芸術論は彼のマラルメ論でもあると言っても過言ではない。至るところでマラルメが喚起され、最終章はマラルメの作品分析にあてられている。言わばこの著作は、フランス現代思想を牽引する哲学者・思想家による「マラルメ贔屓」の一端をなすものであり、ジャック・ランシエール、ジャン=クロード・ミルネールと並ぶ、現在なお健在のフランス人哲学者による「マラルメ」なのである(「マラルメ」はその後ポール・オディやカンタン・メイヤスーによって引き継がれていくだろう)。これら哲学者による「マラルメ」がこの詩人を専門とする文学研究者の側からどう見られているのかはともかくとして、ハイデガーによるヘルダーリンに対抗することもあってか、その最前線に詩人マラルメを担ぎ上げてきたフランス哲学のこの振る舞いは一つの徴候としていまだ再考する余地はあるだろう。
二点目。日本語に訳出したのだから、日本の文脈も考えてみるならば、1998年は、東浩紀『存在論的、郵便的-ジャック・デリダについて』が刊行された年である。この著作では、ゲーデル的脱構築とデリダ的脱構築が、前者に対抗する後者というかたちで論じられているが、否定神学として捉えられ、ラカンの精神分析と結びつけられているゲーデル的脱構築はそれこそ、inという否定の接頭辞を自らの美学esthétiqueに被せ、芸術、ダンス、映画、散文、詩などに「免算soustraction」という表象の外部への接続を見出すバディウの論にそのまま当てはまるのではないだろうか(なお、東氏の著作では「ラカン派精神分析のゲーデル的整理」として1960年代末に書かれたバディウの論文が挙げられている」)。その核心として「無限の多」を措定するバディウの哲学が、この否定神学のなかに収まってしまうのか、その判断はひとまず読者に委ねたい(この「無限の多」の問題を数学の見地から扱った『推移的存在論』も原著は1998年に刊行されている)。
最後に。実はこのバディウの本の魅力はこの哲学者の独特な断定調の語り口であると思っている。この自信はいったいどこから来るのだろうかと思わせるバディウによる芸術論をぜひ味わってもらいたい。
(坂口周輔)