芸術家と医師たちの世紀末ウィーン 美術と精神医学の交差
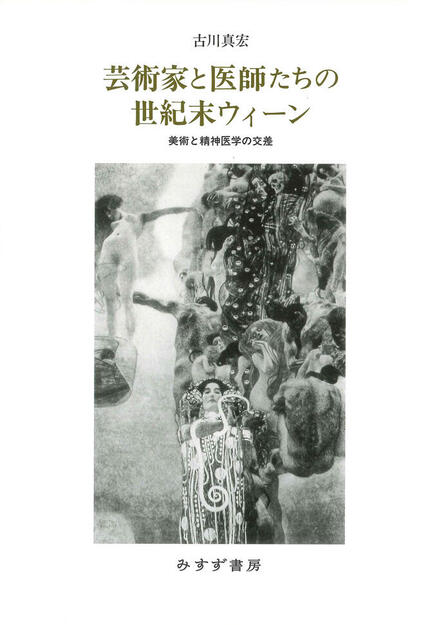
精神分析と固有の19世紀末芸術をともに生んだ都市ウィーン──それは単なる同時性ではなく、相互的な影響関係の下にあった。造形芸術と精神医学(精神分析に加えて、神経生理学、進化論、「退廃論」をも含む)との間の「錯綜した関係」を、テクストと図像の双方にまたがる一次資料分析の厚みのうえに浮かび上がらせた力作が、この『芸術家と医師たちの世紀末ウィーン』である。
著者は、「身体と空間」、「様式と装飾」、「トラウマとトラウム」という三つの問題系を設定し、クリムト、分離派建築、女性の服飾、ロース、ココシュカ、クービンのそれぞれに、新たな視座と解釈を与えてゆく。
第I部「身体と空間」では、分離派の身体表象(専ら「病的」な女性の)と展示空間が取り上げられる。第一章のメインは、クリムトによる女性表象、とりわけスキャンダルを惹起したウィーン大学講堂装飾画である。クリムトらの女性像を評する際に頻用されたのが、ヒステリーと神経衰弱という病理化(そして女性化)された修辞である。前者は抑圧から解放された女性であるファム・ファタル、後者は脆弱で受動的なファム・フラジールという、世紀末固有の相反する女性イメージと結びつく。その背景には、批評家ヘルマン・バールによる芸術への「神経」概念の導入があった。批評言語においても制作においても、芸術と精神病理学、生理学、神経学が連結され、そして女性身体が病理化されると同時に審美化されたこと、つまり芸術と精神医学の共犯関係を、著者は解き明かしてゆく。
第二章では、「白い壁」という共通項をもつ展示空間(分離派館)と病院建築(プルカースドルフ・サナトリウム)が、ともに神経衰弱を惹起する近代都市からのアジールであったことが明かされる。ここには、芸術家と医師たちとの結託がある。女性身体(の表象)と同様に、展示空間もまた神経の病理化のメタファーによって批評され、また当時のドイツ語圏の美学言説の影響も受けて「心理学化」されたことが、種々の一次文献に基づき明かされてゆく。
なかでも、オルブリヒ設計の分離派館に代表される、世紀転換期ウィーンの「白い壁」の分析は刺激的だ。それはモダニズムの機能主義に基づく「ホワイト・キューブ」の前身でありつつ、むしろ反近代的な性質──芸術の礼拝価値に捧げられた「神殿」、地中海建築への参照、近代都市の病理から逃れ心理的休息を得るための避難所──を強く帯びていた。白い展示空間は、審美的な要請と神経病理学・心理学上の言説が重なり合う場であり、それはサナトリウムのような「病からの治癒の場」とも共通していたことが解き明かされる。
第II部「様式と装飾」は、世紀末ウィーンのオブセッション「装飾」というテーマを、女性たちの服飾と建築において論じている。当時、「装飾(モード)」と「様式(スタイル)」は、文化の病と規範という二項対立図式でとらえられていたが、しかし両者の関係は決して排他的ではなく、むしろ装飾にエロティックなものを見出す点において「共犯関係」にあったことが明かされる。いずれにおいても、装飾はフロイトのいうフェティッシュ、つまり挫かれた性的欲望の代替物として機能している。
モードと建築を架橋した論者が、装飾の糾弾で知られる建築家ロースである。著者は、ロースにあっては無装飾とは「装飾の否定」ではなく、むしろ近代における装飾のヴァリエーションであり、換言すれば「フェティッシュとしての無装飾の肯定」であり、そこで性的欲望は安全に隠蔽されることで保持されている、と主張する。他方で装飾擁護派の分離派にあっては、装飾は性的欲望の「昇華」なのだという。ここから、同時代の装飾をめぐる、一見すると相異なる主張(装飾を肯定するバール、フェティッシュとしての装飾を批判し欲望の解放を説くカール・クラウス、そして無装飾にフェティッシュを見出すロース)は、実はセクシュアリティについてのフロイトの議論を共通の軸としていたことが明かされる。続いて著者は、クリムトの絵画、そしてロースによる「装飾的」なベイカー邸案に、欲望をめぐる二項対立図式(見る/見られる、見せる/隠す)を、いわば脱構築する契機を見出している。ここでも、性的欲望をめぐる両義性──その帰結がフェティッシュである──が鍵となっている。
第III部「トラウマとトラウム」では、ココシュカとクービンにおける「無意識」の新たな解釈が展開される。
かの有名な「アルマ人形」を、著者はココシュカによる「肖像」制作の一連のプロセスのなかに位置づけ直し、それが従来指摘されてきたような「トラウマの克服」などではなく、むしろ「投影」のプロセスであったことが明かされる。一連の肖像画において、他者を自己のように、ついで人間を人形のように描く過程を経ているという分析が興味深い。
クービンの絵画作品は、精神分析や病跡学に基づいた解釈を惹起してきた。しかし、この画家はむしろフロイトの夢と記憶の理論に明晰な関心を持っており、それを意識的に制作へと反映させていたという。クービンは、夢の想起(記憶の想起である夢の想起)としての制作から、記憶の想起としての制作へと移行したというのである。
タイトルとサブタイトルが示すように、芸術と(精神)医学とが、本書をつらぬくテーマ系である。この両者をつなぐ重要な補助線が、性的な「欲望」(をめぐる複雑な回路)であるだろう。芸術作品と医学・生理学、テクストとイメージの分野を架橋しつつ、個別の作品と言説を丹念に検討してゆく本書は、世紀末ウィーンの芸術と思想についての新たな展望と洞察を、わたしたちの前に開くものである。
(小澤京子)