ポスト・アートセオリーズ 現代芸術の語り方
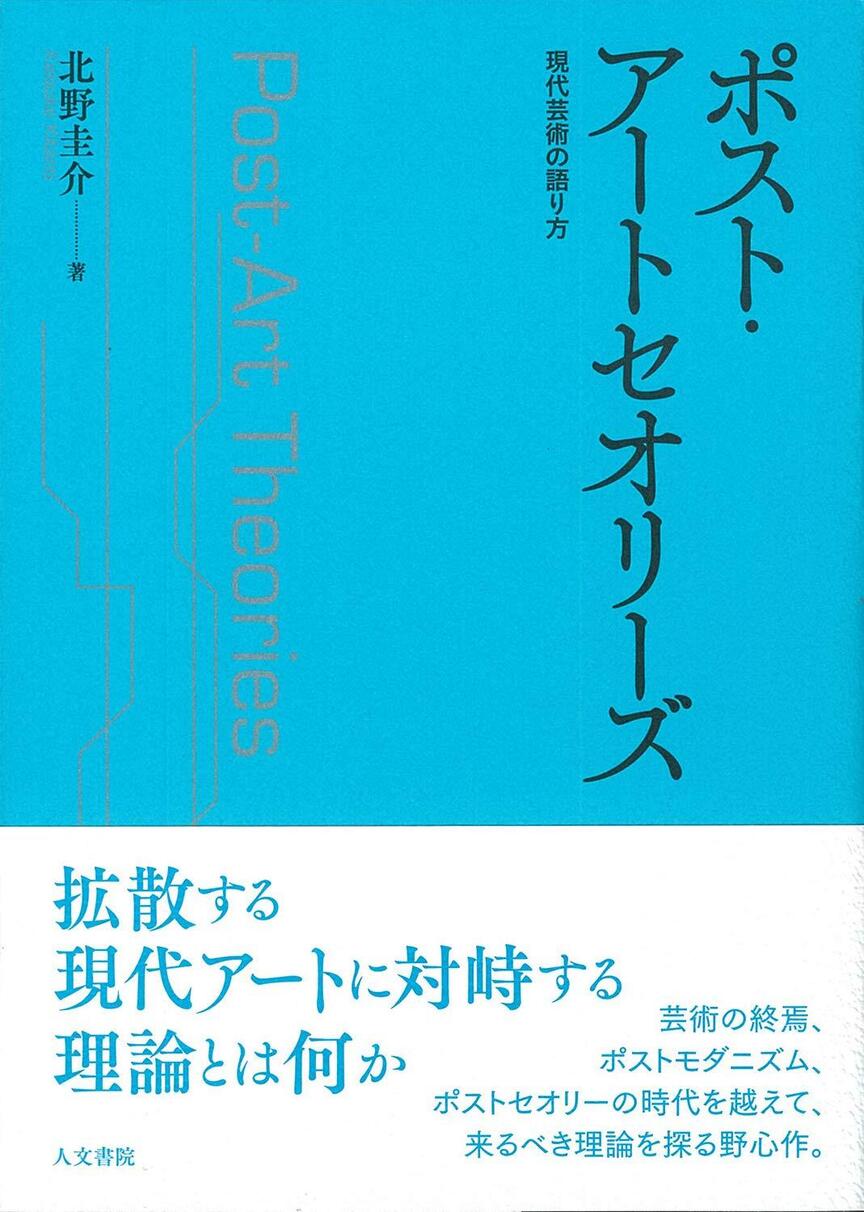
アーサー・C・ダントーによる1984年の論文「芸術の終焉」は、その標題にかかわらず、「芸術とは何か」という問いを深化させてきたと著者は述べる。であるならば、映像やインスタレーションといった作品形態の多様化や、グローバル資本主義による美術市場の巨大化、人々の情動を駆動していくデジタル技術の発展、「知」をめぐる状況の変化と、現実世界の方が変容を遂げた21世紀に、ダントーの論はどのような意味を持つのか。いまや芸術作品と商品はますます渾然一体となっているのではないか。このような問題意識から、著者は自身が間近に接した『オクトーバー』周辺の論者たちを中心に、ポストモダン以降の多様な理論を位置づけ直すことによって、いま現代芸術を「語る」ための言葉を導き出す。
本書でとりわけ注目すべきは、デジタル化やバーチャル化が進むにつれ、むしろ逆説的に身体性や物質性が際立ってきているという指摘だ。モノ、イメージ、メディアそして身体の関係は決して固定的でなく相互に影響し合いながら新たな意味を生み出し続ける、そうしたダイナミズムを自覚することこそが、安易な審美化を見抜く一つの方法なのである。そのために必要なのは、本書後半で著者が行なっているように、個々の芸術実践を、現実との関わりを通して思索し続けることである。
主客二元論を軸とした西洋中心主義の解体を提唱するハンス・ベルティングや、旧共産主義国家という出自から欧米の自由主義的価値観を鋭く問うボリス・グロイスの言説を引いて著者が指摘するのは、どのような政治体制であれ、現代の芸術は政治権力や市場経済という力動的な場に置かれるという構造である。このことは、国家的な管理統制や経済格差といった現状において、芸術と向き合う上で最も必要とされる観点であろう。
(岡添瑠子)