24フレームの映画学 映画表現を解体する
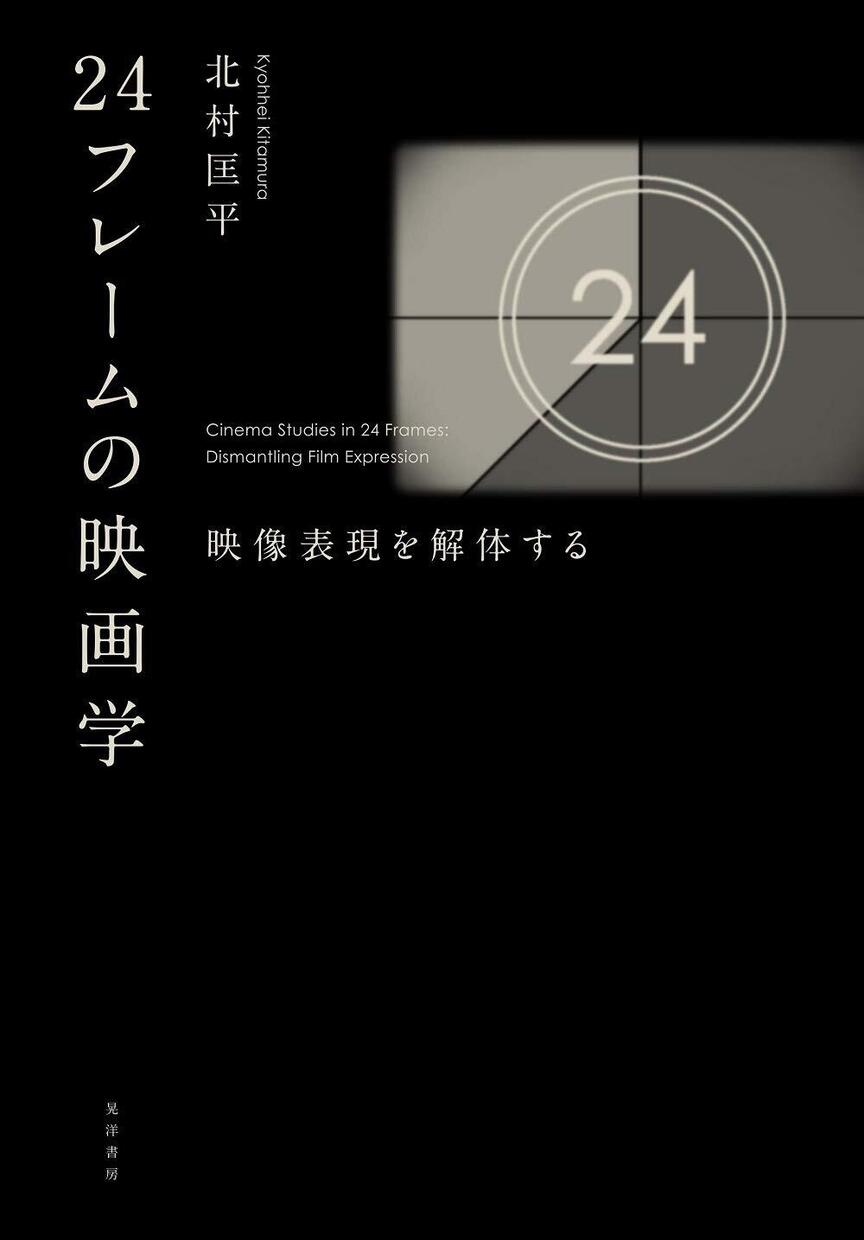
映画をみる環境も多様化しているいま、映画を論じるには何に注意すればよいか。本書は、形式、技術、メディアなどの特徴を簡潔にまとめながら、映画を論じる道筋をわかりやすく示している。基礎を固め、読み手が何より面白く読めるようにまとめられているのがうれしい。フレームやショットを説明するために、序説では仮面ライダーやウルトラマンの「動き」が例に挙げられる。ときには、比較対象としてテレビアニメも対象に、図像が惜しみなく、かつ実証的に示されている。はじめて映画を論じようという読み手も、無理なく読み進められる構成になっているのだ。著者のサービス精神ともいうべき細部までの徹底した構成、緻密な考察が、研究と面白さが両立することを証明している。
標題の通り「フレーム」を注視した成果のうち、たとえば第3章、黒澤明の『羅生門』に迫る部分では、肉眼では視認しがたい剣の一振りがどのように撮影され、編集されていたのかがよくわかる。デジタル技術を用いた情報解析は言語学や社会学だけでなく、映画学にも有効だろう。解析から、従来の「作家」や「作風」への認識が覆されることもあるはずだ。
隣接する領域に通じる議論も豊富である。同3章、『リング』『ザ・リング』の考察は、恐怖を生み出すショット、編集の差異が比較文化論としても読める。篠田正浩とマーティン・スコセッシ、それぞれの『沈黙』に迫る第9章は遠藤周作研究にまで分け入り、翻訳に生じる微妙な、しかし大きな差異が、いかに映画に発揮されたかまで指摘している。
第7章以降および結論は、アニメーションや今日の事例を包括する。映画の異種混淆性やリメイクなどそれまでの議論の集大成であり、今後の映画論が構想される。第1章に提示されたトム・ガニングの「アトラクションの映画」に対して、現代は情報の過剰、メディアの多様化が挙げられる。しかしなお、わたしたちが映画に驚きや快楽を志向しているのが興味深い。これら、映画のはじまりから今日までの道筋を示しながら、映画を論じようとする者の視界を晴らしてくれる1冊である。
(宮本明子)