世界は映画でできている
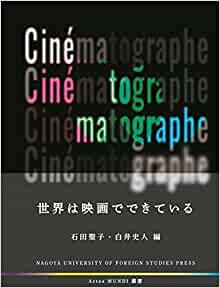
現在、大学の教養教育の枠組みにおいて、映画論、メディア論、表象文化論などの名称で、映画史や映画分析をとりあげる科目は多い。また正面から映画をとり上げない場合でも、文学入門でローレンス・オリヴィエを見る機会もあれば、社会学の演習でケン・ローチ作品が議論の題材となることもあるだろう。
ただし、大学の教室で映画に触れる学生には、「無声映画」なるものの存在を教室で初めて知る者もいれば、定額配信サービスのおすすめに追われるようにスマホの画面で毎日「映画」を眺めている者もいる。映画館のスクリーンで作品に触れる、といった一種のスタンダードを想定することが困難となりつつある映画と若者をめぐる現状において、広義の映像へと向けるべき視線はどのように養われるべきだろうか。
本書は、このような問いを出発点として、名古屋外国語大学の教養教育の一環で使用するための教科書として構想された。前半の4つの「テイク」は(本書は各章をこのように呼ぶ)、フランス、イタリア、ドイツ、アメリカに関する論考で、名古屋外国語大学で開講されている映画関連の講義を担当する教員による。後半はロシア・東欧(沼野充義)、ラテンアメリカ・スペイン(野谷文昭)、中国・台湾・香港(藤井省三)のそれぞれの地域・言語を扱うテイクを収めた。その間にインターミッションとして、イギリス(ムーディ美穂)、イスラム圏(松山洋平)、日本(ライアン・モリソン)、インド(カンデル・ビシュワ・ラズ)、北欧(亀山郁夫)の映画に関するコラムを挟んでいる。
それぞれの章は独立しており、どこからでも読むことができる。ただし、前半の4章には各地域の映画史を概観する第1節と、著者の視点からひとつのトピックを深める第2節をおくことで、欧米の映画史の基礎を押さえ、言語や地域を横断する視点を示すことを目指した。
無声映画期を中心にアメリカ映画を扱い、物語映画の成立と「アトラクションの映画」との関係を論じたテイク4や(小川真理子)、イタリア映画を扱うテイク2での脚本、物語、カメラなどの観点からの『自転車泥棒』の細やかな分析は(石田聖子)、映画研究の基礎文献をカバーし、映画を分析する基本的な姿勢を範例的に示すものであろう。また、フランスに関するテイク1は、ドイツ占領下のフランスで制作された映画『密告』(1943)を取り上げ(ヤニック・ドゥプラド)、ドイツに関するテイク3は、映画の音および音楽を中心に、無声映画『最後の人』(監督:F.W.ムルナウ)のドイツとアメリカでの伴奏の変化を論じ(白井史人)、国家や言語といった枠組みの境界にある映画の運動に焦点を当てた。
執筆者はすべて、2020年現在、名古屋外国語大学で教鞭を執っているか、かつて所属していた教員である。「外大」という機構上の特性により、本書が扱う映画の「世界」の外延が、日本の大学における第2外国語教育の区分やヒエラルキーにゆるやかに対応させざるを得なかったことは、こうした事情も背景にある。しかしながら、ひとつの大学における教養教育の枠内での、厚みを持った映画との関わりを伝えるものともなったはずだ。
本書はデイヴィッド・ボードウェルらによる『フィルム・アート 映画芸術入門』(名古屋大学出版会)に代表されるような、映画分析の基盤となる方法論を網羅することを目指したものではない。それぞれの地域・言語に深く根差し、映画のみならず文学、音楽などの分野で研究を進めてきた執筆陣が、束になって語ることで浮かびあがる複数の歴史記述を、いかに組み合わせるか。そしてそのぶつかりから、どのような世界がいま映像とともに「生成」するのか──これが、やや大仰なタイトルに込めた本書の問いかけである。
(白井史人)