アイデンティティ 断片、率直さ
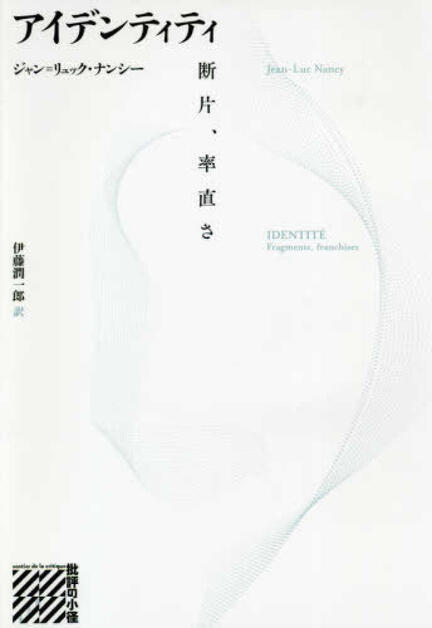
2009年11月、当時のフランス大統領ニコラ・サルコジの呼びかけで「ナショナル・アイデンティティに関する大討論」がおこなわれた。政治的な底意が丸見えのこのイベントに対して、哲学者ジャン゠リュック・ナンシーが(本人の言葉を借りれば「大急ぎで」)著したのが本書『アイデンティティ』である。このように書くと、状況に介入する言葉が並んでいる本だと思われるかもしれないが、そうはなっていないところが本書の一番の読みどころである。むしろ、そのような言葉を期待する読者を裏切るかのように、「アイデンティティ」をめぐる哲学的考察がくり広げられている。
その考察の核心をあえて簡潔にまとめれば、アイデンティティを所有ではなく、存在の観点から捉えなおすことだといえるだろう。主体が何らかのアイデンティティを所有している状態ではなく、主体が何らかのアイデンティティを存在するという行為(他動詞としての存在)が問われているのである。既成のアイデンティティを所有することは、それがたとえ複数のアイデンティティを所有するような状態であっても、アイデンティティそのものを問い直す契機を欠いている。アイデンティティとは、そうした静態的なものではなく、それを言表したり表明したりする行為のなかで、たえず作り直され変形されていくものなのである。
つまり、アイデンティティを表す名は、口にされるたびに、従来の意味とは異なるものを生み出す可能性をもっている。それゆえにナンシーは、「フランス」というアイデンティティを画定しようとするサルコジの企てに抗して、「フランス」という名をあえて口にすることで本書を締めくくる。つまり、「フランス」という名を捨てることなく、さりとてそこに閉じこもることもなく、その先に何を見通すことができるのかが問われているのである。あたかもグローバル化とナショナル・アイデンティティが閉域をなすかのような現在において、ナンシーの問いかけの重要性は、原書出版から10年以上が経過してもなお、いささかも減じるところがない。
(伊藤潤一郎)