宮沢賢治論 心象の大地へ
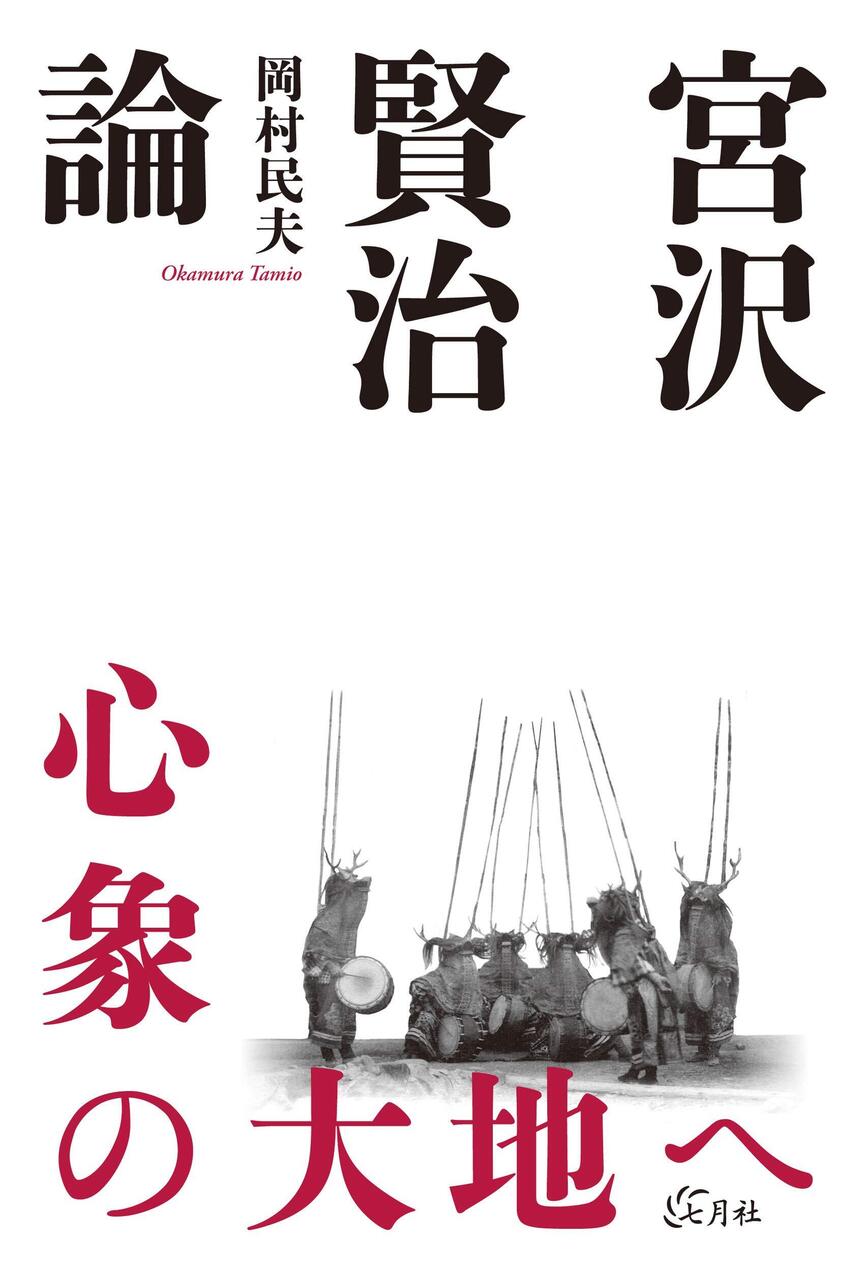
宮沢賢治の文学とは、「心象の文学」なのだと、著者は言う。しかし、賢治にとっての「心象」とは、現実から遊離した個人の内省性からのみ立ち上がってくるものではない。むしろ外的世界からの刺激を多分に受容しつつ、外部と内部とが渾然一体となるような境地からこそ生まれるものなのである。
賢治の数多くの詩や童話の源となったのは、彼自身が山野を巡るなかで偶発的に得た不思議なイメージを、その場で野帳に素早く書き写した断片的な記録としての「心象スケッチ」の群である。自然のダイナミズムと賢治の想像力が呼応するようにして生成した、様々な「心象スケッチ」間の自由な交通を促進し、その作品への昇華を実現するために重要な役割を果たしたのが、賢治作品の重要な舞台としての「イーハトーブ」という謎めいた場所であった。
著者が本書のなかで、フィールドワークの成果を踏まえつつ、繊細な手つきで検討していくのは、設定の統一性や整合性が希薄な多様体そのもの、賢治にとっての「心象の大地」としての「イーハトーブ」のあり様である。本書全体を貫いているものは、「賢治作品に恒常的に認められる不分明さ・不可思議さ・不整合・断片性・多義性・決定不能性など」を、「顕在的な個体に存在論的に先立って縦横無尽に広がる有機交流網の存在を彼が確かに察知していることの証し」と受け止めたいという著者の思いであり(本書14頁)、そこには賢治の作品、そして賢治その人の生が有している動性自体を把握しようとする真摯な姿勢がある。
とくに興味深かったのは、賢治が手掛けた造園事業についての論考である。賢治作品には庭園に関わるモチーフが頻出するが、彼自身もランドスケープ・アーキテクトとしての一面を有していた。近代化を推し進めていた当時の花巻において、文学者でありながら社会的実践家でもあった賢治が創出した、公共空間としての庭園。著者が精査する当時の記録から浮かびあがる、他者性や外的な力によって不断に生成し続けていくような、未来に開かれた空間として構想されたその庭園の様相は、まさに賢治の文学性の写し鏡に他ならない。
(菊間晴子)