第11回表象文化論学会賞
【学会賞】
須藤健太郎『評伝ジャン・ユスターシュ』(共和国)
【奨励賞】
荒川徹『ドナルド・ジャッド──風景とミニマリズム』(水声社)
古川萌『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰──16世紀後半フィレンツェにおける記憶のパトロネージ』(中央公論新社)
【特別賞】
該当なし
選考委員
・沖本幸子
・亀山郁夫
・郷原佳以
・長谷正人
選考委員会
2020年5月17日(日) オンラインミーティング
選考過程
2020年1月に、表象文化論学会ホームページおよび会員メーリングリストをつうじて会員から候補作の推薦を募り、以下の著作が推薦された(著者名50音順。括弧内の数字は複数の推薦があった場合、その総数)。
【学会賞候補作】
- 荒川徹『ドナルド・ジャッド──風景とミニマリズム』(水声社)
- 須藤健太郎『評伝ジャン・ユスターシュ』(共和国)
- 滝浪佑紀『小津安二郎 サイレント映画の美学』(慶應義塾大学出版会)
【奨励賞候補作】
- 荒川徹『ドナルド・ジャッド──風景とミニマリズム』(水声社)
- 岡本佳子『神秘劇をオペラ座へ:バルトークとバラージュの共同作品としての《青ひげ公の城》』(松籟社)
- 桐生眞輔『文身 デザインされた聖のかたち──表象の身体と表現の歴史』(ミネルヴァ書房)
- 古川萌『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰──16世紀後半フィレンツェにおける記憶のパトロネージ』(中央公論新社)
【特別賞候補作】
推薦なし
選考作業は、各選考委員が候補作それぞれについて意見を述べ、全員の討議によって各賞を決定してゆくという手順で進行した。慎重かつ厳正な審議の末、学会賞に須藤健太郎氏の著作、奨励賞に荒川徹氏と古川萌氏の著作を選出することに決定された。
【受賞者コメント】
【学会賞】
須藤健太郎『評伝ジャン・ユスターシュ』(共和国)

このたびは『評伝ジャン・ユスターシュ』を学会賞に選出していただき、まことにありがとうございます。選考委員のみなさま、候補作にご推薦くださった方、事務局の方々、関係各位に心より感謝申し上げます。
受賞のお知らせをいただいたときは喜びよりも驚きが強く、正直こうして挨拶の言葉を綴っているいまでさえ半信半疑のままで、どこか落ち着かない気持ちでいます。
まだ5月の半ばごろだったでしょうか、コロナ禍の影響で日本は緊急事態宣言下にありました。そのころ、私は未曾有の事態に直面してまるでフィクションの世界を生きているような気分に陥りながら、不思議と日々変わらずに営まれていく日常のあり方を楽しむようになっていました。
朝起きて、夜寝る生活でした。
ご飯を食べて、運動をして、掃除をして、洗濯をして、本を読んで、液晶モニターで映画を見て、頭を放心とさせ、食器を洗い、お菓子を食べて。日々違う入浴剤を試して。
近所に食料品の買い出しに出かけ、使い捨てのマスクを帰宅するたび洗うことを覚えて。
たまに激しい物欲に取り憑かれるがままに、ネットで買い物しては後悔をして。
いまのところたまたま収入源を断たれることも健康を害することもなく、毎日を送っている。子どもがたまたまいないから苦労が少ないのかもしれない。不便も不満もあるにはあるが、これといって不自由はしていない。ふとそんな自分に罪悪感を感じて、寄付をしたりクラウドファンディングに参加したり。
もともと行動をともにすることが多かったとはいえ、連れ合いとは文字通り四六時中一緒にいるようになり、語り笑い合い、愚痴を言い合いしているうちに、飽きもせずに毎日が過ぎていきました。
そんなときに、思ってもいないところから、思ってもいない連絡がやってきました。刊行からすでに1年以上が経過していたからなおさらでした。返信のメールに「本当でしょうか?」と書いては消しを繰り返したように思います。日常とは別のところで展開している別の世界があって、あたかもそんな彼方の話が侵入してきたようでした。
それとも、いまやお伽噺のような日常を生きていて、この一報によって現実に引き戻されたのかもしれません。
賞を受けることになって驚き、そして喜んでいましたが、時間が経つにつれてより冷静にものごとを考えられるようになりました。これまでの学会賞・奨励賞の受賞作一覧を前にすると、そのあまりに輝かしい著作の並びと比べて自分の本はどうしたって場違いであり、今回の受賞は偶然に偶然が重なった結果でしかない。そのことを肝に銘じたいと思います。
そもそも思い返してみると、この本が2019年4月末に出版されたのは、たまたまゴールデンウィークの時期に都内でジャン・ユスターシュの回顧特集上映が決まったからでした。出版と特集上映の企画は同時進行で進められていましたが、上映のスケジュールが先に決まり、それにあわせて急ピッチで版元側が出版に向けて動き出しました。
もしこの特集の開催がその1年後に予定されていたら、2020年4月末、映画館は休業を余儀なくされ上映は中止。それにあわせて出版されるはずだった『評伝ジャン・ユスターシュ』もおそらく刊行延期になったことでしょう。当然、学会賞の候補にも挙がらないことになります。
このほど自分の名が著者として記される本が賞を授かり、身に余る高い評価に恵まれたおかげで、はっきりとした目標ができました。次は容易に評価されないものを書かなくてはならない。誰に読まれることがなくても、自分が納得できるものだけを書いていきたいと思います。
最後にもう一度だけ繰り返させてください。このたびはどうもありがとうございました。
【奨励賞】
荒川徹『ドナルド・ジャッド──風景とミニマリズム』(水声社)
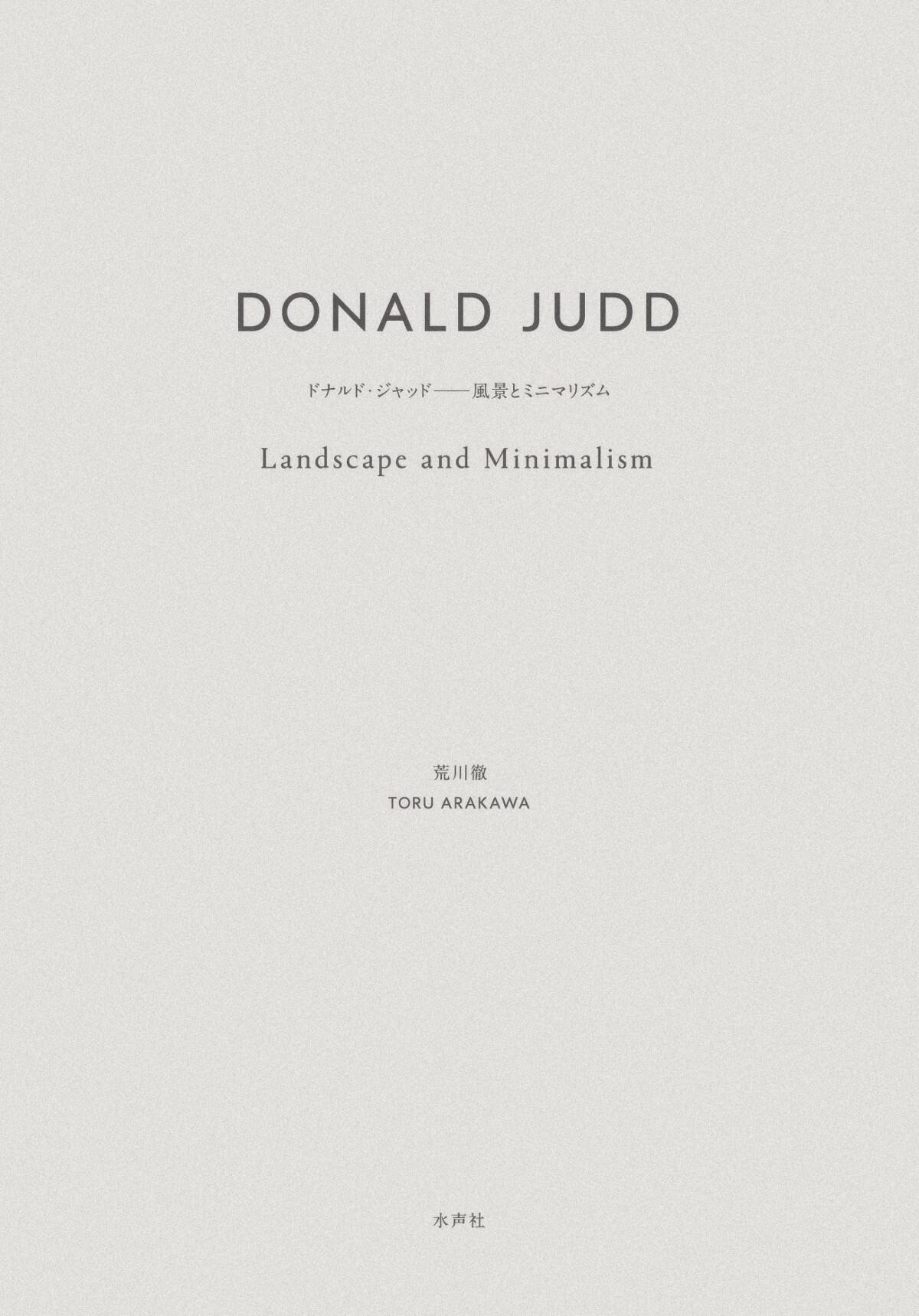
自らが書いた本が出版されるだけではなく、注意深く読まれ、その価値を吟味され、さらには賞までいただけるというのは、自分の手を完全に離れた出来事であり、大きな喜びにほかなりません。何より選考委員の先生方に心よりの感謝を申し上げたいと思います。
この場を借りて、受賞した『ドナルド・ジャッド 風景とミニマリズム』の装幀について語っておきたいと思います。なぜなら本の文章だけではなく、実際に触れる物体としての本の存在そのものにも、さまざまな点で強い意図が働いているからです。準備の作業そのものはかなりタイトで余裕はありませんでしたが、デザイン上の意図は幸運にも具現化され、多くの反応をいただきました。実際に、デザインについて言及されることが多々あり、出版されるやいなやデザインコレクションの本(『ページもの冊子・雑誌のパーツ別デザインコレクション』、グラフィック社、2019年)にも収録されました。
この本は、表紙、本文フォーマットともに、宇平剛史さんにお願いすることができました。宇平さんは、きわめて精緻な、グレイスケールと肌理をもつデザインを手掛けられ、近年は特に写真作品も展開しています。宇平さんに頼むきっかけとなったのは、櫻井拓さんが編集している雑誌『ART CRITIQUE』の隅々まで行き届いたデザインを見たことでした。本人とお話してみると、宇平さんがモノクロームを得意とされているのは、色彩に対する感覚がむしろ異様に鋭敏であるためであることが分かりました。たとえモノクロームでも、そこには十分に色があるのです。
ジャッドについて新しい本を作るためには、研究と同じく、これまでのジャッド関連書のデザインを踏まえつつ、そこには見られない構成上の特徴も必要でした。これまでのジャッド関連本を並べながら、本書のデザイン方針としては、ジャッドの作品の質感をある程度反映しながら、ある意味で矛盾した異質な要素を持ち込むことを考えました。宇平さんはそのコンセプトを、印刷で実現可能なかたちで解釈し、コンクリートのざらざらな質感を想起させる紙と、にぶく金属的に光を反映する箔押しのコントラストで形作りました。ジャッドの作品に、コンクリートと金属の両方を使ったオブジェクトは存在しません。紙というマテリアルで、ジャッドの素材性を圧縮したような質が生み出されています。微妙な色味は環境光で変化します。
本文フォーマットに関しては、書籍全体のモビリティを上げたかったため(近年のミラーレスカメラの動向に影響を受けた)、圧縮した横書きレイアウトになっています。電車で通勤中に読み終えたという声などが聞かれ、軽量化の成果もあったと感じました。ジャッドは意外にも「Small is beautiful」と言っていた人物です。
幸運にも東京大学の刊行助成を得て、水声社という、美しい本を多く送り出している出版社から上梓することができたことは、この本にとって最上の場所だったと思います。ほかの出版社であれば、帯もない横書きの本という、かくも自由な形式で出版できなかった可能性が高い。硬い厚紙でくるんだ完全な上製本ではなく、ややしなる紙で上製本と並製本の中間状態になっているのは、マッスよりも薄さを志向したジャッドとも重なるところがあります。編集担当の井戸亮さんからの提案を受けており、個人的にも気に入っているポイントです。本を読む前から、あるいは日本語が読めなくても、その中身に触れることができる──その可能性をつくることは、今後も大切にしていきたいと思います。
ブックデザインについて語ったこの受賞コメントを、先日亡くなられた戸田ツトム氏への追悼で終えたいと思います。氏が装幀を手がけたドゥルーズ゠ガタリの『哲学とは何か』(デザイン=戸田ツトム+岡孝治)が刊行されたころ、栃木県の駅前の書店で手にしたことは、芸術理論と出会った早い段階の記憶です。当時、電子音楽分野でのドゥルーズ追悼というコンテクストが同時にありましたが、私の経験では、どの論者よりも先だって、まず本国フランスにもない戸田ツトム氏の視覚的ドゥルーズ゠ガタリに影響を受けていたといえます。『哲学とは何か』の単行本の重さや、カバーの奥行きをもった輝く質感には、永遠性があり、これからも忘れることはないでしょう。心より、ありがとうございました。
古川萌『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰──16世紀後半フィレンツェにおける記憶のパトロネージ』(中央公論新社)
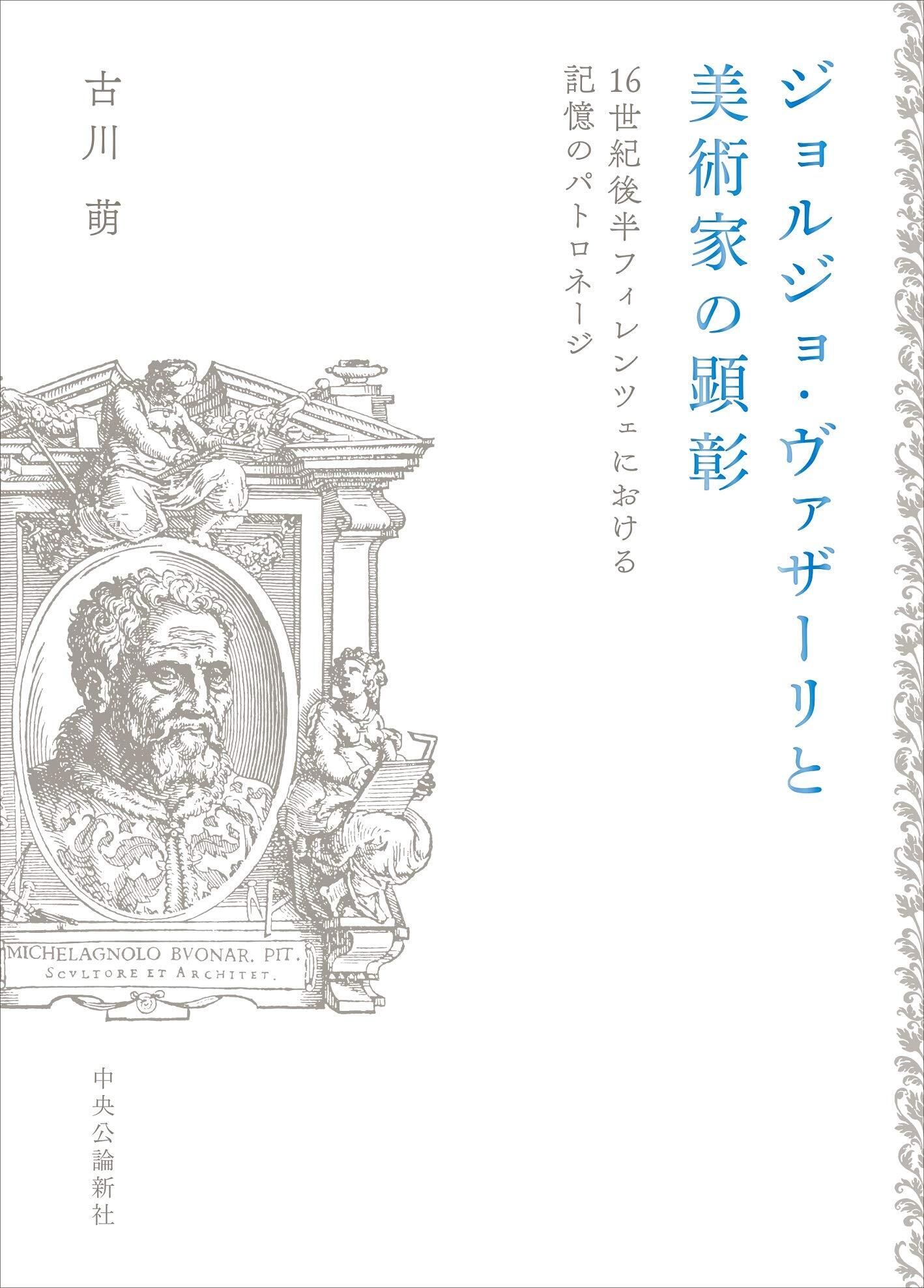
このたびは表象文化論学会奨励賞をいただき、たいへんありがたく光栄に思います。まずは、拙著を推薦してくださった方々、また審査してくださった選考委員の先生方に厚くお礼申し上げます。
本書『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』は、京都大学人間・環境学研究科に提出した博士論文を出版したものです。もともとこの研究は「アーティストに奇人のイメージがつきまとうのはなぜだろう?」という疑問に端を発し、美術家という概念が誕生したルネサンス期の美術家伝を検討するところから始まりました。ルネサンスの美術家伝のうちもっとも影響力の大きかったのはヴァザーリによる『美術家列伝』なので、必然的にヴァザーリを読み込むことになるのですが、調べていくうちに、個々の美術家の表象よりも、これらの伝記を書いたヴァザーリという人が目指したゴールのほうが気になるようになっていきました。ヴァザーリは伝記作家というわけではなく、本業は画家・建築家であり、メディチ家の宮廷画家としてさまざまなプロジェクトを実現した人です。そうした多岐にわたる仕事と『美術家列伝』の執筆の接点を考えたとき、浮かび上がってきたのは「美術家の記憶を永遠化する=顕彰する」ということでした。本書では、このような「美術家の顕彰」を軸に据えたとき、ヴァザーリの諸活動がどのように読み解けるかということについて論じています。
本書のもととなった博士論文の執筆にあたっては、非常に多くの方々にお世話になりました。修士課程と博士課程を通して所属した京都大学の演習では、岡田温司先生にご指導をたまわるのみならず、多様な研究分野を背景にもつ院生の方々からもさまざまなご助言やご指摘をいただき、より立体的な議論を組み立てる手助けをしていただきました。また、ポストドクターとして所属した東京藝術大学では、越川倫明先生、佐藤直樹先生、田邊幹之助先生をはじめとする芸術学科の先生方にご指導いただき、また西洋美術史研究室の学生の方々にも、演習を通して、議論をより専門的な知見から精査していただきました。風土の異なる二つの研究室に所属したことで幅広い視点からアイディアやアドバイスをいただけたことは非常にありがたく、研究を進めるうえでの糧となりました。さらに、中央公論新社の郡司典夫氏は、この博士論文を美しい本に仕上げてくださいました。皆さまにこの場を借りてお礼申し上げます。
新型コロナウィルス感染症の世界的流行により、海外調査の中止を余儀なくされた今、調査でフィレンツェに赴き、ヴァザーリの足跡をたどっていたころが懐かしく思われます。サンティッシマ・アンヌンツィアータ聖堂附属「画家の礼拝堂」に入れてもらうため、どきどきしながら修道士の方に鍵を開けてもらったり、ルネサンス研究所ヴィッラ・イ・タッティでの昼食に同席させていただき、第一線で活躍する研究者の方々の活発な意見交換に気圧されたり……。本書には、駆け出し研究者のわたしが経験した楽しい研究の思い出がたくさん詰まっており、そのような大切な本が奨励賞受賞の栄誉にあずかったことは、わたしにとってたいへん誇らしいことです。まだしばらく現地調査は困難でしょうが、受賞に背中を押された気持ちであの地に舞い戻り、さらなる研究に邁進したく思います。
このたびは本当にありがとうございました。
【選考委員コメント】
沖本幸子
はぐれ人材の私が審査員を務めるということで大変心苦しく思っているが、幅広い分野を抱える表象文化論学会のこと、無知と無謀を承知で腹をくくり、一読者として審査に臨むこととした。
今回、主な軸としたのは以下の点だ。1つ目は、博士論文を書籍の形で出版することが一般化している中で、博士論文の形式や枠組みを超えて、広く読まれる作品としての完成度を持っていること。もう1つは、この先の研究の展開、次の著作を予感させる力を持っていること。加えて、日本で出版すること、日本語で出版することの意味を問いたいと思った。
まずは、学会賞受賞作の須藤健太郎『評伝ジャン・ユスターシュ』。フランス語で書かれた博士論文を自分で日本語に訳したということだが、翻訳の介在を感じさせないスピード感のある文章で、門外漢でもおもしろく読み進められた。評伝自体は資料が揃えば誰にでも書けるもので、特段の技を必要とするものではないという評価もあった。しかし、本書には、外国語を母語とする人間が、しかも、もはや亡き人を研究する限界を見定めた上で、今集められる資料を徹底的に収集し、今聞き取れる限りのインタビューをして書き上げたという迫力があった。広く世界のジャン・ユスターシュ研究に寄与するものといえようし、こうした資料を博捜する力は、次なる研究への確かな手応えでもあるだろう。
次に奨励賞2作。
今回の候補作の中で、その装幀も含めて最も表象文化論的な成果と捉えられるのは、荒川徹『ドナルド・ジャッド』だろう。美しく端正な本で、丁寧な考察の賜。ただ、ジャッドと言いながらトニー・スミス、ロバート・スミッソンの占める割合も大きく、また、文字の小ささ、デザイン性の故か、まとまりとして文章が頭にはいってきにくい点は惜しいと思った。
古川萌『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』も美しい本で、線的に捉えられがちな「美術史」を、もっと広い文脈から丁寧に立体的に捉え出そうとする姿勢が印象に残った。
上記のお二人には、日本の現代アート研究や、日本の西洋美術史研究といった枠組みを超えて、もっと大きな世界を視野に入れて活躍していただきたいと強く思った。
以下、その他の候補作について述べる。
滝浪佑紀『小津安二郎 サイレント映画の美学』は学術書として丁寧に書かれた本だ。英語圏での小津研究の穴を埋める研究として大きな意味を持つものだが、この内容であれば、アメリカで出版すべきだったのではないかという気がした。日本には日本の小津研究の蓄積があり、日本で出版するのであれば、時間がかかっても、そうした文脈に十分配慮した上で、それを超える小津論を書き上げてほしいと思った。
岡本佳子『神秘劇をオペラ座へ』は、もととなった論文のいくつかは、現地の学会で発表、執筆されているようで、そうした姿勢に好感を持った。ただ、逆に、日本で出版することの意味についてはわかりにくかった。なぜ、今、日本でバルトークなのか、しかも「青ひげ公の城」なのか、ということについてももっと意識的に書いてほしい気がした。
桐生眞輔『文身 デザインされた聖のかたち』は、なんといっても入れ墨の文化誌という視点のおもしろさを高く評価したい。ただし、序論も結論もなく、中世が抜け落ちたまま古代と近代(若干近世も)に焦点が絞られていたり、そもそも本書がどういう動機で書かれたものなのか、どこに発表した論なのか、書き下ろしなのかもわからないというのは、やはり学術書としては欠陥と言えよう。また、添付の資料集に一次文献と二次文献が同じように扱われているなど、資料の扱い自体にも不安な要素があり、学術的な価値を減ずる結果となっている。荒削りだからこその良さもあるが、もったいないので、精度を上げて研究を進めてほしいと思った。
亀山郁夫
思いつくままに書いてみたい。
今年もまた、きわめてレベルの高い六点が並び、選考委員としてよりもむしろ一読者として大いに楽しむことができた。最初に、私が基準としたのは、1、着眼点、2、テーマの現代性、3、学問的精緻さ、そして4、リーダビリティの4点である。着眼点については、選考委員の好みに左右される場合が少なくなく、ここに重点を置きすぎることのないよう配慮した。ただ、テーマの現代性という観点は、ほぼ「直観」勝負といった側面もあり、ここでおのずから対象は絞られてくるだろうと予測した。学問的精緻さは、すべてこれをクリアすることが前提だが、仮に注などのない論考が対象となった際のチェックポイントとして意識した。問題は、リーダビリティである。昨年度の選考委員会でも話題になったが、賞の性格上どこまでリーダビリティに重きを置くか、そもそもリーダビリティは不可欠なのか、あるいは何をもってリーダビリティとするか、などいくつか問題があり、私自身かなり神経質にならざるをえなかった。ただ、選考プロセスで、私以外にもリーダビリティに重きをおく委員の発言があり、安心して議論に加わることができた。候補作が、書籍に限られている以上、アカデミズムの成果の社会還元という側面からも、リーダビリティは無視できないという私なりの持論は十分に理解していただけたと思う。ただ、書きぶりの魅力というのは、文章の硬軟を越えて存在するものであり、それ自体がリーダビリティの一部をなすというという考え方にたいして、十分に配慮したつもりである。
選考の順にかんたんに講評を述べると、最初に対象となったのが、荒川徹氏の『ドナルド・ジャッド——風景とミニマリズム』。20世紀を代表するミニマリズムの巨匠ジャッドの絵画、オブジェクト作品等に風景がいかに影響を与えたかに関する論考であり、従来の基準から、当初、この著書がもっとも学会賞らしい著作かもしれないという予感を持った。難解ながら(硬軟を越えた「書きもりの魅力」)、言葉で対象に肉薄する姿勢を好ましく感じたのと、他の候補作が必ずしもそうした方向性を共有しているとは思えなかったことが大きな理由である。ただ、文章面にいくつか瑕疵と思われる部分があり、最高賞に推しきるまでにはいたらなかった。次に、須藤健太郎氏の「評伝ジャン・ユスターシュ」。当初、そのあまりに巧みな語り口に圧倒され、精緻さの基準をクリアできるのか、と懸念が生じたほどだが、杞憂に終わった。結果的に、着眼点、現代性、精緻さ、リーダビリティの4点をすべてクリアしていたのに加えて、同氏の果敢なフィールド精神にたいし高い評価が寄せられた。評価が分かれたのが、滝浪佑紀『小津安二郎 サイレント映画の美学』である。サイレント時代の小津を、同時代においてグローバルに共有されていた映画美学の文脈のなかで捉えようとする労作であり、学問的精緻さと構成面での配慮等に好感を抱いたが、一段階上のリーダビリティを追求してほしかったというのが率直な印象である(とくに序文)。同書を学会賞に強く推す選考委員もいただけに、その点がたいへん惜しまれる。桐生眞輔『文身 デザインされた聖のかたち:表象の身体と表現の歴史』は、入れ墨の文化とその意味を古墳時代にまで遡って解き明かそうとするスリリングな論考で、その着想の大胆さに注目が集まったが、学的歴史の面に若干ハンディがあり、私自身、レベルの高さを量りきれなかったというのが実情である。私がもっとも判断に迷ったのが、古川萌『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰──16世紀後半フィレンツェにおける記憶のパトロネージ』である。ダイレクトに美術作品ではなく、『美術家列伝』に着目するというメタ的発想から出発し、いわば発生段階での美術史を掘り起こしつつ、その美術史に隠された意味をフィレンツェの文化史を背景に読み解くという内容なのだが、ほとんど私の想定・関心外にあるテーマであり、残念ながら十分な責任をもって学会賞に推すまでにはいたらなかった。最後の岡本佳子『神秘劇をオペラ座へ:バルトークとバラージュの共同作品としての《青ひげ公の城》』は、近年、世界的に関心が集まっているバルトーク研究に一つの里程を刻む著作である。ただ、事実説明にかなり紙数を費やしていて、全体として対象への肉薄に欠けるという印象をぬぐえなかった。『青ひげ公の城』は、二十世紀でも一、二を争う作曲家のオペラだけに、粗筋の説明ひとつにしても、それなりのレトリックを駆使し、説明しつくす努力が必要だったのではないか。
郷原佳以
学会賞・奨励賞の候補作6作は、映画、オペラ、美術(ルネサンス、現代)、身体表象(文身)と多領域にわたるが、いずれも博士論文(うち2作は外国語で書かれたもの)を元にしている。私自身の専門はどの著作とも重ならなかったので、いずれからも等しい距離をもって読むことになった。専門と直接関わらないところで研究者のデビュー作を多領域にわたって読むことができるというのは純粋な喜びであった。順番に読んで何より驚いたのは、同じように博士論文を元にしていながら、著作としての印象はまったく異なるということである。いずれの著作についても、当該領域における指摘・発見の新規さを判断する立場にはなかったので、学術論文としての条件の満足度(問題提起、先行研究、構成など)、一読者として説得され、啓発される(他の領域にも示唆を与える)度合いを重視して臨んだ。
ただ、選考会前の段階で、奨励賞は古川萌『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰』で間違いない(荒川徹『ドナルド・ジャッド──風景とミニマリズム』が学会賞でなければ二作授賞となる可能性もある)と思っていたが、学会賞に関しては、須藤健太郎『評伝ジャン・ユスターシュ』をどう位置づけるかで変わってくると思い、決められなかった。というのも、本書は学術書としては破格の書き方がなされているからである。著者は、フランス語の博士論文を元にしているとは思えないほどこなれた読みやすい文章で読者を引き込み、生と映画が切り離せないものだった映画作家の同時代人との関わりや制作プロセスに併走させる。それを可能にしたのは、著者自ら関係者のもとへ足を運んで行った、膨大な量の取材による生きた証言である。この驚くべき労作は、しかし、先行研究との関係で対象における一つのテーマを追究し、新規な命題を説得的に提示するという博士論文の王道からは外れている。所々にはっとするような一節がきらめいているが(アリックス・ルーボーの写真論は魅力的だ)、それを一つのテーマに昇華して考察するよりは、映画作家の軌跡を遺体発見まで辿ることを選んでいる。全体から一つのテーマを取り出すならば、集合的記憶のための無名の語り手による口承の物語りだろうが、このテーマに関連するベンヤミンなどの援用は示唆に満ちているものの、ユスターシュを形作る要素としてのモンタージュ的なものに映る。そうしたすべてがユスターシュの映画制作と呼応しており、この著作自体が圧倒的にひとつの「作品」であることは疑いを容れないが、評伝を学術論文として評価することに躊躇いが残った。しかし、結果的には、本作に魅力を感じた委員が多く、授賞となった。
対照的に、打ち出したい命題が明確に提示されており、十分な文献参照もあり、博士論文として形式的に手堅いと思われたのは、滝浪祐紀『小津安二郎 サイレント映画の美学』である。結論の章がないのは気になったものの、小津のサイレント作品に「過剰なまでにハリウッド的」な性格を、とりわけルビッチ作品への忠実さにおいて検証することで、従来の小津観に異議申し立てを行うという構図は明解であった。ただ、選考会において、異議申し立ての対象が英語圏の小津論に偏っており、日本の小津研究の蓄積を十分に踏まえていない、といった指摘を聞き、説得された。
荒川徹『ドナルド・ジャッド──風景とミニマリズム』の書き方は、以上のどちらとも異なる。著者は、ときに作品の置かれた場所まで実際に足を運び、作品を具体的な次元で論じることで、ロザリンド・クラウスら、影響力の大きい論者たちが植え付けたミニマリズムの美学的概念からその作品たちを解放する。作品の外部からの切断というミニマリズムの固定観念とは異なって、ミニマル・アートの作品群は、実際には作家たちの経験や動機、とりわけ「非芸術的」工学構造への関心に大きく拠っている。そのプロセスを丁寧に取り出す手つきは著者ならではのものであり、「非芸術作品」という概念も新鮮だった。大局的な視点はやや見えにくいが、淡々とした理系的な分析と記述の背後には、作品に即さない美学への異議申し立ての意志が感じられた。ただ、論じられている作家や作品がときに唐突に変わり、どの作品が論じられているのか定かでなくなるほどに、ジャッドのみならずトニー・スミスやロバート・スミッソンの作品も論じられているのに、タイトルを「ドナルド・ジャッド」としているのはもったいないと感じた。選考会では、相対的にインパクトに欠けるという点、今後にさらに期待したいという願いから、奨励賞とすることになった。
上記の通り、奨励賞には古川萌氏のヴァザーリ論がもっとも相応しいと思い、推挙した。執筆当時の時代状況に即した『美術家列伝』の読解として明解で説得的であり、発展史的な美術史の父という後世からの視点を一新する力をもっていると共に、あくまで対象は控えめに限定されていながら、記憶や歴史をめぐる他領域や現代的な問題にも示唆を与えるという、研究書として理想的なあり方をしていたからである。文章も落ち着いており、造本も美しいが、このことも、本書が提示する『美術家列伝』論と呼応している。本書は、『美術家列伝』の各版を精査することで、『列伝』がまずもって、物故した美術家を顕彰し、記憶を永遠化するために書かれたこと、また、『列伝』そのものが墓碑であり、記憶の建築であることを明らかにする。『列伝』におけるエピタフは、やはりエピタフから発展して「……の墓」と呼ばれる追悼詩や追悼曲の伝統が生まれたことも想起させ、記憶の風化への怖れは伝記や歴史、そして芸術作品を生み出した根源的なものだとの思いを新たにした。
他の候補作についても一言述べておく。岡本佳子『神秘劇をオペラ座へ バルトークとバラージュの共同作品としての《青ひげの城》』は、バルトークとバラージュの交流を先行研究に抗して肯定的な関係として示すという明瞭な目的のもとに手稿調査に取り組んだ労作だが、ハンガリー・オペラ上演事情調査など、示されている資料にどれほどの意義があるのかわからない場合があり、全体として、専門外に開かれていない印象を受けた。桐生眞輔『文身 デザインされた聖のかたち』は、日本古典における文身表象を漢字の成り立ちを含めて紹介する部分などには、情報として刺激的なものが含まれていたが、序章がなく、全体の見取り図が示されないため、どこに軸足を置き、いかなる目的で書かれたのかが見えず、文章も、突如として「あなた」への語りかけが現れるなど、行き当たりばったりに書かれたようで、学術論文として評価できなかった。領域横断的で興味深い題材なので、魅力的な研究が現れることを期待する。
長谷正人
今年は2度目の審査だったが、選考審査会での合議の末に、学会賞1作、奨励賞2作を無事選出できて、ほっとしている。昨年と同じような感想になってしまうが、やはり全く異なった専門領域の研究書を同じ土俵で審査することの難しさをまずは感じた。候補作それぞれの研究対象は、小津安二郎のサイレント映画、1970年代フランスの映画作家ジャン・ユスターシュ、ミニマリズム芸術家ドナルド・ジャッド、16世紀イタリアのヴァザーリ『美術家列伝』、20世紀初頭のハンガリーにおけるバルトークとバラージュの交流、そして日本文化における刺青の歴史、といったように全く違っているし、またその研究対象に応じて研究方法や表現スタイルまでもが違ってくるので、それら性格の異なった6冊を公平な態度で読みこなすことはなかなかに大変な作業であった。
しかしバラエティに富んだこれら6作は、いずれも博士論文の審査(アメリカとフランスの大学を含む)に合格した論文をもとにし(去年とはそこが違った)、出版という関門を突破して、さらには学会員から推薦されているといった具合に、専門家の厳しい目をいくつも潜り抜けた果てに私の手元に届いている作品である。最初から一定の水準以上のものに決まっているのだ。だから私は、自分の専門家としての偏差には充分に注意しながら、それらの若い研究者たちの優れた書物の欠点を探し出そうというよりは、いったい何が優れているのかを考えながら読み、そしてこれは面白いと確信を抱けるような本を責任を持って選び出すという態度に徹することにした。それは大変な作業ではあったが、得る物も多かった。
私が今年とくに優れていると思ったのは、須藤健太郎『評伝 ジャン・ユスターシュ─映画は人生のように』(共和国)と古川萌『ジョルジョ・ヴァザーリと美術家の顕彰─16世紀後半フィレンツェにおける記憶のパトロネージ』(中央公論新社)の2冊であり、それぞれ学会賞と奨励賞を受賞することになった。
前者の須藤氏の著作は、ジャン・ユスターシュ監督の作品をただ美学的に論じるのではなく、評伝という形式を取ることによって、1960年代以降のフランスにおいて、若い作家たちにとっていかに長編映画を製作することが困難であったかということ、そしてその困難からテレビ番組の製作にいかに関わったかということなど、スタジオ・システムが崩壊した後の映画製作の歴史的ありようを見事に浮かび上がらせていて、単なる作家論とは異なった豊かな成果を感じた。とりわけ、この1960年代から80年代のフランス映画をめぐっては、ヌーヴェルヴァーグ作家たちの個性豊かな作品を称揚する言説が多いため、本書はそうした個性的な豊かさを支えている下部構造は何だったかに目を向けさせると言う意味で、こちらの常識を揺るがせるような新鮮な視線を与えてくれると思った。そしてもちろん、若くして死んだユスターシュの情熱的な人生と著者自身の情熱的な書き方が重なって熱いものを読者に伝えてくるところが(博士論文とは思えない)独得の魅力を持っていた。
後者の古川氏の著作は、美術史の基本的な著作として評価されてきたヴァザーリ『美術家列伝』を、当時の歴史的文脈のなかに置き直して、それを美術家の追悼モニュメントを収容する巨大な建造物として解釈し直すという刺激的な試みである。著者は、ただヴァザーリのテクストを解釈していくのではなく、この『美術家列伝』という書物が当時担っていた社会的機能は何だったかを考え、そこにメディチ家による「美術家の顕彰」作業を読み取っていくのだが、その読み替えの作業が実にスリリングだった。その作業はさらに他のヴァザーリの仕事にも展開して、「カリオペの書斎」の絵画や彫刻の配置のされ方を精緻に分析して、そこにトスカーナ地方を美術の起源としてアピールする政治的意味を読み取ってみせたり、『素描集』のなかの素描の額縁の枠に、美術作品を聖遺物に格上げする意図を読み解ってみせたりする。このようにヴァザーリの仕事を、美術を神聖化する政治的行為として読み解いていく読解を私は面白く読んだ。また図版もわかりやすく美しい書物だ。あえて難点を言えば、そうした美術の聖遺物化の作業を美しく描きすぎて、(ベンヤミンの「アウラの凋落」以降しか考えられない人間には)政治的批判の視点が弱いと思えた。
以上が私のコメントである。私の任期2年間の審査に関わった審査委員と事務局として協力された先生方に、充実した時間を与えてくださったことを深く感謝したい。また受賞した方々も受賞されなかった方々も、さらなる研究の発展を期待している。