カオス・領土・芸術 ドゥルーズと大地のフレーミング
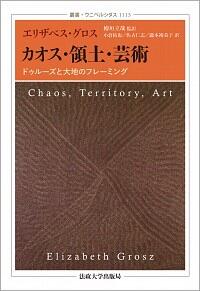
本書は、オーストラリアで生まれ、学位を取得し、現在はアメリカで活躍する哲学者エリザベス・グロスの芸術哲学をめぐる小著である。本書でグロスが試みるのは、ドゥルーズとガタリの哲学を導きとした「芸術の存在論」である。つまり、芸術のある種の「起源」を、歴史的・批評的にではなくその本質的構造の観点から哲学的に探究することである。グロスは、芸術を、粗野で不活性な物質性や決定された機能性から、それら以上のものとしての表現性が創発すること、感覚しえないものを感覚可能にすることと捉える。そしてそれを、ドゥルーズとガタリにしたがい、人間に限らない動物たちが、カオスとしての物質的宇宙のただなかで、それからの際立ちと自律性を示す領土を形成し、その領土をさらに解放していく行為、つまり「リトルネロ」に見いだす。よく知られた「芸術は動物とともにはじまる」という言葉が、ダーウィンにおける自然淘汰に還元されない性淘汰をめぐる議論を丁寧にたどりながら、また、例えばフロイトにおける欲動の昇華をめぐる議論などとの批判的対峙をとおしながら、解釈、理解、展開されていく。こうした芸術の存在論は、第一章では建築、第二章では音楽、第三章では絵画に焦点を当てて論じられるが、ハイライトは間違いなく、第三章のアボリジニ芸術をめぐる議論だろう。神話的なドリーミングを擁するアボリジニの民衆は、自分たちの生きる大地を、その地勢を、そこに住まう生き物たちを、様々な仕方で、とりわけ絵画というかたちで感覚可能にしてきた。作品は、そうして感覚可能にされるものたちを、それらとともにある出来事、つまり神話的な大火や、植民地支配や虐殺の歴史や、さらにはグローバリゼーションのなかで進行しつつあるアボリジニとその芸術の変質さえも含め、俯瞰し、そして祝福する、ひとつのモニュメントであるという。大地に生きること、領土を形成すること、そこに起こった出来事を祝福し、モニュメント化すること。それはその都度、感覚しえないものを感覚可能にする行為であり、感覚しえないものが新たに感覚可能になる未来を切望する行為でもある。だからこそ、芸術は──ここで焦点を当てられるアボリジニの民衆にとってはとりわけ──優れて政治的な意味を担いうるのである。本書は、ドゥルーズとガタリの芸術哲学の解説と援用であるだけでなく、少なくない論者が敬遠してきたドゥルーズとガタリの提起する「芸術と政治」という問題に対する、ひとつの可能な──おそらく白人のオーストラリア人であるグロスにとっては必然的な──引き受けであり、応答であると言えるだろう。
(小倉拓也)