脱ぎ去りの思考 バタイユにおける思考のエロティシズム
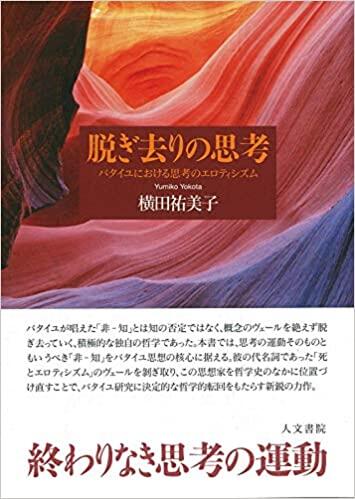
本書はそのタイトルが示すように、バタイユの思想を「脱ぎ去りの思考」という観点から読み解く試みである。そこで描きだされるのは、「エロティシズムの思想家」や「神秘主義的・非合理主義的な思想家」としてのバタイユではなく、絶えず過剰なものへと向かおうと欲する「哲学する者」(9頁)としてのバタイユである。こうした視点からバタイユの著作を読み解くことで、著者は、「死」と「エロティシズム」といった主題や「哲学者ではなく聖人であり、おそらくは狂人だ」という一見過激に見える一節を支えている問題の事柄を、既存の意味規定を脱ぎ捨てて別のものに向かう思考の欲望(この欲望が本書の副題にある「思考のエロティシズム」である)として、決して完結することなく先へ先へと進む哲学のエロスとして、鮮やかに浮かびあがらせている。
本書は大きく分けて、二つのパートに区分される。ひとつめのパートは、「非-知(non-savoir)」という主題を軸に、バタイユの思考の身振りを「脱ぎ去りの思考」として提示する第1章、第2章、第3章である。第1章では、「〈非−知は裸にする〉」という『内的経験』の一節をめぐって、概念知による意味把握を絶えず無効化していく「非−知」の在り様が示されていく。続く第2章では、1930年代の『ドキュマン』期における「低次唯物論」を中心に、「形(forme)」による意味規定に抵抗し続ける「物質」の問題が後年の「非−知」の思想の萌芽として位置づけられる。第3章では、バタイユに大きな影響を与えたヘーゲルおよびコジェーヴとの関係に焦点があてられ、「否定性」の問題をとおして絶対知の円環を絶えず超出する「用途なき否定性」の働きをバタイユが思考していたことが示される。
ふたつめのパートは第1章〜第3章での議論を踏まえ、「脱ぎ去り」と「エロス」という二つの主題がバタイユにおいてどう結びつくのかを考察した第4章と第5章である。第4章では、「私は娼婦がドレスを脱ぐように思考する」という『省察の方法』の一節から出発して、『マダム・エドワルダ』の精緻な作品分析を経由しながら、バタイユにおける「娼婦」や「卑猥さ」(さらには「神」や「逃走」)のテーマが、「脱ぎ去り」の問題と不可分であることが指摘される。第5章では、さらに踏み込んで、バタイユにとってエロスがどのような身分をもつのかが考察される。著者によれば、彼にとって「エロス」は、性愛的な意味でのそれではなく、意味規定を解体し過剰なものへと向かっていく思考の欲望(désir)を指すのであって、バタイユが論考「聖性、エロティシズム、孤独」のなかで「専門化されたディシプリン」としての哲学に「欲望」を対置したのも、哲学という営みをこうした思考の欲望として捉え直すためである。こうして著者はバタイユにとって「エロティシズム」という語が動詞的な「哲学すること」へと向けられていることを指摘し、「エロティシズム」という語の射程を新たに鋳直すのである。そして、結論部となる終章では、バタイユの「思考のエロティシズム」が「知を愛し求める」という哲学的なエロス論の系譜へと位置づけられ、バタイユ研究の「哲学的転回」が力強く表明される。
もっとも、この「哲学的転回」という表現に、バタイユを神秘主義や非合理主義の思想家として描く立場への反発をしか見ないとしたら、本書の枠組みを大きく捉え損ねることになるだろう。というのも、おそらく著者は、「転回」という語によって、「哲学というディシプリンからバタイユを読むべきだ」と主張しているのではなく、バタイユ自身が実践した思考の身振りを想定しているからである。バタイユは、「非−知」、「低次唯物論」、「用途なき否定性」、「エロティシズム」といった様々な名をとおして、一貫して絶えず自己解体するエロス的な思考に向かおうとしている。ここに見られるのは、思考の欲望を語ろうとするなかで、様々な名称を創出しては自分自身も解体し、変貌していく自己回転的な思考の営みである。だからこそ著者は終章で、この転回が「唯一の事象であって、唯一の名をもつわけではない」(274頁)と述べているのではないか。
このように、本書は時期も異なる様々なテクストを読み解きながら、一貫してバタイユにおける哲学の実践を検討している。その過程で本書は、バタイユの内在研究にとどまることなく、プラトン、カント、ニーチェ、ハイデガー、アドルノといった哲学者たちへの関連づけに加え、バルト、デリダ、ナンシー、ガブリエルらのバタイユ解釈も踏まえながら議論を進めており、専門外の読者にとっても極めて読み応えのある内容となっている。
しかし、思考のエロティシズムという「唯一の事象」に複数の名がありうるだとすれば、なぜそれに「哲学」という名を与えなければならないのだろうか。本書において思考のエロティシズムは、過剰なものに向かいながら探求を行う「問い直しの運動」(259頁)としても描かれるが、こうした探求を行うのはなにも哲学者だけではない。こうした運動には様々な名称が可能にもかかわらず、なぜ「哲学」という語を選択しなければならないのか。
もっとも、こうした問いは本書の不備などでは決してなく、本書によって開かれた問題の拡がりのようなものである。「哲学とはなにか?」──読者は本書を読み進めるにつれて、こうした永遠の問いの領野に足を踏み入れることになるはずだ。
(松田智裕)