弁証法、戦争、解読 前期デリダ思想の展開史
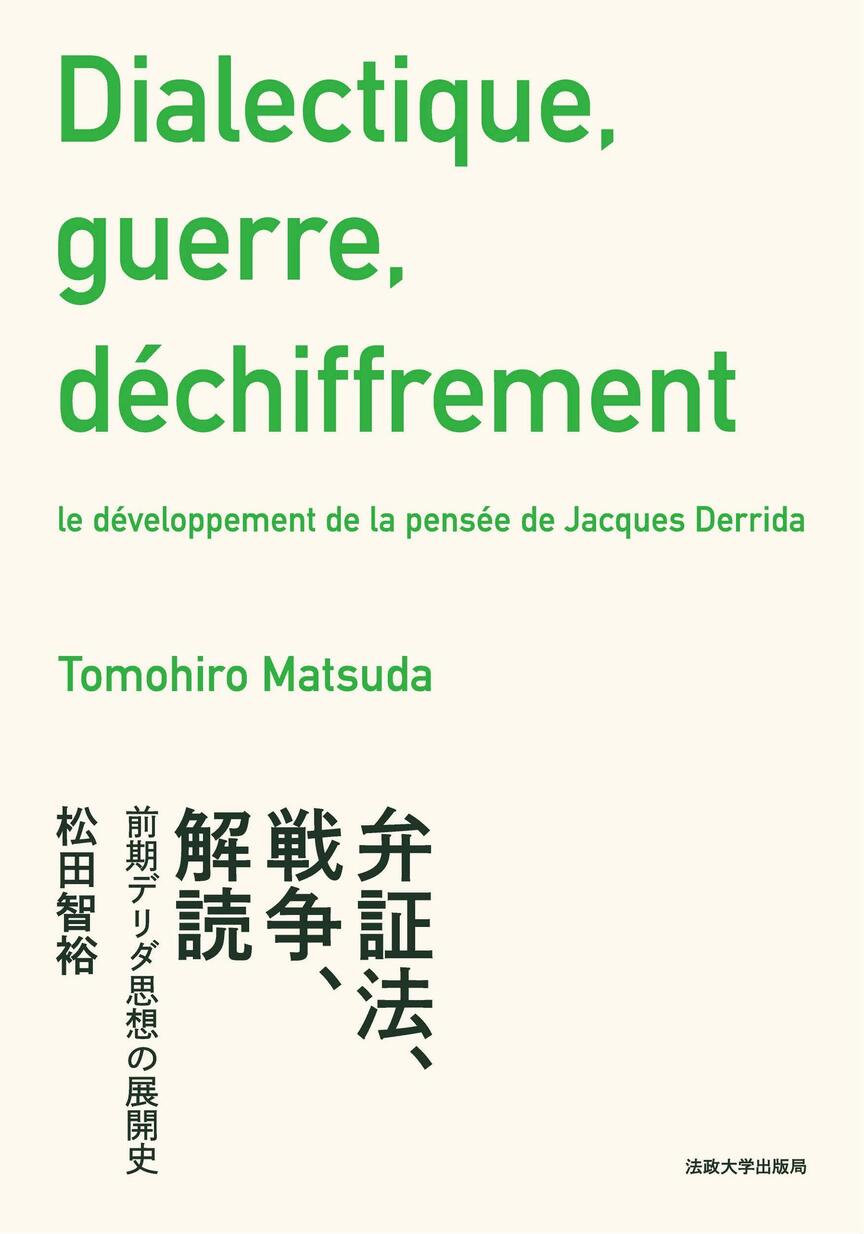
『弁証法、戦争、解読』。メインタイトルのなかで、一般的なデリダ像を想定するなら最も馴染み深いのは「解読」であろう。その他の「弁証法」と「戦争」は、デリダにおいて大きくフィーチャーされることは少ないように思われる。それではこれら三つはいかにして結びついているのか。
「弁証法」とは本書において、この語を定式化し自らの術語としたヘーゲルにおけるそれに限定されるものではない──尤もデリダは「竪坑とピラミッド」や『弔鐘』などの卓抜なヘーゲル論を著しているが。そうではなく、1950-60年代のデリダは、フッサール現象学において、「弁証法」を見出す。曰く、何かが歴史的に発生したときの起源と所産について、「前者が後者を生みだし、後者が前者の起源性を成立させる」(18頁)という相互連関のことであるという。そして、弁証法的なプロセスのさなかで互いに異なるもの同士が「軋轢(heurt)」を引き起こす。この作用をデリダが後年「戦争」と形容するものの端緒と見做し、デリダが自らの思想を開陳した1970年代以降の「争い(conflit)」や、晩年に登場する「ポレモス(πόλεμος)」、さらには彼の鍵概念の一つ「差延」等の思考へと跡づけていく。
この作業によって著者は、デリダの修士論文『フッサール哲学における発生の問題』で展開される思考を、『グラマトロジーについて』『声と現象』『エクリチュールと差異』が出版された1967年以降のデリダから投影して論じるの
また、イヴォンヌ・ピカール、ジャン・カヴァイエス、コスタス・アクセロス、トラン=デュク・タオら、デリダと時代が相前後し、デリダの思想形成に大きな影響を残しながらも、デリダへの影響関係については十分な蓄積のない著者たちが取り上げられている点も、本書を意義深いものにしている。デリダにおける「弁証法」の構想とその放棄を追うにあたって、彼らの思想との比較が不可欠なのだと、本書を通じて理解できるはずである。
デリダは「差異の哲学」や「ポスト構造主義」の思想と言われる。しかし、そのように形容されるべきデリダの思想の源泉は決して浮ついたものではなく、綿密な文献研究によって、同時代の哲学史の影響関係のなか形成されたものであることが本書では示される。そこにはもはや、「ポストモダン」の思想家デリダは姿を見せない。本書で見られるのは偉大な先達のテクストに虚心坦懐に向き合い、格闘し、自らの思考を彫琢したデリダである。
最後に、著者は「弁証法(的軋轢)」や「戦争」を通じて、テクストの、エクリチュールの「解読」が絶えず更新されていくことをもって、デリダにおける解読の無際限性を説き、単なるテクストの相対主義という安易なデリダ理解を斥ける。いわばDerrida before “Derrida”を徹底的に追究するこの書物を繙いた後には、まさにわれわれ自身のデリダ哲学の読解も
(吉松覚)