黒澤明の羅生門 フィルムに籠めた告白と鎮魂
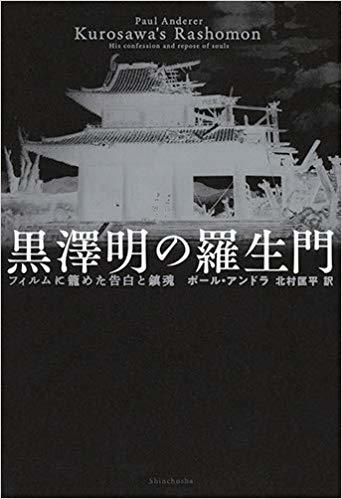
本書は近代日本文学を専門とするポール・アンドラのKurosawa's Rashomon: A Vanished City, a Lost Brother, and the Voice Inside His Iconic Films (Pegasus Books, 2016)の邦訳である。筆者はこれまで日本文学を中心に研究を進め、小林秀雄論:Literature of the Lost Home: Kobayashi Hideo―Literary Criticism, 1924-1939 (Stanford University Press, 1995)や有島武郎論:Other Worlds: Arishima Takeo and the Bounds of Modern Japanese Fiction (Columbia University Press, 1984)など文学研究の成果を出版しているが(後者は『異質の世界──有島武郎論』植松みどり・荒このみ訳、冬樹社、1982年として翻訳されている)、今回刊行した評論は映画論である。
本書は、これまでとは違ったアプローチで黒澤明の『羅生門』を分析する卓抜な作品論であると同時に、一つの作品分析にとどまらない射程をもった黒澤明論でもある。本書の議論においてもっとも重要な資料は「自伝」である。筆者は黒澤の書き残した『蝦蟇の油―自伝のようなもの』を丹念に読み込みながら、『羅生門』のスクリーンに浮上する細部のイメージと黒澤の幼少期の体験を結びつけてゆく。黒澤が実際に経験した関東大震災と東京大空襲、そして活動弁士としてスターであり黒澤に圧倒的な影響を及ぼし自殺した実の兄・黒澤丙午(須田貞明という名で活躍した)の存在──。黒澤映画のショットや編集による映像表現に、激動の時代を生きた黒澤の個人史──トラウマ/カタストロフィーの記憶──を重ね合わせながら、歴史的名画がこれまでにない方法で論じられる。ここでは各章を具体的に紹介するのではなく、本書のエッセンスとなる部分に言及していこう。
周知のように『羅生門』は、森の中で侍の死体が発見され、その事件について複数の目撃者が証言するものの、各人がそれぞれのエゴイズムによって事件を解釈するため、何が本当に起こったことなのかがわからないという物語だ(芥川龍之介の「藪の中」を原作とするが、内容はかなり改変されている)。本書はこうした映画の構成そのものを巧みに取り入れている。すなわち、映画の侍の死と同じく黒澤丙午の死が本書の中心に据えられ、映画同様その死をめぐって複数の証言者が登場する。その一人は自伝の著者である黒澤明である。他にも彼の幼少期からの友人であり、丙午の死や若い頃の黒澤を知る植草圭之助(自伝的小説『けれど夜明けに──わが青春の黒沢明』で黒澤のことを描いた)、丙午を指導した有名な活動弁士である山野一郎、当時の新聞記事などが、当時の事件をそれぞれの視点から物語る。もちろんそこには食い違いがある。
黒澤の兄は愛人と「心中」したが、黒澤が自伝で事件現場を再現した記述では「自殺」という言葉が選択され、兄が一緒に死んだ銀座のカフェーの女給にはまったく触れていない。それはなぜか。筆者は自伝で語られたことのみならず、「語られなかったこと」にも耳を傾けてゆく。そのような沈黙する声を聴き、映画を大胆に読み解いていくのだ。たとえば森雅之が演じた侍が自殺をする場面──。死んだ侍の声を代弁する巫女が、森で起こったことを回想するシーンで、映画は明らかにこれまでとは違った調子を帯びる。オフスクリーンからの声(巫女による外部からの声)が与えられ、森の空地で絶望の淵に立った侍がロングショットで映し出される。映画はここで転調し、悲哀に満ちた時間がゆっくりと流れる。筆者はここにスクリーンの側で映画を説明する活動弁士の姿、そして自死した兄の姿を見る。このようにして映画と自伝や過去の記録を何度も往復し、黒澤自身の過去をフィルムに浮かび上がる断片に跡づけていく。
通常、映画はフィクション(虚構)で、自伝はファクト(事実)に基づくノンフィクション──真実を語るもの──だとみなされる。とりわけ平安時代が舞台の寓意に満ちた時代劇は、作家の人生とはもっとも隔たりがあるように思えるが、筆者は「フィクション/ファクト」という関係を反転させ、ノンフィクション(自伝)を虚構として、フィクションとしての映画を、人生/真実が投影される記録映画(ドキュメンタリー)として読み解いていく。「事実」が語られた自伝にはフィクションや虚偽が入り混じり、フィクションのはずの『羅生門』にはリアルな個人史や肉声が紛れ込む。それによって『羅生門』はむしろ、自伝よりもリアリティのある告白的フィルムとして逆説的に立ち上がってくるのだ。自伝に残された「嘘」──ノンフィクションという形式を使って黒澤が「物語る」ことを手がかりに『羅生門』は「告白的映画」として捉え返される。亡き者たちへと捧げられたレクイエム(鎮魂歌)を読み取るダイナミックな手さばきに、ミステリーを読んでいるかのごとく「謎」が解き明かされるその手つきに、私たちは驚嘆するほかない。本書を読むと、黒澤丙午なくして「世界のクロサワ」は誕生しなかったと断言できるだろう。
ニュークリティシズムの流れからくる「意図の誤謬」(The Intentional Fallacy)──作品そのものの意味と作者の意図を混同する誤謬の指摘──を前提として作品分析や批評を学び、ロラン・バルトの「作者の死」──作者の意図を重視する作品論からテクスト論への移行──の強い影響力のもとで私たちは批評という営為を規範化してきた。付言すれば、日本の映画批評には、それと並行して蓮實重彦の表層批評があった(蓮實的パラダイムには、外在的なコンテクストから離れて細部に執着するだけのフォロワーが大量に増えた)。こうした映像テクストそのものへの回帰は、作家を切り離して作品を読者や観客に解放する一方で、作者が生きた痕跡や経験は等閑に付される。だが、トム・ガニングのフリッツ・ラング論(Tom Gunning, The Film of Fritz Lang: Allegories of Vision and Modernity, British Film Institute, 2000)とアーサー・ダントのアンディー・ウォーホール論(Arthur C. Danto, Andy Warhol, Yale University Press, 2009)に感銘を受けた筆者は、作者を「殺す」ことはない。むしろ歴史の深淵を覗き込み、黒澤が生きた過去に分け入り、作者を蘇生させる。とはいえそれは、多様な読みに開かれたテクストを封じ込めることを意味しない。スリリングな読解によってテクストの豊かさを担保しつつも、作者が確かに生きた歴史をスクリーンに結びつけるのだ。
(北村匡平)