フィラデルフィアの精神 グローバル市場に立ち向かう社会正義
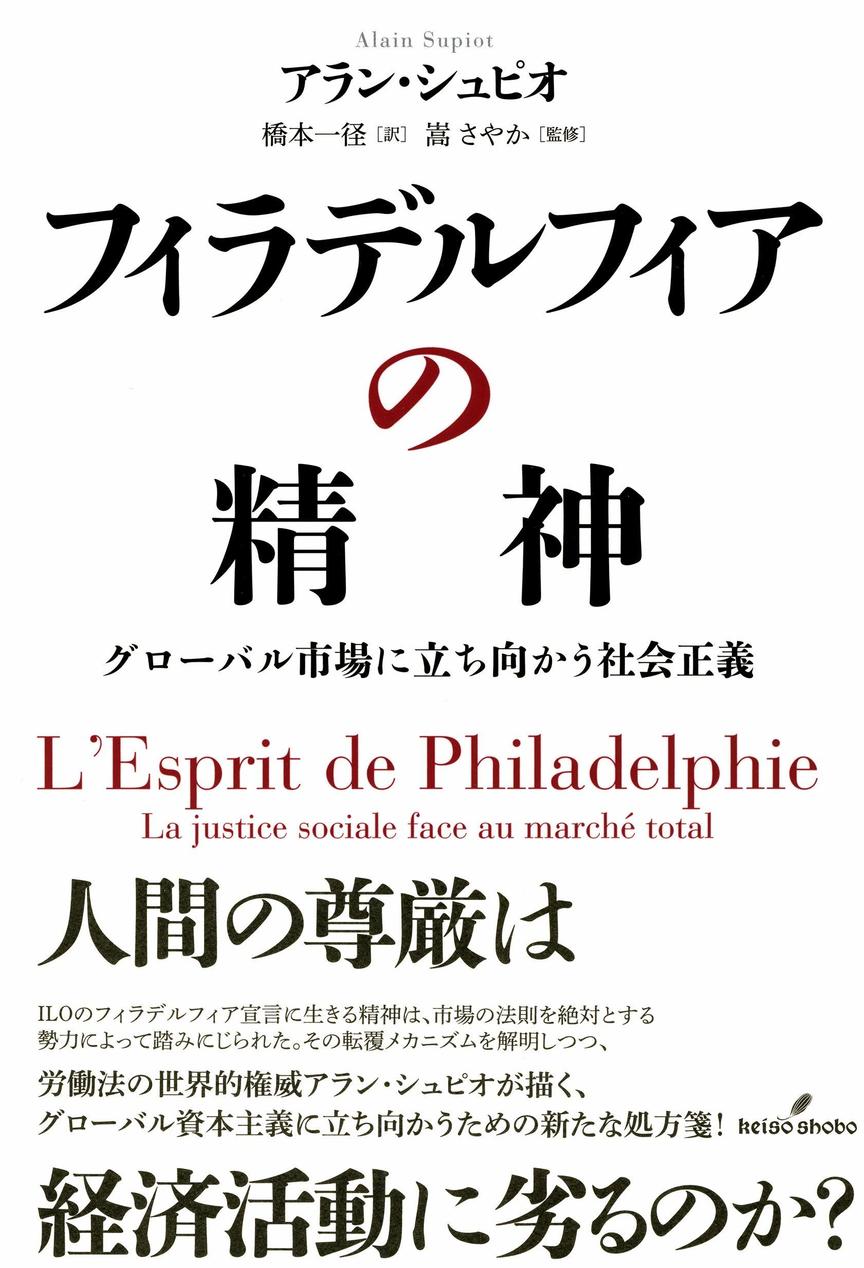
民法や刑法などとは異なり、労働法は19世紀末に成立した新しい法分野である。それは労働法がもっぱら労働者の身体の保護を目的とした法律だからであり、そして「身体」は19世紀末に至るまで西洋の法律の中には不在であったからである。「仮面」を意味する「ペルソナ」という語を語源とする法的な「人格」は、身体を持たない擬制(フィクション)的存在であり、だからこそ個人としての私的な人格と、会社組織のような「法人格」とが、法律の上では、時として平等に扱われもする。フランス人権宣言で「生まれながら」の平等が謳われた個人も、そのような擬制であることに変わりはない。
法的には存在しないものとみなすことのできていた「身体」は、19世紀の労働現場にやおら頭をもたげて、法律もそれを無視することができなくなる。たとえば蒸気機関の登場により女性や子供も工場で重労働に従事させることができるようになる。あるいは電気照明により夜間でも休みなしで労働者を搾取することが可能になる。露呈したのは雇用者と労働者との間の圧倒的な不平等であり、「生まれながら」には担保されない両者の不平等を解消するために国家が間に割って入り、「労働法」によって労働者の身体を保護したのである。
こうした労働法の精神の延長上に位置するのが福祉国家である。一方でそのような国家を障壁と考えるのがグローバル資本主義である。20世紀の歴史は、この2つの相対する流れの拮抗する歴史だったと言える。
ILO(国際労働機関)による1944年の「フィラデルフィア宣言」は、二度の大戦を経て、福祉国家に結びつくような労働法の精神を、国際社会に再び喚起した宣言である。「労働は商品ではない」という文言に代表されるこの宣言が、今日でも色あせていないのは、逆に言えばこの宣言の理念が、今日に至っても少しも達成されていないばかりか、むしろ後退しているようにすら思えるからである。本書で分析されるのは、現代の人類の到達点とも言うべき1944年の理念が、グローバル資本主義によって骨抜きにされる過程である。
本書の議論は、冒頭に記したような身体論の文脈からすると、表象文化論にとっても示唆に富むものである。たとえば19世紀の身体的な知覚の問題を扱ってきたジョナサン・クレーリーが、近年になって『24/7 眠らない社会』のような、不眠不休で労働を強いられる現代人の身体の問題になぜ取り組むようになったのかも、シュピオの議論を通じて、より理解が深まることだろう。
(橋本一径)