アメリカ紀行
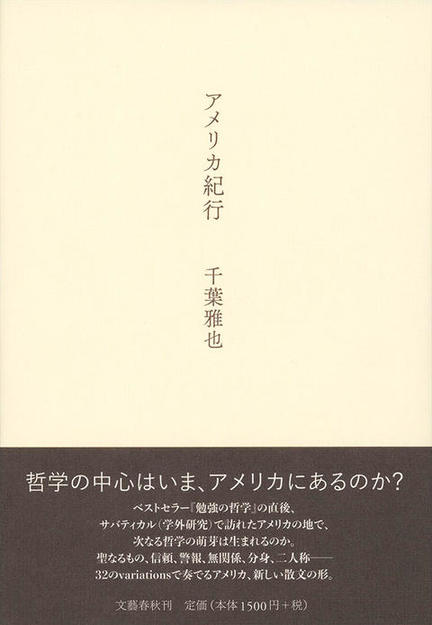
生活習慣がまったくちがう場所で不可避的に被るさまざまな刺激によってそのつど明滅する思考を、さっと保存する──その素早さを素早さのまま言葉に定着すること、それが『アメリカ紀行』の試みではないだろうか。2017年11月から2018年1月末までなされた約4ヶ月間のアメリカ滞在の記録であるが、いわゆるアメリカ研究とは異なる(それは背景に退いている)。著者自身が語っていることだが、本書は彼の最初の小説となる『デッドライン』の準備作業と重なる時期に書かれたとのことで、つまり、『アメリカ紀行』もまた、「書くこと」そのものをめぐる実験の書である。そしてそれはアメリカでなされる必然があった。
さっと閃く思いつきが、「かもしれない」とともに、書きつけられてゆく。あるいは、こう考えみたら面白い、という無責任な仮説も、それとして、提示される。ユーモラスな「あえて」の断定が連打される。かろうじて想像できることも、そのかぎりで、書かれる。その理由が何か、想像もつかないできごとが起こる。身も蓋もない現実に痛打されることもまた頻繁に。哲学のエキスパートとして自信に満ちた推論を展開する箇所もある。さて、驚くべきなのは、「書くこと」におけるこれらさまざまなスペクトルが一挙に取り出され、しかるべきしかたで配列されていることだ。
それは何のために? 書くため、ただ単に書くことの快楽のため、ではないか。はかなく、やわらかい何かが、かたく、持続的な部分で(外堀のようなしかたで)、しかし一連の同じ文の中で囲われる(しなやかなジョーダンさんの側につきつつ、生真面目なヴィンセントさんの話への応答も試みること)。私は、本書から、軽やかで奥深いナルシシズムの味わいを受け取る。このナルシシズムは、著者が述べるように、分身の哲学と対になっている。それは礼と友愛の哲学でもある。千葉のこの哲学が、日本に独特の、つまり、グローバルなI/You関係の「一歩手前」に、日本的な仕方で留まることによって可能になっていたことが帰国時によりくっきりとあきらかになった瞬間「アメリカ紀行」は閉じられる。何という見事な構成だろう。
(三浦哲哉)