デリダと死刑を考える
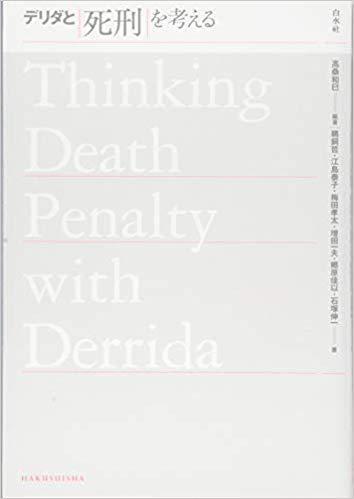
本書は、デリダの1999-2000年度死刑論講義(社会科学高等研究院)の翻訳(『死刑Ⅰ』高桑和巳訳、白水社、2017年)刊行を機に、2017年10月に行われた同題のシンポジウムを元に編まれた論集である。その企画・進行を務めた高桑和巳の序文に続き、登壇者であった鵜飼哲、江島泰子、梅田孝太、増田一夫、郷原佳以、石塚伸一の論考が収められている。デリダの死刑論講義は1999年度から2年間にわたって行われたが、本書では基本的に『死刑Ⅰ』をテクストとして、各々の専門に即した論点からアプローチが図られている。
とはいえ、本書はいわゆるデリダ論集ではない。今日、世界的な死刑廃止の趨勢に抗するかのように死刑を存置し続けている日本において、世紀転換期にフランス(その20年前に死刑を廃止している)で行われた死刑論を読むということは、彼我の途方もない差異を認識し、自らの問題に向き合うことなくしてはけっして済まされないからである。だからこそ、本書は「デリダの死刑論を考える」ではなく「デリダと死刑を考える」と題されている。本書の元になったシンポジウムが企画されたのも、今日、日本において、被害者遺族の感情という切り札の前にほとんどタブーのようになっている死刑をめぐる冷静で原理的な議論を活性化させたいという思いのゆえである。本書の刊行が、従来の死刑存廃論になかった新しい視座によって、日本における死刑制度の再考を促すことに少しでも繋がるのであれば、執筆者の一人として、それ以上の願いはない。以下、各論考について簡単に紹介しておこう。
第一章は鵜飼哲「ギロチンの黄昏──デリダ死刑論におけるジュネとカミュ」。『死刑Ⅰ』は奇妙な構成をしており、デリダはセミネールの真の始まりを第1回講義ではなく第2回で触れられるジュネの『花のノートルダム』の或る一文に託している。他方、カミュは最後の諸章で論じられる。つまり、『死刑Ⅰ』はジュネから始まりカミュで終わる。そう指摘する著者は、まずジュネとデリダを往還する。『花のノートルダム』では、ジュネが心酔していたヴァイトマンという現実の死刑囚が称揚されるのだが、デリダは第2回講義でジュネとヴァイトマンの幻を呼び寄せる。著者によれば、それは死刑宣告によって強いられる時間の変質に私たちが接近するためである。著者はまた、カミュのギロチン論をめぐるデリダの考察に、死刑の問いを植民地の問いへと結び合わせる視点を読み取る。デリダのカミュ論から日本における近代天皇制と死刑制度の関係が指摘される件も、著者ならではの鋭い洞察である。
第二章は江島泰子「ヴィクトール・ユゴーの死刑廃止論、そしてバダンテール──デリダと考える」。著者はデリダによる批判的分析を参照しつつ、『死刑囚最後の日』などで死刑の無条件廃止を訴えた作家の廃止論と、その思想を強く支持して死刑廃止を実現させたロベール・バダンテールの廃止論を検討する。死刑の残酷さはどこにあるのか、死刑の残酷さと人間性、死刑の歴史とキリスト教、ユゴーの廃止論におけるキリスト教的なもの、一つの革命としてのユゴーの廃止論、といった論点が扱われる。ユゴーの小編『クロード・グー』などをめぐって示されるのは、ユゴーの専門家ならではの考察である。
第三章は梅田孝太「デリダの死刑論とニーチェ──有限性についての考察」。『死刑Ⅰ』は第6回でニーチェの『道徳の系譜学』を集中的に論じている。本論文は、デリダがなぜ同書を参照する必要があったのかを、『道徳の系譜学』自体、『死刑Ⅰ』における『道徳の系譜学』読解、デリダが「ニーチェ的身振り」によって死刑存置論に潜む「利害」を暴き出す過程、デリダの死刑論におけるニーチェ的な系譜学の観点、デリダが「ニーチェ的身振り」から離れる地点、といった論点を順に検討することによって解明している。カントを対決相手とするデリダの死刑論にとってニーチェの議論はきわめて重要であり、本論文はその理解を大いに高めてくれる。また、死刑論に限らずデリダとニーチェの関係に関心のある者にとっても本論文は必読である。
第四章は増田一夫「定言命法の裏帳簿──カントの死刑論を読むデリダ」。デリダは、死刑廃止論者よりも死刑存置論者によって共有されている見解、すなわち、死刑は法権利の体系の全体を凝縮した刑罰だという見解を採っている。本論文はまず、デリダが過去に死刑に論及した『法の力』を参照しつつ、このことがデリダに「法の彼方の正義」という視点を要請したことを指摘する。そして、この視点を、神の法を論拠とするユゴーの死刑廃止論の視点と比較する。人命の不可侵性を前面に押し出したユゴーの対蹠点で死刑の必要性を説いたのがカントの「定言命法としての死刑」論である。著者は、『死刑Ⅱ』をも視野に入れ、カントの強固な定言命法に対するデリダの読解を提示している。
第五章は郷原佳以「ダイモーンを黙らせないために──デリダにおける「アリバイなき」死刑論の探求」。デリダの死刑論は、哲学史において死刑廃止論がいっさい存在しないという問題意識から出発し、哲学的に厳密なカントの死刑存置論に多角的に接近を図る。同時期の動物論や主権論を参照するなら、デリダは、原理的論拠による死刑存置論と哲学の可能性の条件の間に何らかの結びつきがあることを示唆していると考えられる。本論文は、デリダの死刑論は全体として哲学および制度としての文学への批判的問いかけを行っているという観点から、アクチュアルな情勢も踏まえてデリダの死刑論を位置づけ、デリダが最終的に目指しているのは、存置論と廃止論の対立を超えた、「アリバイ」──社会への有用性、キリスト教信仰、人間主義、など──なき死刑論であることを示している。
第六章は石塚伸一「デリダと死刑廃止運動──教祖の死刑の残虐性と異常性」。西日本が豪雨に襲われた2018年7月6日、オウム真理教の麻原彰晃と6人の弟子の死刑が一斉に執行された。デリダなら何を語っただろう、という問いかけから、死刑問題に多くの論考のある刑事法学者の考察は始まる。著者は、デリダに即して、ソクラテス、イエス、ハッラージュ、ジャンヌ・ダルクが死刑を科されたのは宗教的権力に逆らったゆえであることを確認したうえで、今回の一斉執行は、国家に逆らった者の思想信条を処罰するものだと指摘する。さらに、米国および日本における死刑の歴史を踏まえ、それが周到に計画されたものであることを示し、死刑の正統性を問う。
(郷原佳以)