ライフ・オブ・ラインズ 線の生態人類学
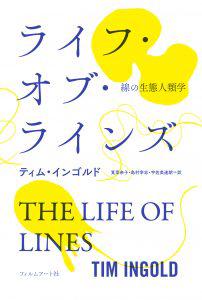
本書は『ラインズ 線の文化史』(工藤晋訳、左右社、2014年)の続刊として構想されたが、著者の軽妙な筆致のおかげもあって、特別な準備なしに読み進めていくことができるものとなっている。「序文」の回想によれば、その構想は自身が創始したライン学(リネアロジー)を天候のテーマと結びつけることにあったが、これは第二部で果たされている(そこでインゴルドは現象学、特にメルロ=ポンティとの興味深い共鳴を見せている)。では、本書の始まりと終わりにあたる第一部と第三部では何が扱われているのだろうか? まず第一部では、ラインとブロブ(そのイラストは邦訳カバーにも用いられている)の考察を通して独自の生命観が提示される。これは本書全体を貫くものであって、「調和=応答」(コレスポンデンス)という重要概念と切り離すことができない点で、インゴルドの思想的な「根っこ」の一つであると言える。その要点は、一種の社会性(ラインを伸ばし、別のラインに応答し、調和すること)が生命そのものに織り込まれているところにある。この社会性は、当然ながら、人間以外の存在にも見出される。第三部では、こうした生命観のもとで人間が、そして人類学の営みそのものが考察される。人類学というディシプリンもまた、生命に本質的な社会性から捉え返されるのである。
さて、せっかくなので少し穿った見方も提示しておこう。ラインとブロブによって示される生命論が本書の最良の部分の一つであるとすれば、第三部の人間論は(オルテガの参照に顕著なように)他の生物に対する人間の特別さを強調する点で一種の退行に見える。おそらくこれはこの人類学者が西洋白人男性であるのと無関係ではない(ドゥルーズ=ガタリを独創的に捉えなおすヴィヴェイロス・デ・カストロとの対照をここに見ることができる)。ラモン・リュイによる人間の定義「人間化する動物」からインゴルドが引き出そうと試みているのは、「man」であることから出発せざるをえない自身の営みを、その出発点を完全に否定し排除することなく立ち上げなおし続ける手立てではないだろうか(非規律的教育のテーマがそこから導かれるだろう)。人間論への偏重はその副産物であるように思われる。議論に見られる哲学的な隙(特にハーマンへの言及はこの哲学者の理論を追っている人を落胆させるに十分だろう)は、しかし本書の良さを決定的に損ねるものではないだろう。今度は読者自身が新たにラインを紡ぎ出すことで、アイデアに満ちたこの書物に応答してゆくべきである。
(宇佐美達朗)