グレアム・グリーン ある映画的人生
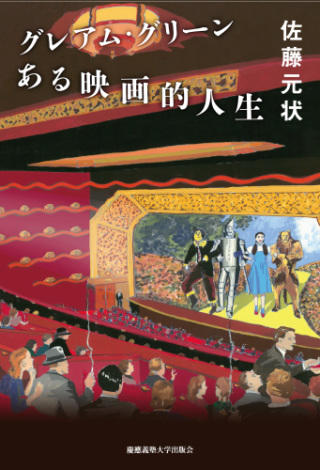
小説家と映画の関係について論じた本といえば、小説の映画化、すなわちアダプテーションをテーマにしたものがまず思い浮かぶかもしれない。その小説家が、フリッツ・ラング監督の『恐怖省』(1944)やキャロル・リード監督の『第三の男』(1949)といった多くの映画作品の原作を提供してきたグレアム・グリーンであればなおのことである。しかし本書は、グリーンの小説がいかにして映画化されたかを追っていくものではない(少なくとも、そこに本書の中心となる問いはない)。四年半に渡って映画批評家として活動していたこともあるグリーンは、映画と切っても切れない人生を送ってきた。この「グリーンの映画との情事」を重視する本書は、彼の小説が同時代の映画からいかに大きな影響を受けていたかを明らかにしていくことによって、「グリーンの小説と同時代の映画との生産的な共犯関係」(16頁)を浮上させていくのである。
本書の魅力の一つは、メディアを越えたその大胆な「共犯関係」を炙り出していく著者の手際にある。グリーンの映画批評を紹介する著者は、フランク・キャプラの『オペラハット』(1936)とラングの『激怒』(1936)を比較するというグリーンの「離れ業」(18頁)を賞賛するが、作品と作品の間に思いもかけない関係を見出すという批評的な姿勢を本書はグリーンと共有しているといえるだろう。たとえば第二章では、グリーンの小説『ここは戦場だ』(1934)における「特別機動隊」が出動する場面が取り上げられ、このロンドン警視庁の特殊部隊がアルフレッド・ヒッチコックの『恐喝』(1929)に登場していたことが指摘される。こうして、ヒッチコックの映画でロンドンを猛スピードで駆け抜ける「特別機動隊」がグリーンの「視覚的無意識」(106頁)を通して『ここは戦場だ』に侵入した可能性について論じられるが、この小説における映画からの影響はそれにとどまらない。続けて著者は、『ここは戦場だ』で描かれる工場労働者のウィンクという身振りにルネ・クレールの『自由を我等に』(1931)の痕跡を見出し、そこからグリーンがこのフランス映画で展開されていた「資本主義批判」を継承していたことを明らかにしていく。こうして、グリーンの作品内にメディア(小説と映画)や国境(イギリスとフランス)を越えた「共犯関係」が次々と探り出されていくのである。
他の章においても、スクリューボール・コメディ、フランスの「詩的なリアリズム」映画、プロパガンダ映画、西部劇、等々が実に複雑なかたちでグリーンの小説へ作用していたことが論じられていく。これらについては実際に文章に触れて確認していただきたいが、最後に強調したいのは、グリーンが同時代の映画から学んだ表現や主題をいかにして自身の小説に取り入れたかが論じられることで、それらの小説に潜在していた「運動」の感覚があらためて呼び起こされるような印象がもたらされていることである。グリーンの文章をイメージとして立ち現れさせ、それらの小説があたかも「上映」されているかのように読んでみること。そのような実践を通して、本書もまたある意味でグリーンの「映画的人生」と刺激的な「共犯関係」を結んでいるように思われる。
(川﨑佳哉)