ラモー 芸術家にして哲学者 ルソー・ダランベールとの「ブフォン論争」まで
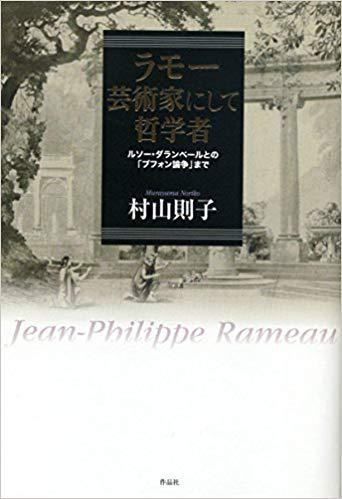
本書は、18世紀フランスを代表する音楽家であり、その和声論によって西洋音楽理論史上の最重要人物にも数えられるジャン=フィリップ・ラモーについて書かれた、恐らくこれ迄で最も大部な日本語の書物である。R.ロランやL.ラロワ等、フランス近代音楽学黎明期の言説から戦後のラモー再評価の旗手たるC. ジルレトーヌやPh.ボーサン、C.カンツレールらの労作、そして近年のS.ブイスーの大著からそれ以降の国内学術論文に至るまで、膨大な先行研究を隈なく網羅した本書は、今後ラモー研究を志す全ての人々にとって有用な参照点となり得るものであろう。
しかしながらまた本書は、一般的な音楽家の個人研究とは若干毛色を異にするものでもある。ここではラモー作品に対する独自の音楽分析や、あるいは彼の和声論に対する新しい読解などが示されるわけでは無い。本著が光を当てようとするのは、芸術家であると同時に「哲学者」であったというラモーの思想的側面であり、いわば彼の具体的なオペラ作品や音楽理論書が生まれ来たその源泉とも言うべきものである。そして、まとまった美学書や哲学書を著したわけでは無いラモーの「哲学」を浮き彫りにする為に著者がとった戦略とは、彼の作品、著作、発言が時代との間に産んだ様々な「軋轢」に着目するというものであった。則ち、最初のオペラ作品《イッポリートとアリシー》が招いたリュリ派の非難、ヴォルテールとの共作《サムソン》の頓挫、「音響体」理論を巡ってのダランベールとの決裂、そしてブフォン論争とルソーとの対決、等々。著者は豊富なドキュメントによってこれらの経緯を詳細に描き出し、それを同時代フランスの哲学・美学思潮、或いは音楽観や舞台芸術観の変遷とつき合わせる。恐らくは、この「軋轢」を巡る「歴史記述」の精緻さ、その情報量こそが本書の一番の見どころであろう。
一方で、ラモーの美学/哲学そのものを巡る議論には聊か掘り下げ不足の感が否めなかったのは少し残念な所でもある。先行研究による様々な見解が提示されるものの、それらを批判的に捉えた上で著者自身の議論を展開し、新しい見解を打ち出すという側面は余り見られなかったように思える。むしろ「自然の模倣」、「真実らしさ」、「快」などの重要な美学概念の理解が、余りにも一部の先行ラモー研究の解釈に引きずられているのでは、といった危惧を感じさせるなど、主に先行研究との距離の取り方に起因する論の粗さがこの部分では目に付いた。しかしながら、これらは今後の著者の、もしくはラモー研究全体にとっての課題となるものであろう。いずれにせよ、本書がここに「芸術家にして哲学者」としてのラモーの理解へ向けて一つの道標を示したことは、日本のラモー研究、ひいてはフランス音楽史研究に於ける大きな貢献であったことは間違いない。
(山上揚平)