水族館の文化史 ひと・動物・モノがおりなす魔術的世界
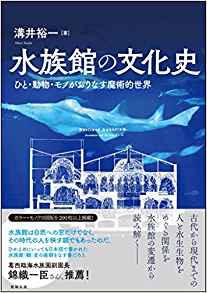
筆者はこれまで西洋における魔女や呪術などの民間伝承や思想に対する研究を積み重ねており、2014年には『動物園の文化史』を上梓している。本著はまさにその続編としての「水族」への探求であり、筆者の膨大なリサーチに基づき、国内外の多様な水族館の情報と豊富なカラー図版によって構成された大著である。
本書は5章で成っている。第1章は、古代から近世までの人と水族との関わりを辿っている。人が海に住む生き物たちを貴重な資源として支配、管理しつつも、同時に死生観にまつわる思想的対象でもあったことを記している。第2章は、西洋近代における「アクアリウム」の誕生を起点とし、透明なガラスの中に一つの生態系を形成していく水族館の変遷、未開の地や深海など人の探求の歴史が述べられる。第3章はアメリカと日本を舞台として、水族館という仕組みがいかに受容され発展していったのかが記されているが、同時に第二次世界大戦という人災が水族館に及ぼした悲劇も記されている。第4章では、戦後の水族館の「テーマ化」や非日常体験の創出という展示空間の変容が記される。最後の第5章では、1970年代以降の環境破壊、クジラやイルカの捕獲に対する問題意識から、生き物の福祉・権利という人の意識変化、またヴァーチャル・リアリティやロボットなどテクノロジーの発達による水族館の「ハイブリット化」を取り上げ、生き物や水族館の定義そのものについて問題提起している。これら5つの章立てに加えて、人と水族との関係にまつわる9つのコラムが挿入されていることも本著の魅力となっている。
このような構成を通して、読者は水族館の歴史を存分に学ぶことができるだろう。だが筆者の意図はそこに留まるのではなく、水族館という表象を通して、西洋文化の基底にある規範、制度、そして宗教的な倫理観に対する批判的検証を試みている。例えば筆者によれば、19世紀半ばの「アクアリウム」、すなわち光射すガラスケースの誕生には、まさに人を頂点とし他の生き物や未開拓の世界を支配しようとするヨーロッパ人の思想があるとされる。近代以降の水族館のディスプレイの変遷では、没入型展示やパノラマ化、「本物らしい」展示というもう一つの世界を創り上げていく。支配と監視、収集(コレクション)と展示そして視覚優位という近代の制度性とその伝播については、ミシェル・フーコーによる『監獄の誕生』はもとより、博覧会の歴史においてもこれまで議論されてきた。本書を通して筆者は、水族館という一見すると魅惑的な対象を題材としながらも、「ひと・動物・モノ」との関わりに潜在する西洋文明の基層を読み解き、これまでの思想史、文化史研究を更新する新たな視座と知見を提供している。同時に、筆者が述べているように、動物の福祉・権利という倫理観の転換が生じた1970年代以後の水族館存立の意義について、文化史という視座から一つの示唆を投げかけている。この点も忘れてはならない要点である。
(山下晃平)