座談会 アーカイヴと表象文化論の現在 阿部崇×佐藤守弘×田口かおり×土屋紳一
1. はじめに
──本日はお集まりいただきありがとうございます。REPREの今回の小特集はアーカイヴを扱うことになりました。会員向けMLに寄せられる情報を見てもアーカイヴをめぐるシンポジウムが増えてきていますが、アーカイヴに関する理論的考察はどの程度まで進んでいるのでしょうか。また作品や資料の保管やデジタル化を巡る制度の面では、人手や予算の不足など、ほんとうに即物的な意味での「アーカイヴの病」とでも呼べる現状があったりします。そうしたことを含めて、表象文化論学会にはさまざまな分野の研究者の方々、あるいはアーティストの方々がいらっしゃいますので、横断的な話をしていただけないかと思ってお声がけし、学会員以外にも土屋紳一さんに来ていただきました。
まずは一人ずつ自己紹介をしていただき、司会の佐藤さんにバトンタッチをお願いいたします。
阿部:青山学院大学の阿部崇です。フランス文学と現代思想が専門です。特にフーコーを研究しているので、たぶん、アルケオロジーつながりということで呼んでいただいたのだと思います。実践的というよりは、理論的・思想的なお話をさせていただくことになると思うのですが、実践的なことについても色々とお話が聞ければ嬉しく思います。よろしくお願いします。
佐藤:京都精華大学の佐藤と申します。専門は、とりわけ写真を中心とした視覚文化論ですが、まあ何でもやっていまして、今度の日本記号学会ではグルメ漫画についてのセッションの司会なんかもやります。アーカイヴに関しては、日頃から利用していて、たとえば土木写真を調べたときも土木学会附属土木図書館などのアーカイヴにはすごく良い資料があるので使っているんですが、僕自身はアーカイヴを作っているわけではありません。今回は、直接的には『AMeeT』という京都のウェブマガジンでアーカイヴについての連載〔「巨大な書庫で迷子になって」〕をしていたことから声をかけられたという経緯です。アーカイヴについては、素人なんですが、いろいろと書いているうちに疑問になった部分もあったのでそのあたりを皆さんにお伺いしたいと思っています。
田口:東海大学の田口かおりと申します。わたしはもともとイタリアで修復士の仕事をしておりまして、工房ではルネサンス〜バロックあたりの時代に制作された絵画の修復を主に担当していました。つまり日々実践的なことをしていたのですけれど、帰国した後は研究方面に舵を切り、近代修復理論の成立と変遷の過程を追ってきました。4年程前から再び現場にも戻り、展覧会のコンサベーションや、国内に収蔵されている近現代美術の修復を請け負うようになりました。モノに関われば関わるほど、理論的な側面からの考察というのが必要になってくるなと考えていて、とりわけ修復作業をしていく中でのアーカイヴの作り方と、コレクションとアーカイヴの付き合い方といったところに最近いろいろと思うことがあります。今日は先生方に多方面からの視点をご提供いただきつつ、現場の話と理論的な話を繋ぐようなお話が出来れば、と思っています。
土屋:私は早稲田大学演劇博物館の「デジタルアーカイブ室」というところに在籍しています。デジタルアーカイブ室というのは世界的に珍しいと思うのですが、さらに演劇と映像に特化した博物館です。日本には演劇・パフォーミングアーツの国立博物館がないので、早稲田大学演劇博物館にいろいろな寄贈がくる。とてつもない量がきて、さらにいろんな種類がくる。演劇に関していえば、台本だったり衣装だったりいろんな小道具だったり、さまざまな分野のものが入ってくる。そういった中で、まずはアーカイヴしていく、目録の方針検討やデジタル化、データベースの公開方法など、研究拠点という側面も意識しながら、現場で常に戦っているという感じ。理論というより、日々、目の前にある資料に対して現実的なところでやっている、それがわたしの仕事です。
じゃあデジタルアーカイブ室でずっとやってきたのかっていうとそうではなくて、もともとはメディア・アートをやっていました。そこでは写真を重要なメディアとして扱っていたのですが、写真がアナログからデジタルへと移行が始まってきた。その時代の流れの中で、デジタルメディアと写真の両方をテーマにやっている人がドイツにいると知って、トーマス・ルフの元でマイスターシューラーになった。デジタルつまりコンピューターの知識と、写真の知識と、作品に関する社会的な意義などを考えるという素地があったことで、自然とデジタルアーカイヴというものに興味を持っていった。そして実際に関わるようになって、いまに至るという感じ。なのでアーティストとしても活動しているのですが、両方を刺激し合い思考できるので、バランスよくやっていきたいというのがいまの願いです。
佐藤:私は、地域映像アーカイヴに関わっている人たちに関わっている、という感じなんですね。その共同研究の論集には、ちょっと変化球ですが、アーカイヴの外側というか、子供達が書いた郷土誌というのがありまして、それはアーカイヴすることの実践の一種ではないか、一つの例ではないかということを書きました*1。その一方で、政官学を巻き込んだようなアーカイヴ・サミットに行きますと、普段いる表象文化論とか記号論とかとは全然違う雰囲気なんで。実際、国策としてのアーカイヴ事業というのがあって、活用する、資源化する、みたいなところにつながっていく。そのあたりの危険性も感じつつ、僕自身もデジタルアーカイヴをよく使う。
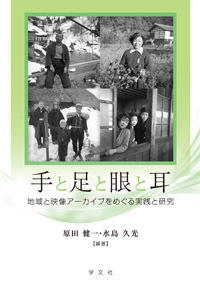 *1 佐藤守弘「郷土を調べる子どもたち──『北白川こども風土記』におけるアーカイブする実践」(原田健一、水島久光編『手と足と目と耳──地域と映像アーカイブをめぐる実践と研究』学文社、2018年)
*1 佐藤守弘「郷土を調べる子どもたち──『北白川こども風土記』におけるアーカイブする実践」(原田健一、水島久光編『手と足と目と耳──地域と映像アーカイブをめぐる実践と研究』学文社、2018年)
多くの方がご存知の通り、本来はアーカイヴズ、と複数形でしかほとんど使わない。これはフランス語でもそうですよね。公文書館という意味になります。日本だと、結構古いのが京都府の総合資料館(現、京都府立京都学・歴彩館/Kyoto Institute, Library and Archives)がKyoto Prefectural Library and Archivesとして60年代からやっていて、その後、各省庁に分かれていた文書が集められて、ナショナル・アーカイヴズとして国立公文書館ができている。もちろん、そういうところにあるのは主にペラの紙ですよね。僕がよくわかりやすいメタファーとして用いるのが、美術館は壁で、図書館は本棚、それでアーカイヴズというものは引き出しあるいは蔵の長持。つまりアーカイヴは見えないところにある。これが本来の形だったと思います。
IT用語で単に見えなくする、zipでアーカイヴするとかメールをアーカイヴするとか、捨てないけれどどこかにとっておくということがもしかしたら本来のアーカイヴズの形なのかもしれない。ただ、壁と本棚と引き出しみたいな比喩が通じなくなってきている、そのあいだの境界線が溶けているというのが今だと思うんですね。フーコー以来の単数系のアーカイヴ/アルシーヴでは、アーカイヴとして見る、という比喩としてのアーカイヴが出てきている。そして何よりもデジタル化ですね。デジタル化によってそれまでのメディウムそれぞれの差異、あるいはメディアの形の差異が、デジタルデータということで一緒に取り扱われるようになってくる。
たとえば美術館だと、本来の中心となるのはコレクション。MoMAのサイトを見るとコレクションのページがあって、花形のキュレーターたちがいて、モノがある。アーカイヴは別のところにあって、モノ以外、たとえば手紙とか関連資料あるいは展覧会の記録、さらに預金通帳もMoMAに直接行けば見られるらしいですが、こういうようなアーカイヴズがある。このように、これまでは完全に峻別されていたものが、デジタル化されるとそこには写真も当然入ってくる訳です。そうなると、これがコレクションでこれがアーカイヴズという壁が溶解しているのではないか。こういうところで美術館museumと公文書館archivesと図書館libraryとかを繋げなければいけないとか、さらに大学universityや産業industryも繋げていくという動きがある。それぞれ別々にはやっていけないというのがある。
一方では、アートの世界でいうと、はじめはデュシャンかもしれないけど、アーカイヴをアートにしてしまう。《グリーン・ボックス》みたいなね。理論と実践の両側からアーカイヴの問題点や可能性を俯瞰していって、議論ができたらと思います。
2. アーカイヴの現在──データベースの横断と増殖
佐藤:まずはアーキヴィストととしての土屋さんにお聞きしたいですね。先ほどおっしゃっていたようにすごく先鋭的な取り組みをなさっているわけですが、アーカイヴをつくっていく中での問題点というお話からお願いします。
土屋:よく言っている話があるんですが、その場で起きた演劇自体はアーカイヴできないということがまずある。では何をしているかというと、周辺資料を集めている。今年で90周年ですがそのあいだずっと台本や衣装などそういった周辺資料を集めてきた。無形文化の収集は、ドーナツ状に資料を集めていって、真ん中は空洞だということ。周辺を集めることによって、真ん中の無いものを想像する、ということしかできないと思っている。しかし、ほとんどの場合メディアの種類ごとに保存されてしまうわけで、たとえば写真だけでまとめて保存されたり、衣装は衣装ケースに保存されたり、台本であれば本棚に収蔵されたり、そういったかたちで分かれていくんですね。そうなると、実際に行われた演劇というグループではなく、周辺資料がメディアごとに保存されるということが起きてくる。
じゃあデータベースはどうするかというと、ドーナツに戻すことは厳しい。写真だけ、衣装だけでデータベースを作らざるを得ない。横断検索はできるんですけど、別のデータベースとの繋がりが、件数が増えるとどんどん見えなくなっていくというのが大きな問題だった。システム的にドーナツ状に近い構造を取り戻すことを念頭に置いた統合データベースシステムを設計し、早稲田大学文化資源データベース(2017年6月~)へのリニューアル時に実装できたというのは大きいですね。全部で50くらいのデータベースがあって、演劇博物館で25くらいだったと思うんですが、これからもどんどん増える予定です。それで、クリップ機能というのをつけて、自分が気になる資料を自由にクリップして、グループ化して保存ができるみたいなことをやった。あと、あらゆる検索キーワードもクリップできる。無形文化だからというわけではなくて有形であっても同じ問題はあって、科学系の資料も膨大になってくるとどういう風に分けるかということが重要になってくる。もともと演劇は真ん中がないという状態だったんですが、ほかの場合のデータベースも資料が増えれば増えるほど似たような問題が出てくるということがわかってきて、とても興味深い。
佐藤:[データベース一覧を参照しながら、]こういう感じで並んで出てくるわけなんですね。それはログインしてできるの?
土屋:これはあえてログインしなくてもできるようなシステムを作ったんです。
佐藤:一時的に?
土屋:いや、保存もできます。また、一般公開もできて、TwitterやFacebookにもボタンを押すだけでリンクを貼れるようになっている。ログインが必要になるとユーザー数が限られると考えたので、今回は敷居をできる限り下げた。クリップしてみんなが自由にまとめて公開できるんですけども、そうした場合、正しくない情報も当然保存される。そういうのもある程度飲み込んで、しっかり保存しようと考えています。
──データベースの中に「正しくないもの」が入ってしまう、というのはどういう意味でしょうか?
土屋:自由に書き込めるので色々な意見を受け入れることを最初から想定しています。例えば「これはこういうものです」とか根拠もなく書いちゃう人もいるかもしれない。それを他の人が、「いやこれはこの資料から判断するとこうです」と書いたりする。さらに「いいね」、「悪いね」ボタンみたいなのがあって、間違っていると思ったら「悪いね」を押すことで、第三者が、評価できるようになっている。メタデータは現物をしっかり確認した内容を博物館がコントロールして、それ以外の部分はなるべく、公開側、閲覧側という垣根のないオープンな関係にするという。
佐藤:それは、淘汰されやすい仕掛けにしようと。つまりアクセス数が増えれば増えるほど誤差が少なくなる。
土屋:よく言われるのは、最初の頃は変なものが書き込まれるんですけれど、時間が経てば経つほど、過去のものをみて書き換える人が増えてくると思うので、だんだん精度があがる。全部間違いみたいな書き込みから始まっても、最終的には精度が上がってくるかもしれない。
阿部:ウィキペディアみたいなものですね。
──いわゆる「情報の民主主義」に任せると情報が改善するのではないかという楽観的な見方もあるし、フェイクニュースの拡散や、集団で悪意ある「通報」を行うといったポピュリズム的測面もあるので気になりました。
土屋:早稲田大学のデータベースは、研究者がメインの利用者だということもあり、こういうことはやっても問題がないだろうと考え、敷居を下げるということを重視したんですけれど。利用者層が広がった時や、大きなシステムになった時にはもっと慎重にやらなきゃいけないところはあると思います。
佐藤:敷居の問題ってまた後で出てくるかもしれないですけれど、難しいと思うんですよね。というのは、僕が前に講演をしたのが……知的障害者施設での作品アーカイヴに関する学習会で〔詳細は以下を参照。『みずのき美術館の学習会〜福祉施設の作品をアーカイヴするには〜』、2017年1月29日開催。〕、そこはある程度公開範囲を定めないとプライバシーにすごい関わってくる。ただ土屋さんのお仕事の場合は、公共のものってことですよね。
アーカイヴを繋ぐことというのは非常に大問題で、重要なところだとは思うんですね。特に、地域映像のデータベースとかやっている人たちにとっては。それぞれが別のシステムを使って、デジタル化している。そういったものをどのようにして繋いでいくか。
土屋:そうですね。データベースを公開しても研究予算が5年とかで終わってしまうと、インターネット上から消えてしまうとか、海外でもデータベースを維持する予算は厳しいという話もある。早稲田大学に関しては運が良かったというか、今回のシステム更新で、永続的に維持する体制が出来たと思います。学術研究プロジェクトだけでなく、各地域でやっている歴史保存を目的としたプロジェクトも消えてしまうという危機感が常にあって、さまざまなところで議論されている。国会議員を巻き込んだナショナルアーカイヴ構想がありますが、個人的には政治主導であったとしても、残る可能性の高い組織ができれば良いのかなと考えている。デジタルアーカイヴというのはデータを残すっていうのが最大の目的としてある。立ちあげても、いつか消えてしまうという不安に対して、100年後でも存続し続ける環境が実現できれば、政府を巻き込むやり方もあるのかなと思う。
佐藤:よく日本は遅れていると言われます。特にそこで出てくるのがEUのEuropeanaですよね*2。あれは完全に横断検索できる。あれはEU自体がやっていますよね。
*2 本特集の寄稿3 石関亮「ファッションをアーカイヴすること」も参照。
でも一方で、本題とは関係ないかもしれないけど、浮世絵検索ってご存知ですか。あれは個人がやってしまったんですよね。ニューヨークかどこかに住んでいる個人が浮世絵検索を作って、そこに行ったら、世界中──ほぼ日本のデータベースだけど──を繋げていて、北斎と入れたら北斎がズラーッて出てくる。そういうとてつもないものがある。あれを個人でやっちゃったっていうので、そういうこともできるんだと驚いた。
──あれはつまり、立命館とか演劇博物館とかのデータを使っているんですよね。
佐藤:そうです。実は私も使うんですが、刷りの違いも一目で見える。というのは、さっきMoMAの例があったけど、MoMAがすべての展覧会をデータベース化して公開し、最新のものまで常に更新し続けています。化け物みたいなデータベースをデジタル化した。すごく面白いんですけれど、それのインターフェイスが使いにくいと言うんで、MoMAがGitHubで公開しているデータを利用して、イギリスのデザイン会社が新たな検索ページ(MoMA Exhibition Spelunker)を作ったのはとても面白い事例だと思います。そういう感じでもしかしたら、デジタル化するコレクションとインターフェイスとの分離みたいなのが起こってくるのかな。
土屋:浮世絵の話をすると、海外にも色んな浮世絵データベースがあるんですけど、演劇博物館のデータベースは所蔵資料以外は検索できないじゃないですか。他館と連携してシームレスに検索するとかは、現状ではむずかしい。一般論として話すと、世界中の同じカテゴリのデータをどこかに収集して、まとめて検索できると確実に便利になる。あったほうが利用者にとって必ず良い。そして、調べていた人は、発信元のデータベースへ辿っていくはずなので、それぞれの機関の利用者数もプラスになるのです。やはり思うのは、インターネットで検索して引っかからないと、存在しないことにしてしまう世代がこれから多くなるので、そういった状態を考えたときに、まずデータがあって、オリジナルはここにありますってことが、世界中の人から分かりやすくするのが、一番大切なんだってことです。権利問題も法整備によってクリアにして、それを進める必要がある。ただ、個人で運用をやっている場合も、維持は難しいって聞きましたね。データ公開側も再利用を積極的にサポートする時代になって来るかもしれません。
佐藤:本のデータベースの横断的な検索だと、個人的には最近はカーリルを使いますね。あれは良い。
土屋:本だと、ほぼフォーマットが決まっていてそこまで難しくないので維持管理が可能だと思います。それがいろいろな資料を含むアーカイヴの場合は、それを一つにまとめようとするとそれなりにコストがかかる。そういった意味では政治が主導しないといけない、みたいな問題に戻るのかなっていう気はしますね。
佐藤:大きい大学や機関が複数のデータベースの統合を進めていく動きもあります。立命館のアートリサーチセンターや。あそこはゲームもある*3。日文研がいろんな種類のデータベースを作っていたり、東大も最近デジタルアーカイヴを全部統合しましたよね。昔はあり得なかったような、アーカイブズ間の横断が進展している。一生懸命積み上げたデータベースのデータだけを流用して、検索インターフェイスだけでおいしいどころ取りをすることには問題もあるけれども、デジタルがはじめて可能にした利便性を認めないわけにもいきませんね。
*3 本特集寄稿1 向江駿佑「ゲームアーカイヴをめぐる理想と現実について 日欧米の所蔵館の調査と近年の動向から」も参照。
さっきMoMAの話を出しましたけれど、競争するかのようにメトロポリタン美術館がウェブサイトで超高精細画像を公開し、しかもものによってはダウンロード可ということをやっている。早いのは英国のナショナル・ギャラリーでしたか。昔から相当精細度の高い画像があって、ジョルジオーネとか、授業で使う場合もスライドで見せるよりそこにいってクリックして拡大した方が楽しいわけです。これらと対極にあるのが、「囲い込む」ということですね。昔の茶人とかが言うような「目垢がつく」みたいな感覚なのかなって(笑)。こういう骨董屋さんとかコレクターが外に絶対に出さないものがある一方で、横断的な検索にひらいて積極的に見てもらおうとする動きが加速しているといえるでしょうか。
3. アーカイヴと権力
佐藤:こうしたパブリックドメインみたいな話であっても、その背後にある所有権、著作権といった法律、さらには権力の問題を無視できません。ここで阿部さんに、フーコーがあえて単数形でアルシーヴとあえて使った意図、アルシーヴと権力、デリダの議論との関わりなどの問題を語っていただければなと思います。
阿部:まずは現代思想におけるアーカイヴの問題に触れておきます。フランスの現代思想でもアーカイヴへの興味は高まっているらしい。最近出版されたんですが*4、「哲学とアーカイヴ」というシンポジウムがあったりして──フランスのナショナルアーカイヴ、国立中央文書館が協賛していたようですけれども──、そこで哲学において「アーカイヴ」という語が持つ意味は何かというと、哲学に「歴史」とか「記憶」を導入したことではないかと書いている人がいました。基本的に哲学というと歴史や時間性とは関係のない、普遍的なものを追求しているイメージがありますけども、そうではなくてやはり「歴史」や「記憶」が大事なんだ、と。ある仕方で哲学に歴史を持ち込んだ人としてフーコーは重要なわけだし、デリダはしきりに記憶を問題にしていますね。

4 F. Jedrzejewski et D. Sardinha, La philosophie et l’archive : un dialogue international, L’Harmattan, 2017.
フランス語でも英語と同じで、アルシーヴという語は複数形で使われるもので、単数形で使われることはまずありません。やはりこれはフーコーが流行らせた用法ということでしょう。アーカイヴの語源は──佐藤さんが「巨大な書庫で迷子になって」でまとめてくださっていますが──、まず一つにはアルケイオンArcheîon、役所や政府を意味する語があって、さらにその手前の語としてアルケーArkhē、始まりとか起源とかを意味すると同時に掟も意味する語がある。やはり、アーカイヴにはこの二つの意味が関わっている。
佐藤:この語源のアルケーってOED(『オックスフォード英語辞典』)とかで見ていてもなかなか出てこないんですよね。「役所」とかでとどまっている。でもアルケーの方はアルケオロジーの方に繋がっていく。それで先取りすると、フーコーはアルケオロジーとの語呂合わせでアルシーヴというのを作っていくわけですよね。
阿部:そうですね。最初に、デリダの『アルシーヴの病』という本*5を参照しておきましょう。ここでデリダははっきりと名前を出していないんですけれども、当然フーコーへの目配せはあると思います。ここでデリダが簡単にまとめている語源が、さっき言った二つの意味に関わっているわけです。デリダが言うには、アルケイオンとは、アルコン、すなわちギリシャの政務官や執政官──平たくいえば役人──が住む家を指していた。役人が住む家ということで、それは書類を整理したり保管したりする場所であると同時に、書類を読んで解釈するという力が働く場でもある。要するに保存(歴史)と起源という系列と、権威や掟、秩序といった系列の二つがあるのだと。だからアルシーヴと言ったときに、記録そのものという意味と、記録を管理したり解釈したりする力という意味の二つがある。
*5 ジャック・デリダ『アーカイヴの病──フロイトの印象』、福本修訳、法政大学出版局、2010年
そのことを押さえた上でフーコーのアルシーヴなんですが、フーコーは『知の考古学』*6の中でアルシーヴという概念を出している。そこでフーコーは、過去、歴史の中で発せられた言葉とか書かれた文書とか、要するに「言表」を出来事や事物として設定するシステムのことをアルシーヴと呼ぶんだと言っています。つまり、一つ一つの言葉が意味のある言説として定着されるためには、意味という効果を成立させる条件とか制度が必要なんです。「言表」を「言説」に変えるシステム、意味のある言葉にするシステム。それをフーコーは単数形のアルシーヴと呼んでいる。
*6 ミシェル・フーコー『知の考古学』、慎改康之訳、河出文庫、2012年
『知の考古学』に面白い例があって、フランス語のキーボードの配列に、azertという並びがあるんですね。その並びはそれだけだと全く意味はないただの「言表」で、言説にはならないんだけれど、もしもazertという配列がタイピングの教本に例として挙げられている場合にはそれは意味を持つ、つまり言説になる。同じazertという語であっても、それが意味を持つかどうかという点である種のコンテクストが必要になる。そのメカニズムがアルシーヴです。だから気をつけなければいけないのは、フーコーが言っているアルシーヴっていうのは要するに記録の集合とか貯蔵されたテクストを意味しているわけではないということです。むしろ、フーコーはそれについては図書館という比喩を用いている。アルシーヴというのは、発せられた言表のうち何が言説になるのか、何が記録されるのか、されるべきなのか、ということを決めるものなんです。
佐藤:選別ですか。
阿部:そうですね。選別とか選択する権力ですね。ここでも、デリダが言っていたような権威や秩序といったものが問題になります。
アーカイヴに働く力、アーカイヴを成立させる力ですが、フーコーがそれについてはっきり述べているのは『知の考古学』よりもむしろ、「汚辱に塗れた人々の生」(1977年)*7という文章においてでしょう。少しご紹介します。

*7 ミシェル・フーコー「汚辱に塗れた人々の生」、丹生谷貴志訳、『ミシェル・フーコー思考集成』第VI巻、筑摩書房、2000年に所収。
どういう文章かというと、フーコーが図書館や古文書館、つまりアーカイヴに遺された無名の一般市民の記録をそのままアンソロジーとして出版するという計画を一時期持っていまして、結局は実現しなかったんですけども、その意図を説明するために書かれたテクストなんです。どういう記録かというと、例えば、フランス絶対王政の時代に一般庶民が国王に対して嘆願書みたいなものを書くわけですよ。うちの親父が酒飲んで暴れるから捕まえて監禁してください、みたいなことを国王に嘆願する。すると国王の側から封印状というのが発行されまして、封印状が発行されると司法手続きを経ずに人を監禁することができた。フーコーはそういう事例を研究して、絶対君主が権力を行使するとき、必ずしも王が上から行使しているのではなく、庶民の方が下からそれを要請し、それが契機になって権力が行使されているんだということを示そうとしたわけです。
それはともかく、全く無名の人間、本来歴史に名を残さないような人、例えば父親の悪行が、たまたま嘆願状や封印状のなかに記録されることでその存在が歴史に残る。だからこれは、権力の作用のなかに偶然組み込まれたことで、そういう人の存在が残った、つまり権力との衝突がなければ残りえなかったようなものなわけです。アーカイヴ化される、記録されるということの前提に、やはり権力や制度があるのですね。
佐藤:それは単純にいうと、記録を残す、あるいは記録するのが権力である、と考えていいんですか。
阿部:そうですね。もっと正確に言うと、何を記録するかしないかという選別ですよね。その切り取りを行うのが、フーコーのイメージしているアーカイヴを成立させる力、アーカイヴをめぐる権力じゃないかなと思います。これはやはり、さきほどの土屋さんのお話にもつながると思うんですけど、やはりアーカイヴってある種の権力がなければ成立しえないものなのかなと。予算とかそういう話もそうですし、いろんなアーカイヴを横断的につなぐっていうのはやはり、デジタル化されていることが前提なわけですよね。いろんな記録があるとして、必ずしもすべてのものをデジタル化できるわけではないので、何をデジタル化するか、しないのかっていうふうに、すでにそこには選別の力が働いてますよね。そういう意味で、アーカイヴと力との関係というのは切り離せないんじゃないかな、ということをフーコーを読んでいると感じます。
佐藤:じゃあフーコーは、実際にいま存在するアーカイヴズとシステムとしてのアーカイヴというものとの関係をどういうふうに考えていたんでしょう。写真論の場合、フーコーの影響下にアーカイヴが出てくるのは、アラン・セクーラという人の"The Body and the Archive"*8があるんですけど、あれも人々の身体をどのように規律=訓練していくかを論じるところでとりあげるのが犯罪写真のアーカイヴズなので、そういうところにも響いているとは思います。ただ、実際のアーカイヴズとフーコーが言っているアーカイヴとの関係っていったいどうなんだろうと。
*8 初出は以下のとおり。Allan Sekula, "The Body and the Archive", October, Vol. 39 (Winter, 1986), pp. 3-64. また関連して、第9回研究発表集会で開催された企画パネル「アラン・セクーラ、写真とテクスト、イメージと地政学のあいだ」も参照。
阿部:それに対して直接のお答えになるかはわからないんですけれど、複数のアーカイヴズと、単数形のアーカイヴの関係について言うと、フーコーも複数のアーカイヴズを統合する普遍的なアーカイヴみたいなものを考えていたと思うんですね。フーコーにとってそれがなんだったかと言うと、やはり「歴史」だったんじゃないか。つまり歴史的な記録の集積とか集合体というようなものがフーコーにとっては重要で、彼がそれをどういうところで問題にしたかと言うと、1970年代から取り組んでいた系譜学という方法論につながっていくと思うんです。フーコーが、権力の系譜学のなかでどういうことをしたかと言うと、彼は歴史をさかのぼって、社会において権力が作用するメカニズムがどのように生まれてきたか、ということの歴史や系譜を描き出すわけですね。フーコーはそこで過去の文書記録とか、記録された発言とかテクストとか、要するに過去の「言説」ですね、そのすべてを系譜学者としての視点から、現在の視点から読み直すわけです。つまり、歴史家とは違って、過去の客観的な事実を再構成しようというのではなく、むしろ、系譜学者として──あるいは哲学者としてでもいいんですけど──現在の視点から過去のものを読むことで再活性化させる。そうして、過去のものを用いて、現在我々が生きているアクチュアリティというものを批判的に捉えなおす。それがフーコーの系譜学の営みだと思うんですよね。
だから、フーコーがイメージしている歴史というのは、客観的な事実としての記録が保持されているアーカイヴというよりは、むしろ解釈者が現在の視点からその都度読み出し、活性化させることによってまた新たなストーリーを紡いでいくもの、つまりある種のデータベースのようなものとしてイメージされていたのかなという気がします。それこそが複数のアーカイヴではなくて、最終的には統合された普遍的なひとつのアーカイヴというかたちになるのかなと。もちろん、そこには権力との関係が(またもや)入ってきますよね。様々なアーカイヴをツリー状に統合していく、インターネットにおけるGoogleみたいに、強い一者が統合していくっていうこともあるでしょうし。ただ、フーコーはそれをかなり自覚的に、あくまで現在の自分の視点から過去の歴史を読み出したらどういうストーリーが生まれるのかという、まさにデータベース的な考え方をしていた。その意味で、アーカイヴとデータベースという対比で考えるならば、さきほど佐藤さんが、アーカイヴというのは基本的に見えなくするものだ、とおっしゃったけれども、それを見えるようにする、読み出す、アクセスする視点っていうのが必要になってくると思うんですよね。
佐藤:データベースとアーカイヴの違いってわかりにくいんですよね。すごく互換的な言葉として使われる場合もありますが、アーカイヴを検索するための機構としてのデータベースを考えることができる。データベースっていうのはむしろエクセルの表みたいな検索可能なもので、実際のものにアクセスするためのものというぐらいに解釈したらいいんでしょうかね。
土屋:デジタルアーカイヴをやっていると、歴史にはすごく興味があります。アーカイヴというものがあってそれを公開するという作業をしていて、自分がやっていることは歴史に対してどういう関わり方をしているんだろうか、そもそも歴史ってなんだろうと思うところがある。ヒストリーの語源はもともとストーリーと同じですし、歴史と言うと史実みたいなふうに考えるけれど、物語と考えると自由な部分があって、さきほどのようにデータをとってきて自由につなぎ合わせる、ストーリーを作っているって考えても良いと思う。その意味では、自分が文化資源データベースで作っているシステムって、正しいか正しくないかではなく、その人の視点の歴史を作っていくっていうことをシステム的にやろうとしているんだっていうことを最近感じるんですよ。
阿部:歴史を「解釈する」というのがやはり重要な問題になってきますよね。つまり、過去のデータを用いて自分なりの歴史を作るっていうのは、フーコーの系譜学も結局はそういうものだと思うんですけれども、悪く言えばそれは歴史を自分の好きなように、恣意的に操作するっていう歴史修正主義みたいな話になる。ただ、そこも含めて、それにはいろんなヴァージョンがあっていいんじゃないかということですよね。
土屋:そうですね。それが、いまはネットワークがつながっていると恣意的操作のハードルが下がってきているんですよね。ネガティブな印象も多いですが、それがデジタル化の良いところな気もするんですよね。ただ、デジタルアーカイヴと歴史との関係はどうなんだろうというのがよくわからないところがある。
佐藤:未来の部分っていうのが絶対にあると思うんです。というのは、やはりアーカイヴを作るときって、誰がどのように使うのかはあんまりわからないと思うんです。突拍子もない使われ方をするかもしれない。そういうところで未来に送り出すという側面がある。そういうところは作っているときにどうお考えですか。
土屋:100年先に必要だろうという漠然とした作成と、注目を浴びるだろうということがわかっている場合の二つを想定しています。たとえばいま若い研究者で流行っていそうなものを公開するとアクセス数が増えるというのがあるので、そういうことを考えてやらなきゃいけないというのもひとつあるんです。ただデータを出しました、検索したらキーワードが引っかかりました、「はい終わり」というのを続けると、未来は厳しい状況が来るだろうと危惧していたので、参加型のシステムにしたいと思ったんですね。そういうのがいままでのデータベースには一切なかったので。そういったなかで、正しくない情報も含めてどんどん巻き込めるというのがあると、未来に対して蓄積ができるし、そのとき考えていた人はこういうことをまとめていたっていうことが分かる。そういうことがまたアーカイヴされる。いま公開しているデータベースの構造は、まだ第一ヴァージョンくらいで、本来なら使う側の人がどう関わっているか、どう取り上げていたのかという内容も含めたものを残す、抱える。データベースを公開する側が抱え持っていくっていうことも必要だなと思っています。
4. アーカイヴは何を抱え込むのか──モノとメタデータ
阿部:ちょっと土屋さんにお伺いしたいんですけど、データベースを作るとなったときに、検索エンジンに引っかかるキーワードの付け方というのは気にされるわけですか。これもさきほどの選別の話で、キーワードをどこに紐付けるかによって検索結果も変わってきちゃいますよね。
土屋:目録を作る段階で、研究者によって重要項目が異なり、「この項目は欲しい」っていう要望に対してまとめなくてはならないという、選別の難しさはあります。そこは折り合いをつけるしかないんですけど、検索のキーワードに引っかからないのは、「表記ゆれ」みたいなものが原因になってることが多いと思います。表記が異なっても同じ内容であれば紐付けるようにすることが一番難しいところかなあと思うんですよね。そこも新システムの機能のなかで挑戦しています。単純な例で言うと、例えば「渋谷公会堂」で検索をかけると、「C. C. Lemonホール」は、普通だと引っかからないんですよ。
阿部:そこで田口さんにもお尋ねしたいんだけど、絵画とか美術作品を分類したり美術館に入れたりするときに、キーワードというのは問題になりうるわけですよね。つまり、本来非言語的な表現である絵画作品に言語によるキーワードをつけていくというときに、どういうキーワードを割り当てるのが正しいのか、というのは美術史における永遠の課題じゃないでしょうか。
田口:確かにそうですね。また、みなさんのお話をずっと伺っていて、選別・選択する力と秩序、というトピックについてあらためて深く思うところがありました。作品をいかに分類しどのように取り扱うのかについて、実は保存修復に関わる者たちは、永遠のトラウマみたいなものを抱えていると思うのです。何故かといえば、修復という行為が、つまるところ、繰り返される選択そのものでありながら、明確な正解というものを持たない行為だからです。まず基本的な傾向として、修復に関連するデータって、いまこれだけデジタルの情報にアクセスできる時代になっても、意外とまとまって出てこないところがあると思うんですね。ただ、個々の作品にどういう修復歴があるのか、どんな経緯で現在に至り、その過程で例えばどんな不慮の事故があってどんな修復措置を受けたのか、といった情報を含む、いわば人間のカルテみたいなものは、美術館に収蔵されている作品に付随しているものなんです。国外から展覧会のために作品をお借りしてくる場合にも、形式は様々ですが、こうしたカルテはそれぞれの作品に基本的にはついてきます。展覧会のコンサベーションを担当する修復士は、実物とカルテの内容を照合しながら状態を確認していきます。当然、この「コンディションチェック」という作業の過程で、それぞれの作品についてどれだけデータの蓄積があるのかを目の当たりにするわけなのですが、どれだけ著名な作品であっても、カルテを見てはじめて知る情報が結構多いと感じます。実際問題、そういった細かな作品の「健康状態」や「病歴」のようなものは公開されにくいという問題があるように思います。何故かというと、これまで行われてきた過去の修復歴のなかにはとんでもなく非常識なものや、現在では考えられないような選択もたくさん混ざっているから。つまるところ作品のカルテという名の情報データベースは、その作品について行われてきた様々な介入についての反省と後悔の蓄積のデータベースでもある、という面が少なからずあるのではないか。あまりにもヒューマンエラーが多すぎる、そのために公開されにくい部分があると思うんですね。私たち人間がどのように作品を取り扱い、修復を行い、それをどう記憶してきたのか、という選別の問題に、すべては結びついている。作品を修復し保存する者が一回一回、アクションを取るごとに、作品の外観や構造は多かれ少なかれ変わっていってしまいます。そこに多方向からの権力や暴力が働いてしまうということもあり、そこが修復のとても怖いところであり、この言い方が良いのかはわかりませんが、面白いところでもあると思います。
保存修復の分野に携る者が、これから先、アーカイヴあるいはドキュメンテーションの問題を考えたりすることの意義は、まず、こういったカルテをいかに書き残し、読み解き、情報を伝達し、公開し、共有していくのか、その可能性を探ることだと思っています。修復というのは、作品の経年変化の記録をし、同時に作品の未来を予想をしていく行為ですから。
ただ、作品のカルテを私たちが作っていくときに、行った介入が可逆的なものかどうかを付記する、ということは、面白いポイントかもしれません。つまり、作品を修復する人々は作品の行く末を否応無く選択しているわけですけれど、同時にその選択が可逆的なものでなくてはいけないということをすごく意識しています。修復理論が成立したのは近現代に入ってからですが、そこにいたるまでに散々、作品を洗い、破り、ちぎり、切って、貼って、という無謀な処置の数々が作品を破壊してきたという過去を、私たちは自覚しています。その経緯への猛烈な反省があるからこそ、「可逆性」というキーワードが、修復分野において重要視されるようになっていったと思うんですね。「最小限の介入こそ最良の修復である」と多くの修復士が唱えるのも、こういった背景が大きく影響していると思います。繰り返しになりますが、作品のアーカイヴに修復分野が付与できるもっとも重要な情報は、過去の人々や私たちが、今、ここにある作品をどう読み、なぜ介入をし、なぜ介入をしなかったのかという選択史の再構成であり、同時に自分たちが今どのような選択をしたのか、その意思表明を責任をもって残していくということに尽きるのではないか、と個人的には考えています。
佐藤:ちょっと確認したいんですけど、修復歴が残っていないというのは、これは日本だけってことですか。それとも世界的なことですか。
田口:海外でも修復歴を公にするという試みは、まだあまり進んでいないと思いますね。「1800年代に流行った技法で全体が修復されていますよ」というような、修復史上ある意味一見本のような方法が用いられていれば、たとえいまは採用されないような方法で修復された作品であっても、「これはその時代のモードだったから」ということで現状や修復歴が公開されますけど。10年とか20年のあいだに修復の技法ってくるくると変わっていくんです。ちょっと問題のある新しい修復歴などが公開されてしまうと、困ってしまうケースも出てくる。
佐藤:作品の所蔵歴(プロヴェナンス)を、ヨーロッパとかアメリカはものすごく克明に残しているけれども、日本は残してなくて、それが美術史のなかでも問題になっている。こうした所蔵歴との違いって、ヨーロッパでも、作品の価値に関わってしまうからということなんですかね。
田口:そうですね。でも、そういうなかで私が去年すごく面白いなと思った展覧会が、ベルンとボンで開催された「グルリット:ステータス・リポート『退廃芸術』──没収とその成り行き」展です。アドルフ・ヒトラー専任の美術商だったヒルデブラント・グルリット(1895-1956)の息子コルネリウス・グルリットが隠し持っていた1000点以上のピカソ、ルノワール、マティスなどのいわゆる「退廃芸術」、略奪絵画がわっと発見され、その貴重なコレクションがコルネリウスの死後、ベルンの美術館に遺贈されたんですよ。でも、ワシントン原則というものがあって*9、つまりはユダヤ人の元々の所蔵者に作品を返していかなきゃいけないという義務が、作品を受け入れた側に生じてしまうんですね。そういった状況下で美術館がどういう選択をするのかということに注目が集まりました。
*9 ナチスにより略奪された作品はもとの所有者および遺族に返却すべきであるとし、その手続きを容易にすることを国際的に定めた1998年の原則。スイスを含む44カ国がこれに合意した。
ベルンの美術館が昨年初めてコレクションを展示する際に、キャプションに、誰が所有していた作品がどう移動して、このような介入があって……といった事細かなタイムラインを明記するという試みをしたんですね。作品の生をある種まざまざと隠し立てせずに見せる、展示のなかに作品の来歴情報を組み入れていく、という意欲的な展示であったと思います。悲劇の歴史をふまえた上で国が主導する大きいプロジェクトで、国際的な注目を集めるなか、プレッシャーと責任がベースに立ち上がった展示企画であったからこそ、可能になったプランだとは思いましたが。
佐藤:いま、生っておっしゃったけど、特に修復をやっている人ってすごく作品を生き物的に扱いますよね。Treatment(治療)っていいますしね。
田口:そうですね。作品が制作された当時から現代に至るまでの経年の痕跡を辿りながら、何が最善なのかと考えるとき、「生」というキーワードで捉えるとイメージしやすい。結局、作品を「よくする」ということはどういうことなのかを考えたときに、決して元の状態に戻すことがよくすることではないことのほうが多くて。
とりわけ困るのが、現代美術ですよね。これは、高松次郎の《紐(黒)》《紐(黒 No.1)》を先日修復した時の写真資料なんですけど、山手線事件のときに駅や公園をひきずってまわっていた紐のうちのひとつで……。

高松次郎《紐(黒 No.1)》《紐(黒)》ミクストメディア、1962年、豊田市
佐藤:ハイレッド・センターの頃ですね。
田口:そうです。その当時高松がこんなことをしていた、あんな格好をしていた、みたいな証言やノートはあるんですけど、実際にこの作品をどうやって制作していたかが明確にわかる情報はほとんどありません。作りとしては、紐がまずあって、ところどころに結び目があり、ぐるぐると布で全体を巻いて、ところどころに瓶の蓋のような硬いものも巻き込んだりしながら細い紐でさらに縛ってあって、その上からペンキみたいなものをかけるか浸すかした、という感じのものです。これを、イギリスで開催された高松の展覧会[Jiro Takamatsu: The temperature of sculpture(2017年7/13-10/22)]に貸し出すための調査と、安全に輸送するために必要な処置をする、という仕事でした。なにぶん、タイトルが《黒》なのに表面がところどころ白いのも気になっていて(笑)、つまりは汚れているように見えたんですよね。埃っぽく見えていて、これをなんとか洗浄できないかと最初は考えていました。
たしかに赤外線写真を撮影して見てみると、肉眼で白っぽく、埃っぽく見えるところは全部くっきりと色が違って斑に映り、ああ、確かになにか付着しているのかな、という感じはあったんですね。でも、実際にこれを調査していくと、これは埃ではなくて、上に塗られていた塗料に含まれている樹脂が乾いていくときにガラスのような状態になって、それが細かく割れているんですよね。砂みたいに。その樹脂の部分だけがまた、黄変化して。
佐藤:ちょっと釉薬みたいになるのね。
田口:砂がかかって全体が汚れているように見えただけで、実際には高松が使用した塗料の変質だったんです。ということはつまり、これはオリジナルの一部なので、ある意味ではこの現象も自然な変化の一部であるという解釈が妥当なのではないかと私は思って、このまま保存するのが良いんじゃないでしょうか、と言ったんですね。光学分析の結果ナトリウムとかが出たりして、手汗や唾液がついているということは確かなんですけれども、埃や砂のようなものというのはほとんど検出されなかったんです。
佐藤:鉄が錆びたり、銀が黒くなったりするのと同質のものだったと。
田口:はい。ただ、いくらなんでも《黒》というタイトルでこれはまずいのではないかっていうふうに思っていた箇所が他にもあって。つまり、紐に巻かれた布が部分的に破損して、白い紐が露呈してしまっていた部分があったんです。ここに関してはビタミンB2で染色した和紙を黒く塗って、それを布と布のあいだに挟み込んで固定する処置をしました。どういうことかと言うとですね、普通の蛍光灯のもとでは一見、処置をした部分は真っ黒で作品と同化しているんですけども、作品のコンディションチェックをするときやなんかに、紫外線ライトを当ててやるとその部分だけ蛍光に発光して「ここを修復してありますよ」ってわかるようにしました。
佐藤:作品のなかに修復歴が残るような仕掛けっていうことですね。
田口:そうです。普通に見ただけではわからないんですけども、特殊な光を当てた時、どこがオリジナルでどこがオリジナルじゃないのかが明快に判別できて、しかもそれが後に取り除けるものであって可逆的な歴史をつくることができるように、そういう修復の仕方を目指したんですね。これは本当に一例なんですけど、こういうことをすることで、なんとか……。
佐藤:作品そのもののなかにアーカイヴを忍ばせるみたいな。
田口:はい。結局、保存修復のなかのアーカイヴというのは作品自体の情報の蓄積であり、同時に作品に関わってきた人たちの取捨選択というか、意志の蓄積そのものでもある、というのはこの《紐》の時にも感じたことです。未来を選ぶ、という選択に寄り添う暴力の影は、私の中にもいつも感じていて、それこそ佐藤さんがこの座談会の最初のヒントとして送ってくださったリンクの原稿にもあった、中島敦の『文字禍』でナブ・アヘ・エリバが字の霊の祟りで圧死してしまうくだりはゾクッとするところがあるんですけど。いつか作品にリベンジされるんじゃないかみたいなことを思っちゃうことはありますね。
5. アーカイヴは何を生むか
佐藤:さきほどの話で印象的だったのが、やはり作品の生という言い方だけれど、作者が亡くなった後とか現代にいたるまでのひとつの歴史って、かつての美術史もそれはあんまり見てなかったことだと思うんですよね。でも多分いまはそういうところも注目されだしている。
田口:そう思います。
佐藤:アルジュン・アパドゥライの編集したThe Social Life of Thingsという論集があって、要するに「モノの社会的人生」みたいなことというのをすごく重要視しているんですが、それこそがアーカイヴの対象となっていくべきことであり、さらにできれば公開していくべきことかもしれない。
阿部:田口さんがおっしゃったことは、それこそ歴史学者が歴史を書く場合にも当てはまるでしょうね。どういう視点から歴史を書くべきかっていう話があるときに、修復士のやってらっしゃることはすごく参考になるかもしれませんね。つまり、自分がどこまで介入したかまでをも明らかにするという歴史の書き方。芸術作品の本当の姿とは何か、などと考え出すと、これは結論が出ないわけで、作者が作った当時のものが正しいのかそれとも今われわれが見ているのが正しいのか、とかそんな話になりますよね。
佐藤:パフォーミング・アーツの/における復元あるいはアーカイヴの問題、アーカイヴするしかないコレクションにもつながりますね。音楽も、近代の複製技術、録音、映画、フィルム、ビデオというのが出てきてから少し異なってきているでしょうけれど、何をアーカイヴしどこまで復元するのかという問題は大きい。
技術の文脈でいうと、近代以降、モダニズム以降に形が変わっていく中で、インスタレーション、ランド・アート、あるいは再制作という問題ですね。僕はシンポジウムなどにちょっとだけ関わっていたんですけれど、古橋悌二のLOVERSを京都の芸術資源研究センターというアーカイヴセンターを京都市立芸術大が立ち上げて、石原友明さんが中心で、加治屋健司さんもいました。その時ひとつ面白かったのが、メディア・アートにおいては、ソースコードしか保存するものはないんじゃないか。設計図なんじゃないかという意見もありましてね。メディア・アートの場合。例えばナム・ジュン・パイクだったらブラウン管じゃないといけないのかという問題がありますよね。ところによってはブラウン管に液晶がはいっていたりするらしいんですけれど。要するにハードウェアの問題というのがある。LOVERSの場合はレーザーディスクだったんですよね。あれ自体が再制作なんです。
田口:私はLOVERSのプロジェクトに直接は関わっていないんですけれど、今タイムベーストメディアという言い方もようやく名前が知られるようになってきて、京都が中心となって保存修復のプロジェクトの全貌とか修復のカルテをオンラインで公開するということを始めていますよね。だいたい2004年くらいにMoMAがそういうことを始めて。MoMAはタイムベーストメディアのキュレーターを置いているんですよね。それこそナム・ジュン・パイクのブラウン管について、エミュレーションとしてどんなことが可能なのかを考えたり、同じような作品素材でも場合によってはアップグレードしたもので使えないだろうか、とか。色んな提案や発案に皆がオープンで、電気技師、音楽家、プログラマ、配管工、多くの専門家と繋がってネットワークの中で修復を考えていくシステムを作ろうとしている傾向はあると思います。ただ、なかなか日本でそれが難しいなと思うのは、やはり保存修復機関として現代美術を専門的に扱うようなシステムができていないので、一つ一つケースバイケースでやっていくしかないんですよね。LOVERSの保存修復プロジェクトはすごくいい取り組みだったと思うので、その学びが次に繋がっていったら良いんだろうなと思うんですけれど、なかなか他の館でもあらゆる情報を共有して、となっていかないという。資金的な問題もあると思うんですけれど。
佐藤:MoMAにオリジナルはあるんですよね。MoMAもきっちり修復していて、オリジナルもちょっと遅れて公開しているんですよね。
田口:自分が修復をするので、これを修復するとしたらどうするんだろうという考え方でものを見てしまうんですけれど、モノとしてそれを物理的に残すということと、そういうものが確かに存在したのだということを文章化して残すという二つの保存の在り方を考えたとき、前者に関してはテクニシャンの方に関わっていただかないとどうしようもないなということを思っていて。最近いろいろな美術館で、機器的なメカニズムが大部分の作品の再制作とか再展示をよく見ますけれど、そういうところでよく聞くのが、作品を設置した際にいらした美術品輸送や展示のスタッフの方たちが定年退職を迎え、いなくなってしまう瀬戸際で、いなくなる前に覚えていることを全部教えてもらわなくてはいけない、という話です。でもその方たちもありとあらゆる手順をすべてドキュメンテーションしているわけではないので「そんなこと言われても何から何までは覚えてない!」みたいなことを仰るらしいんですけど、「やったら思い出しますよ」とキュレーターの方が当時のスタッフの方を指名して、もう一回展示作業に加わっていただいて、今度はその作業の流れ全てを記録しておく、という。なんとかもう一回それを展示しましょうという話に将来的になった時に、これに従えばいいというような指示書ですね、それを作ろうとしておられる館は多いみたいですね。タイムリミットがあって、急がないといけないことなんだろうなと思います。人間の記憶も失われていくし、作品の記憶も失われていくので、火急の課題という気がしています。
佐藤:まさにアーカイヴが救うことになるわけですよね。つまり伝えることになっていくという。
田口:配線とか、何ボルトの電圧でとかそういうことも含めてですよね。アーティストみんながみんなダン・フレイヴィンみたいに、ネオン管がなくなった時に備えて自分でネオン管を作る会社を立ち上げればいいや、というようなダイナミックな策をとれるわけではないから、やはりエミュレーションのシステムをどこかで考えていかないといけないだろうと思います。グッゲンハイムなどが99年くらいから言っているのは、タイムベーストメディアに関しては、同じ種類の新機種への移行=ミグレーション-Migration、新しいハードかソフトで再生環境を代替する=エミュレーション−Emulatuon、作品の根幹となるアイディアは尊重しながら再解釈を試みる=リインタープリテーション−Reinterpretationのための手段を考え続ける、という3つが方策として有効、ということです。〔詳細は以下を参照。「タイムベースト・メディアを用いた美術作品の修復/保存のガイド」]古典的修復の中でも再解釈自体は様々な形で行われてきましたが、エミュレーションやミグレーションという選択肢が修復の方策に入ってくるというのは、すごく大きい変化ですし、具体的に何が可能になってくるのか、もっと実践的に考えていかないといけない時代なんだな、と。
佐藤:同じようなことがビデオゲームの保存に関しても言われているようで、この前僕がアーカイヴ・サミットで司会をやった時に、細井浩一さんという立命館のアート・リサーチ・センターの方が、プレイ動画も保存するということを言っていて。ゲームは本当に場所によって違って、千差万別らしいんですよ。
いろんなメディアが出てくるたびに、アーカイヴの方法、それが歴史を記録する、それを将来再生する時にどのようにやっていくかという問題が次々あると思う。昔のメディア、絵画とか伝統的なメディアの場合は再制作とかまずあり得ないことですよね。それがいまは再生策であり再演、そういう意味では音楽のモデルなのかなという感じもしないではないですけれど。
──アーカイヴによっていろんなジャンルの学問の風景や方法が変わったりするようなことはあるのでしょうか。研究費獲得におけるデジタルアーカイヴ・バブルには功罪があると思うのですけれど。
阿部:歴史学のあり方なんかは多分変わってくるでしょうね。何でもかんでも簡単に保存できるようになるということで。学問のあり方についてではないんだけれど、ちょっと関連するかもしれないのでお話ししたいのが、芸術作品を作るクリエイターの側からしてアーカイヴという原理とはどういうものなんだろうか、と。作品をめぐる記憶だとか情報だとか、それらはどんどん蓄積されていて、言いようによってはものすごい重荷となるものですよね、創造する側からすると。ニーチェ的な考えですが、歴史というのは重荷にしかならないのであって、何か新しいものを作ろうと思ったら歴史は忘れなきゃいかんのだという考え方も当然ありうると思うんですよね。だからデータベースなりアーカイヴというものを、クリエイターが作品を作るときの重荷として捉えるのか、あるいはそれとも別の考え方で、データベースというのが作品を作るときの源泉、ネタ元になるということもありうるわけですよね。東浩紀が言っていたように*10、ポストモダン文化というのはデータベース的な文化であり、データベースから色々なものをパロディー化したりリミックスしたりして文化ができていくんだ、という考えもあるでしょう。作品制作の原理としてアーカイヴというのはどうなんでしょう。プラスの面、マイナスの面があると思うんですけれど。
*10 東浩紀『動物化するポストモダン──オタクから見た日本社会』、講談社現代新書、2001年。
土屋:つくる側としては、作った作品がずっと残るのかは考えてないです。自分だけかもしれないですけれど、5年後に評価されるように作ろうという気持ちを持っていて。今あるもので、流行っているからつくるというのだとダメなんだと。10年先に行くと全く相手にされないと思うので、5年先に評価されるものを作らないとダメだろうというのは自分の基準としてあるんですよね。作った段階ではなんだこれ?と言われるんですけれど、5年くらい経ってくるとあの時ああいうことが言いたかったんだみたいなことが振り返ると分かる。それが楽しいんですよね。5年先どうなるんだろうということを考えるから、少し先の時代に常に寄り添っている感覚があります。
それはアーカイヴと関係ないかというと関係ある部分もあって、修復とデジタルアーカイヴの大きな関わりの違いというのは、社会とのつながりというのを意識していると思うんですよ。修復というのは作品をまず対象とするじゃないですか。デジタルアーカイヴというのはネットワークを使っているので、作られた年は何が起きたかというところや、こういう事件が起きたとかが調べられる。そういったことが作品に影響してたりするんですよね。外部リンクと親和性が高いので、デジタルアーカイヴでこれから重視したいと思っているのは、作られた年はどういう社会だったか、作家はどういう人生だったのか、そういうところを入れていくことが重要になってくるだろうと。そういう意味で修復の人とは戦っちゃうのかもしれないですけれど、自分にとっては表示メディアが変わっちゃうとか、ネオン管がなくなるとかそういうことよりも、その時に何が起きたかという時代をしっかり記録する、公開してリンクをつなげるということをしっかりするのが役割だなと思うので、すごく役割の違いを感じました。こうしたことを自分はやらなきゃいけないと考えています。
特に現代美術というのは、現代と言っている以上、時代性のつながりはすごく密だと思うんですよ。それを作品単体で見ていいのか、という状況ではなくなっている。LOVERSもゲイ文化とかエイズとか、そういった当時の時代背景が分からない世代が既にいると思うんですよ。当時の状況を正確に再制作したけど、よくわからないという話があるのは、当時がどうだったかという情報が置いてかれているからだと思う。自分の作品への関心と同じように、この作品がこういう時代でこう向き合ったという物語と寄り添うことに興味があって、それによって何か隠れていたものが浮き上がるかもしれないと考えている。
佐藤:ポストモダン・アートとかが喧伝されていた時というのは、データベース的というか、全てが同一表面になって、それが歴史の流れから切り離されて同一平面上にある。それはポストモダンだけじゃなく、ベンヤミンが写真の時に言っていたことだろうし、僕自身が興味のある岸田劉生なんかは全くそういう人だったと思うんですよね。デューラーも中国の古典も浮世絵も全部同一平面上で、それは1910年代、20年代という複製技術時代だから、というようなところ。ただ、そこでもう一度そのコンテクストが重要であるということはどういうことなのか*11。一旦、アーカイヴができてくることによって、コンテクストとかがない状態で新たなものが作れるようになったという面も一方ではあると思うんですよね。そこをどう考えていったらいいんだろう。ファウンド・フォトとかファウンド・フッテージみたいな誰が作ったのかわからない写真を並べたりするのは―ボルタンスキーあたりから始まったと思うんですが―、すごくアーカイヴ的なアートという風に言われ出したとは思うんですよね。そういったものに関して、土屋さんのカセットテープを使った作品について説明していただければと思います。
*11 アーカイヴされるものとコンテクストに関しては、本特集寄稿2 長門洋平「映像音響/サウンドトラックのアーカイヴ」も参照。
土屋:水戸芸術館でやったやつなんですけれど、Cタイプのカセットテープなんですよ。水戸という場所だったので、実は原発事故がベースにあるんですね。最初は福島第1原発、1号機・2号機・3号機・4号機がそれぞれ稼働を始めた年に製造されたカセットデッキを見つけて、それを解体する写真を、時系列にコラージュした写真作品を制作しました。また、小さい頃に録音したカセットテープを聞かずにおいてある人って結構多いじゃないですか。それをイヤホンで何十年かぶりに聞いてもらう。その状況を、ただ定点で映像を撮る。何を聞いているかは分からないですけれど、その人の表情だけを撮ることで、聞いている人の表情が当時を表現する再生機になっている作品です。最後に、年表を作ったんです。フィリップスが規格を作ったんですけれど、オープン規格にしてという話から始まって、展示した年までをちょうど年表で作って、それを半分で切ると前半が昭和で後半が平成になったので、カセットテープのA面、B面みたいな両面刷りにした。原発事故が起きたら、稼働した年がいつです、何年経ったという話しかなくて、その間にあった40年間くらいが語られなかったというのがあって、そのとき自分たちも電気使っていたし、どうだったんだろうということを考えることをしなきゃいけないと思った。わかりやすいメディアとしてカセットテープというリニアにつながっている時間軸、ものすごく長く愛用されていて、象徴的に面白いと思ったんですよ。ちょうど原発が増えていって、電気の需要も増えていく時代とカセットテープが普及していく時代が重なって、バブル崩壊とともにMDとかCD-Rとかリッピングが出てきて、どんどん勢いが下がっていくみたいな。昭和と平成という時代がすごくリンクしていたというのが年表を作ってわかったというのがあるんですよ。B面が終わったら、A面に戻る気なのかという未来への投げかけにもなった。ちょうど1964年の東京オリンピックがA面の最初に出てくるので。


土屋紳一、《recorder》、水戸芸術館での展示風景
佐藤:カセットテープ以外は、それと重なるのはないんですか?
土屋:カセットテープは意外と寿命が長いんですよ、そういう意味では。
佐藤:今カセットテープ専門のレーベルとか、うちの京都精華大学のポピュラーカルチャー学部で作ったりするなど再評価されていますね。アメリカとかは圧倒的にカセットテープ文化というのがずっとあって、カーステレオもあるし、道端でミックステープを売っていたりする。ジャマイカもそう。
土屋:ものすごく身近に記録できる装置でもあったわけですよね。現代のランダムアクセスできる時代に、テープのリニアな時間軸というのをもう一度考えることができる場を作りたかった。それが社会とか人のつながりというのは、なんかアクセスが全部ランダムになってきていると感じます。だからこそ、ちゃんと繋がっていることを考える、とにかく時間は繋がっているんだと。
ちょっと話はずれちゃうんですけれど、データベースを作るときの共通項目って時間軸なんですよ。いろんなメディアであったとしても、いつ作られたとかという項目などがあるので、時間って共通としてだいたい持っているんですよ。持っていない項目ってないと思います。だから、年表を作りたいとか、時間で何かを調べようというのをトライするんですけれど、自分もやっているんですけれど、だいたいうまくいかないんですよ。それがなんでだろうと考えたときに、一番しっくりきたというか、思ったのは、今の時代は時間の単一化が進みすぎた気がするんですね。もっと時間って、人の人生みたいなものがあったりとか、いろんな時間の尺度を持ってたような気がするんですけど、データ化が進むと、グリニッジ標準時に縛られて、それ以外はないみたいな考え方になって、おかしくなっていると思う時がある。人の人生で考える尺度ってもっと強かったような気がするんですよ。だけど、何年に生まれ、何年に死んだ、という時間軸じゃなく、どういう密度だったかとか、しっかり考えなきゃいけないということがあると思うんですよ。そういった意味で、もう少しリニアな時間というものを感じられるデジタルアーカイヴが必要だろうというのも今後のテーマとしてある。
佐藤:アーカイヴってランダムアクセスができればできるほど便利だと僕らは思ってるわけですよね。とにかくできるだけ簡単に一箇所から全部を見晴らしたい欲望みたいなものがちっちゃな権力者になってるというかね。
土屋:そこに自分は、物語なんですよ。物語って時間軸として繋がっていないと物語にならないので、ランダムアクセスしたものから、みんなが物語を作っていくということがリニアな時間を作っていくということなのかな。デジタルアーカイヴの今後の懸念として、データが大量にありすぎるとどうしていいかわからないみたいな感じになってきて、一回キーワードを入れて、よく分からないから終わりみたいなことになってきちゃったら、衰退していくような気がするんですよね。そのためにはどうすればいいかという時に、物語に行き着いた。物語(ストーリー)ってヒストリーであるから、またデジタルアーカイヴのところに関連していくから、物語をキーワードにしていくと、もっとデジタルアーカイヴは活性化するんじゃないかという目論見がある。
阿部:なるほど、アーカイヴって実は反歴史なのか。ランダムアクセスが行われるなら、アーカイヴは歴史の集積ではないんだ、という。
佐藤:先ほど僕が「データベース的」といったのもそういう意味です。ただ歴史が集積するけれど地層がない。
土屋:デジタルアーカイヴを単純に時間軸でまとめようとしても、うまくいかないという落とし穴の原因かもしれない。
田口:そういうテーマの作品も芸術祭で増えてきている気がするんですよね。2015年のヴェネツィア・ビエンナーレの金獅子賞をとったアルメニア館も、アルメニアの修道院の時間軸の中に現代の移民の時間軸を重層的に重ねていって、いろいろな物語がランダムに絡まりあって点在して、地層が訳わからないようになっていく中で鑑賞者も迷子になっていくっていう。
阿部:だからその中で自分のヒストリーというものを持っておかないとそういう作品を作ることもできないし、地層の迷宮の中で一人一人の人生というのは残らない訳ですね。
6. アーカイヴ/データベースの生──その不可能性から
土屋:ちょっと話変わるんですけど、日本の有名な人の作品が、海外に流出してしまう。まあ以前からあるんですけど、そういったことがやはり直近でいろいろあるんですよね。じゃあ日本でどこか買ってくれたり、博物館なりが受け入れてくれるところがないかって、いろいろ考えたりしたんですけど、まあないんですよ。有名な人ほど。で、そうなってくるともう、流出しかないんですけど、ある国に行った時に、じゃあ自分たちは何ができるのかと考えた時に、やはりそれは目録とかを作って、可能であれば画像も撮って、それをデータベースだけは持っておく。そのデータベースを日本語でちゃんと閲覧できて、どこの国でどこの機関に資料がありますということを、ちゃんと日本語で伝えるということが大切だなと思ってて。どう考えても今の日本の状況では、流出し続ける。そういった意味では、データベースくらいは持っておくということを、頑張らないといけないんだというのがすごくある。まあ本来はオリジナルを持ってた方がいいんですけど。
佐藤:日本に技術博物館があまりないという問題と関わりますね。イギリスのヴィクトリア&アルバート博物館とか、あるいはフランスの技術博物館みたいに技術やデザインをアーカイヴする場所がない。つくばにある科学館の産業技術史資料センターがすごく頑張っているんだけど、あそこは、物は持たないらしい。ただし、それも一つのやり方かもしれない。そうじゃないと企業が出してくれないらしいんですよね。
──つくばには、物じゃなくて何があるんですか?
佐藤:写真とデータっていうことらしいですね。それが未来技術遺産として登録されていくっていうような形。
阿部:やっぱり権力のイニシアティヴがないとアーカイヴ自体が成立しないということで。フーコーの自筆原稿、マニュスクリプトについても、フランス政府が国の資産として買い上げたんですよ。それを国立図書館に入れて散逸を防いだらしいんですけど。逆にデリダの自筆原稿は、アメリカの大学に一部が買われて行っちゃったでしょ。だからやっぱり、何か権力なり、権威なりが、ガチッと作るぞという風にしないと、アーカイヴは成立しないんですね。
佐藤:しかもアーカイヴを作ることが、権力の一つの証になっていくという。
──歴史とアーカイヴの話を聞いていて、アナール学派とフーコーの関係も気になりました。権力中心の政治史に対して、名も無き農民たちの歴史を書いていくといった方法が、アナール学派の貢献もあって歴史学の一大潮流となったのはフーコーも見ていたと思うんですけど、それはある種の反権力的な歴史記述のように聞こえるわけです。しかし、先ほどのフーコー「汚辱に塗れた人々の生」の話をうかがっていると、そういった人たちも実は、あるいはそういった人たちこそが権力を呼び込んでいるという、もう一つねじれた関係にある。アナール学派は彼らなりに、いわばデータベースにアクセスして今まで光の当たらなかったヒストリーを引き出そうとしとも考えられますが、歴史や権力に対するフーコーとの視点の違いというのはどのようなものでしょうか。
阿部:そうですね、やっぱり歴史学者とフーコーの一番の違いっていうのは、歴史学者の仕事とはあくまでも、当時の客観的事実というのを、復元し確定しようとすることでしょうね。フーコーはたぶん、そういうことにはあまり興味がないようで。要するに、フーコーは「汚辱に塗れた人々の生」に出てきた、酒飲んで暴力を振るうおっさんがどういう人だったのかを論じたい訳ではなく、そういう存在が権力と一瞬触れ合うことによって、歴史の中で浮かび上がってくるメカニズム、言説を選り分ける力のシステムとかメカニズムの方にこそ興味があったんでしょうね。
佐藤:僕は、さらに言えばギンズブルグや、そのもうひとつ元にあるヴァールブルク学派のことも思い浮かべたりしたんだけれど。たぶん方向性がちょっと違うわけ。ヴァールブルクはもしかしたらちょっと似てるかもしれないけれど。
阿部:アナール学派は、いわゆる正統的な歴史、権力者の歴史とは別の歴史を描こうとした訳ですよね。フーコーは、一つ一つの文章記録の中にある、それこそベンヤミン的な記憶みたいなものを呼び起こすことを考えていたんでしょうか。アーカイヴの中に生というもの、一つ一つの生を、呼び出そうとしたのかもしれないですね。
──データベースとアーカイヴという言葉の関係について、もう一度確認させてください。アーカイヴの原イメージは、建物があって、本棚があって、引き出しがあるツリー構造。データベースは、タグのついたデータの集合体にランダムアクセスするということでよろしいでしょうか。
阿部:たぶんそうでしょう。誰も全体像が分からない塊ですね。
佐藤:資料目録がデータベース。一方で実際、行李などのなかに入っている大量の手紙とかがアーカイヴなのかなという理解が一番良いのではないかな。まあそこに加えるならば、コレクションという概念もややこしいんですよね。
──アーカイヴは、どこに何があるか分かってる人は素早く目当ての文書や物を引き出せるけれども、ある程度の規模になるとデータベース化して検索しないとアクセスできなくなっちゃいますよね。そこでちょっと問題提起したいんですが、ある閉じたアーカイヴをデータベース化することは、根源的にアーカイヴを内側から外に食い破るところがあるんじゃないでしょうか。Googleが図書館自体のカタログでは見つからないような本文データを検索してくれるように、アーカイヴの中を把握しようとして作ったデータベースの情報を外側の横断的な検索エンジンが拾ってくれる場合もある。先にも話題になったことですが、データベースというものは、本質的に横断検索的なものであって、アーカイヴの輪郭を内側から食い破って、世界中の個々のアーカイヴを繋ぐ単一の“The データベース” みたいなものを志向せずにはいられないのではないでしょうか。
佐藤:今の話聞いてて思い出したのは、データベースの分かりやすい例がOPACだと思うんですよね。要するに、図書館に本がザーッと本棚に並んでいて、近くにコンピューター端末があって、そこにOPACがあって検索していた。物のアーカイヴズがここにある、データベースがそこにある、という風にある程度分離していた。それが、もはやデータベースとアーカイヴズを分離する必要さえなくなっているのではないか。アーカイヴズの中に、物と、それがデジタル化されたデータと、そのメタデータとかがどんどん入っていってるから、もしかしたら、それらを弁別する必要がなくなっているのかもしれないなという気もしますね。
──音楽の比喩で言うと、昔は音楽を所有しようとしたら、レコード買ってくるか、必死でカセットテープでエアチェックとかしましたよね。何月何日、あのラジオ番組をエアチェックしたとか、あの時自分は中学生で、このラジオ番組のラジオDJの語りと共にこれを録音したとかのヒストリー/物語ないし地層と共に音楽を所有していました。自分だけのちょっとしたアーカイヴズが形成される。今はSpotifyとかAmazon Musicとかに全部あるから、そもそも所有しなくていい。録音するとか所有するとか、そういう欲望がなくなってきて“The データベース”みたいなところにアクセスすればいい。だけれども何を聞いていいか良く分からないから、誰かのキュレーションに従う(笑)。
佐藤:そう、だからSpotifyは、それこそプレイリストがね、すごい重要になってくる。
阿部:いやもっと言ったら、人間の記憶全部が外在化してる。すごく分かりやすいのが、最近の学生にフランス語教えても、単語なんか覚えようとしない学生が結構いますよ。要するに、調べりゃいいと思ってる。分かんなかったらその場で調べる。データベースだから、自分の記憶にして持っておくという発想がないんですね。まあ、あらゆることに関してそうなのかも知れません。音楽でもそうだし、記憶でも。とすると、どんどん外在化した後で、自分に何が残るのかということですが(笑)。
佐藤:まあ記憶を、どんどんどんどん外に出してきた歴史みたいな、写真もそうですしね、まさに。
阿部:そうですね。
──現在の歴史研究だと、一次資料にどこまでアクセスできるかという問題より、アクセスの可能性が無限にあるように一瞬見えてしまうデータベースをどこで区切るか、というところが歴史記述の上ですごく問題になる。そういったこととも関連しますね。
佐藤:ただSpotifyなんでもあるっていうけど、Spotify、結構無いものありますよ(笑)。実は、僕の好きな曲なんかは無い場合が多い。
土屋:デジタルに無いものは無いんですよ、若い人にとっては。存在しない。
──デジタル時代のバークレー主義(「知覚されないものは存在しない」)とでも言えるでしょうか(笑)。
佐藤:ところがSpotifyは自分のコンピューターの中も検索するでしょ。あー、この曲あったやんって思ったら、他の人には聴けないの、僕しか持ってないから。あれこそ統合データベースを目指してるんだと思うんだよね。Spotifyの向こうにあるのと、自分のコンピューターの中にあるのを聴くことができるっていう。Spotifyにはマニアックな曲あんな、とか思ったら、違うこれ俺のコンピューターの中やったっていうような(笑)。
一同:(笑)
阿部:すごいですね、データベースの果てまで行くと、自分のとこに戻ってきちゃう(笑)。キューブリックの『2001年宇宙の旅』みたいに、宇宙の果てまで行ったと思ったらいつの間にか自分の中に戻ってた、という。
土屋:デジタルアーカイヴは、「デジタル」とついているじゃないですか。和製英語なんですけど、面白いなと思うのは、デジタルに集約しているところ。さっき出た話で、アナログのままのものは存在しなくて、デジタルにあるものだけが存在しているのがアーカイヴだよ、と言っているような怖さもある気がしてて。そういった意味で、そのアーカイヴはデジタル化されてるものか否かと、突きつけているような名称だなと。
佐藤:この学会の学会員でもある松谷容作さんがね、匂いの話を出して。『手と足と眼と耳』というタイトルに、鼻がないよねっていう。彼は神戸映画資料館という、とてつもないフィルムを持ってるところの整理を大学院生時代からずっとしてて。『手と足と眼と耳』にも彼は書いてあるんですけど、すっごい匂いやと。で、アーカイヴというのは、もしかしたら匂いなんだと。その匂いの問題で、匂いはそれこそコレクションとかデータベース化できるのかっていうようなね。
田口:私もずっとその、匂いの保存とある種の修復みたいなものに興味があります。去年もそのテーマでシンポジウムを開いて、MoMAの方とかに来ていただいて、匂いの問題を抱えているような作品を逐一どうするのかという話をしました。いくつかやり方があって、私が興味を持って取り組んでた事例というのは、作家が自分の、たとえば体液とか、血液とかを使うような作品のケースです。それがやっぱり酸化していって放つ悪臭みたいなものを、オリジナルと捉えるべきなのか。まあ展示や収蔵をする側としては、脱臭や抑制をしてほしいところもおありだと思うのですが、作品の保存修復のあり方としてそれは正しいのかどうかというのが、ずっと自分の中に葛藤としてあります。いろんな人の話を聞こうと思って、シンポジウムを開いたんですけど。
そういう問題について、今のところあまり議論されてなくて、むしろ問題として挙がってきたのは、たぶんいま佐藤先生も頭にあるのはそっちの方の事例なんじゃないかと思うんですけど、要はその作品の一部として、いい匂い、まあ不快でない匂いを元から使っているものが、作品としてそれが薄れて行く時に、その失われていくものをどうするのかということです。MoMAの方とか、あとはドイツのヴォルフスブルグの美術館なんか、わりとそういうセント・アート(scent art)みたいなのを、最近展示に入れているんですけど。一つの方法としては、香りの、調香師さんですね、その方にレシピを書いてもらって、それを買い取るという方法と、その展示の時に使った物を、すかさずこうバッて、容器に入れて、可能な限りそれ保存する方法です。時々ふって嗅いで、あっ、まだ残ってるって(笑)。
一同:(笑)
佐藤:うん。ただ作品によっては、経年変化でなくなっていくことも作品の一部なのかもしれないんですよね。そういう時にどこまで手を出すべきか。
──色の退色とはちょっと違う問題なんですよね。
田口:そうですね。消失していくものとして制作された作品を購入したとなった時に、じゃあ何を購入したのかといったら、やっぱり「匂いを購入した」と考える。じゃあそれどういう風に保存するか、あるいは再展示ってなった時にどうするか…。
佐藤:だからその、調香で再現というのでいいのかどうかという問題ですよね。
田口:はい。やっぱり匂いって非常にパーソナルなもので、人によってその感覚があまりにも違うので。結局、匂いを再現するとなった時に、正確なレシピがないと、こんな感じ、こんな匂いというのは、個人の言語で言い表されたものが最大の手がかりになる。言語化されたものを手がかりに作りなおしていくしかないらしくて。すごくやっぱりそこは、どの館もどうしたらいいか分からないという感じですね。
あとは、最近ちょっと論文にも書いたんですけど*12、2016年のカイ・アルトフのMoMAでの個展で、自分の子供の頃の思い出の品々とか、摩耗した人形とか、食べ物みたいなものとか、そういうあれこれをこうワーッて並べたカオスな部屋を展示室の中にカイ・アルトフが作ったんです。まあ当然その匂いが酷くて、修復家が無断で消臭剤を置いて、そしたら本人が怒っちゃって(笑)、 そういうことはしてほしくないと。でもあまりにもひどい匂いなので、どうにかしてほしいと言ったら、ものすごく高い香水をカイ・アルトフ自身が選んで、これを振り撒いてほしいと言ったんですね。もうそれが本当に高くて、ル・ラボっていう香水メーカーの。もうそれを毎週何mlって吹きかけていくだけで、予想を遥かに超えるお金がかかって、最終的には大変な赤字だったらしいんですけど。でも結局それも、これはある意味作品の一部だからということを言われて、押し切られて、撒かざるを得ず。でもそれで、監視員の方が気分が悪くなって、来れなくなって病欠しちゃったとか、すごい二次災害が発生していて。結局、そういう方針や緊急の方策が必要だった経緯も含めて、じゃあ作品をどこまで保存をするのか、全然マニュアルがないことなので、どこも困っています。
*12 田口かおり「近現代美術の「臭気」をめぐる一考察──展示、収蔵、保存、修復のケーススタディ」『ディアファネース』京都大学人間・環境学研究科岡田温司研究室紀要、No. 5、2018年、pp.45−64.
佐藤:だからヴィジュアル・カルチャーがあって、オーディトリー・カルチャーがあったら、そのうちやっぱり匂いのカルチャーもあるだろうけれど、これに関しては本当記述することが難しいところ。
田口:やっぱり一番記憶と結びついている感覚というように言われているので、ということは、こう、それを吸った時に思い浮かぶ物とか色とか、景色っていうものが違うので。本当にそれは再現が難しいものですよね。
佐藤:うん。「セント(scent)」って言葉自体がね、「センス(sense)」とも繋がるようなね。
──ワインの分析とかがさらに発達して、それこそアーカイヴされるようになったら、アーカイヴから学問が発生するかもしれない。ヴィジュアルの物がアーカイヴされて、アクセスできるようになることによって、ヴィジュアル・スタディーズみたいなものが発達するように、アーカイヴがその学問の可能性を開くということはあるんじゃないですか。
佐藤:だからやっぱり、写真と美術史の関係なんていうのはまさにそうで。要するにあの、美術史は写真の子供だ、とかドナルド・プレツィオージっていう美術史家が言っちゃって、まさにそうだと思うんですよね。様式なんていうのは、写真があって、それを並べて、初めて比較という概念が成立したことを考えると、もう明らかに写真以降のことだろうし。それこそ平倉圭さんの、ゴダールをAdobeプレミアで解析する、のようなものも、まさしくそれはテクノロジーと学問というのがやっぱり特に関わってくるだろうし。その匂いとかもまさにそうかもしれない。
本当に記号学の問題でもあるし、美学の問題でもあるし、重要なんだけど、なかなかみんなやりきれてないところかもしれません。このあたりが、なんでもデジタルアーカイヴ化してしまう力と、デジタルアーカイヴ化されざるものとの臨界で、もしかしたらここからすごく面白い探求が可能になるのかなと思います。
──まだまだ話題は尽きませんが、そろそろお時間がきてしまいました。様々な分野や立場からアーカイヴに関わる学会員にとって、表象文化論とアーカイヴとの関係を改めて見つめ直す貴重な視座が示されたように思います。今後も継続して、場合によってはワインでも傾けながら(笑)、アーカイヴの現場を交えて意見交換を深めていければと思います。本日はどうもありがとうございました。